

寒かった。フルシチョフみたいに厚着しているのに。しかし、寒いからといって、シュラフに潜り込んでいるわけにはいかない。さっきから盛んに湖のあちこちで跳ねているのだ。この夜明け時を逃すことはできないのだ。朝食は、ニジマスのホイル焼きと決めたのだから。
ナイロン糸の先に銀色の疑似餌(ルアー)をつなぐ。竿をすばやく振ると、ルアーは20mほど糸を引っ張ってゆき、湖面に落ちる。それが少し沈むのを待ってからリールを巻き始める。ルアーがそれらしく泳ぐように竿をゆらしながら。確立からいうと百回に一度、いや千回に一度というところか、好奇心の強いのがルアーに喰らいついてくる。巻き終えると再び投入(キャスト)。釣れるまで。いやになるまで。
山の縁から太陽が顔を出した。標高1500mの水面に光が差す。結局一時間ねばって釣れたのは一匹だった。千回に一度は訂正だ。一万回に一度だ。いいかげん空腹だったので、釣れたニジマスをナイフでさばき、湖水で洗ってテントに戻る。
10月も終わり頃だったので、私のほかにキャンプしている者はなかった。キャンプ場貸切で朝めしだとテントに戻ってみると、しかしテントの横に置いたバイクのシートに腰かけている女がいた。見たこともない顔だ。美人といえた。
「一匹だけ?」彼女が言った。
「僕のことかい? それとも魚のこと? 魚だったら、客が来てるとわかってたらもう一匹釣ってきてたんだけどね。」
「もちろん、お魚のことだけど。でも気にしないでいいわよ。わたしは魚を食べないから。」
私は食事の用意をしながら彼女を観察した。肌は私と同じ人間とは思えないほど白く、上品な顔立ちはトレイになんか行ったことないんじゃないかと思わせた。正確に左右対称になっている顔の造りの中で、目だけは左のほうがやや大きく、それがかえってグッとくる魅力を彼女にもたらしていた。髪は茶色がかっていて、まっすぐに流れ落ち、肩の下でカーブを描いていた。
全体にやせているようだが胸はけっこうあるらしい。だから、私はそこから目をそらさざるを得なかった。なぜって、ここはさわやかな高原の湖なんだぜ。
膝までのスカートの下から伸びている下肢は、軽く組まれ、美しい曲線をつくって白いズックに収まっている。たかが曲線の一つや二つ、なんだ、と自分に言い聞かせつつ、私は呼吸の乱れを制した。
ニジマスが焼けたのでコンロから下ろし、代わりに水の入った鍋をのせる。ときおり鳥の声。水が沸騰する。沸いた湯を二つのコッヘルに分け、インスタントのみそ汁を作る。その様子を彼女はずっとモナリザみたいな微笑を浮かべて見ていた。私は小さいほうのコッヘルを彼女に差し出した。女だから小さいほうを勧めるのが礼儀だと思ってだ。しかし、彼女は首を振って言った。
「ごめんなさいね。いらないの。」
「じゃあ、パンは?」
そう聞くと、彼女は本当にすまなそうな顔をして言った。
「気を悪くしないでね。私はなにもいらないの。」
もう食べたからという訳ではなさそうだった。どこか変だ。だいたいこんな朝早くにこんなところに彼女のような女がいること自体、不思議だ。
「何もいらないって、なぜ?」
「私は人間じゃないから」
「そうじゃないかと思ってた。君は天使か。天使なら、みそ汁はいらないだろう。」
「アンドロイドなの。天使じゃないわ。」
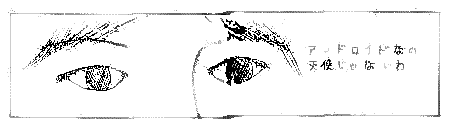
クスリでもやっているのか、それとも生まれつきなのか。しかし、彼女の姿を見ている限り、そのどちらも当てはまらないように思えた。
私は食事を始めた。彼女は黙って見ていた。その姿は朝日を正面から受けて、まぶしいばかりに輝いていた。これなら天使だというほうがまだ信憑性がある。
私は、パンとみそ汁とニジマスの朝食を終えた。習慣で、ごちそうさまと小さく言った。
「おいしかった? なんだか幸せそうね。」と言った彼女の笑顔は素敵だったが、幸せそうだと言われるのは、単純なおバカさんと言われているようでしゃくにさわった。
「やっぱり食べたかったんだろう?」
「アンドロイドは原子力電池で動くから食事はいらないのよ。だから食欲もないの。」
「よし、わかった。じゃ、僕のバイクを湖に投げ込んでくれよ。」
彼女は表情を変えずにバイクのシートから降りると、バイクのハンドルと荷台に手をかけた。私は、うそだろとつぶやいた。中古だが、5万もしたんだぞ。
しかし、バイクは少々揺れただけだった。
「だめ、できないわ。」
私はホッとして言った。
「女の子なら、もっとかわいいウソをつけよ。」
「バイクは持ち上がらなくてアンドロイドはアンドロイドよ。パワーがなかったらロボットじゃないって言うの?」
そんなにガンバルなら、少しゲームをしてみようと思った。
「ロボット工学の三原則ってのは、知ってるかい?」
「ええ」
「言ってみて」
「第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条 ロボットは人間に与えられた命令に服従しなければならない。ただし、与えられた命令が第一条に反する場合はこの限りではない。
第三条 ロボットは、自己を守らなければならない。以上よ。」
見たところ彼女は20歳にはなっていまい。そんな女がロボット工学の三原則を正確に言ってみせたのは意外だった。まあ40歳のおばさんにしても、知っていたら意外だろうが。
ただ、一箇所だけ抜けていた部分がある。第三条には、「第一条及び第二条に反する惧れのない限り」という但し書きがつくのだ。
「よく知ってるな。」
「アンドロイドはロボットの中のロボット。知ってて当然でしょ。」
私が彼女に三原則を言わせてみたのは、彼女がロボットのふりをし続けるならばその三原則を遵守しなくてはならないことを利用してからかってやるためだ。
さて、どうしてやろうか。私はタバコに火をつけた。タバコを覚えると食事は二度楽しめる。一度は料理そのものによって、一度は食後の一服によってた。しかし、これは名案を生む手助けにはならなかった。とりあえず、歌を歌ってくれと言ってみた。アンドロイドなら命令に従わなくてはならない。第二条だ。
「できないわ。」
「なぜ?」
知らないから、と彼女は平然と答えた。
「じゃあ、キスしてくれと言ったらやってくれるかい。キスのしかたは知ってるんだろうから。」
彼女はまったく動じないで答えた。
「言ってごらんなさいよ。キスしてほしいなら。」
多分、私は少し頭に血がのぼっていたのだろう。タバコの赤くくすぶっている部分を右の手のひらに押し当てた。すぐさま、私の手からタバコがはたきおとされた。彼女によって。
「そんなこと、しないで。」
「なぜだ。第一条による自動的反応だって言うのかい? それとも人が痛い目にあうのは自分にとっても辛いという人間の感情か?」
「どっちも、きっと同じことよ。」
「ふざけるのはもうやめてくれよ。僕はおふざけが嫌いなんだ。」
その時の私は、ジャン・バルジャンでも同情したくなるくらいの不幸な表情をしていたに違いない。彼女は私の手をとって、小さく火傷を負った部分をさすってくれ、言った。
「そんな顔しないで」
私は彼女から離れて、食器を片付け始めた。胸はスクールボーイみたいに高鳴っていた。「君は、どこから来たんだ?」
心を動かされた女性に対しては言葉遣いが荒くなる癖は、まだ直っていなかった。
「研究所」と彼女は答えた。
「分かったよ。もういい。」
彼女はあくまでもアンドロイドで押し通すらしい。私はテントをたたみ始めた。
「もう帰るの?」
「ああ、明日は会社だしね。」
「そう。」
「君はどうするんだい?」
「別に」
「下におりるんなら乗せてくよ。街に着くまでは警察はいないだろうから、僕のヘルメットをかぶればいい。」
彼女は笑顔で応えてくれた。それを見るためなら、貯金をすべて提供してもいいと思わせる笑顔だ。もっとも、私の場合、貯金はしてないが。
両側が水田になっている田舎道で、彼女は降りると言った。私は素直に従ってバイクを止めた。彼女はバイクを降り、ヘルメットを脱いだ。もしアンドロイドであるなら、自分を差し置き私にヘルメットをかぶらせるべきだった。しかし、バイクに乗っている間、ヘルメットをかぶっていたのは彼女だった。もうどうでもよいことだが。
彼女はヘルメットを私に手渡し、それから私の首に腕を回し、キスをくれた。軽いものだったが、その効果は後遺症が出そうなくらいヘビーだった。
「名前を聞いてなかった。」
「アンジーよ。」
その響きは私の脳に刻み込まれた。
「あなたは?」
私は自分の名を言った。そのまま彼女を見つめていたかったが、三つ数えて切り上げた。ヘルメットをかぶると、甘い香りが残っていた。
私は彼女に片手を振ってみせてから発進した。加速する。バックミラーの中に立つ女の姿が見えなくなるまで加速しつづけた。
頭の中では、ギター一本で弾く”ANGIE"が鳴り響いていた。ポール・サイモンのじゃなく、バート・ヤンシュのほうのだ。
次の年になってから、仕事の関係で晴海の展示会に出向いた私は、そこで再び彼女に会った。いや、彼女に似てはいるが別のものといえた。
それは、ある外資系のコンピュータメーカーのブースに立っていた。入場者としてではない。展示品として、赤のツーピースを着て立っていた。その横に置かれたパネルには、家事や事務に、あるいは秘書として絶対服従の高性能アンドロイドとあり、果てはダッチワイフにも使用できるということが遠まわしに説明してあった。次の火星探査隊には雑務を処理させる目的で同行することになっているともあった。処理するのは、雑務だけではないということだろう。
「アンジー」
私はやっとのことで声をしぼり出した。彼女はニッコリと笑ってみせた。
「いらっしゃいませ。私は高性能アンドロイド、アンジーです。何でもご質問ください。」
その返事に、私は自分の中で何かが壊れる音がしたような気がした。
「君はバイクを投げ飛ばすことができるかい」
「残念ですができません。力仕事をするようにはなっていませんので。」
つぎに私は、私がアンジーと会った湖の名を言い、知っているかと聞いてみた。
「はい、その湖畔には、私が作られた研究所があります。」
研究所! そうか。
「ロボット工学の三原則を言ってみろ。」と私はロボットに命じる口調で言った。彼女はスラスラと言ってみせた。第三条の「第一条及び第二条に反する惧れのない限り」の部分も抜かさなかった。
おそらく私が湖畔で出会った女は、未完成のアンドロイドだったのだ。それはたぶん、第一条、第二条に反してでも自己を守るという自己保存欲の強い状態だった。だから、正常なロボットへと修正されること、つまり自己が改変されてしまうのを恐れて逃走したのかもしれない。そして私に会った。その後、研究所に連れ戻され、アンドロイドとして「完全」にチューンされた。すべて憶測に過ぎないが、だいたいそんなところだろう。
こいつはキスぐらい軽々とやってみせるのだろう。人が火傷しそうになったら、やはり助けてくれるのだろう。どんな質問にもはぐらかさないで答えるだろう。しかし、バイクに乗せてやったら私にヘルメットをかぶらせるに違いない。私が湖で出会い、一生消えないだろう鮮烈な記憶を私に刻み付けたのは、ここにいる完全無欠のアンドロイドではない。自我の強い、未完成の、あれは人間だった。
「さよなら」
そう言って私は、決まり過ぎの笑顔を浮かべているアンドロイドの前を去った。そして、記憶の中のアンジーには、まださよならを言えないでいる。(おわり)
*この作品は、学生時代に発行していた同人誌からの転載です。
(2002.2.24)
[戻る]