
���䂾�������ƕW���������A�ŏI���̐��V�̋L�O�B�e�B
���_�x���Ł`���䍂�x�`���䍂�x�@�@�P�X�V�X�N�@�P��
�@�N���u�����čŏ��̐������h�ł����ˁB�����̐ϐ���͑�n��������̂���ԂŁA���g���l���܂łR���Ԃ��炢���������悤�ȋL������܂��B����Ɋ��g�������̒��Ƀe���g�����Ă����������A�����������X�������ꉺ�����Ă��܂�����B����ɏ㍂�n���ʂ̏o���ɂ͊W�����Ă������悤�ȁB�������Ȃ��ƐႪ��������Ńg���l���o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł��傤�B����ɉ��͊��S�ɓ�����Ă��āA��̃X�P�[�g������Ă���悤�ł����B�܂������g���̂Ȃ��ŃA�C�[������킯�ɂ͍s���Ȃ����˂��B

���䂾�������ƕW���������A�ŏI���̐��V�̋L�O�B�e�B
���̓�������A�u�s���N���f�B�̃~�[�����ƃP�C�����̂ǂ������D���H�v�Ȃ�ăA�z�Șb���Ȃ炪�A���u�P�C�����v�Ƃ����Ɓu���`�H�C���������A���ʂ̓~�`�����v�ƁB�������㊴��������̂�C�Șb�ł��˂��B���H�Ƃ���ł��̓�l�ŋߍČ��������Ƃ��˂��B�ł��S�b�����͂��̍����łɈ��ނ��Ă��܂�����ł��ˁB
�吳�r�̂�����ł́A���������H�����J�X���Ă��܂����B�����������G���Ă܂����ˁB����Ɍx�������A�v�揑�̒�o�����Ƃ߂Ă��܂����ˁB�㍂�n�łT�O�Z���`���炢�̐ϐႾ�������H�@�ł��g���[�X����������t���Ă��܂������B
�@���_�̓��ł͂���Ȃɓ���Ȃ��āA�m�������o�[�̂����Q�l�͂P�P���ɒ�@�ɂ����Ă����ł����u���̂Ƃ��Ɠ������v�Ƃ������Ă܂����B�O����߂��Ēݔ����ł͂����������Ⴉ�ꂽ�܂ܖ��c�B�������䂩��V�畽�ɂ����Ƃ����A�W�����_�����Ƃ����o�̎��Ƃ������āA�N�T�����������肵�Ȃ���u�c���H�Ȃ̂ɁA�~�͓���Ȃ��v�Ƃ��v���Ă܂����B�V�畽�Ń����o�[���X�m�[�\�[�g���āA�u�L�W�ꂫ�ꂢ�ɍ������v�Ƃ������Ă܂����˂��B����ɏo���Ƃ��ɂ͉����ɂȂ��āA���̂Ƃ��͍ō��̋C���ł����B���ꂩ��㍂�n�ɉ����āA�⊪����ɔ��܂�����ł������H�����ċA���B�y�������h�c���������ł���B
�@�C�O�̃`�����X������Ƃ�����A����͓o�R�ł͂Ȃ��ė��s�̕����悾�낤�Ǝv���Ă����B���⒙������ł���B���̑O�N����o�C�g�������ɂ����B�u�n���̕������v���o�ł���ĊԂ��Ȃ������B�u��Ɛ�v�ɁA���Z�~�e�̃g���v���E�_�C���N�g�Ȃ郋�[�g���傫���Љ�ꂽ�̂����̍��B�܂������Ă݂邱�ƁA�ڍׂ͌ォ�炾�Ǝv�����B����ł������ł͎g�������Ƃ��Ȃ��חg���̃o�b�N�Ƃ��āA�Â��L�X�����O���Ă���ɓ��Ă��B���}�[���i�y�b�c���j���w�������B�����炻�ꂪ���A��g�o���Ɖחg���A�㑱�̃��}�[�����O����悤�ȓo�����ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂����A���������ĉ\�����Ƃ����W�����҂����ۂɂ������B
�@�G�A�[�̂݉����\��i�P�W���~���炢�������j���āA�؍݊��Ԃ͂Q�O���ԁB���ɂƂ��Ă̊C�O�́A�D�Ńn���C�ɂQ���Ԋ�������Ƃ����邱�Ƃɂ��łQ�x�ځB����������߂ĂƂ����Ă������B�p�[�g�i�[�͍��Z���ォ��̂P�N��y�B���ł����܂Ɉꏏ�ɎR�ɍs���A�C�S�͒m��Ă����B�ނ����n�q�B��̐��c�ɍs���������ő����̊O�l��������āu�ȂA���ꂾ���ŊC�O����Ȃ��v�ƔށB���������悤�ȋC�����������B

���[�g���ȂǂƂ����ɖY��Ă��܂������A�Ƃɂ��������ɂ͂Ȃ���̊��G�������i���Z�~�e�k�J�j
�@�T���t�����V�X�R�ɓ���B�n���̕������ɏo�Ă���YMCA�ɏh���B�u�ȂA�A�����J���ĉ����Ȃ��v�B�C�O�Ȃ̂�����A���h�̐��{�͔��������łȂ���Ȃ�Ȃ��ƁA���߂������Ă����B���ۂ���ȃ��[�g�s�A�����̒��ɂ���킯�͂Ȃ��̂��B���̂��ꂢ�������������Ȃ�A���{�͐��E��̃J�e�S���[�ɓ���B���_�́A��X������Ă��āA�r���̏ォ�琅��������ꂽ�ƒQ���Ă����B�u�A�����J���ĂƂ�ł��Ȃ��Ƃ��낾�v�B
�@�����ł͂P���������āA�������ƃo�X�Ń��Z�~�e�Ɍ������B�O���C�n�E���h�Ƃ����嗤���f�o�X�ƁA�g�����X�|�[�e�[�V�����Ƃ����n���o�X�ɏ�芷����B�P��������Ń��Z�~�e�ɓ���B���Z�~�e�͔����������B�A�����J�͓c�ɂɌ���Ƃ����̂��������B�G���L���s�^���͂��ꂱ�����̓�����ɂ����āA�n�ʂ��炠�̉ԛ���̃X���u�̂P�O�O�O���[�g���̊�ǂ��A�܂�Ő����Ă���悤�ɂ����藧�B�u����Ȃ̐��̒��ɂ��肦�˂���v�B���ɂ̓z�e��������B�V�����[���A���X�g�������A�R���r�j���A�����ăL�����v����B���Ȃ炪�㍂�n�̃L�����v��ɁA�X�[�p�[�ƁA�V�����[�ƁA���X�g�����ƁA�R���r�j�𑫂��A�ꉞ���Z�~�e�̂悤�ɂ͂Ȃ�B�T�j�[�T�C�h�Ƃ����L�����v��́A���m�ɂ́u�E�H�[�N�C���E�L�����v�v�ŁA���Ɨp�Ԃ��������ɗ����l�p�̃e���g��ɂȂ�B�܂肻��ȊO�̑唼�̃L�����v��̓I�[�g�L�����v�ł���A���ꂪ�嗬�ł���B
�������͂��̕����ē���e���g����\�����ށB�P���Q�h�����������B���~�b�g�͂P�T�Ԃ̌p���h���܂ŁB����ȏ�؍݂������Ƃ��ɂ́A��U�����o�čē����B����ɂ܂��P���e���g�R����܂łƌ��߂��Ă���B����ɂ��Ă��A�R����ŗ]�T���Ⴍ���Ⴍ�B�����ɂ̓e�[�u��������A�����Ηp�̃X�y�[�X������A�f�b�L�\�t�@�[��l�������ׂĂ��A�܂��܂��]�T������B���{�̃L�����v��Ƃ͑卷�ɂȂ�B�g�C���ł́A�y�[�p�[������ɂ���Ȃ��悤�ɂ��łɌ��t���������B�L�����v��\�����ނƂ��Ƀ^�o�R���z�����܂܃����W���[�̎o����ɑΉ�����Ɓu�^�o�R�������v�ƌ���ꂽ�B���܂ɔn�ɏ���������W���[�������ɂ���B�L�����v���Ɍf���������āA���ÃU�C���̔̔����Ƃ��A�p�[�g�i�[���ނ��Ƃ�����B
���|���ꂽ�̂́A���̑������߂��閳���̃V���g���o�X�������Ă������Ƃ��B���U��������[���X�����܂ŁA�P�O���Ԋu�B���͂�͂�㍂�n�Ɏ��Ă��āA���_�A����Ƒ����B���̂��炢�̋���������悤�ɃA�X�t�@���g�ɂȂ��Ă��āA���̃o�X������B���܂ɂQ�K���ăo�X�������āA����͉����̏�ɍ��Ȃ��t���Ă���悤�Ȃ��̂ŁA�Q�K�Ȃ͑�l�C�B�^�]���Ă���̂̓T���O���X���|���������h���C�o�[�������������B�i�D�悷����̂��B�������I�[�g�}�`�b�N�̓d�C�o�X�B
�l��́A���͂V�����ɂ̂��̂��N���āA���X�g�����̒��H�o�C�L���O�ɍs���B���т̓p�����������A�[�H�͂�͂背�X�g�����Ƀr�[�t�̒�H�A�P�O�h�����炢���������B�����h���͂P�W�O�~���炢�����B�ł��܂��ꉞ�؍ݔ�͍��v�P�O���~���炢��ڕW�ɁA����Ȃ��Ȃ����牽�Ƃ��Ǝv���Ă����B����ȂɐߖȂ��B
���ׂĂɋ�������邻�̊��ŁA�ʂ����ăN���C�~���O�ɏW���ł���̂��B����A�͂����茾���Ă��܂��A�N���C�~���O�Ȃǂ��Ă���ꍇ�Ȃ̂��ƁB
�ł��Ƃ肠�������X�Ń��[�g�}���B�t�@�C�u�I�[�v���u�b�N�X�Ƃ����O�b�����x�̊�ꂪ�K���������B�m���ɖ��O�̒ʂ�ɂT�{�̃��[�g������B�R�s�b�`���炢�Ŕ������ċA��͕����č~���B�O���[�h���������ɂ��傤�ǂ����A�S�����x���B�������A�����J�̃O���[�h�͉��̂��T�̌�ɁA�U���炢����P�R�܂ł̐����ŕ]������B�܂�T�C�U�`�T�C�P�R�B�o���̂́A�T�C�W���炢�����x�B�ŏ��ɂ��̂����Q�{��o���āA�����͋x�{�B���̗����P�{�o���Ă܂��x�{�B����ɂP�{�ƁA�`���^���̃L�����v�����ɂȂ�B����ɂU�����Ƃ͂����A�������������B�J�͂��܂������ɍ~���������ŁA���Ƃ͐��V�����������B
��̏����́A�����\�����Ȃ��B�����t���[�N�����C�o�b�N�ň��������Ă���ɂ͂���Ȃ��B�z�[���h�X�^���X������邱�Ƃ��Ȃ��B�i�b�c���g�����̂����̂Ƃ������߂ĂɂȂ邪�A����ł��܂������ƃZ�b�g�ł���B����Ǒ��̃��[�g�ɍs�����Ƃ��ɋC�����̂����A�n�[�P���ނ��قƂ�Ǒł��ĂȂ����߂ɁA�����������[�g�Ȃ̂������łȂ��̂����悭������Ȃ��̂��B���[�g���Ƃ�����u�����A����ȂƂ��o���Ă����́v�Ƌ�������B�חg���̕K�v�ȃ��[�g�Ɏ��t�����ƂȂǁA��������s�\���Ƃ������ƂɂȂ����B�Z�R�C�A�̔w�̍������̐j�t���ɑ��͕����āA�܂������������B�T�O�O���[�g�������郈�Z�~�e�̑���A�n�[�t�h�[�����A������������B
���������A�n���o�X�ɏ�芷�����Ƃ��ɁA���{�l�̏��q�w����l�����悵�Ă����B�������Z�~�e�ɍs���̂����u�A��͂ǂ�����́H�v�u�����H�R�T�Ԍキ�炢�ɂȂ邩��A���߂ĂȂ��v�u�H�H����Ȃɂ���H�����������A��v�B�u�H����A�����ɗ����́H�v�B�Ƃ����g���`���J���ȉ�b�ɂ��Ȃ�B�����Ȃ̂��A�ޏ������͂��̂����ɓ��{�̊C�O���s�̎嗬�ɂȂ�A�O��̓y��������łT���Ԃ̗L���Ƃ������@�ŁA�s���X���Ԃ̊C�O���s�������̂ł���B�����ȍ~�͂܂���������ɏ������̂����B���Ƃ�����A���C�݃c�A�[�Ń��Z�~�e�܂œ���q�͂���܂������h�ɂȂ��Ă���B�P���ł��ґ�ȕ��Ȃ̂��B�Ƃ��낪�����̎��́A�C�O���s�Ƃ����A�Q�C�R�T�Ԃ͍Œ�ł��K�v���Ǝv������ł����B�܂��ēo�R�Ȃ炻��ȏ�B�ޏ������̗��s�Ɉ�a�������������A���������͂���Ȃ��ƂɁA�D�z�����������B
�����ł��̗��K���[�g��o������ɁA�������[�g�ɗՂނ��Ƃɂ����B�Ƃ����Ă��ȒP�ɓo���̂́A���S�����郋�[�g�̓��ł���������Ƃ����Ă������A���C�����A�[�`�Ƃ����P�T�s�b�`���炢�̂��̂������B����͊m���J���V�J�̓X���������A�呠����ɓX�ɍs�����Ƃ��ɋ����Ă�������悤�ȋC�������B���t���܂ł͗�̃o�X�𗘗p���Ă���ɂP���ԂقǕ������B���̂��߂ɑO���ɂ����Ƀr�o�[�N�����B���U�����ɏo���B������₷���������[�g�Ȃ��߂ɁA�s�b�`�͐i�ށB�ł��P���Ԃ����Ƃ��炫���R�l�p�[�e�B�ɒǂ������B���[�g�̓r���ɐU��q�g���o�[�X�������āA�����ʂɓo��ƂT�C�X���炢�������̂��B���_���g�b�v�ł�������Ȃ����B�ނ͊��ł���B�㑱�̎��͐U��q�ɂ���B����Ȃ��Ƃ����Ȃ�����A�܂��\��ʂ�ɏ�ɔ����āA���R�͓r���A�v�U�C�������������肵�����߂ɕs���ŁA�ǂ����ꂽ�㑱�̂R�l�ƈꏏ�ɉ������B�����Ƃ������[�g��o�����̂͂��ꂾ���B�������v�揑�̓����W���[�ɒ�o���Ă����B�m����́u���v�̏Љ�̒��ɁA�\��ʂ�̉��R�����Ȃ��ƁA�����W���[������Ƀw�������đ{���ɂ���Ə����Ă������̂��B�������͉��R�\�肪�[���̂U���B�Ԃɍ��킹�邽�߂ɂ͑��邵���Ȃ��Ƃ����A�����҂��������߂ɁA���������ꏏ�ɂȂ������l�̂R�l�Ɉ��A�������ɑ������B�����Ɖ��R�����i�K�ŁA�C���������ƁB

���̌�́A�O���b�V���[�|�C���g�E�G�v�����Ƃ��Z�����[�g�o������A���̃G���L���s�^���̎��t���܂Ō��w�ɂ�������B���łɂ��̂����ɂȂ��āA���t���܂œk���P���Ԉȏ�̃��[�g�ɂ͍s���C�ɂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă����B���̂��߃��Z�~�e�̃}�[�N�ɂ��Ȃ��Ă���n�[�t�h�[���ɂ͍s���Ă��Ȃ��A�������͉����ɂ���̂��B
���͂��̂P�T�Ԃ�����ƂŁA���łɒB�����ɖ����Ă��܂����B����Ȃ��Ƃ����A��͂菗�����o�X���^�]���邱�Ƃ�A�T�}�[�^�C���Ŗ�̂P�O���܂Ŗ��邢���ƁB�K�\���������b�^�[�{���ɂR�O�~���炢�Ŕ����Ă������Ɓi���ۂ̓K�������P�ʂȂ̂ł��邪�j�B���������A�����J�Ɋ������Ă��܂����̂ł���B����͗Ⴆ�A�����������͂̊��Ȃǂɖڂ����ꂸ�ɁA�R�o�肾������悤�ȃf���J�V�[�̂Ȃ��ɁA�ނ������Ă��܂��قǂł��������B�C�O�̋L�^��ǂނƁA�قƂ�ǑS���̓��{�l�����˖Ґi�B�{���Ȃ̂��낤���B�K�\������R�O�~�ɋC���Ƃ��āA��͂�R�ȂǓo���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��Ǝv�����ށB
���_�ɂ��������B�u���͂������Z�~�e���o��B���T���[���X�Ƃ��n���E�b�h���������v�B�u�����H���ƂP�T�ԑ҂��Ă�B��������ꏏ�ɂ����v�u����A�҂ĂȂ��v�B�������ĂQ�l�̃p�[�e�B�͕ʂꂽ�B�ȍ~�͑o���P�ƍs�ɂȂ�B���̓o�X�Ń��T���[���X�Ɍ������B�n���E�b�h������B�Q�C�R������Ƃ���ɗ~���o�āA���X�x�K�X�ɂ��s���Ă݂����Ȃ�B�����͂S�O�O�L���B�o�X�ɂ܂����B����ƍ��x�̓O�����h�L���j�I���ό��̃Z�X�i�ɏ���Ă݂����Ȃ����B��������o�Ă���̂��B�����Ă܂����X�Ƀo�X�Ŗ߂�B���Ɨp�ԂƔ�s�@�ȊO�ł̓o�X�����Ȃ��̂��B�S���ɏ��l�͓��{�ŋq�D�ɏ�邭�炢�ɒ������B�����ċA�������������ɁA�ނƗ\��ʂ�ɃT���t�����V�X�R��YMCA�ŗ��������ɂȂ��Ă����B�����ɓS���ōs�������Ȃ����B���C�����[�h���g���C�����ʂ��Ȃ��B�A���g���b�N�Ƃ����̂��B���ꂪ�P�Q���Ԉȏ���������ăT���t�����V�X�R�ɂ����B�o�X�����x�����炢���B�����`�����������͂���B���͂��̃T���t�����V�X�R�́A�嗤�S����������ݐ��ɂȂ��Ă����B�o�X�łQ�O���قǂ̃o�[�N���[�ŗ�Ԃ��~��ď��p�����ƂɂȂ��Ă����B���������͂����m��Ȃ��B�ł��s�R�Ɏv���Ă͂����B���̉w�̒�Ԏ��Ԃ̊ԂɁA�T�[�o���g�̂悤�Ȑl���A��Ԃ̎肷���@���Ă����B�u�T���t�����V�X�R�͎�����˂��H�v�B�ނ͓{�����悤�Ɂu�Q�b�g�I�t�A�Q�b�g�I�t�v�Ƌ��ԁB���Q�Ăč~�肽�B�����C�����Ȃ��Ƃ��������A�ꂽ�̂��낤���B���������ɂ͗\��̔�s�@���o��B�u�悩������Ȃ��A�܂������ƂɂȂ�Ȃ��āv�Ƃ��Ƃő��_�Ƙb���B
�ނ͂P�������̏ꏊ�ɂ��Ă����B�����o�Ă���͂��܂��ܓ��{�l�p�[�e�B�����������ŁA�ނ�ƈꏏ�ɓo�����Ƃ����B�����đ�������������́A�ό��œK���ȃo�X�ɏ������Ƃ�ł��Ȃ������ɍs���Ă��܂��āA�����Ɍ���ƂQ���Ԋ|���Ė߂��Ă����Ƃ��B�ł��Q�T�Ԃ̎��Ԃ�u���āA�����ƖړI�n�ō����ł���̂�����A��͂�R������͂������肵�Ă���B���E�̃��[�g�t�@�C���f�B���O���ԈႤ�悤�ȃ��c�́A�R�֍s�����i�͂Ȃ��Ƃ���͍��ł��v���Ă��邱�Ƃ��B�҂����킹�ɂ��Ȃ��ƁA�������ƒu���Ă����Ă��܂��܂��B�g�т̘A�����́A�����Ɍ����ł��B
�A�����J�̎R��o��O�ɁA�܂��A�����J�Ƃ��������̕�����Ȃ��ƁA����ł��܂���B�킩��Ȃ����ł��R�o��قǁA���͎R�Ɏ����͂Ȃ��̂�������Ȃ��B
���̌�W�O�N��̌㔼�ɂȂ��āA��̂X���ԊC�O���s�͉��x�����邱�ƂɂȂ����B�Ƃɂ����A�����J�̎h���͋��������̂ł���B���v�ŃA�����J�ƃ��[���b�p�ɂ͂T���炢�͗��s���邱�ƂɂȂ����B�d���̊W��A�����x�݂�S�[���f���E�B�[�N���Z�����߂ɁA����ɏt�x�݁A�H�x�݂����傤�ǂP�T�Ԃ������B����𗷍s�ɓ��ĂāA�Ă͂�͂��ɒʂ��Ƃ����̂��A���̍��̔N�Ԍv��ƂȂ����B
���[���b�p�̓A�����J����������₷�������B�N���}���Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��A�����J�Ƃ͈���āA�����Ă����v���B���{�l�̊��o�ɂȂ��݈Ղ��B�����������^�J�[���Ȃ��Ǝ��R�ɗ��s���ł��Ȃ��Ǝ��͎v�����̂��B��Ђɗ��s���̃x�e���������āA�ނɕ����B�u�ʂɓ�����Ƃ͂Ȃ��˂��v�B��������G�C�r�X�����^�J�[�ŗ\�������Ή��Ă̂ǂ��ł��Ԃ͗p�ӂ���邱�Ƃ��킩�����B���ɃA�����J�̓����^�J�[��������P�T�Ԏ�ĂR���~�B���[���b�p�͓��{���݂ł��������B

�h���~�e�̒��S�n�̃R���`�i�i�C�^���A�j�B�X�̒����炷�������Ɋ�ǂ��B
���[���b�p�̗��͎��R���s���ƓS���̗��ɂȂ�B�c�A�[���ƃo�X�B�v����ɂ��鏄�肪�A���������s�̓T�^�ɂȂ�킯���B���͂�����������B�ŏ��̃��[���b�p���炵�āA�t�����X�̃h�R�[����`�ł��̃����^�J�[�̗\������Ă����B�v�������X���[�Y�Ɏn�܂�B�����ŏ��́u�v���[�Y�v�Ɓu�T���L���[�v�����ʼn��Ă���낤�Ƃ������߂Ƀ����^�J�[�́u�C���V���A�����X�i�ی��j���ǂ�����H�v�̈Ӗ����S��������Ȃ��āA��]�Ԏ���Ă��܂�����������B
�N���}�͑���o�������s�����W���͂������肵�Ă���B�܂��V�����j�Ɍ������B���R�ł��傤�B�����ă����u�����g���l�����z���ăC�^���A�̃N���}�C���[���ɁB�ŏ��̃��[���b�p���s�ŋC�������̂����A�~�̃I�����s�b�N���������������A����͉ē~�Ƃ����]�[�g�n�ł���A���炩�Ƀ��[���b�p�A���v�X�̒������܂悦��̂��ƁB���ʓI�ɂ��̗\�z�͑哖����������B��̃V�����j���炵�đ�P��̓~�G�ܗւ̊J�Òn�������B�h���~�e�̓R���`�i�A�X�C�X�̓T�������b�c�A�I�[�X�g���A�̓C���X�u���b�N�B����ɊF���D���ȃc�F���}�b�g��O�����f�������h�Ȃǂ́A�ǂ�����ł�������قNj߂��B��̃X�C�X�ȂNj�B���x�Ȃ̂�����A���̋C�ɂȂ�P���ʼn���Ă��܂��B���ĂłP���T�O�O�L���N���}�𑖂点��ȂǓ�����Ƃł��Ȃ������B�P�T�ԂłR�O�O�O�L���B���[���b�p�ł͂U���ԂłU�J������B�X�C�X�A�C�^���A�A�t�����X�A�I�[�X�g���A�A�h�C�c�E�E�E�B���̂����ɃN���}�Ń��[���b�p�A���v�X���c�����Ă���C���ɂȂ��Ă����B�T�������b�c�ȂǕW���͂P�W�O�O������B����Ƀ��[�v�E�F�C�ɏ��ƁA�R�O�O�O�܂ł������B�^�Ăɂ����ł͐Ⴊ�~�����B�~��Ă���Ɣ����ł����B
�m���E�F�[�̎R�͕W�����Ⴂ�Ɣn���ɂ���邪�A�Q�O�O�O�ł��C���炻���藧���Ă���A����͂��Ȃ�Ȃ��́B�g���[���E�H�[���̓t�B�����h���炻���藧���Ă����B����ɂ��̍��͍������t�B�����h�ɂȂ��Ă���B���͕X�͂̎c�[�C�ɍs���~�܂��āA�t�F���[�ɏ�芷����B��������낵���ȒP�������B�P�T���N���Ƀt�F���[�͂���B�~�܂����D�ɎԂ��Ɠ����Ă����B��������^�̃g���[���[������B�łT�����炢�ő҂��Ă���Ԃ����ׂď�荞�ނƑD�͂ł�B�����̂��̃t�F���[�̃`�P�b�g�w�����Ƃ����Ԃ��Ƃ��^�C���̎Ԏ~�߂��Ƃ��́A�ʓ|�͈�Ȃ��B�h���C�u�}�b�v�̓�����ē_���ɂȂ��Ă��邱�Ƃɏł��Ă����������A�z�炵���Ȃ����B�t���ƃm���E�F�[�Ȃǂ͓��z���͗�������̕ǁB���E�͂�͂蔼���B���������܂������A�������̂������B
�ԂŌi�F�̂����c���H��T�����Ƃ͖�̂Ȃ����Ƃ��A�\���m���Ȃǂ���Ȃ��B�A�����J�̃A�g���X�Ƃ����n�}�ɂ̓V�[�j�b�N���[�g�i�i�F�̂������j�ɂ̓}�[�N���t���Ă��邵�A���[���b�p�ł̓~�V�������̒n�}�ŃA���v�X�̓��z���̓���K���ɑ��邾���Ŋ��҂͗���ꂽ���Ƃ��Ȃ��B�X�C�X�̓��z���ł͂Q�O�O�O���z����Ƃ���������̂����A����͏o������݂���m�q�̂悤�ȃJ�[���n�`���_�ɂ��g���o�[�X����悤�ɋ삯�����ēo���Ă����B�X����������B����ɉ���ł̓e�[�����b�W����܂��t���܂ɓ˂�����ł����悤�ȓ����������B���̕X�͋}�s�ɏ�����l�Ȃ番���邾�낤�B�S���ł������ꂾ���̃X����������Ȃ�A�����ʼn^�]���铹�ł���ȏ�̃X�����������āA�y�����Ȃ��킯���Ȃ��B�t�ɃA�����J�ł͂S�O�O�O�̍��x�������āA�x�m�R�ȏ�̍����ɂ܂œ������Ă���̂����A�R�͂Ȃ��炩�ł��ƂȂ����A�L�傾�B���b�L�[�z���Ƃ����Ă��A�o�X�Ń{�[�b�Ƃ��Ă���ƁA�C�����Ȃ����炢�ł�����B
����Ȍo�������x�����āu�����^�J�[���Ė{���ɂ����ł��ˁv�Ƃ��̃x�e�����ɂ����ƁA�u�z���g�ɂ��������B����ȗ��s���Ă�����{�l�͂P���l�ɂP�l���炢�炵���ˁv�B�c�A�[����������ɂȂ邪�A�y�����͂P�O�{�ȏ�ɂȂ�B
���̗��s�ł́A�܂�o�R���邻�̑O�i�K�Ŕs�ނ��Ă��܂����Ƃ�������̂��B�N���}�̏c���ŏ\���B���Z�~�e�ɂ��ẮA���̌b�܂ꂽ�ԛ����o���Ă��܂�����A������m�q�ȂǃA�z�炵���ēo��C�ɂ��Ȃ�Ȃ��ƁA�����������ċC����������Ă��܂����B����A���Z�~�e�œo��Ȃ���ǂ�o���悤�ɓw�͂������Ƃ����ƁA���������Q�[���N���C�~���O�́A�̌^�̑���������B�₹�C���Řr�͂̂���l�B���̑��I�肾�Ƃ�����y���N���u�ɓ����Ă������Ƃ����������A�ق�̐������ŃN���C�~���O�Q�[���ł͕����Ă��܂����B�����������Ƃɕ������B
���܂��̃��Z�~�e�Ə�m�L���i�����j�̔N��W�����߂ċC�����āA����͂킸���ɗ��N�̂��Ƃ������̂��B���֊W�͖��炩�ɂ���Ǝv����B���ӎ��ɂ��������o�R�ɕς���Ă���������F���ł���B�u�m��ʂ�������v�ƌ���ꂽ���Ƃ��������B���Z�~�e�����m��Ȃ���A�����Ɠo���ɏW���ł����̂ɂƁB�ł��܂��l���̌��ʂ͓����悤�Ȃ��̂��낤�B�ǂ������ǂ������̂��́A��͂�O�҂��낤�B��肽�����Ƃ�����āA���̌��ʎ������ȍ~�����������Ǝv�������Ƃ����Ă����B���ꂪ���̓o�R�̃v�����ɂȂ��Ă����̂��낤�Ǝv���B
�ŏ��̃A�����J�s�̋A��̔�s�@�Łu�啽���S���Ȃ��āA��������ɂȂ�����v�ƕ����āu�s�m���̗�������H�v�ƊԈႦ�����炢������A�N��͊Ԉ���Ă��Ȃ��B���Ă̎R�͌b�܂ꂷ���Ă���B���������̊����܂������Ⴄ�B�A�E�g�h�A�ł͓��{�����Ăɏ��Ă���ɂ͂Ȃ��̂��B����͎d���̂Ȃ����Ƃł���B�ł������̎R�X�L�[�ɂ́A�܂��܂��O���Ă͂��Ȃ����B
������E��m�L���@�@�P�X�W�P�N�@��

���_���B���Ă��ꂽ�ʐ^�Łu����G�C�݂����ɉj���ł邼�v�Ƃ���ꂽ���́B��m�L���ŏ��̃S���W���ӂ�B
�@���̔N�̏H���}����Ǝ��͂Q�T���}����Ƃ�����������A�܂��Q�S�̉Ă̂��ƁB�p�[�g�i�[�̓N���u�łP�N��y�A�N��łR�Ώ�̔ނ������B�v��������o�����͎̂��B�R�x��ɓ����ĂR�N�قǂ����Ă���B
�@�Љ�l�R�x��̂R�N�Ƃ����̂́A���ɑ������̂������B���i�͊�o��̃g���[�j���O�R�s�����A�����ƂT���ɂ͐�R�̍��h�B�U���ȍ~�̓z�[���O�����h�̒J��x�ɒʂ����B�v��R�s�͖��T�̂悤�ɂ���B�ӂ��Ă��Ȃ���u�̏�ɂ��R�N�v�����H�ł����̂ł��낤���B�������ł���B������ƕ��ς��ȎR�s���������Ȃ����B��o��Ƃ����A�킪�N���u�͉��̂��O�����āA����͊�o��̈�i���̃����N�Ɏv���Ă����B���͑�^�ʖڂɁu��m�q�v�����āu��v����Ȃ����A�Ɣ������A����͏��b�́u�������v�ƕ߂炦���Ă����B�{���������ƁA��m�q�̖{���̖�����ł���P�O���̖{�J�̎p�����Ă݂����Ƃ�����]����ɂ������̂ł���B���������̃`�����X�Ƃ����̂́A�����Y��Ă��܂��Ēʂ�߂����B�U��������R�����m�q�ł́A������k�𑖂��ď��A�e�[�����b�W������Ɏ��t�����B����͌�ɂȂ��Ă݂�Ύ��ɍ����I�Ȃ̂ł��邪�A���̂Ƃ��͉������ē��̃n�C�L���O�݂�������Ȃ��̂��ƁA�̂ڂ������Ƃ��v������������B�����b�������ЂƂ�Ń��[�g�����ēo���Ă݂����Ƃ����Փ��ł���B��m�q�ł͂���Ȃ��Ƃ͖����Șb�������B�K����y�̓��[�g��m���Ă������A���͂ɓo�R�҂͑吨�������A���l�̌��ǂ��Ă����A�Ȃ�Ƃ��Ȃ��Ă��܂������̂ł������B�k�ł̉��~�Ƃ����̂��A���v���Ă݂Ă��ʔ����Ƃ�������R�ɑI���̂��ƁA��m�q�̐�l�ɓ���������B
�@��m�L���ɍs���ƌ����o���āA�p�[�g�i�[�͂����Ɍ��������B�ł��唼�̉������͂��������R�s�͖�������Ă����B���ꂾ���������|����Ȃ�A���������ǂ�o�肽���ƁB
�@���y�ɑ��h�O�Y������B��m�q�̃R�b�v���ǁE���[�g�̏��o���҂ł���B�����͉�̏W��ɂ��܂ɏo�Ȃ���Ă����B�W��̋A��ɓd�Ԃ̂Ȃ��ő�삳��ɂ��̃v�����������Ă݂��B
�@�}�ɏΊ�ɂȂ��āA
�u�����A����͂ƂĂ������R�s���˂��B�ł������͕|����B��J�~��ƃS���W���тł͂P�T���[�g�������������v
�@���炩���Ă���̂��A�{���ɃA�h�o�C�X���Ă��ꂽ�̂�������Ȃ��B��삳��͂������₩�ɘb���l�Ȃ̂��B�������Ђ����ꂽ���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����Ȃ�����ǂ���������B
�@���ꂩ�琔���́A�d�ꂵ�����X�������Ă����B�傫�ȎR�s�̑O�́A���̏d�ꂵ���C���ȂǍ��ł͂قƂ�ǂȂ��B���������R�����Ȃ�ǂ��ɂ����Čv��𐋍s�������Ƃ����A���̈ӋC����ł���d�ꂵ���C���́A�Ⴂ�Ƃ������̓����Ȃ̂��B���ƂȂ��Ă͏������������̂��B
�@�܂��Ȃ��v��̓�������Ă���B��o��Ƃ�������ȋZ�p������̂��Ƃ�����A�����̎�������l�ɂ͂���͊F���Ƃ����Ă����B��o��ł͂P�`�U���Ƃ����O���[�h�������͕t���Ă������A�܂��S�����x�Ȃ牽�Ƃ��o���Ƃ������x�̌o���ł����Ȃ��B����ƒO��̂������̑�o��̌o���������B���̂ق����ׂĂ͌���ōl����Ƃ������ƂɂȂ����B���R���[�Ƃ����o�ŎЂ���A��̃��[�g�}�W���������ꂽ�̂����̍��ɂȂ�B��m�L���̍��́A��ɒm�荇�����ƂɂȂ�A�����b�����M�҂������B
�@���ł����̎R�s�̓����͖Y��Ă��Ȃ��B�_������Ί݂̓��œ��R���āA���œn���M�ɏ���āA�_���K�łP���B����ɐi��œr���łQ���ځB�R���ڂ͖�t��̏o�����B�ŏI�����Ő��ɔ�������ۏ�z�������B�S�����V�Ɍb�܂�Ăقڌv��ʂ肾�����B�������̔N�̓~�́u���a�T�U�N����v�Ƃ���ꂽ�N�ŁA���ʂ������̂��Ȃ��Ƃ����s�������͂����Ă̓��R�������̂����B
�@�����̉������̃X�i�b�v�ʐ^�����Ȃ���A�Ȃ�ׂ��v���o���悤�ɏ����Ă݂�B
�@�����ɂ́A���_���ނ�̓���������Ă��Ă��āA�_���K�̓���o�����̃e���g��ŗ[���Ɋ⋛�ނ���n�߂��B���͂��ꂩ�琔���Ԃ͐l�ɂ͉��Ȃ����낤����ƁA�l�������Ȃ��āA��������M�ɓ���Ɖ������q���b�e������炵���ꏊ�Ȃ̂����A�����Ɍ��������Ƃ���Ɓu������A�����Ȃ��āv�ƁB�����ړI�ŏ����ȂǂɊ��Ƃ����킯���B�܂�������ʂ�ł���B����������炵���Ƃ��납��T���قǐi��ŁA�͌��̑�n�Ƀe���g��B�ڂ̑O�ɗI�X�ƍ�����E��m�L��������A���ɒN��l���Ȃ����̉͌��Ƀp�[�e�B�̓�l�����B�f�����ɂȂ������ĒN�����Ă��Ȃ��B����ȏ�������ǂ����ē����悤�Ƃ���B�m���ɑ��_�̌����Ƃ���Ȃ̂ł���B�Q�O���قǂő��_�͐��C�̊⋛��ނ��Ă����B�a���ނ蓹��Ŕ����Ď����Ă����悤�ł���B�����Ă��炤�Ɠy�̒��ɗc�������āA���ꂪ�a�ɂȂ�B�y���Ə����ȃP�[�X�ɓ���ĉ^�ׂA�����͐����Ă���炵���B�⋛�͊ȒP�ɒނꂽ�B������ɂ��ďĂ��ĐH�ׂ�B�������_�͂���ɒނ낤�Ƃ��đ������点�Đ����ł�낯�āA�Ȃ�ƌ��̊J���Ă����E�G�X�g�o�b�N�̎c��̉a��d�|�������ׂĂ��̏����ɗ����Ă��܂����Ƃ����̂��B���s�ł���B���͉��Ă����Q�C���炢���y���ɂȂ������B�⋛��H�ׂ��̂͏��߂ĂɂȂ�B�����������ȍ~�̂��Ƃ��l����ƁA�d�ꂵ�����͋C�ŁA�ނƊy������b�������L���͂Ȃ��B��s�œ��R�������߂��낤���A�Q�t���܂łɂ͎��Ԃ͂�����Ȃ��B

���̂��炢�̓n�́A�����̖_��E���ăO�C�O�C�Ɠn���Ă��܂��B
�@�Q���ځB�ĎR�Ȃ̂����A��̐��͑����ɗ₽���B��������Ȃ��Əo������C�ɂ��Ȃ�Ȃ��B�u�V�����ł�����v�Ɣނ͂����B��o��Ȃ�Ă���Ȃ��̂炵���B�����n�߂Ă܂��Ȃ��A�Ƃ��鐔�l����ʂ��ɉ��R���Ă���B�X�m�[�{�[�g���P�������Ă���B������ɂȂ��Ă���B�����炩�猾�t�����킵���̂��B�u�����A������Ɓv�ƌ��t������͓̂��R�̂��Ƃ��B�l�q������Ε�����B���̂Ƃ����Ă��A���̒���ȏ�m�L���̂܂����t���Ȃ̂ł���B����ȂƂ���Ŏ��̂��āA����Ȃɓ���Ƃ���Ȃ̂��Ƃ����v�������������A�ނ��날�܂�ɂ���͂ȃp�[�e�B�̐ӔC�ł͂Ȃ����Ƃ��v�����B�u�������̓r���Łv�Ƃ���ꂽ�悤�ȋL��������B���Ǒ���⎖�̂͂��̌�̎R�s�ł͉��x���o��̂����A���͂��̂Ƃ��u���N�ł��Ȃ����̂����Ă��܂����v�Ǝv�����B���_�́u������Ɏ�����킹����v�Ƃ����Ă����B
�@�ŏ��̃S���W���Ƃ����̂́A��͂�܂��Ȃ����ꂽ�B�����߂��ŗ����Ă��ɂ��Ȃ��Ƃ�����ւ��Ă������B���邢�͐����ɂ����X�^���X�i����j�������邩�B���̐����Ƃ����̂��A�����������ɗ��B���邢�͑Ί݂։j���œn���Ă��܂����B�n�ȂǂƂ����Ă��A����͌҉����x�����E�ɂȂ�B����ȏ�̓U�C�������ĉj���ł��܂������������B������㗬���牺���Ɍ������ĉj���B�ő�����m�ۂ���Ƃ��ɂ́A�t�ɏ㗬������������Ă�����ƁA����͊y�`���ʼn������Ȃ��Ă�����ɑ̂�������Ă����瑤�ɂ��ǂ蒅���Ă���̂��B���ꂪ�J�[�u���Ă���Ƃ���ł́A���̊O�������l���ۂ��Ȃ��Ă��銄�ɗ��ꂪ�����B�܂�����̊����ł��邾���O�i���āA�O�������Ɍ������ăW�����v�ő���������z���āA��͈�C�ɉj������B���̂���������_���ȏꍇ�����������ɂȂ�B���j�����ӂ������͎̂��̂ق��ŁA�j���Ƃ��ɂ͎�����s�����B���ƂȂ�ΐ����ɂ��Č�����̂����A�n��j���ʼn����̂Ɂu�����������v�Ƃ����̂́A��������O���Œʗp���鈫�K���ł���A�ނ���댯�Ȃ��ƁB�G���̂�����Ȃ�A�ŏ������ɓ���ȂƁB
�@�����������Ƃ͋����Ă����l�͂��Ȃ������B����ł�����ɑ�������A���Ƃ����f�ł���悤�ɂȂ�B����̊O���������ȂǂƂ������Ƃ́A���ꂱ�����w���̗��ȂŏK�����悤�ȁB�@���ۂɃS���W���◬�ꂪ���������̂͂Q���Ԃ����������B��t��㕔�͌����Ƃ������ė���͉��₩�ɂȂ�B���̂Q���Ԃ����ɁA�������͂P�O�炢�͗�������E�ɉ��f�����̂��B���̌o�������ł��A����ɂ͒m��ׂ����Ƃ͒m�肦���悤�Ȗ������ɐZ�ꂽ���̂��B�@���ȍ������͎��͊댯�ł�����B�l�Ԃ͖{�\�I�Ɉ��S�n�т̏�ցA��ւƓ���������B���������ǂ܂���ɖ߂�Ȃ���ΎR�s�͂͂��ǂ�Ȃ��B�ނ�����ɉ��~���邱�Ƃ��K�v�Ȃ��ƂɂȂ�B���A����Ȃ��Ƃ͊�o��ł��悭���������ƂȂ̂��B����ɍ������Ƃ����̂́A���Ɏ��Ԃʂɏ���Ă��܂��B��������ɖ߂��Ă���ɉ����Đi�ނ��Ƃ̂ق��������Ɗy�������A���S�ɂ��Ȃ�B
�@�P���̍s�����Ԃ͒����Ȃ��B�V������[���̂S�����܂łŏ\���������B�����͂���B�������n����Ȃ�j���ƁA�܂�����̃J�[�u��������Ɠ������ƌJ��Ԃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����A���̃v���b�V���[�ɉ����Ԃ��ꂻ���ɂȂ����B���������~�ł͂Ȃ��̂����A�����o�Ă���̂��s���ɂȂ�B
�@�n�}������ƁA�m���Ɂu��m���r���K�v�u���m���r���K�v�Ƃ���B�����������O���B�����m�^����v�u����J�v�����������B�������������͖̂��O�����ł���B�Q���T��̒n�}�������Ă���̂�����A���������x���̑��ڕW�Ɂu���ƂP�L���v�u���ƂT�O�O���[�g���v�Ǝ����Ɍ�����������B�m����m�L���͂Q���T��̒n�}���R���K�v�������B������K���e�[�v�Œ��荇�킹�āA�O�x���炢�܂�Ԃ��Čg�s�����B�ł���������ʂɂ��Ă�A�T���炢�傫���B�������������B���݂��i�ނƂ��̉�ʂ�܂�Ԃ��悤�ɂȂ��āA���ꂪ�܂��O�i�ł����؋��ɂȂ��Ċy�������̂������B�S���W���ȊO�ł͋C�y�ȉ͌������̏ꏊ�������B���������Ƃ���͂͂��ǂ����B�Q���ڂ̃e���g��́A���ܐՂƌĂ��͌���������Ȃ����Ǝv���B�u�����͏�m���r���K�������v�Ǝv�����悤�ȋC������B�����ʉ߂���Ίj�S���͏I���ɂȂ�炵���B
�@�������O���ْ̋������ێ����邵���Ȃ������B�j�S���̌㔼�̕��ɂȂ�B�ʐ^�ɂ̓U�b�N��w�������܂܊^�̗��Ԃ��̂悤�ɋ����ɂȂ��āA�o�^���B�U�b�N���ւ̂悤�ɂ����w�j�œ҂�ʉ߂��Ă���ʐ^���c���Ă���B
�@�j�S�����ߑO���ɏI�������ɁA���_���E�����w���āu��t�x�̃J�[�����v�Ƃ����Ă����B���͂������グ�đ��Ƃ�ł����B�킸���Ȃ��炻�̗l�q�͋L���Ɏc���Ă���̂����u���グ���R���┧��������ĉ��Ȃv�Ƃ����v�������B�i�F�Ɍ��Ƃ��]�T�͂܂������Ȃ��B���̊��Ƃ������ς��ȋ���₪�����Ă���̂����A��������_�ɋ�����ꂽ�B����ɂ��Ă����ł���ȎR���Ɂu���̂��t�����₪����낤�v�Ƃ����^��́A���ŋ߂ɂȂ��Ă킩���Ă���B���ׂĊ������Y����̋ƐтȂ̂ł���B�m��ʂ����A�L�ɏ����A�u�^�ɐ^��E�E�E�B��C�̎���ł��̂قƂ�ǂ�y���œ��ݎU�炵�Ă����̂��낤���A���́B���Ƃ�����A�ґ�Ȏ��Ԃ��߂����Ă������ƂɂȂ�B
�@�[���A��t��o�������߂Â��ƁA�ނ�l�������B�ł������͂܂��o���܂łP���Ԃ��̋����ɂȂ�B�⋛�ނ�l�̓U�C�����g�������������悤�ȓn�ł��A�����������C�ŗ���ɐg���ς˂Ă��܂����̂炵���B�ނ�l�͑�o�艮��������A���͑�̑k�s�͏��Ȃ��̂Ȃ̂��B���̐l�̍��̃r�j�[���܂ɂ́A�Q�O�C�ȏ�̊⋛���j���ł����B�u�������˂��v�B�Q���Ԋ|���āA���Y�̏����ɉ^�Ԃ̂��낤���B�������⋛�ނ邾���ł����܂ō~��Ă�����̂Ȃ̂��B�����A�܂����������������̂炵���B�u����ނ炸���ĉ��ő��o���Ă���́H�v�Ƃ����悤�ȁA�����^�₪�������Ă��������B

�n�Ƃւ��g�ݍ��킹�����̂ł��ˁB�����ɃX�^���X����܂����B
�@��t��o�����́A�����k�s�ł������Ƃ̑O�j���݂����Ȗ��c�ɂȂ����B��������㕔�́A�����W���u�W���u���V�т炵���B���ʂ����������Ă����B���������Ă��낮�B
�@�����́A���ꂱ�����ƂȂ��Ă͍��������̂܂��ɂ��������Ƃ���́A�i�ϖL���Ȃ��U���o��Ȃ̂ł��邪�A���ꂷ�玩�o���Ȃ��B�����u�����悩�����A�����|���Ƃ���͂Ȃ��v�Ƃ����R�s�����̗D�z�������B�o�������ۏ�z�́A�_�m������̓o�R���Ȃ̂����A���̂����̎�O�t�߂Ńe���g�����B��o��ɖ��c�w��n�͂Ȃ��Ƃ����A���Ȏ�`�B�܂�����͍��ł������������H����Ă���炵�����B�[�Ă������ɂ��ꂢ���������ƁB��������₩���������ƁB
�@�ŏI���͗�����R�[�X����u�i���������������B���͂��̉��R�R�[�X�����̂Q�Q�N�̊Ԃł�������Y��Ă����̂��B���N�A�����_���ɍs�����Ƃ��ɂ悤�₭���̌����v���o�����������������B���ɉ��R���[�g���Ȃ��͂����Ƃ����A�t���I�Ȗⓚ����v���o�������ƂɂȂ�B�_���T�C�g�e�̕s����̒ނ苴�����āu�����A�����͒ʂ����L��������v�ƁB���̎�O�ŌC�E���ŁA�����Œ��n�������̂������B���_�Ɖ��R�������Ă������A�Ő��ł͏�����ʂ邽�тɁA�W���[�X���Ĉ��݂܂������B�Â����̂͂��������B���_�͂��̑O�N�Ƀ��[���b�p�o�R�c�A�[�ɂ����Ă��āu�t�����X�ł̓W���[�X���g�I�W���[�h�Ɣ��������v�Ƃ����Ă����B
�@��m�L���̖����k�s�́A���̓o�R�l���̃G�|�b�N�Ƃ����Ă����B���̌ケ�����č��������ɂ܂��ւ��悤�ɂȂ��Ă���̂�����A�l���͕s�v�c������B���͂�A�̗͓I�ɂ��Ă̑傫�ȑ�͂����Ȃ��Ȃ��Ă���̂����A����������ƁA�Ⴂ����̎����̎R�s�����ȃm�X�^���W�A�Ƃ��ĈԂ߂ƂȂ�̂�����A�������ȋC�����ł���B�������A���m�ɂ́A���m�L���ƍ��������ƕʂ�Ă���炵���B���x�����O��ǂݑւ���قǁA������͐l�Ɉ�����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̎R�s�́A�ԈႢ�Ȃ��ȍ~�̑�̊�ɂȂ����B������ɂ����Ƃ����A�ԐΑ�ɂ����Ƃ����A��������̉�����ɂ������Ƃ��ł��A���ʂ͌����ڂŁA�u��m�L���̉����̂P�v�Ƃ�����ł���B�Ƃ������Ƃ́A�S���W���ɑ������Ă��A�\�����ł���B�����W����t�F���g�C�ɂ����̂��A�S���W���p�ɔ����ŃE�G�b�g�X�[�c��������̂��A���ׂĂ͂��̎R�s����ɂȂ����B�������O�������čl����ƕ�����₷���ȂǂƁA����Ɏd���ɉ��p�������Ƃ�����B���m���r���K�Ə�m���r���K�ƌ����̂��Ƃ��B�v�����݂��������������̃x�X�g�N���C�~���O�ƂȂ����B
�����d�����`���x�@�@�P�X�W�P�N�@���@�@
�@�O�����獕���쉈���̓����āA�c���Ă���ʐ^���邾�������ǁA����ς�|�p�I�ȓ�����˂��B�吳�N��ɍ����Ƃ��_���J���ō�����ɒ��ڂ��āA��̍����̎R�����������ꐿ�������āA�c���n�V�ő��ǂɐ������������݂����킯�ł���B�������Y��������̓��ʂ����킯�ł���B���������ɉ����āA���̃S���W���ѓ˂�����ł������킯����Ȃ��͂����ˁB

�����d�����̎u���J�t�߁B��ǂ�����т��Ă����ς�ꗎ���Ă��铹�B
�@���l�̌��݂̂Ƃ��ɂ��܂����̓��g��ꂽ��ł��傤���ǁA�ł������n���g���b�R�������Ǝv���܂���B��O�̃_�����݂����ł��ˁA���̓��́B����ł��p���ɂ��Ȃ��ŁA�������Č��݂܂Œʗp�����Ă���킯�����A�܂��ɒ[�ɂ����Ă��܂��A��ǂɏ����āA�傢�Ȃ鎩�R�j�����̂����ǁA�ł����j�����܂���˂��A���̓��ɂ́B���̌�s�������ƂȂ����ǁA�ł��܂����U�����Ă��������炢�̊������Ă܂����ˁB
�@�ʐ^�Ō���قǓ��͋����Ȃ����A�܂��܂Â��Ă������g�������߂�A�R���痎�������Ă��܂����Ă��Ƃ��Ȃ��ł���A�ł����������Ă���Ƙb�͕ʂł��傤���B�܂�������ƂP�T�O���[�g�����炢�܂��t���܂ŁA������܂���B
�@���x�̉č��h�ɂ��̓�������낤�ƌ����o�����̂́A���̂Ƃ��̂R�l�g��S�ŁA�����ʔ��������������牞�����킯�ł��ˁB�����Č��Ƃ����ƁA�_������������A����������邩����ԂŁA����ɂ����O���Ă��܂�������ˁB���]���łP�����ė�����l�r���猕��ɉ����āA�x�[�X�͐^�����������������킯�ł��ˁB

��l����̘I�V���C�B�R�����̋߂��ɉ��N���Ƃ����D��ȂƂ���ł����B
�@�O���߂��Ă����ɁA�����R�̊�ǂ̑Ί݂��s���킯�ł������A���̊�ǂ̈�ۂƂ����̂́A����قǂł��Ȃ�������ł��B�v����ɉ��m�L�����\�����Ă��闼�݂̈�p�ɉ߂��Ȃ��킯��������ł���B�k�J�̑傫���ɔ�r����ƁA�����Ă���قǂł��Ȃ������B�����N���C�}�[�͂��̕ǂɒ��ڂ��Ă��邩��A�K�C�h�ނɂ͎��ɑ傫���Љ��Ă����킯�Ȃ�ł��傤���B���̌㉜���R��o������`�����X�͂Ȃ������ł��B
�@���܂������]���ł́ABC�ɉחg������E�C�X�L�[���d���������̂Łu����ł��܂��v�Ƃ������ƂɂȂ�A�R�l�ŋ���ۂɂ��Ă��܂��܂����B���̂��߂ɁA�����͓�������ł����C�������������ł��ˁB�ł�������ɐ�l�r�ɏo�鍠�ɂ͐������o�߂āA�����̘I�V���C�ɂ������Ă��܂��B�u�����牷��ɓ���ƃ_������Ȃ��v�Ƃ������Ȃ�����A�r�m���̏��������������[�����H������A�����̃o�C�g�̎o����Ɍ������R�̖��O�����Ă��������A���̓���|����̓��R�̕����A���h�̏o���������o���Ă��܂���B������̑�N���V�b�N�����ł���A�f���炵���B
�@���h�ł͎O�m���Ɉړ����ă`���l�ȂǓo��܂����B���Ԃƃ��C���C�Ŋy�����������ł��ˁB
�@�����Ƀt���[�X�s���b�c�Ȃ�Ă������[�g���J�ꂽ�Ƃ��ł����������A���a�c�R�̏���ʼn��x���g�b�v���[�v�Ńn���O�C���̊����K���Ă������ł��������B������������������Ƃ̂���A�����R�ɂȂ����B��ǂ̑O�������Ȍ����̂悤�ɂȂ��Ă��āA�����łP�����ă��[�g���Q�{�o�肽�������̂����A����ڂ͏��J�Œ�B����ɐΊD��̂��̊�́A������ƔG�ꂽ�����łƂĂ�����₷���āA�p�[�g�i�[�͂��̓��ɂ͎��t�����������悤�Ȃ̂����A���͂����܂��×~�ł��Ȃ��āA�A�b�T��������ߍ���ł����B���̗����������ŁA�����Ƃ��Ղ����ǂ̍����̃��[�g�Ɏ��t�������̂������B

�g�t�Ŋ�ǂ��F�Â��Ă������̓o���B
�@��ǂ̑O�𗬂�������f����̂ɁA�����ǂ̏�ɐN������悤�Ȃ��ƂŁA��Ɏ��t���Ă����B�u����Ȉ������������Ƃ��Ȃ��ƁA���t���Ȃ��̂��v�Ƃ�����ƃr�b�N�������B����ɗѓ��̂����e�ɁA���̊�ǂ��ނ������Ă��āA����Ȃ��Ƃɂ���a�����������B�ΊD��̊�́A�����̓�q�R�Ƃ��������o�����Ȃ��̂����A�Ƃɂ�����̂Ђ炪���悤�ɒɂ��B����ɖ��ɕ����e���X�ɃS���S�����Ă��āA������Ɠ����Ƃ��ꂪ���ƂȂ��č������B
�@�������Ďʐ^������ƁA�g�t�Ƃ����قǂł��Ȃ��̂����A�ł������X���F�Â��Ă���B�ʂɂ̂�т肵�Ă����킯�ł��Ȃ��̂ɁA�㑱�̃p�[�e�B�ɔ�����āA�I�����Ē�����o�R���ĉ��R���Ă����Ƃ��ɂ́A�[��ꂪ�����Ă����B��ʃ��[�g����̉��R�͎��ɑ���ɂȂ�B�Ŋ��w�͑厅���̏���B�A��̍ŏI��ԂɊԂɍ����������Ȃ��B�d���Ȃ��āA���������������n���̔_�Ƃɐ����|���āu�Ԃ�݂��Ă��炦�܂��v�ƁB�肽�ԂŃf�|�̃e���g�p�i��������ċ}���ʼnw�Ɍ����������悾�����B����ł��Ԃɍ�������Ԃ͎����삩��M�z���o�R�ŗ����ɓ����ɖ߂��s�����������B��s�ɏ��Ƃ��ɂ́A�S�l�|���{�b�N�X�̃V�[�g�����ɉ��낵�Ă��܂��āA������x�b�h�̑���ɂ��āA���ɑ�̎��ɂȂ��ĐQ�Ă��܂������̂������B�ԏ����������������Ȃ������B�������Ė{���ɏn�����ē����ɖ߂������̂ł���B�M�Z�咬���璆�����ŋA�鎞�ɂ��A�[���̂U�����߂��Ă��܂��ƁA��P�O�������̖�s�����Ȃ������B�����͒��A��̗�Ԃ𗘗p������Ȃ������Ƃ������������B�������ƂĂ����������B
��A�E���x�E�ԐΊx�E����x�@�P�X�W�Q�N�@�P��
�@��A���v�X�̓암�ɓ���ɂ́A�����I�ɔ���_�����璃�P�x�ɓo�铹�ȊO�ɁA�K���ȓo�R���͑��݂��Ȃ��̂ł���B����̂��̒����ѓ��́A�і쒡�����������Ɛ肵�Ă��āA�N���}�̒ʍs�͔F�߂Ă��Ȃ��B�������猻�݂܂ł���ȏ������Ă���B���̂Ƃ��A��������l�́A�e�ʂ��������y�����Ԃɏ���āA��������É��Ɍ��������B����_���܂ł��āA���������ėѓ��ɓ����̂ł͂Ȃ����Ƃ��������Ƃ���A�Ԏ~�߂̃Q�[�g�������̓��C���[���Ă��邾���̊ȒP�Ȃ��̂������B���̃��C���[���M���M�������グ�Ă݂�ƁA�y�͂��̉������傤�ǂ��������̂������B����Ȃ�Ɛ���̏o���܂œ����āA����������R���邱�Ƃɂ����̂������B
�@�N�����Ƃ����̂ɁA�Ⴊ�Ȃ��B��A�͂����������̂Ȃ̂��ƁB�ӏH�̎R�s�̗l�q�ŁA����̓o�R����o��B�Ő��ɂł鏭���O�ɂ悤�₭�Ⴊ�o�Ă����B����ł��Ő��͐^�����ŃA�C�[���̐��E�ɂȂ�B

�吹��������̐ԐΊx�B�����ł���͏��Ȃ��B
�@�ߋ��ĂɂQ��͂��̗Ő�������Ă���̂����A�u�~�͉��ʼnĂ������Ԃ�������낤�Ȃ��v�Ǝv�����B�����ɔ��܂��������ɁA���x���o�Ē����ێR�܂ł��������Ȃ������B���̗����ɐԐΊx���z���āA�吹�����܂ŁB�����ɔ��܂������ɐϐႪ�����āA�g���[�X�����ׂď������B�����������͉����Ŗ������Ƃ��Ȃ��B��̓��ɂ͒N���o�R�҂����Ȃ������̂����A�����ɂȂ�ƁA�Q�l�A�R�l�ƌ�������B�u�����Ɠo�R�҂Ƃ����̂́A�ǂ����炩�K���N���Ă���v�Ǝv���B�����������������v���Ă��邾�낤���B
�@����x���z������́A�疇�~�G�����ɓ���B�����ł͂P�O�l���炢�̓o�R�҂Ƃ����������̂��B���������~�G�����Ƃ����̂́A�����̂Q�K�̉��������J������Ă��āA�܂��ɋ������A�̂悤�ȂƂ��납������Ă����ƁA���͂��������L���������̂������B��V��̓~�G�����ɓ������Ƃ�������Ȃ������B���X�ƌq�����A�̎�Ő��̐^�������ɂ���̂ɁA�����͂��ꂪ���R�̂��ƂɎv���Ă����B�Ⴂ�Ƃ������ƂȂ̂��B�ґ���R�Ɉ͂܂�Ă��Ă��A���ꂪ������O�̂��ƁB�̗͂������鍠�ɂȂ��āA�����̉��l���g�ɂ��݂ĕ�����B
�@���R�͂������瞹���։����ăN���}�ɖ߂����B����ƃN���}���������炳�ꂽ�̂��낤�B�㕔�̃K���X�������Ă����̂ł���B�����܂ŃN���}�œ��������Ƃɑ��̓o�R�҂������点�����̂��A���h�����B���������ɔ�Q�͂Ȃ��B�ѓ��������Đ�̎Ԏ~�߂̂Ƃ���ɂ���ƁA�Ď������ɐl������B�����悤�Ƀ��C���[���グ�Ēʉ߂��悤�Ƃ���ƁA�Ǘ��l���~���w������B�Ƃ����Ă��A�邾���B�������ċA�r�ɒ����B
�@�S�C�T���̎R�s���I���āA�s���Ɋ�������łɋA��ɂ܂�������B�����I�o�T�����o�Ă��āu���܉��R�ł��v�Ƃ����Ɓu���������̂˂��v�B�S�C�T�����������H�܂��P�T�Ԃ��炢������ƍs���ɂ���������A�����^�Ɏ��̂��낤���B
�@�������ĂȂ�ƂȂ������̂�������A�̓~�c���͏I������B
�@���̎R�s�͌v��̒i�K�ł���Ȃ��Ƃ��������B�u��Ȃ����������c�v�u�댯�ȃ��c�v���p�[�e�B�ɉ��������Ȃ��ƂɂȂ��Ă����̂��B
���̔N�̂X�����P�O���Ɏ��͂��̐����̌v����N���u�Ō����o�����B���N�̃p�[�g�i�[�����s���邱�ƂɂȂ����B���͂��̑���A�Ƃ����V�l���Q���������|�𑁂����猾���o���Ă������̂������B�u�������ˁv��OK���Ă����B�N���u�̏W��͌��ɂQ��B���̂��тɁA�����̌v��A�H���̌v���{���͘b�������B�����{�v��̑ł����킹�A�ύX������B�Ƃ��낪�ނ͂ǂ����l�t�������������Ă����̂��A�W��I���Ƃ������ƋA��Ă��܂��Ă����B����Ȃ��Ƃ��R�炢�����Ă����B�ʏ킾�Ɛe�������Ԃ͋A�肪���ɋ������Ɋ�����������̂����A����ɂ��Q�����Ȃ��B�ނ������đł����킹���������Ɖ��x���v���Ă����̂����A�ނɂ����̈ӎv�͂Ȃ��悤�����A���ɋ@��Ȃ��܂܂ɎR�s�������Ă����B���͔ނs�����Ȃ����Ƃɂ����B�����������Ɂu���x�̌v��ɃL�~�s�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƁB�ނ͓��h�����悤�������B�u�ǂ����āA����Ȃɑ����\���o�Ă����̂Ɂv�B�u����A��x�Ƃ��Čv��̘b�������ɎQ�����Ȃ������v�B�ނ͂ӂĕ��ꂽ�悤�Ɂu�����ł����v�ƁB���̌�ނ͕䍂�̊�o��œ]�����ē��@���邱�ƂɂȂ����B�މ@�����Ɠ����ɑމ���B�����ɂ����A�ǂ����C�ɓ���Ȃ���A���C�̂Ȃ���ȂǁA��y�͓����Ă����K�v�͂Ȃ��Ǝv����B���̎��ɂ��Ă��A����ł��ǂ�����y�ɋC�ɓ���ꂽ�����������āA�����܂ł����B�����������n�肪����ȐV�l�Ƃ������A��y�ɍD����Ȃ��l�A�F�l�Ƃ��Ė��͂̂Ȃ��l�ɁA�Ȃɂ��������Ă����炪����܂�K�v�͂Ȃ��̂��B����Ȃ��Ƃ��v���o�����B���[�_�[���p�[�e�B�̍s���ɋC���˂��Ă��ẮA�낭�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ��B
������E�����J�E�J�V��[�w�J�@�P�X�W�Q�N�@�ā@
�@�O�N�̏�m�L������o�茳�N�������Ƃ���A����͂Q�N�ڂ̎R�s�������Ƃ������ƂɂȂ�B���[�g�}�ɂ͓����U���̍ō��O���[�h���t���Ă����������A�I����Ă݂�ƁH�̊��G���������B�{���ɂ���Ȃɓ���̂��ƁB���������̍��͖��N�̂悤�ɁA���̃g���b�R�d�Ԃɏ���Ă������ƂɂȂ�B�F�ތ��������āA�r���̍���w�ō~��āA�p���ɂȂ����O�������ɕ����Ė����J�ɒB�������̂��B���������̕ӂ�ɍs���Ɖ��̂��H���p�̃g���b�N�������Ă����肵�āu���������ǂ����炠�̃g���b�N�͓����Ă���v�Ƌ��������̂Ȃ̂����A�ǂ����z��������k���J�ɓ����Ă����悤�ŁA���Ǎ��̓_���ɂȂ��Ă���悤�����A���̍H���p�g���b�N�������̂��낤�B

�W�����v��Ԃŗ���̂U�����炢���z���āA���������̐ɒ��n�B
�@�����J�ł͂��炭�{����k�s���邱�ƂɂȂ�B�����������������Ă����ɁA�S���W���ő�̉��f�����x���łĂ����B�j���A�W�����v�Ȃǂ��낢��Z������̂����A���Ȃ��Ƃ����͓҂��j���Ƃ��͕ʂƂ��Ă��A�����쏰���痣���Ƃ��ɂ́A�K���U�C�����g���悤�ɂƍl�����B����͂����Ǝ���Ă����B�܂�j���悤�ȂƂ��낪�����ɂ́A�P�Ƃł͓���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�ł����ǂ͂���܂Ńg�b�v�ŗ����ꂽ���Ƃ͂Ȃ������̂����A����͊�o��̃U�C���̃g�b�v�Ŋ����������Ƃ��Ȃ��Ƃ��������ŁA�u�Ȃ�P�Ɠo�����ł���̂��v�Ƃ����ݖ�ƈꏏ�ŁA����͕s�\�ɂȂ�B���ꂪ�o�R�Ƃ������̂Ȃ̂��B

�Z�J���h�́A�U�C���ɑ̏d��C���āA���R�ɂ�����݂̊Ɉ���������B
�@�{���ł͉��x���̉��f�����āA�x���̃J�V��J�ɓ���̂����A��͂肻���ŋɒ[�ɐ��ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ƃ��A�����͂��c�O�Ɏv�����B������Ƃ����āA�ŏ�����{���̌v��͗��Ă��Ȃ��B
�@�x���̗l�q�͂قƂ�ǖY��Ă��܂����B�����������̑���h���h���z���āA�Ō�͐�k�̏�ɏo�āA�L���R�ɓo������͂��ł���B����ɐ����x���甒�n�x�֏c�����āA�����̏����ɔ��܂������Ƃ����͊o���Ă���̂��B�k�s�j���Ƀr�[���Ŋ��t������A���������K���K���ɒɂ��Ȃ��āu��������R�a�Ȃ̂��v�Ə����������̂������B���_���z�c�̏�ŃV�����t�ɓ���Ɓu�{���ɋC�����������v�Ƃ����Ă����B
�@���̎R�s�́A���ʂ̑�����̃X�e�b�v�A�b�v�݂����Ȃ��̂ɂȂ����B���ɂ��Ďv���ƁA���펞�ł��ꂾ�����ʂ�������o��́A�{���Ɋy�����B�����炢����㕔�̊�ǂ����h�ł��A���ʂ��̂��̂����Ȃ���͂��ꂾ���ŁA���܂薣�͂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂������̂������B�����͕̏ʂƂ��āA���ʂ̑��������Ōv�悪�����Ԃ����悤�Ȃ��Ƃ́A���̌���قƂ�ǂȂ������Ƃ����Ă����B����͍����̏㗬��≺����ɏ���قǂ̑�́A�����̂ǂ��ɂ��Ȃ����낤�Ƃ��������ł��������̂��B
���������x�@�P�X�W�R�N�R��
�@��l�ɂȂ��āi�P�W�Ή߂��j���߂Ă̂܂Ƃ��ȓ~�R�́A�A���o���̍ŏ��̃y�[�W�ɂ������A�V�V�N�P�Q���i�Q�P�j�̉�����������ܗ��x�o���ɂȂ��Ă���B����ȑO�ɂ͍��Z����̎R�x���ŁA�����ɔ����x�Ə�B�����x�B�R���ɏt�x�݂ɍc�C�R�Ɠߐ{�x�ɍs�������炢�ł������B���̉��������͒P�Ƃł̎R�s�������B�X�L�[��ŏ㕔����g���[�X�ɉ����ĕ����A�m�������悤�ȒP�Ƃ̏����Ɛ����ԓ��s�����悤�Ɋo���Ă���B�ޏ��͐������Ƀx�[�X���Ă���R�x��̍��h�ɒx��č�������Ƃ���炵�������B���������悤�ɂ��̏ꏊ�ɉėp�̃c�F���g�������̂������B�ޏ��ƒ��ǂ������ԕ������̂ł��邩��A����P�Ƃ̎������������̃x�[�X�L�����v�ɏ��҂ł����Ă����̂��Ǝ��͓��S���҂��Ă����̂����A�ޏ������̒c�̂ł͐V�l���ۂ��āA�҂��ɑ҂��Ă����V�l�̏�������̍����B���ȂǂɁA�Ê��̒j���������}����킯���Ȃ��̂��낤�B���R�̂悤�ɕ����Ă����ꂽ�܂܂������A�܂����R�Ȃ̂����B
�@���̓���ɉJ���~���Ă����B���������ȉJ�ʂ������B�~�̉J�Ƃ����͍̂ň��ł���B�����e���g���ɂ��݂Ă��āA����ւ��܂��ĐQ�Ă��邻�̎����̑̂̂Ƃ���ɐ����肪�ł��Ă���B�G�A�}�b�g���ו��ɂȂ�ƁA�e���g���̕~���͉��������Ă��Ȃ������̂��B�H�ѕ��𒅂ăV�����t�ɓ����Ă����̂����A���̂��ׂĂ����т����ɂȂ����B�����Ė钆�ɐk���Ėڂ��o�߂�B�w�����G���̂����₾��������A�������ɐQ��B����ɂ��ĂR�O�������ƁA���̉E�����₽���Đk����B��������ƍ��x�͔��Ό����ɂȂ��Ă܂��Q��B����ł��������Ƃ܂������ɖڂ��o�߂āA�܂����Ό����ɂȂ�B�Q���͐�����ɂȂ��Ă���B����Ȃ��Ƃ����Ē��ɂȂ����B�J�͂��œ܂�������B

�ܗ��x�`�L���b�g�Ԃ���̎������ݔ����B����ȂɃi�C�X�V���b�g�̎ʐ^���B���Ă������Ƃ��A�����܂Œm��Ȃ������B
�@�������ɖ��c�����A���͒��ɂȂ�ƁA�قƂ�ǂ��s�����J�n�����B�����ނ�̃g���[�X��ǂ��āA���x����Ő��̔����Ɍ��������B�����͐����x�݂̘A���ł����������G���Ă����R�C�S�O�l�قǂ�����鏬�����قږ������������낤���B��������R���܂ł͂Q���Ԃقǂ�����B���̓�����Ɍ��������̂������������̂��A�Ƃɂ������̎R�s�Ōܗ��x�̎R���ɂ͉^�ǂ������Ƃ��ł����B���̓r���Ɉ�ӏ���ǂ�o��Ƃ��낪�������B�U�C�����o���Ă���p�[�e�B������B����Ȃ̂ɁA������O�����ɕ����ĉ��R���Ă���l������B��̋}�X�Ƃ����̂́A��͂肢��Ȃ��̂��B����������l�ʂ�������B�Ƃɂ������̃p�[�e�B��ǂ��Ă����Ύ��R�ɒ���ɏo��Ƃ����A�܂����Ղȓo�R�ɂȂ����B
�@���ォ��̉���̂�����Ƃ������ł́A�o��q�Ƃ̂���Ⴂ�̂��߂ɏ��ԑ҂��ƂȂ�B����ɒ��ɂ͂P�O�l���炢�̒c�̂����āA��l�̎��͏��ԑ҂��̊ԂɁA���R�Ƃ��̒��Ɋ��荞�ނ悤�Ȃ��Ƃɂ��Ȃ����B�u�������Ď~�܂��Ă���Ƃ��ɂ́A�葫�������ɂȂ�₷������A��������Ďw�擮�����Ă��Ȃ��ƃ_���������v�ƁA���̃p�[�e�B�̃��[�_�[�������B�u�͂��A����Ȃ��̂ł��ˁv�ƁA���������o�[�ƈꏏ�ɃI�[�o�[��܂̎w���O�[�p�[����̂������B�t�[�h�����Ԃ��ăT���O���X�����Ă���ƁA���������o�[�̈�����Ǝv��ꂽ�̂��낤�B���Ƃ����āA������őтł͓�������ȂNJ�p�Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ��B����Ɍ�̐l�������A���̂��ƃ����o�[�̈�����Ǝv���Ă���B�ł����������������邱�Ƃ��A�Ȃ��P�ƂɂƂ��ẮA�S�����Ƃ������͖{��̕������������̂��B
�@��̋}�Ȑ�ǂ̉���ł́A���̃p�[�e�B�̓U�C�����o�����Ƃɂ��Ă����悤���������A�������ɂ���ɉ����̂͂��������āA�T�d�ɃN���C���_�E�����Ă������B�����ł͂P�����������A�Q���������ǂ����͖Y��Ă��܂����B���͂��̎R�s�Ɏ��̓U�C�����g�s���Ă����̂ł���B������ɏ������悯��Ύ��������ʂɏc���ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ����A�W�����҂�����Ă����̂��B�ĂȂ炻�����ʃ��[�g�Ȃ̂�����B�L���b�g�łP�����~������ƁA����̓K�C�h�œǂ�ł����̂����A���̂��߂̃U�C���ł���B�������ܗ��̒��㉝���ɂ���͎����Ă����Ȃ������B���x���x�̃g���o�[�X�ɐT�d�������Ȃǁu�~�͎v���Ă���ȏ�ɂނ��������v�ƁB����ɏ�������o������p�[�e�B�́A�قƂ�ǂ������v��̋�g�Ȃ̂ł���B�Ƃ������Ƃ́A��͂莭�������ʂ͑����ɓ���̂��낤�Ƃ������ƂŁA���҂͂������藠��ꂽ�B
�@���̌�x�[�X�ɖ߂����B������ςȂ��ɂ��Ă����c�F���g�͐ϐ�Ŕ������܂��āA�ւȂ��傱�ɕ���Ă����B�s���ɓ��s���Ă����������A�u���炭�i��͂�Q�����炢���j�߂��Ă��Ȃ��������A�S�z���Ă��܂����v�Ƃ������B���҂��Ă���Ȃ��Ă��A�C���炢�g���Ă������Ȃ��ƁB�u��̏����ł�����肵�Ă�����ł��v�B
�@���ꂩ�琔�N������͂萳���x�݂ɁA���x�͂R�l�œ������[�g�ɂ����B��������������̎R�X�L�[�łR�l�p�[�e�B�œ���B���͎������̑���J�N�l�����ʂɍs���Ă݂��������̂��B�Ƃ��낪�r��̏o���܂ł��������ǂ����B������Ȃ��Ă����̓n���X�L�[�𗚂����܂�GO���Ă��܂����̂��B���Ԃʂ�B�V�[�������Ԃʂ�B����Ȃ��Ƃ������Ă����͂����Ȃ��B���Ɉ�������ꂽ�����o�[���u�����߂�܂��傤�v�ƑS�R���̋C���Ȃ��B�����������āA���������ɓ]�i�������̂������B���̂Ƃ��́A�Q�����f�ŏ㕔���炢���班���V�[���œo�������̂́A����܂ȃX�L�[�̓f�|���āA��͂�g���[�X�ɏ]���Ĕ�����o��A�Ő��ł͏����O�ɂ������ᓴ�𗘗p���āA�܂��ܗ��̒���ɂ������B���̂Ƃ��Ɏ��������ʂ̓�����݂��̂����A���ꂪ�S���Ȃ��B�u�~�ɂ������ɍs���l�͑������Ȃ��Ȃ��v�ƁB���̂Ƃ��Ɏ����Ă������X�L�[�́A�ȍ~�R��قǂ����g��Ȃ��āA���̎R�X�L�[�̓Q�����f�ŗV���Ƃ̕��������������炢�ł�����B

�L���b�g�����͐������ϐ�̂��߂Ɏg�p�s�B���̘e�Ƀe���g���Ĕ��܂�B
�@�������ɂ͂Ȃ�ƂȂ�����Ǝ����͂������̂����A���܂�ɂ����R�Ƃ��Ă��Čv�搫�Ɍ����Ă����B
�@�����Ă݂�ƍŏ��̉����������炱�̂R���̎������܂łT�N�قǗ����Ă���B���̊ԂɎЉ�l�N���u�œ~�A�T���̌o�������킹�ĂP�O����x�߂��������ƂɂȂ�̂��낤���B�T���̖k�������ɂ������̂́A���̒��Ԃ��炢�ɂȂ�W�O�N�̂��Ƃ������B
�@���ĂW�R�N�̂Q�l�ł̎R�s�́A�v�����͑��_�̂��̂������B�W�O�N�T���̖k�������ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��ނ��������A�ȍ~�ɓ~��o�肾�����A��ɉ�Œ��N�`�[�t����邱�ƂɂȂ���S�Ƃ̃p�[�e�B�ɂȂ�B
�@�ߔN���߂Ă��̔ނƂ��̎R�s�̂��Ƃ�b�����̂����A�u�p�[�g�i�[��������Ȃ��Ă��P�Ƃł��̎R�s������Ă����Ǝv���v�Ƃ����̂��B�O�N�ӂ�ɁA���n����̗Ő����g���[�X���Ă����悤�ŁA���̑����̎R�s�������Ƃ����̂��B�ړI�������Ă������̂͐i���������B�����Ď��Ƃ����A�~�͍��h�ɂ��Ă����������قƂ�ǂɂȂ��Ă���B
�@�v���o���Ă݂�ƁB�W�O�N�̂T���̖k���́A���̑O�̐���̃`�[�tK�̍Ō�̎R�s�������悤�ȋC������B�������Ă��̂W�R�N�̎������́A��y�ł���̂������̐���̃`�[�tS�Ƃ̎R�s�������̂��B�v���o���Ă݂āA�ϐ���Ɋւ��Ă͂��̓�l�̃`�[�t�Ɍb�܂ꂽ�����A�����̎R�s�ɎQ�����āu���������Ƃ�����v�����Ă����̂ł���B�����ނ�Əo���Ȃ������Ƃ���A����͐ϐ�������o���ɏI����Ă�����������Ȃ��̂��B��y�ƌ�y�Ɍb�܂ꂽ�Ǝv�킸�ɂ͂����Ȃ��B�����Ōv�悵���̂́A�����̐ԐΊx����r��x�̓�A���v�X�ƁA�����悤�ɐ����̏�O�x���琼�����������Ȃ̂ł���B�`�[�t��֎����̃����o�[������Ȃ��������̐������h�Ƃ������ƂɂȂ낤���B���̒��x�����̎R�s�ɏI����Ă����Ƃ�����A�߂����ϐ���̌o�������ɏI����Ă������̂��낤�Ǝv���B
�@�����A��͌b����ŏW����s���Ă����B���̋i���X�ŁA�ނ����̎������̌v��������o�����B�Q���������Ǝ��͂����ɔ�������B����͂R�����{�̘A�x���͂����āA��莞���������A�P�O�����̓����������B���̎������C�ɓ����Ă����B�u�g���[�X�̂Ȃ��ϐ���ɓ����Ă݂����v�Ƃ����v�������͑O���炠�����̂��B����ɂ�͂�p�[�g�i�[���ނł��邱�Ƃ��A�S�����B
�@���R�͔����������炾�����B�K�X�̂Ȃ����A���ёт���Ǝ��ɂ������Ȃ��Ő��ɔ�яo���āA�~�G���������������B�N�����Ȃ��B���̏����̒��Ƀe���g���ĂQ�������B����ڂ����V��Œ�������Ƃ��o���Ă���B���ė����A�c�����n�܂�B
�@�ܗ��x�ɓo���������Ƃ͂����Y��Ă��܂����B���͂������玭�����Ɍ������Ő��ɓ����Ă��炾�B�����Ȃ�}�Ζʂ̉��~�ɂȂ����B�~�R�̋Z�p�̍����ł�B���_�͑O�����ō~��Ă����B���͍ŏ��N���C���_�E���̎p���ɂȂ����B�u���O�A�m��Ȃ������ɂȂ��܂��Ȃ����Ȃ��v�Ǝv���B���ꂪ�������B���ꂩ�牄�X�Əc���͑����B�N��ł͂Q�C�R�Ώ�̔ނł��������A�N���u�ł͎�����y�B���������W�������猩��Ɣ����ɂ������̂ŁA���݂��C���˂Ȃ��V�C�̂������͏���ɐi�ށB������Ƌx��ł���Ɓu����A��ɂ����Ă邩��v�ƁB�u�����A������v�B�ォ��s�����̂͊y�ł���B��ɂ͔ނ̃g���[�X���c���Ă��邵�A�ނ͎�������Ɉ�l�ŕ��������Ƃ����C���������������̂��낤�ƁA���ɂȂ�Ǝv����B������őтł́A�g���[�X���Ȃ��킯�ŁA�Ȃ��Ő��Ɖ��̊������ƕʁX�̃��[�g��ʂ����Ƃ����������悤���B

�L���b�g���������~������ɁA�k���̃N�T���ꂩ���g���o�[�X���n�܂����B
�@�ߌ�ɂȂ�Ƃ��������ɔ��Ă����B���A�����x���o�����Ă���̂�����A����Ȃ��̂Ȃ̂��B�L���b�g�ɓ���Ƃ��ɁA������Ə����Ȑ�݂����z����Ƃ��낪�������B�Ă����͂����ŗ����~�܂���Ȃ��Ȃ�B��ɃL���b�g�̓~�G�����ɒ������ނ́A�x�����Ɍ������āu���[���A���[���v�ƂQ�C�R�x����ł���B���ĕԎ����ł��Ȃ�����������Ɂu�Ȃ��`�v�ƁB�u�ǂ������H�v�u��ꂽ���`�v�B���̂���肪�A��ɏ��b�ƂȂ����B�S�z���Ă����ނ́A�ق��Ƃ����Ɠ����ɁA����Ă��܂����̂��낤�B
���̎������Ɍ������Ő�����B�����ʐ^�ɁA�Ƃ��Ă��ꂢ�ɒݔ������ʂ��Ă�����̂��������̂́A���߂ċC�������B�l�̎ʂ��Ă��Ȃ��R�̎ʐ^�Ȃǂ܂�Ȃ����̂������̂����A�����̃A���o���̒��ɂ���ȑf���炵���ʐ^���������Ƃ́B�p�[�g�i�[�ɂ��čs���������̎R�s�ł́A�������Ă��܂������Ƃ��A�܂����ɑ������̂������B
�@�����͐��Ⴉ�ꂽ�B����ł��L���b�g�Œ����킯�ɂ͂����Ȃ��B����̒����o�����A�܂��Ȃ��L���b�g�Ō������~���A�ȍ~�͍��܂ł̑僉�b�Z�����Ζʃg���o�[�X���P���������āA�ǂ��ɂ��ݔ����̕��R�n�ɗ[�������̂��B���̃��[�g�́A�Ă̌o�����Ȃ��B�ނ͂ǂ��������̂��낤�A���������Ƃ��Ȃ������B���x������Ƃ��ɕ����Ă݂悤�B�k��Ζʂ��㕔�܂œo�肷���čs���l���ĉ��~������A���̉��~�ł��A���U�C���������܂܂ɂȂ�B������U�C���͂����ςȂ��B�X�^�J�b�g�Ńg���o�[�X���Ă������Ԃ����������B�悭�������Ȃ��������̂��Ƃ����̂́A���ɂȂ��Ďv�����ƁB�����������悤���Ȃ��B�����������͒������̂Ȃ̂��H�s�����Ă������̂��H�@�����N�ł��s������B�^���悩�������ƂɂȂ�B

������o���̑�f�u���B����Ȃ̌����̂͏��߂Ă������B���������f���Ă����p�[�g�i�[�B
�@�ݔ����e���g���̗����͉����Ɍb�܂ꂽ�B���̓o�肪���������}���������Ƃ��v���o���B�s�b�P���̐Εt���͕s�v���B�s�b�N�������肪����ɁA�A�C�[���̑O�܂����œo�����B�N���X�g���Ď��ɋC�����̂����Ζʂ������B���Ƃ͒���̋L�O�ʐ^�ƁA���X�Ɨ�r�̏����܂ŁB�����̉������琅���|�^�|�^�H���Ă����̂́A�����������؋��ł���B���l�̓o�R�҂Ƃ����������B�����Ԋ�����̉��肪�A��ʃ��[�g���ƌy�����Ă������ɁA�Ă������Ă��܂����̂��B�Ő����炢���Ȃ艺��Ζʂ͂����B���������ɂ̓g���[�X���������B�P������邾���ŁA�K���l�C���[�g�ɂ͓o�R�҂��o�v���Ă�����̂��B���N�̏t�ɖk�ҒJ�ɂ����Ďv�������ƂȂ̂����A�����͈�ʃ��[�g�Ƃ͂����Ă��A���̌X�̓o���G�[�V�������[�g�Ƃ܂����������ł���Ƃ������ƂȂ̂��B�����n�}�ɐԐ��������Ă��郋�[�g�͂��ꂾ���ňՂ����Ǝv�����݂����Ȃ̂ł��邪�A�ϐ���ɂ͂���͑債���Ӗ��������Ȃ����̂��Ƃ����̂��A���N�����������Ƃł�����B�������ĐԊ�����������Đ�����o���ɒ����B�Ƃ��낪�����͖k�ҒJ����̑�f�u�����҂��Ă����B������ȃf�u���������̂��A���ꂪ���߂ĂɂȂ�B�V���[�N���[���̃A�C�X���������悤�ɁA��k���g�ł��Ă���B��N���̃f�u���̂��Ƃ����́A�Y�ꂽ���Ƃ��Ȃ��B���������Łu���Ă͂����Ȃ��ꏊ�ɂ��Ă��܂����v�Ǝv�������̂��B���������i�C�[�u�����A����Ӗ��ŗc�t�ŏ��ɓI�Ȏp���ɂȂ��Ă����B�ʂɌ��邾���Ȃ�N������͌���Ȃ��B�������ϐ���̒J�ɓ����Ă͂����Ȃ��Ƃ����ÓT�I�Ȋi���́A�f�u��������Ƃ���ɂ��s���Ă͂����Ȃ��Ƃ����Ӗ��ɂ��Ȃ�B�����Ƃ����v���Ă����B
�@�Ă̑D���������̂ɁA�~�ɂ͂������ΓI�ɉ�����Ă������ƁB���̎������瓦���ꂽ�ŋ߂ɂȂ��āA�悤�₭�R�X�L�[�̊y������������悤�ɂȂ����B�ߋ��̃g���E�}���瓦���Ƃ������Ƃ́A���Ԃ̂����邱�ƂȂ̂��B
�@���̎������͐ϐ���̍ō��̎R�s�ɂȂ��Ă���B���N�U���A���̎R�s����Q�O�N�������Ă���̂����A���Ȃ��Ƃ��玭������k�ҒJ����ēo���邱�ƂɂȂ����̂��B���̖k�ҒJ���i�C�X�E�N���C�~���O�ƂȂ����B�����������A�Q�O�N�O�̂R���̎����������������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�Y����Ȃ��R�s�Ƃ����̂́A�o�R�ς�L���ɂ��邱�ƂɂȂ����B
�J��x�E��m�q��E����O�X���u�@�P�X�W�R�N��
�@�Q�O�Α�㔼�̂��̍��́A�Ă̊�o��ɍł��[�����Ă����Ƃ��ł͂Ȃ������̂��ƁA���߂ăA���o�������Ă���Ǝv���Ă���B�p�[�g�i�[��S�Ƃ͓����œ���ĂT�N�ڂƂ����Ƃ��낾�����B�ނƂ͂���ȑO�ɂ����x�̃`���l�A���̖����R�Ńp�[�e�B��g���Ƃ�����B�W��̐ȂŁu��O�X���u�ɂ�������A�N�ł��������Ljꏏ�ɂ����Ȃ����v�ƗU��ꂽ�B�������₾���ɏW�����Ă����ނ͓����͐�D���̂悤�Ɍ����āu�Ƃɂ����N�ł���������A��čs���Ă���v�Ƃ����Ă����B���͂��̃��[�g�ɘA��čs���Ă�������̂ł���B
�@�����̊�o��̂��Ƃ𐳒��ɍ�������ƁA���߂Ĉ�m�q���o�����̂́A�N���u�ɎQ�������N�̂U���̒����łƂ������������̃��[�g�������B�����Ă��̂Q�C�R�T��ɁA��������̑S���[�g�̓o����ڕW�ɂ��Ă����Q�N��y���A�����̊x�l���[�g�ɂ����̂��ƃp�[�g�i�[��T���Ă����Ƃ����������B�����x�l�N���u���J�����[�g�ł���B���܂��ܓs���̂������肪���Ȃ������肵���悤�������B�u�L�~�̏T���̗\��́H�v�ƕ�����āu���͋Ă��܂�����A�ǂ����A��čs���Ă����Ȃ�A�ǂ��ɂł��v�ƁB�u�V�l�����H�ł��܂��������v�ƁB�������Ĉ�m�q��̂Q��ڂ̌o���ŁA�����͍œ�ւ���A�����ł��ł�����U���̃��[�g�ƏЉ��Ă�������́A������Ղ����Ȃ��x�l���[�g�Ƃ������ɁA�t���čs�����ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł������B�u�܂��A�V�C���悯�����Ȃɓ�����Ă��Ƃ��Ȃ�����v�B

����̑����Z�J���h�ŕt���čs���B
�@���̌�̔ނ̋L�^��ǂނƁA�ނ����N�O�Ɏn�߂Ĉ�m�q�ɓ������Ƃ��ɁA������Ƃ����L���ȑ������ŋN�����āu�ނ�̎c�u�����U�C�����A��ǂňٗl�ɐ��ꉺ�������܂܂ɂȂ��Ă����v�Ə�����Ă���B�����������i��ڂ̓�����ɂ��Ă��A�ނ̖ڕW�͏���ɓ����T�{�������S���[�g���g���[�X���邱�Ƃ������������B
�@���̓��̓o���́A���T�����ɏo�����ŗ��������āA�ނ��Q�{�����Ă����U�C���̂P�{��S���ŁA�قƂ�Njx�ނ��ƂȂ���k����e�[�����b�W�𒆉��Ńo���h�܂ŏオ�邱�ƂɂȂ����B�����œo���̗p�ӂ����āA�ނ̓R�s�[�������[�g�}�ƌ���̊�̗l�q������t����T���Ȃ炪�A���͂����ƌ�ɂ��Ă����B�S�U�s�b�`�قǂ̃��[�g�͂��ׂĐ�y�̔ނ��g�b�v�����[�h���A���͌ォ��t���Ă����B�r�������̐l�H�o�����������̂����A�Z�J���h�œo���Ă����Ԃ�ɂ́A�܂����Ƃ��Ȃ����B������ǔ����炢�܂ł���ƁA�������ɍ��x�����o�Ă���B���₪�قƂ�ǐ����ɐꗧ���Ă���Ƃ����͖̂{���̂��ƂŁA�������牺�̎Ζʂ��A�`�����܂Ȃ�����͑S�������Ȃ��B�܂�̑S�̂��ɒ���o���Ă���悤�ȍ��o�ɂƂ���āA�^���ɂ͏��X���u�̂��̔������ɌX�Αт̒J�ꂵ�������Ȃ����̂Ȃ̂��B���̍��x���̋��|�S�ŏՓ��I�ɂ��̏����Ȋ�̃X�^���X���o�������C���ɏP����B�����������h�����C������}���邱�ƂɁA���_�I�ɔ�ꂽ���̂������B�����Ԃ��ꂻ���ȋC���́A�@���Ƃ����������B��ÂɁA��ÂɁE�E�E�Ƃ����킯�ł���B
�@�ǂ̒������炢�܂ň�C�ɏ���āA�����ňꏏ�ɋx�e���Ƃ�B�ނ������S�������Ă��āA�������������B�ꑧ�������ƂɂȂ����B
�@�S�ʓI�ɐ�y��M�����Ă���A�����̓o���͂Ȃ�Ƃ��Ȃ邾�낤�B�u������y���v���I�ȃ~�X��Ƃ��Ă��܂����ꍇ�ɂ́A����͈ꋓ�ɋ��|�ꂵ���Ȃ��Ȃ��v�ƁA�r���Ŋo������߂��B��o��Ńp�[�e�B��g�ނƂ����̂́A�����������ƂɂȂ�B
�@�㔼�̊�o��́A�����O���ŋ��|�ɑ��Ă͊�����q�ɂȂ��Ă��܂����̂��낤���A�J��x�ł͗L���ȓD�̑��t���e���X���A�D���ƑS���O���O�����Ă���̂����A������x���Ȃ����������Ă��܂����肵�Ȃ���A�Ȃ�Ƃ��I���_�܂œo������B���ۂɂ͂T���Ԓ��x�̓o���������̂��낤���B���~�͖k�ł��������~�����B���̂Ƃ��ɂ��A�U�C���̌��іڂ̈ʒu��A����̕��@�ȂǁA���������A�h�o�C�X���Ȃ���~��Ă��������̂������B�܂����邢�����ɗ]�T�ʼn��R�ł����B
�@�����̓t���[�N���C�~���O�̃u�[���͎n�܂��Ă����̂����A����ł��u�y�؍H���v�Ɲ�������Ă����l�H�o���̃��[�g�ɍō��O���[�h���^�����Ă����B������̈�̂����������[�g���������g�b�v�œo��Ă����A�{���̐����Ƃ����Ă����̂��낤���A�t���Ă����ēo�炳�ꂽ�����ł��A��͂肱�̓��̓o���͎����������Ȃ����B�����ЂƂ�ŋ��ɔ�߂Ċy���ނƂ����̂ł͂Ȃ��āA�����������Ȃ����Ƃ��A����͂܂����������ł��Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B�u������̏����o���Ă݂܂����H�v�Ǝ��₳���ƁA�u�������A���̂P�����ł�����������ł��v�Ƃ����̂������ȓ����Ȃ̂��B�}�X�ŕ|�����ƁB����Ƒ��l���ߋ��ɖ��ߍ��{���g�ɂ��Ԃ݂��|���鎖�ɁA�ǂ����Ă���a�������������ƁB����ɂ��������s�ׂ��A���{�ōō������N�̊�o��ł���u���ꂩ�璷���l����o������Ă������Ƃ��Ă��A�O���[�f�B���O�́A�K�����̏���̉��ʂɃ����N������̂���Ȃ̂��낤���v�Ƃ����˘f���B�Ȃ܂�������[�g��o���Ă��܂������߂ɁA�O���[�f�B���O�̕��Q�������Ɋ����āA�����ŏ����s�ǂ��N�����B���낽���Ă��܂����̂ł���B�����������Ƃɓ������o�Ȃ��܂܂ɁA���̌��щz���Ă��܂������ԂɈʒu���郋�[�g���̘A���̓o��n�߂邱�ƂɂȂ�B��ŁA�G�X�q�≚���ǁA�ό`�`���j�[���[�g�E�E�E�B�P��P��̓o���͑f���炵�����̂Ȃ̂ł��邪�A�ǂ����Ă������f���Ɏ�����Ȃ��B�u�ǂ������̏���ȉ��̃��[�g�ł����Ȃ��v�B�Ȃ�Ƃ��c�p���������̂��ƁA���v���B�O���[�h�Ȃǂ͑��l���t�������́A�����ł����Ɗ��������̂�f���ɔF�߂�ƁB���t�Ō����͈̂Ղ����B��������o��ɔM���Ȃ��Ă���Q�O�Α�̏��m�����́A���[�g�̓�Փx��ӖړI�ɐM���Ă���A����Ȃ̂��B���l�����O���[�h�̍������[�g��o�����҂��A�D�ʂɗ��B�����̋����S�ɗD�t���B����Ȕ������C��������A���̂Q�N��Ɏ��͑��X�ƁA�ό����s�̃`�����X���܂߂āA���Z�~�e�ɂQ�O���قǑ؍݂����̂��B
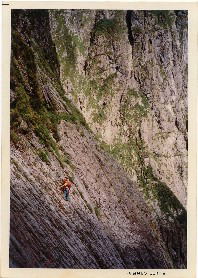
�X���u�̃g���o�[�X�B�i�F���f���炵������B
�@�������Q�O���ԁA��������P�T�Ԃ̃��Z�~�e�̌��ŁA��o�肪���܂��Ȃ�Ƃ��v���Ȃ��B�A�����āu������[�g�ɂ����Ă݂悤�v�ƃ��Z�~�e�̃p�[�g�i�[�ƁA��Ńt�����P�Ƃ�����m�q�ł͒��̏キ�炢�̃��[�g�Ɏ��t�����B�����������́A�₪���낵���Ƃ��̂��B���ނ�����{���{���ƕ���Ă���B�Q�s�b�`�o���āA���͑��X�ƒ��߂ĉ��~�������C�����ɂȂ����B���_�́u���������Ȃ̂�����A������Ƃ���܂Łv�Ƃ����̂����A������Ȃ܂��������E��R���f�B�V�����̃��Z�~�e��m���Ă��邾���Ɂu����ȃ{����̈�m�q�ȂǁA��o��̑ΏۂɂȂ�Ȃ��v�ƌ������āA���̓��̓o������߂Ă��܂����B����ꍇ�ɂ́A�ڂ낭�ĕ���₷������x���Ȃ���o��Z�p���A�K�v�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B�������u��m�q��o��v�Ƃ����ڕW�Ȃ����͕K�v��������Ȃ��̂����u���K�Ȋ��o��v�Ƃ����ݒ�ł́A��͂��m�q�͂��̑Ώۂɂ͂�����Ȃ��ꍇ���������̂��B�u�A�����J���Ԃ�̑�n���ҁv�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ��������̂��B
�@�����̈�m�q�̓V�[�Y�����͑�l�C�œ��R�҂����������B�ɒ[�ɂ����A�V�C�W���̏T���ɂ́A�K���P���͑���҂��o���Ƃ������Ƃ��������B�N�ԂɂQ�O�l�ȏオ���̈�m�q�Ŗ��𗎂Ƃ������Ƃ�����B����T���̑����ɁA������悤�ɓ��R���鎩���������܂߂��o�R�҂��݂āu�����́A���̂Ȃ��ŒN����l�����ʌv�Z���Ȃ��v�Ƃ����āA�����Ă����B�m���Ɍ��Ă��Ă���Ȃ��������A����������ł�������̂��B���t���ɍs���܂ł̃e�[�����b�W�Ƃ����ꏊ�ŁA�������U�C�����o���Ă���p�[�e�B������B�u����ȂƂ��ŃU�C���o���悤�łǂ�����́H�v�B���N�̌o����ςނƁA���������������͂܂��ɓI�Ă��邱�Ƃ��Ǝ����ł��悤�₭�������Ă���B���V�l�̗{���Ȃ�Ƃ������A��ʂ̃p�[�e�B�ł���Ȃ��Ƃ��Ă��ẮA���̐�̓o�����v���������̂��B
�@���G���Ă��钩�̓��R������āA�O�̓��ɓ�Ńe���X�Ƃ������t���܂œ����āi�o�������P���Ԕ��j�����Ńr�o�[�N���āA�����͂P�ԂŎ��t�����Ƃ������Ƃ��������B���邢�͐^�Ă̂��~�x�݂̍ŏI���̗[���ȂǁA�����قƂ�ǂ����R���Ă��܂������ƂɁA�G�X�q�X���u����X���u�ȂLj�ʂɂ͗��̒ʂ蓹�Ƃ��Ĕ������Ă���ꏊ���A�����ēo���~���Ă݂āu����͉��K����Ȃ����v�Ɗy�����Ƃ��������B�u��m�q�̓o���͂�������ׂ����v�Ƃ�������ɁA�����ċt����Ă݂������ł�����B����A�{���͊�o��ɒ���Ȃǂ���킯���Ȃ��B�����Ŕ��f���Đ������Ǝv�������Ƃ����s���Ă݂���̂��B�_���Ȃ�Έ����Ԃ��B�Ƃ��낪���ꂾ�����ԑ҂��ō��G���Ă�����m�q�ł́A�r���܂ł����Ĉ����Ԃ��Ă��܂��ƁA����͏��Ԃ̍Ō�ɂȂ��Ă��܂��̂��B����́A���̓��̓o�������łɎ��s�������Ƃ��Ӗ�����B�o�[�Q���Z�[���̔������ɎE������悤���Ȃ��Ƃ��A�����̈�m�q�ł͌J��L�����Ă����̂ł������B

��O�X���u�ŏI�s�b�`�t�߁A���̂��Ə��������Ă���h�[���̓o���ւƑ����B
�@���̂悤�ɁA���������̎d�����ς���ė]�T���ł��Ă���A�ÓT�I�ȃ��[�g�Ƃ�����A�O���[�h�͒��̉��̃����[���[�g�ɂ������悤�ɂȂ����B��o��̉��������̈�m�q�ł�����Ă݂�Ƃ������Ƃł�����B�{�J�̎l�����[�A�O�����[�A���[�B�A���t�@�����[�E�E�E�B�G�X�q���ǂ�o���ĉG�X�q��ɏo�Ă��u�������炸�ɖk�ł���~��悤�v�Ə��̓��܂ʼn��~���悤�Ƃ������Ƃ��������̂����A���̉G�X�q�����̉G�X�q��Ə��̓��܂ł�����قǕW���������邱�Ƃ����̂Ƃ��ɏ��߂Ēm�������Ƃ������B�����������邭�炢�ɐ^���Ɍ������B�܂��l�����Ȃ��Ƃ��ɂ́A���̓�����R�b�v�X���u�ɍ~��āA���̂܂܃X���u�����~�������Ƃ�����B����͐�k�ɔ�шڂ�Ȃ����Ƃ������̂����i��k�̕������j�A�G�X�q�X���u�̕����Ƃ܂��܂���k�ɔ�шڂ�邱�Ƃ����������B��͂肱�̒J�͒m��Βm��قǖ����o�Ă���B���ꂾ���̕X�͂̒J�̂Ȃ������R���݂ɕ����܂���̂́A���̑�J�ł����ł��ł��Ȃ����Ƃ��B�䂪�N���u�̉�̎��c���u��m�q�͐��E��̊�ǁv�Ƃ������A���̈Ӗ��������������肩���Ă����B
�@���c�͈�m�q�ɑ����P�O�O��ȏ���R���Ă���B�u�������Ă������v�u���x�o���Ă������v�Ƃ����B���������A�J��x�̈�ʃ��[�g����R�O�O�O��߂�������֓o���Ă���I�W�T��������B���������C���������ɂȂ��Ă悤�₭�����肩���Ă����B�u�P��o������Q�x�Ɠo��Ȃ��v�Ƃ����Ă���l�́A�܂��܂����n�҂Ȃ̂ł���B��m�q��Ɣ�ׂāA�ł͗Ⴆ�Α����x���������Ƃ��悤�B��m�q�ɂP�O��o���āA�P�P��ڂ��炢�ɑ��ɓo�邱�Ƃł���͂��傤�ǒ��a����ƌ��������邱�Ƃ��ł���̂��B���̎��ɂ܂��P�Q��ڂ���Q�O��ڂ܂ň�m�q�ɒʂ��āA�Q�P��ڂő��ɍs���Ƃ����Ӗ����B�y�����̃o���G�[�V�����𑄃��x�̂P�O�{�����Ă���̂��A��m�q��ɂȂ�B�哇���g�́u�߂��Ă悢�R�Ȃ�v�́A��m�q�̓��R�҂����Ȃ��Ȃ������܂����A�{�̂�����B
�@���đ��̑�O�X���u�̓o���͂���ȂƂ��̌v��ɂȂ����B�����ڍׂ͂Ƃ����ɖY��Ă���B�ł��p�[�g�i�[�ƂȂ���������S���B���Ă��ꂽ�ʐ^����������c���Ă���Ƃ������Ƃ́A���̓J�����������Ă������A�ނ͂��̎R�s�ɖړI�ƈӎv�������Ă����̂��낤�B����Ƃ���͔ނ��g�b�v�������B���łɓ�����D���̔ނ́A�����ƂȂ����玩���ł��ׂĂ���Ă݂���Ƃ����Ă����قǂ������B�ނ������^���C�œo�������A���Ȃǂ̓w�����b�g������Ă��Ȃ��B����Ȃ��̂͐ϐ���̂��̂��ƁB
�@��O�X���u�́A�ߋ��ɂ�����ł��b��ɂȂ������[�g�ł�����B�����ŕӂ肩��݂�ƁA�����������Ă���B����قǃs�J�s�J�Ɍ�������͍����̂ǂ��ɂ��Ȃ��ƌ������Ă����B������o���Ă���Ǝv�������ŁA���ȓ����̂悤�Ȃ��̂��B
�@�������̓��ɂ́A�ߌォ��J�͗l�ɂȂ��āA�Ȃ�ǃh�[�����P�s�b�`�o�����Ƃ���ŁA���Ԑ�ɂȂ��Ă��܂��A�������͗[���Ɨ��J�̂Ȃ����A�r�o�[�N������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂����̂��B���̓o������x����������������B�u���傤���˂��Ȃ��A�܂��r�o�[�N�Ȃ̂���v�B�ނ͂��̃V�[�Y���ɂ�͂�N���ƈ�m�q�ŁA�r�o�[�N���Ă��܂������Ƃ��������悤�Ȃ̂��B���j�̖��f�������̉ĂɂQ��ڂ��Ƃ����Ă����B
�@�ł����ƂȂ��Ă͂��������v���o�ɂȂ�B�Ƃɂ����A�ߋ��U�O�O�l�̑���Ƃ������E��̐����̒J��x�̂��̑唼�̐l�������Ŗ��𗎂Ƃ����B�ȒP�Ɏ��t���銄�ɂ́A���g�͂Ƃ�ł��Ȃ�����Ƃ����킯�ł���B�G�ꂽ���t���Ƌt�w�̃X���u�B�ǂ�ȃx�e�����ɂł��A�ْ���������B�t�Ɍ����A��m�q��o���A�䍂���������ɈՂ����̂��B����͖{���̂��Ƃ��B�����߂��ɂ���̂ɁA����͗D�������u���h�[����S�[���f���ł͂Ȃ��āA�쐶�̃n�X�L�[��b�㌢�Ƃ����T�݂����Ȃ��̂��A���̒J�ɂȂ�B����̉���q�̃I�o�T�����A�^�N�V�[�����č��ł����̏o���ɂ͌��w�ɒ��Ă���B����ǎ������́A��ɋْ����ƑΛ�����悤�Ɉ�m�q��Ɛڂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
��A�ԐΊx�E�ԐΑ�`���k��@�P�X�W�S�N�@��
�@��ʂ̎��Ƃ��o�āA�b����̃A�p�[�g�Z�܂����n�߂��̂��A���傤�ǂ��̉Ă������̂��v���o���B���̂����������ĂŁA���Ƃ̎����̑��g�t���̃G�A�R�������ɍs���āA�}篂��̃{���A�p�[�g�Ɏ��t���āA�ǂ��ɂ����̉Ă����̂����L��������B����ȂƂ��̎R�s�ɂȂ�B���̂����̃p�[�g�i�[�ƁA�V�l�œ����������A��Ă̂R�l�̎R�s�ɂȂ����B�ǂ�ȐV�l�ł����Ă��A���s�����邭�炢�͊ȒP�Ȃ��Ƃ��ƁA�����������M�͂��������̂��B���̂Ƃ����N���}�ő���ѓ��̉��܂œ����āA�قƂ�Ǒ�̎��t���ɒ��Ԃ����͂��ł���B

�ԐΑ�A�����̃S���W��
�@��ɓ����Ă܂��Ȃ��A���ɒ��������ƂɂP�O�l���炢�̑�p�[�e�B��ǂ��������ƂɂȂ����B��Œm��̂����A�������؍��̗F�D�o�R�p�[�e�B�������������B
�@�ŏ��ɂ������̓҂╣��ʉ߂�����ɁA�j�S���̑��ɏo��B�����̒J�Ǝ�l�q���Ⴄ�̂́A���̑��ӂ�ł���̗��ꂪ���������}�X�ŏオ���Ă������Ƃ������B����ɐ��ʂ�����B�u�傫�ȑ�Ƃ����Ă��A�������͉��ɗ���Ă��邾���ł͂Ȃ��Ȃ��v�ƁB�܂�������O�̂��Ƃł�����̂����B
�@�r���̍������ŁA���Ⴂ���đS���t������o���Ă��܂��A�ǂ��ɂ��������̌p�����ł��Ȃ��B�P���Ԃ��炢���X���Ďd���Ȃ��~���ƁA�Ȃ�ƌ��̒n�_�ɖ߂��Ă��܂��B�悭�悭����A���̑Ί݂ɂ���炵�����オ����B���Ă��ă}�k�P�Ȃ��Ƃ����Ă��܂��Ƃ�������̂��B�ǂ��Ŗ��c�����̂��͂����Y�ꂽ�B

�����̓j�b�R�E�L�X�Q�̌Q���ł����B
�@�ԐΑ�̖{�����l�߂Ă����ƁA�c���H�̕S�ԓ��ɏo�Ă��܂������B����ł͂܂�Ȃ��Ə㗬�͑��k��ɓ����āA���x�ɏo��v��ł������B
�@�����ɓ���ƁA���ǂ̃g���o�[�X�������������B������Ɠo�肷���ĕ|���v����������������B����ɏ㕔�͐�k�o��ɂȂ����B���ォ�琹���ɉ���ƁA�����Ƀj�b�R�E�L�X�Q�̌Q���B����قǂ̃j�b�R�E�L�X�Q�͌������Ƃ��Ȃ������B���̂Ƃ��͏����ɔ��܂��āA�������R�B�v�������ȒP�ɏI�����āA�Ȃ��Ȃ��Q�t���Ȃ������B�ѓ��ɉ��R���ăN���}�����ɖ߂�P���Ԃ��炢�̊ԂɁA�V�l�̔ޏ�����₵��������Ă���Ă����B�f���炵���ƏЉ��Ă��銄�ɂ́A���Ҕ��������̂��o���Ă���B
�@
�����x�E�k�������@�P�X�W�T�N�P��
�@�����ɂ����ƁA�ϐ���̎R�s�ł�������L���Ɏc���Ă�����̂Ƃ����̂́A�قƂ�ǂȂ��B�܂�Ȃ������̂��A��ۂ����������̂��B�Ƃ͂����R�s�����Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�N���N�n�̋x�ɂ𗘗p�����������h�Ɍ����Ă݂Ă��A�V�W�N�̏t�ɎЉ�l�̃N���u�ɓ��������́A�Q�������Ō�̂W�W�N�܂ł̊ԂɁA��Ƃ��Ă͖��N�s���A�P�O��̎R�s���������킯�ŁA���̂������͂X��ɎQ�������͂��Ȃ̂ł���B�ŏ��̔N�͏㍂�n���疾�_�x�ɏオ���āA�O��`����`����Əc�������B���N�͕s�Q�����������A��O�`���Ƃ������N�����������A��A���v�X�̐ԐΊx�A������������ܗ��x�E�E�E�B�����ɉ͓����̏�ŎB�����ʐ^���c���Ă���N������̂����A���̌㖾�_�ւƂ��������Ă���̂́A�ǂ���o�����̂��낤�H�o���Ă��Ȃ��B�ǂ�����o���āA����x�̐������i���c�x�m�̔����j�����������Ƃ��������̂����A���̂Ƃ��̑O���̍s�����悭�o���Ă��Ȃ��B
�@������̑��ɂ��A�T���̍��h�����N�������̂����A���̋L�����������肾�B�A���o�������Ă悤�₭�v���o���Ƃ����n���ł���B���A�䍂�E�E�E�B�k�������ɂ͐��N�O�̂T���ɂ��o�������Ƃ͊o���Ă���B�Q�x�ڂɂȂ�B
�@�Љ�l�N���u�̍��h�v��Ƃ����̂́A��͂�g�D�l�Ƃ��ă��[�_�[�i�ӂ�̃����o�[���v������߂ĎQ���҂��W�߂�B���͂��������g�D�l�Ƃ��ẮA����܂Ŏ��i�҂������B��������ȍs���������Ƃ悭������B�Ƃ������Ƃ́A���h�̃v�����Ƃ����̂͂قƂ�ǎ����̕��ł͂Ȃ��āA���l�����߂��v��Ɂu���Ⴀ�A�����Q�����܂���v�Ƃ�����������ł��������̂��B�܂葼�l�̌v��ɕt���čs���Ƃ����̂́A���h���l�̃����o�[�̒��̉��ʂɂȂ�B���������o�[�̌��t���Ă����A�܂�����ɏo���邵�A���R���ł��邾�낤�Ƃ������Ղ�������B�ʂɍs���v��̉����ׂ����Ȃ��Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂����A�ǂ������l�C���B�Ȃ�A���������Ƃ��낾��������̂��Ƃ����ƁA����������Ƃ͌���Ȃ��B

�ƕW�߂����ӂ�̖k�������B�o�b�N�ɑ呄�A�q���A�����B
�@����A���o�������ď��߂ċC�������̂����A�����o�b�N�ɉf���Ă��邱�̎ʐ^�Ȃǂ́A�呄�A�q���A�����Ƃ��ꂢ�ɂR�{�̑����ʂ��Ă��钿�����ʐ^�ł͂Ȃ����ƋC�������B���͂��̎q���A�����Ƃ������̐��m�ȏꏊ�����ł��鏇���ɂ��Ă��A���ŋߒm�������̂������B�R�̖��O��m��Ȃ���Ύ������ʂ��Ă���ʐ^�̎R�ɂ������͂Ȃ��͂����B�ʂɎR�������������킯�ł͂Ȃ��̂����A���������o�[�ɂ��Ă����āA�~�R�𖡂���������Ƃ�����Ȃ��R�s�������킯�������̂��낤�B���s�ɂ��Ă��o�R�ɂ��Ă��A�P�Ƃ���Ȃ���Ζ{���̂��Ƃ͕�����Ȃ��Ƃ����l���A�����h�ł���̂����A�܂��ɂ���͌������Ă���ꍇ��������̂��B
�@����ł��������h�ɂX��������Ă���̂�����A���������ł͂Ȃ�ƂȂ��o���Ă��邱�Ƃ�����B���e�Ȃǂ͓Ɛg����́u�����ɉƂɂ������Ƃ��A�܂������Ȃ��v�Ƃ����Ă������A�ŋ߂ł͍Ȃ��u�T���ɉƂɂ��Ȃ��˂��v�ƁB���ʂ̎R�����Ƒ��Ɍ�����悤�Ȃ��Ƃ��������āA�U�X�����Ă����ߋ������݂�����B�Ȃ̂ɁA�~�̋L���͔����B
�@�ŏ��̐����́A���V��̂Ȃ��䍂�̒ݔ����Ŗ��c���A�����͐���̗Ő��ɓ����ēV��̃R���B���̗����ɂȂ��Đ���̒���ɒ������ɁA���̂����������ɂȂ����B�����ł����܂ɂ͉����ɂȂ�ƁA�����������Ƃ�����B
�@�L�Ȃ����O�ɓ������N�́A���b�Z���Ŋۓ���������Ƃ�����A�㑱�p�[�e�B�������ԂŒǂ��t���Ă��Ă��܂��āA�K�b�J���������Ƃ�����B�R���ڂɎR���ɏo�āA��V��̓~�G�����ɓ������̂͑�A���B���������������ł��邾�����܂ŋ߂Â����Ǝv�����̂����A���ǂR�l�p�[�e�B�̑����݂�����āA���x�̉�����Œ�R���܂ł������ɖ��c�B���ꂪ���������B�����͍r�V�Œ�B����ɗ����������r�V�Ŏ��E���Q�O���[�g���قǂ̐���Ȃ̂�������ł����Ԑ�ŏo���B�Ƃ��낪���ʂ̏c���ł���͂��Ȃ̂ɁA�U�C���Ŋm�ۂ��Ă₹������i�݁A��������P���|���Ă��R���܂ʼn���邩�ǂ����B���̓~�G�����ɓ����Ă����ʃ��[�g����̒��Ԃ��T�|�[�g�ɂ��Ă���āA�Œ�R�����킸���ɒ������Ƃ���ō������āA�g�����g������������Ƃ����A��Ȃ��R�s���������B����ɗ����́A���ɓ����Ă����ʂ̓o�R�҂����ׂĊ܂߂ĂQ�O�l�̃��b�Z���Ő���z�����ˑ�����邱�ƂɂȂ����B���b�Z���͋��܂Ő���B�擪�ƂQ�Ԗڂ͉ו���u���ċ�g�̃��b�Z���B�㑱���m���m���Ƒ����B���ǂ������Ă��A�V�䍂�ɂ����͖̂�̂X���B���قɘA�����Ƃ��āA�S�������ɏh�������B������̎��Ԃ���[�H������Ă�������̂��B�F���������Ă����B�Ăт���ɂȂ��Ă��܂����B�u���R����2���������̂ɂ˂��v�Ɨ��ق̏����B����Ȃ��Ƃ��������B�V��ɕ����߂���ƂЂǂ����ƂɂȂ�B���V�̂����ɍs�����ł��Ȃ��Ă��������Ƃ��B�������̂Ƃ��̂Q�O�l�����o�[�̂����A����̐l�������Ǝv���̂����A��ˑ犗�c��E�����h���h�������āA��J�o�������߂����ӂ�ŁA�u���̕ӂŗѓ��ɏオ��Ȃ��Ƃ��߂Ȃ��ǁv�ƁA�ѓ��T���ɎΖʂ��@�ɂ��������l�������B�ѓ������܂邻���������b�Z���̃��[�g�s���̂Ȃ��ŁA���Ă̋L�����炱���������Ƃ��ł���A���ɓ���������v���������̂��B
�@����͐�T�ɂ��̃��[�g���n�C�L���O�̂悤�Ɏn�߂ĉ��R���Ă����Ƃ��ɒɗ�Ɏv���o�����B���o��o�����߂��ŁA�Ƃ�ł��Ȃ�����ɂ������o���킷�B���̒J�͐V�䍂���甒�o�o�����܂ł́A����̂��߂ɒJ�������Ȃ��̂ł���B���Ƃ��ĎR�ł͋����悤�Ȏ��̂�����̂����A���ɃK�X�Ɛϐ�ł��̉���݉z���Ă��܂�����A����͍������P�O���[�g�����z������̂�����̂��B�����������E�Ƃ����Ƃ���ŁA���瑘��ȂǁA���ꂱ�����b�ɂȂ��Ă��܂��B�ϐ���̓g���[�X���������u�ԂɁA�Ƃ�ł��Ȃ�����Ȃ�A���₻�ꂪ�{���̎p�Ȃ̂����B
�@���Ă��̂Ƃ��̖k�������ɂ��Ă��A���̐��N�O�̂T���̓����[�g�ɂ��Ă��A��͂���t���܂ł��������������B�k��������o��Ƃ����̂ɁA�����̏�����̐�����S���W�����z�����Ȃ��Ƃ����̂��A��Ȃ��̂����B
�@���͂��̂Q��ڂ̖k�������ɂ��Ă��A�ƕW�Ƃ��k�����Ƃ����ꏊ��m��Ȃ������B���O�����͒m���Ă���̂����A���̏ꏊ���͂�������肷�邱�Ƃ́A���ł��ł��Ȃ��B������O�R�N�Ă̐����n�C�L���O�ł悤�₭����炵�����̂ƁA�o������͂��̖k���̃R���ɂ��Ă��A�Ȃ�ƂȂ����̏ꏊ������ł������x�̂��Ƃł���B���͂T�����P�����A�V�C���ǂ��āA�o�R�҂����āA���[�g�����Ă���A���̓�Փx�ȂljĂ������ς��Ȃ��̂ł���B����ȃ��[�g������Ă��āu�k���͖ʔ��������v�ȂǂƋC���������Ȃ����A��͂�L���Ɏc���Ă��Ȃ��Ƃ����̂́A���قǖʔ������Ȃ������Ƃ��������̂��ƂȂ̂��낤�B��̃g���[�X�ǂ���ɕ����Ă��܂�����Ƃ��������̂��ƂȂ̂��B

�@�T���ɍs�����Ƃ��ɂ́A�ƕW��O�ӂ肾�Ǝv���̂����A���p�[�e�B�̃e���g�ƈꏏ�ɂȂ����B�������͑��̎R�����瑄��������ĉ�������܂�����ɓo��Ԃ��Ē��Ԃƍ��������̂����A����V���̎��̕ɂ��A�L���b�g�t�߂ŃX���b�v��������̂́A���̓��A�k���ňꏏ�ɂȂ��������̈�l�������悤�ł������B����Ȃ��Ƃ��������B
�@�ʐ^�ɂ���悤�ɉ��ӏ����̓U�C�����g���Ă���̂��B�Ō���ɓo��Ƃ��ɂ́A�R�s�b�`�قǂ����Ɗm�ۂ��Ȃ���o�����L���͂���B���p�[�e�B�������Ō����������Ƃ͊o���Ă���B����ɕ��ւ́A������Ƌ}�Ζʂ��������Ȃ��ƁB
�@���̐����̎��ɂ́A�T�l�����o�[�̈�l���A�r���Ōy�������ɂȂ����B��ŕ��������̂́A�̎��I�Ȃ��Ƃ炵���B�C�̓ł��B���̎R�s�ɂ��Ă��A�ł͒��ォ��ǂ̂悤�ɉ��R�����̂����ꂪ�A�����ς�o���Ă��Ȃ��̂��B���̂܂c�����ăL���b�g�z���͂��Ă��Ȃ��͂��ł���B���Ƃ����Đ��N�O�̂悤�ɁA��ʃ��[�g�̔�ˑ~�̋L�����܂������Ȃ��B�܂��ē�x�������Ƃ��������ϑ����[�g�ł��Ȃ��͂��Ȃ̂��B������ˑ�Ȃ̂��낤���A�܂������o���ĂȂ��̂͂ǂ����Ă��B���V�ł����g���[�X�ɂ����č~�肽�����Ȃ̂��낤���B���Ȃ��Ƃ����N�O�ɐ�����J�������Ƃ��v���o���Ă��ǂ������Ȃ��̂ɁA������Ȃ������炵���B�̂�C�ȉ��R���i���B
�@�����V�䍂�ɉ��R��A����h����\�肵�Ă����̂����A�����ŗ�̓����ɂ��������ނ̂��Ƃł��߂����Ƃ����͎v���o���B�u�����̎��Â͑����ق�����������A���R�ɏo�ĕx�R�o�R�ŋA������v�ƌ����o�������[�_�[�ɑ��āu�y���݂ɂ��Ă�������h�����Ȃ��Ȃ�̂͂��₾�B�ǂ�������ɂ���Γ����̎��Âɂ��Ȃ�B��҂͓�������Ȃ��Ă�����B�����甽�v�Ƃ����̂́A���B�łT�l�p�[�e�B�͎����c���ċA���Ɏ^�����Ă��܂����̂��B�����ł��p�[�e�B�͕ʂꂽ�B�Ƃ����Ă�����l�ʼn���ɏh�������L�����Ȃ��B���R��ɂ���Ȃ��ƂŌ��܂���̂́A���ɋ��������܂������Ȃ�����Ȃ̂��낤���B�����̓p�[�e�B�̐V�l�������̂����A���Ȃ��Ƃ����łɉ��E�Ȃ̂ł��邩��u������l�ŋA���ł��܂��B�����o�[�͂�����肵�Ă��������v���炢�A�ǂ����Č����Ȃ��̂��낤�Ǝv�����B������������̂��B�u��l�ŋA��̂͐S�z�ł��B�����ɂ����v�B����ȃ}�k�P�������K�v�͂������̂��낤���B���[�_�[�͎R�ł͌����������������D�����l�������B������l�]���������̂��낤�B��̃`�[�t���[�_�[�N���߂��B���ɂ��̌o���͂Ȃ��B�����A���ݎ��Ɣނ͂Ȃ���̗F�l�ŁA�c��Q�l�͔N�ɂP���W�ŁA�V�l�̔ނ����͂܂��Ȃ����R���ł��Ă�������Ă��Ȃ��B
�@�����̌o���̂Ȃ��ŁA�k��������~�Ət�ƂQ��o�����Ă��邱�ƂȂǁA���ɖʉf�����ƂɂȂ�B���N�ɂȂ��āA�k���̎��t���́A�����̐�����̏��������߂ɁA���ł͑�V�䂩��n�R���V���ɉ����āA����ɖk�����o��Ԃ��ĂƂ���悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�m�����B�āA�T���������炵���B��V��q���b�e�̎�l���A������HP�ł���𐄏����Ă���B��V�䂩��̖k�������Ȃljߋ��ɉ��������`�����X�͂������͂��Ȃ̂ɁA�悭���ĂȂ��̂��B�o���Ă��Ȃ��B�������n�}����z������ɂ́A��V�䂩��قړ����x�Ɍ����鑄�ɂ����̂ɁA��������P�O�O�O�������āA����ɂV�O�O�o���Ėk���̃R���B��������S�O�O�̏c�����đ��Ƃ����̂́A�܂����n�ɂ����A�u���������܂ł��Ėk���Ȃ́H�v�Ƃ������ƂɂȂ�͂��Ȃ����B����ł����̃��[�g��I�Ԑl������Ƃ����̂��B�q���b�e�ł�������Љ��B�܂荡�ł��k���Ƃ����̂́A�����܂ł��Ă��o�肽���f���炵�����[�g�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��B���������Y�����a�P�O�N���ɂ����ő���āA���Q�������ɑ���āA���������͍������[�g�ɂȂ��Ă���B����ł������_���ȂǂƂ������̂��ł��āA������̑f���炵���鋫��䖳���ɂ����B�����R���ɂ��Ă��q�͏��Ȃ��Ȃ����B�����čr�p���������Ȃ̂ɁA����ł��k���Ȃ̂��낤���B���������Ȃ̂��낤�B
�@�O�R�N�Ăɐ������������邢�āA�����ł�����ς�ϐ���ɂ͗��h�ȃ��[�g�ɂȂ肦��ƍĔF���������̂��B���������āA������f���炵���B���͂R�����ɋ}�s�Ȕ�����o���āA��Ő��͖k��ւƑ����B�������Đ��V�Ȃ�A�Ă��~�������悤�Ȃ��̂Ȃ̂����A�R�̎����Ă��閣�͂Ƃ��Č��Ȃ�A��͂�R�̊������́A���������������Ă͂��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�N���d�˂�Ƃ��������v���ɂȂ��Ă���B�̗͂����������A�����ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B
�@�@
�x�m�R�@�P�X�W�T�N�R��
�@�x�m�R�Ȃǂ́A�D���ł��Ȃ��R�Ȃ̂����A�o�����͖��ɑ������̂������B��̉Ă̕x�m�ɂT�C�U���Ă���B�����������́A�N���}�̖Ƌ���������������̂��܂�A�x���Ƀo�C�g��̉c�ƎԂ��T���ɔq���Ă��܂��āA�Ȃ������X�o�����C���̂T���ڂ܂ŏオ���Ă��܂��A�v�C�̂܂ܗ�₩�������Œ���܂œo���Ă��܂������Ƃ��������B�S���ԂŒ���B�u����A�Ђǂ��l�̓n�C�q�[���œo���Ă��鏗�̐l�����邭�炢�ŁA��C�œo���Ă��債�����Ƃ͂���܂����v�Ə����̃o�C�g�Z����B
�@�X�o�����C���̔��Α��̑��ѓ��Ƃ����́A�A���y���h���C�o�[�ɂƂ��Ă͂�����Ƃ������n���������Ƃ������āA���̈��H���������肵�āA������ʔ����h���C�u���������̂������B�ŋ߂ł͐��N�O�ɉƑ��œo������������B

������Ă���R�����̃x���`�ŋx�e
�@���N�P�P���ӂ�̐�P�̎����ɂ́A�����ɂ悭�ʂ������̂��B���ԈˑR�Ƃ���������~�ȂǂƂ����P�������ł�����Ă���̂����A���ꂪ�{���ɖ��ɗ��������Ƃ͂Ȃ��B���̂����̒�~�p���̓A�C�[���𗚂��������y�����ɕ�������̂����A�u����́A��������|�����A�C�[���ŁA���܂��Ȃ����߁v�������ł���B�}�Ȑ�ʂŎ��ʂ��Ƃ��������������Ƃ��ɁA���ܖh���̑��グ�ȂǁA�܂����������̂Ȃ��R���ƍ��ł��v���Ă���B�s�b�P�����h���Ɠ����ɁA�������ڈ�t�L����Ȃ�A�Ζʂ��A�C�[���ň��������Ȃ肵�āA��Ɍ��˂��Ăł�������h���������ɂȂ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B�����玄����P�������Ƃ��ɂ́A�ނ��뒸��܂œo������~�肽�肵�ăA�C�[���Ɋ���邱�Ƃ̕��������Əd�v���Ǝv���āA�x�m�o�����邱�ƂɑS�͂����������̂������B���邢�͌P���ł́A�Ζʂɓ���������╠���œ˂�����ŁA�������犊����~������������Ǝ��H�ɓK���Ă���Ǝv���Č�y�ɂ�点�����̂������B
�@�{���̓~�̕x�m�ɍs�����ƌv�悳�ꂽ�̂́A�܂��ɂ��̂Ƃ������ɂȂ�B�����̂��傤�ǂP�N�O�́A���͈����ŖƋ��������̎����ŁA�N���}�C�J�[���Ȃ��A�x�m�}�̂��̃I���{���S���ŋg�c������R�������̂������B
����ł��f���炵�������ŁA���̓�����͕x�m�̋��|�͂ǂ��ɂ��Ȃ������B�ϕ��p���̂܂ܑ̂��ƒ��ɕ����オ���Ă��܂��˕��ȂLj�Ȃ��B�x�m�g�c�̓o�R������T���ڂ��炢�܂ŏ����ɓo���āA�����͓o���B�ʐ^�����Ă��A�܂������̋�g�œo���Ă���B
�@�o���Ă���̂́A����t�߂���̉���ŁA�K�Z�[�h��A���������Ƃ������B�����̒��˂Ő�͏����ɂ�ł���B�����X�s�[�h���t�������Ă��܂��ƁA���ꂪ�~�܂�ɂ����B�K���ȃX�s�[�h��ۂ����܂܁A�ǂ�ǂ�~��Ă����̂��B�ҊԂɓ˂��h�����Εt���ɂ�������R������B��������ƁA���x�͒��ˏグ���Ⴊ�ҊԂɂǂ�ǂ܂��Ă��܂��āA���̂��߂ɐK�Z�[�h���~�܂��Ă��܂��B���̓x�Ɉ�U�����オ���āA�ҊԂ̐���ǂ��Ă���܂��J�n�Ƃ����킯�������B
�@����Ȃ��Ƃ����ėV��ł������߂ɔn���Ȗڂɂ������B��s�̓�l����ɍs���߂��Č����Ȃ��Ȃ����B���R�r������͎R�����͌������ꂢ�Ɍ�����B����Ȃ̂Ƀe���g���Ă����T���ڂɂ��ǂ蒅���Ȃ��̂ł���B�r���Œn�}�Ɖ��x���ɂ�߂����������̂����A���K�̃��[�g�����E���Ɋ�肷���ĉ��R���Ă��܂����炵���B��Œn�}������ƕs���Ƃ����K����ɓ��荞��ł��܂����B�x�m�̎Ζʂ͂��ꂢ�Ȉꖇ�Ζʂ��Ǝv���Ă����̂����A�ΎR�̎c�[�̂悤�ɁA�����炩�̃K���������������̂Ȃ̂��B�u�ǂ����K���ɉ����Ă��A�ǂ����̗ѓ��ɏo�邾�낤�v�Ƃ₯�ɂȂ�A���̍��ɂ͕G���炢�̐ϐ�̏d����̃��b�Z���ɁA������Ƌ�J�����肵�Ă��܂����̂��B����Ȃ��Ƃ��Ă悤�₭�A���ѓ��̂S���ړ�����ɍ��������炵���B�܂������g���[�X���Ȃ��B�G�̃��b�Z�����v���B�������琳�K���[�g�ɖ߂�ɂ́A�T���ڂ��炢�܂œo��Ԃ��āA��������o���Ă����o�R��������Ƃ����킯���B
�@�������g����Ȃ��v���āA�d���Ȃ��o��Ԃ��Ă���ƁA���Ԃ̃R�[�����悤�₭���������B�����E��������߂��Ă��܂������Ƃ�m��ƁA�u�����A�悩�����v�Ɣނ�͐K������t�����B�u��������Ǝv�����v�B�m���ɂ낭�ł��Ȃ����ƂŐS�z���|���Ă��܂����B���Ԃ������Č}���ɗ��Ă���āA���̃��b�Z���̂������ŁA�y�ɂȂ����B�V�C���悷�������߂ɁA�o���o���ɉ����āA�Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B
���x�E�����Y�����@�P�X�W�T�N�T��
�@���̔N�̃A���o�������Ă�������Ă��܂����B�W�T�N�T���Ƃ����̂́A���������N���ł���BGW�Ɍ�����A���āA���Ђ��P�T���B���͂��̔N�̂W���ɂ����ɓ����Ă���̂����A����͂V���ɔ�I��������������Ƃ������ƂɂȂ�B�^����œ��q�@�̌䑃��R�ė��̃j���[�X�����B���j�����܂ꂽ�̂��P�Q���B�L���Ɩ��O�������B�����R�ɊW�����閼�ɂȂ����B���ꂪ���łɍ��Z�R�N�B�����������̂��E�E�E�B�u���������ɎR�ɂ�����������v�Ɖ��x���ȂɌ���ꂽ���Ƃ����������A�U��Ԃ��Ă݂�Ɩ��炩�ɂ����������B�����͎��o���Ȃ������B�킪�N���u�̉�͎��c�b�q�j�Ƃ����R�x�E�ł͗L���l�Ȃ̂����A�u���[�ƎR�ƁA�ǂ����ƕt�������������Ǝv���Ă���v�Ƃ����̂����_�ŁA���������v���Ă����B�t���������������̂�D�悷��ł���A�������B�r�����犄�荞��ł������̂͏����Ƃ��Ă��̎��ɂȂ�B����ɂ��Ă��I���ȎR�s���A����ȑO�Ɖ����ς��Ȃ������Ă������̂��B
�@���ɂ́A����܂œs���łT�C�U����R���Ă��邱�ƂɂȂ�B�ŏ��͂��̃N���u�ɓ���O�ɁA�j�m�ؓ����z���ĕ�����n���ɏ���āA���̍��X�����̗��j�I���[�g���猕��ɓ������̂͗ǂ������̂����A�����ł킸���ɂP���������������V�̓��ɁA��ʃ��[�g����J�j�̉����ȂǂƂ����Ƃ����ʂ��Ē���ɗ����������B������Ԃ̐��V�́A�������y���T�|�[�g���邽�߂ɓ���|���ă_���̉����B���Đ�y���������������͉J�̂��߂Ɂu����A�\����J��グ�ĉ��R���悤�v�Ǝ����Ɍ��������̂��B���̃N���u�́A���Z����̗F�l���Q�����Ă����Ƃ���ŁA���͂��̂Ƃ��q�l�����ō��������̂����A���̃A�z�v��ɕ���Ĉȍ~��������B

���x�B�����Y�����@��̎Ζ�
�@���̌�͍��̃N���u�ɓ����Ă���ɂȂ�̂����A����N�͓����悤�ɉĂɌ���Ƀx�[�X���āA����Ƀ`���l�o���̂��߂ɎO�m���ɂ�����e���g�����̂��B�^���C�𗚂����܂܂����ɍ��������̂����A��k�̑����ɋ����āu�ł��A�����n��������ΊȒP�ł���v�Ɛ����O���炻���ɑ؍݂��Ă��������ɂ����āu����A�n���}�[�ő��v���v�ƂȂ����B���̂Ƃ��͂�������l�C�̍��Ő��Ƃ���ɂ����P�{�̓o���������B�����ɍĂь���ɖ߂�Ƃ��ɂ́A���傤���Ȃ��^���C�̂܂O�m����k���������̂����A�債�Ĉ�a���͂Ȃ������B�Ƃ��낪�������炢�̂��ƁB���̌㒷���`�[�t���߂��ނ����̔N�ɐV�l�������̂����A�p�S�[���A�C�[���������Ă����悤�������B�Ƃ��낪�T�C�Y������Ȃ��B���̂��߂ɎO�m���̉���œ]�|���āA���܂����炢�̂��B����ł����Ƃ����ǂ蒅��������A�����ɂ͍������Ă���OB�ɂ���Ԃ���āA�܂��ɕs���_�̓P�ނƂȂ��Ă��܂����̂ł���B�u����ȃz�L�ȃ��c�́A�ǂ����܂��Ȃ����߂邳�v�ƒN�������������������B�m���ɔނ͂��̌サ�炭�x�E���āA���t��̂܂܉�̏W��ɏo�ȂȂǂ��Ă����B�Ƃ��낪�C�������Ă���C�z���Ȃ��B����Ȃ�ƁA��₩��������܂��Ȃ���V��ł������A����������ɂ͂�������ƕ��A���Ă����B���̂W�T�N�̐����̖k�����A���̌����Y���������̔ނ����[�_�[�ƂȂ����B�����̖k���ɎQ�����������o�[�ł��̂T���ɂ��Q�������̂́A�ނƎ������������B
�@���̂ق��A�T���ɂ͔��������珬��������o���ē��R�������Ƃ�����B����ɂ��̔N�̉Ă̌��́A���ƃp�[�g�i�[�̓�l�ŁA���ʎR�̕ʎR�J��o���āA�^����̖{�̂ƍ��������B���̑��ɂ�͂�T���Ƀ_��������R�������Ƃ��������̂����A����͖Y��Ă��܂����B�������ĉ��x�����ɂ͑����^��ł���̂����A���ł����ƕ����Ɓu����Ȃɉ����Ƃ���܂Łv�Ƃ�������������ɗ��B��͂�A��̂Ȃ��ŒN���̌v��ɑ���肵�Ă��������̂��ƂƂ����A���l�s�V�ȎR�s�����Ƃ�Ȃ�����Ȃ̂��B
�@���̔N�̌��́A�A���o�����������ł͐��V�Ɍb�܂�Ă���B�U�C�����o�����ӏ������x�������āA��ł̌������~������B����炵���Ƃ���ŋL�O�B�e�����Ă��邪�A�W������ɖ�����Ă���̂��낤�A�����ς蒸�ゾ�Ƃ����v���͂Ȃ������B

���E�����Y�����@��Ł@���������ł��������~����B
�@�Ƃ���ł��̂Ƃ��̎R�s�ɂ��Ă��A�͂����Ăǂ������R�����̂��A��͂萳�m�Ɏv���o���Ȃ��̂��B����܂Ŏ��͑���������ʂ����o���͂Ȃ����A���Ƃ����Ď����ł��Ȃ������悤�Ɏv���B�L���̒��ł͂T���ɒr�m�J��k�����������Ƃ���x��������̂����A���̂Ƃ��������낤���H����������̘b�ł���B
�@���͎��̐���̌����R�̂Ȃ��ŁA�ł���ۂɎc���Ă���̂́A���̒r�m�J�̉���Ȃ̂ł���B����m�ɂ����A�㕔�Ő�����̒r�m�J�K���[�̉��肾�����B�}�Ȑ�k�̉��~�Ƃ����̂́A���ł��C�����B�X�L�[������Ă���A���ꂪ���K�ȎΖʂ��Ǝv���Ă���l������̂��낤���A���ɂ̓X�L�[���낤�ƁA�A�C�[�����낤�ƁA��͂�s���ɂȂ�B�K���[���㕔����`�����Ƃ��Ɂu����ȂƂ���A�ǂ�����ĉ���v�Ǝv�����B�m���ɂǂ̃p�[�e�B�������悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă���B�U�C�����o���Ă���p�[�e�B������B�m�[�U�C���ŃN���C���_�E�����Ă���l������B�����������ł��A�����K�����鐔�l�Ƃ����̂́A���ʂɑO�������ĉ����Ă���l������̂��B�T���ɟ���O��E�k�����̂T�E�U�̃R���ɓo�����Ƃ��ł��A����ɋ}�ȂR�E�S�̃R���ɓo�����Ƃ��ł��A��������O��E���ǂɎ��t�����߂ɉ��邠�̎Ζʂ��A�ǂ�����ĉ���̂��B�k�䂩���J�Ɏ��t���Ƃ��ɂ��A���g�₩��`�����ޑ�J�́A�Ƃ�ł��Ȃ��}�X�Ɍ�����B�����������ɂ��A�������g���[�X�͕K��������̂Ȃ̂��B��k�̉�����ǂ���������̂����A���Ԃ̗L���Ȏg�����ɂȂ�B�����ɓo�R�̋Z�p�̈Ⴂ���ł������Ɍ����B
�@�K���[�̉���ł́A�������u����ȂƂ��ŃU�C���o���悤����_�����v�Ƃ������āA���Lj�l��l�ŏ��̓N���C���_�E���Ő�k�ɓ������悤�Ɏv���o���B���̂����ɎΖʂ������ɂ��Ȃ��āA�O�������ĉ���n�߂��̂��H�@���̓��͎O�m���Ƀe���g�����̂����A�����͎O�m����k�̉���ɂȂ�B�������ɂ����ł̓U�C���̕K�v���͂���قNJ����Ȃ��̂����A����ł��o���Ă�p�[�e�B������B�ނ���������̂́A�A�C�[���ɐႪ�t�����ă_���S�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������B���͂��̐��N�O�Ƀ��[���b�p�ɂ������ނɕ������̂����u�������̃K�C�h�̂Ȃ��ɂ́A�����Ă����̎��ɂ͕Б������A�C�[���𗚂��Ă���l������v�Ƃ������Ƃ������B�����̖{�œǂ��Ƃ�����B��������������Ă݂����Ƃ����x���������̂��B����Ƃ��ꂪ���������s���������B�E���̃A�C�[�����O���āA�����炪�L�b�N�X�e�b�v�B�����̓t���b�g���n�B���̂Ƃ�������ł������ƁA�Б��A�C�[���ʼn���n�߂��B��͂肤�܂������B�_���S��ɋC���g���̂��Б������ł����̂��B

�����Y�����㕔
�@�Ƃ��낪�r���ŁA���ɕ����̏������A���������������[���ꍞ��ł���X�e�b�v�������Ă���̂��B�ٗl�Ȋ��������ĉ����Ǝv���ƁA���ꂪ�����A��̃p�[�e�B���A���X�ƃN���C���_�E�������ՂȂ̂ł���B�O�������ĉ����Ƃ�����A�R�肱�N���C���_�E���ł́A�������~�̎��Ԃ͂R�{�͒x���Ȃ邾�낤�Ǝv����B�܂�������ȂƂ���Ō������~����l�͂��Ȃ����A����ł��N���C���_�E���ł���Ƃ���ŁA�������~����A����͂P�O�{�����Ԃ�Q��邱�ƂɂȂ�B���~�̋Z�p���ǂꂾ�����Ԃ̐ߖ�ɂȂ�̂��A���ꂪ�܂����V�̎��ɂǂꂾ�����S�ȏꏊ�܂ňړ��ł���̂��A���̐��ۂ����͓o�R�̂Ȃ��ł��Ȃ�d�v�ȈӖ��������Ƃ��A���̎O�m���̉��~�Ŏv���m�炳�ꂽ�̂ł���B�ނ����_�Ɂu�����X���b�v���Ă�������v���炢�ʼn��~��������A�����ƈ��S�Ȃ̂ł���B�킩���Ă���̂����A�Ȃ��Ȃ����s����ƂȂ�Ɠ���B�X�L�[�Ɠ����ł���B���~�Ɗ��~�͓������̂ŁA���ꂱ�����Z�p�̍��̂��ׂĂł���Ƃ����Ă����B
�@���Ēr�m�J�������Ɖ����Ă��ƁA�S���W���̎�O�œ��ݐՂ͏��������ɏオ���Ă����B�r�m�J�ɂ��������S���W�������邱�Ƃ��A���̂Ƃ��ɏ��߂Ēm��̂��B����ɔ�����ɉ��肽��ɁA�܂��E���̔����ɏオ���Ċ����B�����Ƀ^�J�m�X���������邱�Ƃ��A����͍��N�ɂȂ��Ēm�������ƁB�������������ƒJ�̎�_������˂��Ă����T���̎R�s���A�����͖ʓ|�������Ǝv���Ă����B�����v���Ƃ������Ƃ͍D���ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�ϐ��c�Ⴊ�������Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�B�D���Ȃ̂́A�X�L�[��̐Ⴞ���������B����Ȃ̂ɁA���h�Ƃ����u�܂��A�Q�����邭�炢�Ȃ�A�Ȃ�Ƃ��Ȃ邩�炢����v�Ǝv���Ă������B������R�D���Ɩ{���Ɍ������̂��낤���A�^��ɂȂ�B
�@�ȂƂ͐E��̌����ɂȂ����̂����A����ȑO�̂R�N�قǂ́A���̃N���u�̒��Ԃ��܂߂āA�O���[�v���ۂ̃Q�����f�X�L�[�ɓ~�̊Ԃ͖����ɂȂ��Ă����B���ꂱ�����T�̂悤�ɏo�����Ă����B��̋ߏ�̓��A�肪���������̂����A����͂܂�Q�n���̃X�L�[��Ȃǂ́A�قƂ�ǂ��ׂĐ��e�������炢�ɂ��Ȃ����B
�@�Ƃ��낪���̃Q�����f�X�L�[�ɂ₪�ĖO���Ă���B�ǂ�ȎΖʂ����āA�~��Ă��邾���Ȃ牽�Ƃ��Ȃ�Ǝv�����Ƃ��Ɂu����ȏ���ɂȂ�ɂ́A��͂茟�肾�v�݂����ȋ@�^�ɂȂ��āA�^���ǂ������A���������Ă���ȂǁA�܂�Ȃ������ɘb���i��ł����B����Ɍ��C���������B�������ăN���X�J���g���[�Ɉڂ��Ă����B������s�����x���̃��[�X�̃X�L�[�ł���B�����Ă���ɂP�O�N�����āA���x�͎R�X�L�[�ɂȂ��Ă���B���������Ƃ��ɁA�����Q�O�N�߂����O�́A���̂T���̐�k����̏d�v�����A���ɂȂ��Ďv���o���̂��B����ɂT���̂��̐^�����Ȑ�R�ƁA�^���Ȃ��̐��V���B�s�v�c�Ȃ߂��荇�킹���Ǝv����B

�r�m�J��k�̉���
�@�ŏ��ɂ��̃N���u�ɓ������N�A���̂S���̏T���ɎO�b���Ŋ�g�����������B�{�i�I�Ȋ�o��͏��߂ĂƂ����Ă������B���ꂪ�ƂĂ��Ȃ��ʔ����B����������o�肪�������āA�Љ�l�̃N���u�ɓ�����̂��B�Q���|���Ă��A�O�b���̃Q�����f�S����o�肫���킯�ł��Ȃ������B����ɂ܂����T�������ɒ��ēo���Ă݂����Ȃ����B�Ƃ��낪���T��GW�̍��h�ş���ɂP�T�ԓ��邱�ƂɂȂ��Ă����B��������Q������B�����������̎��́u����ɂP�T�ԓ��邭�炢�Ȃ�A�O�b���łP�T�Ԃ����������v�ƌ����o�������̂������B������y�ɏ�������ɂ����Ȃ߂���B�u�A�i�^�T���̟�����Ēm��Ȃ��́H����Ȃɑf���炵���ꏊ�͂ǂ��ɂ��Ȃ��̂�v�ƁB�u���ǁA�����ĉ�����́H���̎O�b�������f���炵����o�肪�ł���́H�ǂ����V�l�ɂ͓o�点�ꂭ��Ȃ����v�B�����͂������̂́A�v��ɂ͏]�����̂����B��͂���ۂɂ́A�O��E�k�����Ɩk��E���ł��̂ڂꂽ�����ŁA����������ǂ��o��Ȃ������B�o���Z�p���Ȃ������B�u��͂�v�����Ƃ��肾�B���ܟ���ɂ��������A���̎O�b���ŗ��K���Ă������������Ƃ��̂����v�Ǝv�����B�����v�����Ƃ��������Ǝv�����B���̍��h�ɎQ���������߂ɁA���̊�o��̗��K���P�T�Ԓx�ꂽ�ƍ��߂����v�������̂��B
�@����ȓ����̎v�������v���o���Ƃǂ����낤�B�����͐������A�����͊ԈႢ���B�Ƃ������Ƃ͂ǂ���ł��悩�����Ƃ������ƂɂȂ�̂��B�������������ĂT���̎R���D���ɂȂ����Ƃ��ɁA���̗��R�̈�ɁA��͂肠�̂Ƃ��̐^���Ȑ��V�̟��猩�グ���O��Ɖ���̒ݔ����̔������́A��͂�]���ɏĂ����Ă���̂��B���̐�i�Ƃ����Ă������^�����Ɛ^���ȃR���g���X�g�̌i�F�́A�O�b���ɂ͐�ɂȂ��B
�@�N��ƂƂ��ɁA�R�̊��������傫������Ă����̂��B�����͑S��������Ȃ��������̂��A���ɂȂ�Ƃ悭������B���邢�͋t�ɁA�����͕����������̂����͕�����Ȃ��̂�������Ȃ��B�������A�ߋ��ƌ��݂������Ȃ�A���͗��������Ă��鎞����߂����Ă���ꂽ�̂��ƁA�v���B���������Ӗ��ŁA�����R�ɐڂ���@����邱�Ƃ��A�K���Ɏv���̂��B
�����ʎR��E�E���@�P�X�W�T�N�W��
�@�Ă̍P���o�������}�j�A�b�N�ɂȂ��Ă����̂��낤�B��̉č��h���^����ōs���邱�ƂɂȂ��āA�����ɓ��R����̂ɁA�����ʎR�̑��o���Ă��獇������Ƃ����v��������B�p�[�g�i�[�Ɠ�l�ł���B�����ׂĂ����ƁA�䂪�R�x��̐�y�������A���̕ʎR�ʼnč��h���������Ƃ��������悤���B�G���u��Ɛ�v�̌Â����ɂ��̕��������B�����̓o�b�N�i���o�[�Ȃǂ��ł��邾�������Ă������̂������B

�����A���y�����[�g������Ēʉ߁u������j�ӑсv
�@���R�͐��ɂȂ����̂����A�����������W�����J�̗����ŁA���̃A���y�����[�g���s�ʂɂȂ��Ă����̂ł���B���~�߂�H�������́u�����Γ��R�ł���̂��H�v�ƕ������̂��Ǝv���B�M�����Ȃ����Ƃ�OK�ɂȂ��āA���̃g�����[�o�X�̒n���g���l��������ē��邱�ƂɂȂ����̂��B�u������j�ӑсv�Ƃ����ŔŋL�O�ʐ^�ȂǎB�����̂����A���܂ƂȂ��Ă͒��������̂ɂȂ�B�������ă_������ʎR�̑�ɓ����ď����s�����Ƃ���ŁA�r�o�[�N�ƂȂ����B
�@�����A��k�̏����Ɍ˘f���Ă���ƁA�Ȃ��R�l�p�[�e�B���������̑Ί݂�o���Ă���ɏo���킷�B�u�����A�g�����[�o�X�œ����Ă����̂��H�v�Ǝv���B���Ƃ�����A�����J���ă_���܂ŕ������w�͂͂����������������ƁB

�N���o�X�̌������~
�@��k���~���Ƃ��ɂǂ��ɂ����@���Ȃ��āA�g�̂����邭�炢�̃N���o�X�ɌÖ�n���āA������x�_�ɂ��Č������~���Đ�k�̉��ɍ~�肽�肵�����̂������B�������Đ�k��������A���o���āA���̓��̂����ɔ�����ꂽ�̂��A����ɂ��������₵���̂��͖Y��Ă��܂����B��������ėŐ�����^����Ɍ������Ƃ��ɁA���͍s���H����Ă��܂��āA�܂����������Ȃ��o�e�Ă��܂����̂��B�u�����o�e�ł����H�v�Ƒ��_�Ɍ����āA�s���H�����������Ă�������肵���̂��B�������ƂĂ���Ȃ��B����Ȃ��Ƃ����ł��g���E�}�ɂȂ��Ă��āA�ŋ߂ł͂����]���Ď̂ĂĂ��܂��قǁA�R���r�j���ɂ���Ƃ��A�t���b�V���T���h������ł��܂��̂ł���B�P���R�s�ȂǂŁA�P�P�Q�O�~�̂��̂��ɂ��肪�ܖ������߂��ė]���Ă��܂��Ď̂Ă�̂͂��������Ȃ��̂����A�܂��H�����̂��Ȃ��Ȃ��ĕ����Ȃ��Ȃ�����܂����낤�ƁA����͂����J�������Ă�����̂��B

���������̐�k����
�@�ʎR�̎R���͉��̕W�����Ȃ������Ǝv���B��������ǂ������R�����̂��́A�����Y��Ă��܂����B�����^���ɂ��āA���̌�����ȒP�Ȗ̋��œn��Ƃ��ɁA�Ȃ�Ƃ���Ȃ����������������̂ƁA���łɉ��d��_���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ԂɂȂ��Ă��܂��Ă����B���v���A����̉��f�́A���N�������҂��āA�����̃I���W������n���Ă���Ă���̂��낤�B�ƂĂ��ł͂Ȃ����n�ł��鐅�ʂł͂Ȃ����A���̂����������Ō���͗���Ă�����̂��ƁA���x���ʂ��Ă����͂��Ȃ̂ɍĔF���������̂������B
�@����ƒ��������̗[���́A���͌䑃��R�œ��q�@�̒ė������������̓��������̂ł���B���Ԃ����W�I�ł��̃j���[�X��m�������肾�����̂��낤�B�u�ǂ��ɗ������H�v�Ƃ����킯���B���v�ӂ肩��k���������������A����Șb�ɂȂ��āu������Č���R�i�������܁j�ӂ肩�ƁH�v�B���Z���̂Ƃ��ɁA��͂�}�j�A�b�N�ȎR�Ɏ��͍s���Ă����̂��B

��k�㕔�ɑ�
�@�ړI��B�����āA�������͕ʂ̈�l�Ɖ��R�����̂��Ǝv���B�ŋ߂ɂȂ��čȂɌ���ꂽ�̂����A�u���̓��̋A��́A�ė��̌�ʋK���ŏa���āA�x���A���Ă������ˁv�ƌ���ꂽ�B�܂������o�����Ȃ��B���͂��̂Ƃ��V���̗����B�S�z���Ă����ȂƁA�܂��������S���������́A�����̓o�R�ɑ���C�����̈Ⴂ�������̂��B
�@�m���ɍ����ʎR�̓}�j�A�b�N���Ƃ����Ă����B�W�����Ⴂ�B�Q�R�O�OM�����Ȃ��B�������Ɛ�k�ō\�����ꂽ�R�ł��A���̔��������̊�Ɛ�k���r������A�N���[�h�͍��������Ƃ��Ă��A�����̒��x�A�C���^���X�g�̒��x�͂���قǂł��Ȃ������Ǝv����B�҂��\���Ă����ւ́A�K���z���Ă����ƈӋC����ł��������́A�s���l�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��������A���ꂪ���ł��L���ɂ悭�c���Ă���R�s���Ɩ����ƁA�K�����������������̂ł��Ȃ��̂��B
�@
���������E�k���J�`�R�l�J�@�P�X�W�U�N�W��
�@�k���J�͍���������ł́A�����J�ƕ���łQ��x���ɂȂ�B���̖{���̊j�S�����y����Ɏx���̘R�l�J�ɓ����āA���̎R�Q�Q�O�OM�ɔ�����Ƃ����A������S�C�T����₵�������R�s�ɂȂ����B������ɒ��ԂT�l���W�߂ē������̂́A������ɂȂ����B

�ŏ��̑�ҁB�˔j���悤�Ǝ��t�������̂́A�����₽���Ċ��������s�ށB
�@���͂����A���쉷��z�������z���ē������Ƃ���́A�_���ɂȂ��Ă���炵���B�����łR���ԁA�^�N�V�[�����͂��̃_������܂œ���ƍ��̒n�}�ɂ͏����Ă���B�����͂��̍H�����n�܂��Ă����B�ѓ�����k���̗���ɏo�āA�͌������������ƁA�ŏ��̃S���W���ɏo���B���傤�ǐ�s�p�[�e�B�����āA������j���Œʉ߂��Ă����悤�������B���������������Ƃ����悤�Ǝv�����̂����A�����됅���₽������B�N������э���ōs�����̂����A�u���ɓ������u�ԂɁA�₽���ł܂����������ł��Ȃ��v�Ɗ��������s�ށB�����������悤�Ƃ������ƂɂȂ�B������Ɩ�Q���ԁB������Ǝv�������̂����A�܂����Ԃ�������������肢�����ƂɂȂ����B

�����̃e���g���ɂȂ������~�߂̑�B����������������ɂ͓o��Ȃ������B
�����̏h���́A���̓���x�ڂ��炢�̍���������~�肽�Ƃ���́A���~�߂̑�A���O�̂Ƃ��낾�����B�傫�Ȋ��������ēo�ꂻ�����Ȃ���B�������܂���������������ƂɂȂ�̂��ƁA������ƗJ�T�������̂��B�Ƃ��낪�[���ɂ�����P�Ƃʼnj���ʼn����Ă���͓��݂����Ȑl�������B�E�G�b�g�X�[�c�ɑ��Ђ�����Ă���B�Ƃɂ�����͔�э���Ŋ����j���Ƃ�������̃X�^�C���Ȃ̂ł���B����Ȃ��Ƃ��ł���A�����̎������̍s���͂Q���Ԃ��炢�ʼn��R�ł���̂��낤�ȂƎv�����B�[���R�̒��̒J�ŁA�����Ȃ萅������l������ė���̂��B�������ی�F�̂悤�ȗΐF�̃X�[�c�𒅂āB����ɂ͋������ꂽ�B�������A�C�f�A�ɕx���R�̕��@�ł���B

�����A���̊��̑������ł��j���Ŏ��t���A�o�낤�Ƃ����̂������s�B��͂荂�����ɓ������B����ł��A���o��������ƁA�y�������ȓn��j����������ł�����B
�k���͕W��������قǍ����Ȃ��B�������Ƃ����Ă���ł��o�Ă���킯�ł��Ȃ������B�ނ���e���g�̒��ɁA��ԂɉႪ��ʂɓ��荞��ŁA���N���Ă݂�ƒ��Ԃ̊炪�͂�オ���Ă��邱�Ƃ������������B

�قƂ�Ǘ���̂Ȃ���҂́A�S�g���v���Ă�����قǒʉ߂͓���Ȃ��B
�O���ڂ̏h�����������A���̉��ɐ�k�̂��������Ƀe���g�����B��ŗ�₳�ꂽ��������Ă��āA�m���ɒ��͂��Ȃ��B�������t�Ɋ������炢�̃e���g���ɂȂ����B�{������R�l�J�̏o���́A��҂ɂȂ��Ă����B�����ڂ��̒��s�����n�߂Ă����̂Ƃ��ŁA�S�g���Ԃʂ�ɂȂ��Ċ����ē������ɁA�����Ȃ��x�~���ĕ������Ď��Ԃ��Ԃ�����������B

�R�l�J�ɓ����čŌ�̍k���B��̍������ȒP�ɓo���B
�������Ďx���̘R�l�J�ɓ���A���ʂ̏��Ȃ��Ȃ������o���āA�Ō�ɂ͒��̎R�ɂł��B�����x�̒���̎ʐ^�����邩��A�������o�R���Ę@�؉���ɉ������̂��Ǝv���B���������Β����x�̒���ӂ�ň�l�̃I�o�T���ɏo������B���ł���̏����ʼn����Ԃ��̃A���o�C�g�������A�肾�Ƃ����Ă����B�Ƃ��낪���̂������{���Ă����B�u�]�ƈ��ɂ́A�L���x�c�̐c�����H�����^����ꂸ�ɁA����Ȃɋ��J�I�Ȉ����������Ƃ͐��܂�ď��߂ĂŁA�������ďo�Ă����v�ƁA�܂Ȃ���ɘb���̂��B�܂������N�̓o�R�u�[���͗��Ă��Ȃ����B�������q�����Ȃ��āA�]�ƈ��̈������������������������̂��낤���B�ŋ߂ł̓w���חg���Ȃǂł��������b�����܂蕷���Ȃ��B����ɂ��Ă��A�������������J�͎��Ԃ�������B�ł��ĒZ���Ԃŋ삯�オ�낤�Ƃ��Ă������ŁA������蒅���Ƃ������ƂȂ̂��B
�����E�ΑŎR�E�\����{�J�@�P�X�W�V�N�W��
�@�\����͖����̉ΑŎR�k�ʂ��オ��J�ł���B�x���̓��[�g�}�ɂ��Љ��Ă������A����Ȃ�{���ɍs�����Ƃ������ƂɂȂ����B���������Ⴂ�Ƃ��납���k���o�Ă��āA���̓˂�������ɂ����Ȃ�o��Ȃ��ꂪ���ꂽ�B

�X�^�[�g�͂قƂ�ǐ�k�B
�@������卂���������Ȃ��Ƃ����킯�ŁA������z����̂ɂQ���Ԉȏ�B���̌��k�A�ꂪ����āA��łR�����炢�����̂��Ǝv�����I���͉ΑŎR�ɂȂ����B�y������o��Ƃ͂قlj��������B

��k�̓˂�������ɑS���o��Ȃ���
�@��͊y��������s���Ƃ��������A�����ɑ��邩����R���Ă݂�Ƃ����X���������B���̊��ɂ͏T�������ł����邱�Ƃ����Ȃ��āA�ċx�݂��₵�Ă��܂��B���Ԃ肪���Ȃ��ƁA�Ȃ��ċx�݂̉߂������Ƃ��Ă��������Ȃ������悤�ȋC�ɂ��Ȃ�B

�@�����ɋ߂���
�@�傫�ȑ�͋��H��������Ȃ��āA���ԐH�����Ȃ̂��B�⎿���ΎR�₾���炾�낤���B�C��̒J�������悤�Ȃ��̂��B�����o��Ȃ��ꂪ������A��̃O���[�h���オ��Ƃ����l���ɂ͎^���ł��Ȃ��B���������J�́A�~�ɎR���Ȃ璭�߂邩�A�c����Ɉ�C�ɏォ�犊���Ă��܂��Ɍ���A���ł͂����v���Ă���̂��B
�z���P�x�E������E�I�c���~�Y��@�P�X�W�V�N�X��
�@�z���P�x���ӂ̍ŏ��̑�o�肪���̃I�c���~�Y�����B���v���o���Ă��A���������x�������i�����̌㔼�j�������Ȃ��Ƃ����v���ɂȂ�B�����ȒP�ɂ́A���̕ӂ�̑�ɓ��ꂽ���̂���Ȃ��ƁA�v���Ă����̂�������Ȃ��B���̌㐅�����{���̖k��A�k�̖����n�i��Ɠo�������A�����͍ŏ��ɂ��čł���ۂɎc����̂������B����ɂ��Ă��A���ꂾ���z���Ɏ������Č��ǂR�{�����o���Ă��Ȃ��Ƃ����̂́A���Ȃ�����B������ɂ��Ă��A�k�m���̖{���ɂ��Ă��A���邢�͍r��x�ɂ��Ă��A�O����ɂ��Ă����ׂČv��|��ɏI������B�܂��������A���̈�т̑�o��ȂǁA���F�X���ɂȂ�Ȃ���V�[�Y���Ƃ͂����Ȃ��킯�ŁA����ɂP�O�����ɂȂ��Ă��܂��A�����I�t���}���Ă��܂��B���̂킸�����T�Ԃ̊ԂɁA�T���łQ���Ԃ̐��V���K�v�Ȃ킯���B�������V��̂��߂Ɍv��|��ɂȂ��Ă��܂������̂����m�ꂸ�B�܂����̂��Ȃ��悩�����Ƃ���̂��낤���B
�@�z����т́A�J��x�Ƃ͉_�D�̍��ŁA�^�����ŋC�����̂����ԛ��₪�I�o���Ă����ɂȂ�B�������c����x���܂Ŏc��B����ɑ�ɓ���l�����|�I�ɏ��Ȃ��B���̓o�R�҂ɉ�������Ƃ��Ȃ��B�B�������l�Ƃ����A����̏����̃I���W�����Ȃ̂��B���̍��z���R���̏����͓S���̂T�O�N�ϗp�ł��闧�h�Ȃ��̂Ɍ��ĕς�����B�����ɃI���W������Ƃ����̂ɁA�h���͑f���܂�ŃV�����t�̎��Q�����B�����J�b�v�k�[�h�������͔����Ă��āu�������炢�Ȃ�o�����v�Ƃ������z�̂Ȃ����̂������B�I���W�͂Q�T�ԂɂP�R���āA�������H�ׂ镪�����̖���グ��Ƃ����Ă����B���q�̐H���Ȃǁu�����グ���Ȃ���v�Ƃ����̂��B�����������͖{���ɗ��h�������B����ɋq���قƂ�ǂ��Ȃ��B����Ȃ�A�����ɂP�T�Ԃ��炢�U���āA��l�Ŏd���ł����邩�H�͂��ǂ邾�낤�Ȃ��A�ƂĂ��������Ǝv�������̂������B�@
�@�z���̑�ɓ���ɂ́A�ꉞ�����̊o��͂�����̂������B�Ƃɂ����Ղ�����Ƃ����̂͊F���ɂȂ�B��U�������ɓ����Ă��܂��ƁA���~�͊ԈႢ�Ȃ��������~�ɂȂ��Ă���B������S�O���[�g���߂��͉��̎肪������Ȃ���k���Z������̂P����̃X���u�B����ł������̌o���Ɏ��M���������̂��낤���A���قǂ̕s�����Ȃ��A�N���u�̂Ȃ��Ńp�[�g�i�[��T���ĂQ�l�œ������B���̔ނƂ͒J��x�E�����Y��ɓ��s�������Ƃ��������B��o�肾���ɂ��ẮA�Ⴆ���肪�V�l�ł����Ă��A�����A��čs����C�T�͂��������̂��B

�J�O���ꂾ�������A�T�i�M�ꂾ�������B���グ��U�i�Q�O�O���[�g���Ɍ����鍋���ȃt���[�N���C�~���O�B
�@�I�c���~�Y��̏o�����́A�����쉈���̗ѓ�����ɂȂ�B�A�X�t�@���g�̗ѓ����̃h�J���ɁA���͗���o�Ă����B�����Ȃ�X�̂����X���u��̊�ŁA��͗ѓ�����삯�オ���Ă����B�O�G����Ȃ������Ȃ�j�S���B�ѓ��ŃU�C�������э����B
�@���[�g�}������ƁA���̑�ɂ̓J�O����ƃT�i�M��̓�̑�ꂾ�����������Ă���悤�Ɍ�����B�m���Ƀi����̃X���u�ŁA�傫�����́A�U�i�Q�O�O���[�g�����炢�������悤�Ɏv���B���ꂪ���Ɋy�����o�ꂽ���̂��B
�@���̑��ڂ̓�����ɂ����Ƃ��ɂ́A���R�Ƃ������̂��B����قnj|�p�I�Ȃ��̂��A����Ȑl���m��Ȃ��c�ɂɁA�������o�R�҂̊Ԃł����قǗL���ł��Ȃ��Ƃ���ɑ��݂��Ă����̂��낤���ƁB�������d����A����̊댯�����܂������Ȃ��B���̐S�z���Ȃ��B�K�C�h�ɂ��u�����ȃt���[�N���C�~���O�v�Ə����Ă������悤�Ɏv�������A�܂��ɂƂ̒ʂ�ɂȂ����B�Ȃ�ʼnz�����ɂ���ȉ��K�ȃX���u��ꂪ���݂���̂��낤���Ǝv�����B���̎R�s�̌�ɁA�����������������ɂ��闘����̉z���ɂ��s�����ƂɂȂ�̂����A�����ɂ������悤�Ȍ����ȑꂪ�������B�����R��̓����x�t�߂ɓ�����̂��낤���B����܂ł������̑��������A�o������A���������肵�Ă����̂����A�ł����l�̂����́A�܂��ɂ��̕ӂ�̑�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���Ǝv���Ă���B�X�͒n�`���c���Ă��邩�A�L�x�Ȏc��̃u���b�N�����ɖ�����Ȃ�����A���ꂾ���̑�͏o�����Ȃ����̂Ȃ̂��Ǝv����B�z���̑�̐ϐ�͂T�O���[�g�����O�ɂȂ�̂��B
�@�I�c���~�Y�͎��͑�ꂪ�Q�����������ł͂Ȃ��B�o��ɂ����P�O���[�g�����O�̑ꂪ�A�����ɏo�Ă����B���������ɃC���ɂȂ�قǁB�P���ڂ������̂悤�ɒ��̂U�����Ɏ��t���ė[���̂T�����܂ŁB�Q���ڂɒ���ɔ������̂��[���ɋ߂������͂��ł���B�r���̂�т肵�Ă����L���͂Ȃ��B�������̒���t�߂���A���E�̊։z�����ԓ��������A�傫���֍s���Ȃ��瑖���Ă���̂��������L��������B�܂��̓o�s�����ŁA�Q�O���Ԃقǂ������Ă��邱�ƂɂȂ�B���R�̓w�b�h���C�g�̒��ɂȂ����B�։z�����S���Ԃ��炢�œ����ɔ���Ă��A�������p�[�g�i�[�͍Ŋ���JR�̉w�Łu�n����҂��ċA��܂��v�Ƃ����Ă����悤�ȋC�������B���̂܂o���鎞�ԂɂȂ��Ă����B�����͒Z����Ȃ̂����邪�A���ꂾ�����x�������A��������Ă����B
�u�����ȃt���[�N���C�~���O�v�Ƃ����̂́A���悻�R�����x�̊�o�肪�A���X�Ƒ����Ă����Ƃ����Ӗ��ɂȂ邾�낤�B�w�łȂł�ƁA�^�����Ȋ₭�����t�������Ȃقǔ����B����ɐ����ɖ����ꂽ��́A�Ⴆ�J���~���ĔG��Ă��A�ۂŊ���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��̂��B���i�̓J���J���Ɋ����Ă��āA�ۂ��琶���Ă��Ȃ��B���̑�ɁA�m�������b������͂P�Q���ɃA�C�X�N���C�~���O�œ��������Ƃ��L�^�ɏo���Ă������Ƃ��������B���̍���n�т̐ϐ���ɑ�ɓ���̂��B����قǂɂ܂̊��Ⴂ���N�������Ă��܂��قǁA���̑��͖��͓I�Ȃ̂ł���B
�@���̐�����̖{���̖k��ɂ���֖�̑���A������̓X�P�[���͏������T�O���[�g���قǂ��������A�����������悤�ɉ��K�ȃt���[�N���C�~���O�œo�����̂������B����ɂ��̐�ɂ��A���X�ƃX���u�������Ă������̂��B�u�������͂��������X���u��o�邽�߂ɁA�������ĉ��X�ƂP�O���Ԉȏ���̃A���o�C�g�ɑς��āA��̉��[���ɐN�����Ă���̂��v�Ǝv�������̂ł���B

���̏㕔���s���B
�@��o��͂�����x�o�傪�ł���ƁA���������Ă��|�����Ƃ͂Ȃ��Ǝv���Ă���B�o��Ȃ��ꂪ��������A����͍����������B�s�������Ȃ�U�C�������ēr���܂ōs���Ă݂�B�����j�������Ȃ�A�o�債�Đ��ɓ����Ă����B�Ƃɂ����O�i�s�\�ȂǂƂ������̂́A���Ȃ��猕�̌��̑��ƊC��̕s���삭�炢�Łu���̂ق��͂�قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����A�Ȃ�Ƃ������ł�����̂��v�ƁA�������ߍ���ł������̂������B
�@�ނ��낻��܂ł̌o���̒�����ӊO�������̂́A�b���P�x�̔�����ɂ������Ƃ��̂��Ƃł���B�ŋ߂ł͉��������ȗ����āA���˔����̂T���ڂ��痬��ɉ��~���Ď��t���Ƃ������@���Ƃ��Ă���悤�ł��邪�A�Ȃ�قlj���������R���Ă݂Ă��ꂪ�킩�����B�Ƃɂ����ŏ��̑�ł���A���̂��������ʂ��ɔ����ŁA����͊��S�ɓo��Ȃ����̂Ȃ̂��B�\�z����āA���̂Ƃ�����͂�����Ƌ������B����ɑ����ďo�Ă����������悤�ɂ܂��������t�����Ƃ���ł��Ȃ��B�ł��W�����Ⴂ�Ƃ���Ȃ̂�����A������ł��������Ƃ��ł���̂����A����ł��u�b�V���т�~�������āA����������J���Ă��܂������̂��B�p���ɂȂ肻���ȓ�����������B����Ȃ��ƂłP���ڂ͖��p�Ɏ��Ԃ�Q����B�Q���ڂ́A���@�J�̉E�҂���R���Ɍ��������̂����A��͂肻���ŗ[�����}���āA���˔��������R���Ă����̂͐[��ɂȂ��Ă����B����͂܂��U���ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��Ƃ��ŁA�k���V���[�Y�Ɣ�̓o�R�C�ƃA�C�[���s�b�P�����g�s������o�肾�����B
�@���̕ӂ�ł́A�啐��̌K�ؑ�A��͂P���Ŕ�������������A�{�����s�����Ƃ��ɂ́A�ނ�����˂��y���C������������Ȃ̂��A�ѓ����ĂP���Ԃ���̂Ƃ���̃S���W���ōs���l���Ă��܂��A�E�������������̂̌��Lj����Ԃ��Ă��܂������Ƃ��������B�y�j�͒��̂P�Q���ɂ����Q�Ă��܂��A���_�ƋC�����ċN�����̂͂P�W���Ԍ�̗����̒��ɂȂ��Ă����B�d���̔����R�Ɏ����Ă����ނ�R�s�ɂȂ����B����Ȏ��Ԃ����₩���őO�i���Ă݂悤�Ǝv���Ă��A�p�����卂�������Ă��̃S���W����ʉ߂��Ă���悤�Ȃ̂����A�����T�����C���Ȃ������B�m���N���u�̒��Ԃ̈�l�ɁA�b���̐ԐΑ�̉��ǂŊ�o������āA�A��ɉ������Ⴂ�����̂��A�{�������X�Ƒ�ɂ����ĉ��R���Ă����l�����āu�Ƃ��Ă��Ђǂ������v�ƈꌾ���������Ă������Ƃ��������̂����A������̃S���W���Ƃ����̂́A������ƊԈႦ�Ĉ��Ղɓ����Ă��܂��ƁA���ꂪ�O�i�s�\�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�������̂��A�����Ƃ��Ȋo������Ă��Ȃ��ƁB��͂��܂ł����Ă��o�R�҂����낽��������B

�����͎��ɂ��ƂȂ����Ȃ��āA���ʂ̉͌��̂܂܉z���P�x�̎R���ɔ������B
�@���Ƃ����̂��A���̎x���ɂȂ�̂������̓��ɂ��������Ƃ�����B�������������I���͂قƂ�ǃ}�j�A�ɋ߂��B�Ȃ�Ƃ��̑�Ŏ������͐��N�O�̔������̂̑���҂����Ă��܂����̂��B�Q���ԁA�܂������l�̋C�z���������Ȃ���������̂����A�������ɂ����Ȃ�Е��̌R�肪�����Ă����̂��A���ꂪ���Ɉٗl�Ɍ����āA�E���グ�Č���ƁA�������d�������l�܂��Ă����B���v������͎�̍b�̍��������̂��낤�B�������Ă����ƍ��x�̓Y�{���������Ă���B����ƌ㑱���Ă������_���u�����H�����H�v�Ƌ���ł���B�[���������ɂ͂������̂��B�킪�N���u�ł́u���悯�̃h�N���}�[�N�v�Ɉ���������̂����A���̖{���ɏo����Ă��܂����̂��B�r�̍��A�����A���̍����m�F�ł���B���≽���|�����Ƃ͂Ȃ��B�R�ł����Ȃ�\�z�O�ɏo����ĕ|���̂͐����Ă���l�Ԃ����B������͂��C�̓łɁE�E�E�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂��Ȃ��Ő��ɔ����āA����͖P���O�R�̒n���x�ɂȂ����B�����̏����ł��̎|�����Ə����Ԃ͂����Ȃ�吺���o���āu���[�A����͖{���Ȃ̂��H�v�ƁB���Ă��邱����͂��̐��Ƀr�b�N�������قǂ������B�ǂ����R�N�قǑO�̏H�̒P���s�҂̂悤�ŁA��������R������������Ƃ����A�߂��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B������x���{�������炵���B����ł����悻�̘b�����������ŁA�����낱�̂Ƃ�������ɏo���̂͗[���ɋ߂������B���R���Č���z��̏����Ɏ������͊���āA�����œ͂���Ƃ������ƂɂȂ����B�Ƃ��낪�R�[�œo�R�����炢���Ȃ�ѓ��ɏo�铹���A�N���}��u���Ă����W�őI�������́A���̂܂܌���ɂ�炸�ɁA�Ƃ肠�����B��̉w�܂ł����A���R�j�����Ƌ������ɂ܂�������̂����A���͂��̋������ɂȂ�ƒn���x�@�ƎR�x�W�҂��������̉��R��҂��Ă����̂��B�u�����A����Ҕ����̌��ł����H�v�u���������Ă���̂��ˁA�����҂͌���ɉ��R���邱�ƂɂȂ��Ă��āA�������͂����҂��Ă���B����ɂ��Ă����R�̒x�������҂Ȃ��Ȃ��v�ƁB���łɐ[��ɂȂ��Ă���B�u���̔����҂Ƃ����̂́A���ł���v�u��H���H����ɂ܂����R���Ă��Ȃ���v�u�������A�Ⴄ�����牺��܂����v�u���ł��̓X���ƕ��������v�u����A���܂��܁B�������͂������������Ă��Ȃ���������v�B����Ȃ����̂��Ƃɂ��炭���āu�����A����Ҕ����ɋ��͂��Ă��ꂽ�̂́A�N�����Ȃ̂��B�������������A����͖{���ɂ��肪�����v�Ƒ劽�}����̂��B�W���b�L�r�[�������{���������Ă��炢�Ȃ���A�ނ�͍q��ʐ^�������o�����B�ׂ̐ȂɁA�n���x�@���������B������ɂ��Ă����}������Ă���B�u�����ꏊ�͂ǂ��ł����H�v�B�������R�N�O�̑{�����̍q��ʐ^��������ꂽ�Ƃ���ŁA����Ȃ��̂悭������Ȃ��̂��B���͔����ɂ����悻�̒n�}�������B�u�����̓�Ɏ��n�т������āA���̎�O�ɕ��n�������āA���̎�O�ɂ₹�����������āA���̃R���Ɏ������͓��o������v�ƁB�u���̓o����R���قǎ�O�ɂ��ꂪ�������v�ƁB�Ƃ��낪�u��ȕ������Ȃ��H���̕ӂ͏�������R���Ɍ������t��������Ȃ��H�L�~�����{���ɓ��o�����́H�k��Ȃ��́H�v�u���̂˂��A�Q���|���đ�o�肵�āA��������ԈႤ���Ƃ���킯�Ȃ��ł���B����Ȃ��Ƃ�����A������������ł���v�B���ǂR�N�O�̑{���͗\�z�O�̕����������炵���B�u�������̂₹�����ɖڈ�ł��H�v�u�����A����͖Y��Ă��܂����v�B�������߂Ď������������ɓ��s������̂��Ƃ���v���Ă����̂����A�u�����A���̂��b���āA������ő{���ł��܂���v�ƁB���̗��������X���ɂ́A�����ɔނ�͎R�ɓ������悤�ŁA�����ł��܂����Ƃ̘A�������B�⑰��������͂����B�ނ��뎄�����́A�����ʼn��{���̃W���b�L�r�[�������y���ɂȂ��āA�[��̂P���߂��ɓX���o�āu���C�����āv�̈ꌾ�ŁA������ꂽ���Ƃɕs�v�c�Ȏv���������B
�@�\����{���̃t���J�Ƃ����̂́A�����̉ΑŎR�̖k�ʂ���{�C���璼�ڏオ��J�ł��邪�A���̂Ƃ������{���ɓ����Ă����̑���������������Ō�A���X�Ƒ卂�����ɏI�n���Ă��܂����R�s�ɂȂ����B��̒��łQ�������̂��낤���B����ł��Ő��ɏo�钼�O�ɂ́A�S���W���̗l����悵�Ă����k���߂āA���Ԕ��Ɖ_�C�̓��{�C�ɒ��ޗ[�z���y���߂����̂������B
�@�ǂ��֓����Ă��A�������҂𗠐�Ȃ������̂͂�͂荕����ɂȂ�B�����̏�m�L���̑��ɂ́A������̍����E�����J�̖{���ƃJ�V�i�M�[�w�J�B�k���J�̘R�l��B��������S�C�T���̎R�s�ɂȂ����B�����J�̖{���͔��n�x�ɓ˂��グ�A���̌������͂��t�X�L�[�̃��b�J�ɂȂ��Ă���ƕ����ƁA��������������������F�l�ɂQ�O�N�Ԃ�ɏo������悤�Ȋ��G�ɂȂ�B
�@��o��̃v�����́A�������R���[�̃��[�g�}�W�ɗ������̂����A���̒��ł���͂肱�̉z�����ӂ̑�o��ɏo������Ƃ������Ƃ́A����R���悭�m�邫�������Ƃ��Ȃ����B��̎R���\����������ƕǂƑ�̊W������Ȃɂ����͓I�ɕ�����₷�����o���Ă����R�����������͂Ȃ��B���ɒO��Ɖ������̑�o�肾�������m��Ȃ������Ƃ���ƁA���ꂱ����o�肪�ł��Ȃ��҂��A��Z�ȑ�ɓ����Ă��邾���Ǝv���Ă��d���̂Ȃ����ƂɂȂ�B�R��o�~����Ȃ��ŁA��͂ƂĂ����͂�����̂����A������댯�ɕx���͂Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��A�}�炸�����������Ă��ꂽ�̂��A�����������ꗬ�̑f���炵�������̂ł���B
������E�z���@�@�P�X�W�W�N��
�@��o��͓s���łP�O�V�[�Y�����炢�M�����Ă������ƂɂȂ�B���N�U������X���܂ł̂S�����B�T���ɂ��ĂP�W�T�B���̊ԉċx�݂ɂ͂T���Ԓ��x�̒�����o��������Ȃ����B�S���R������Ȃ�A�����̕S���J��k�s���Ă݂悤�ȂǂƂ����A�Ƃ�ł��Ȃ��ڕW�R�ƌf���Ă������Ƃ��������B�J�œ��R�ł��Ȃ��T���������̂����A����ł��V�[�Y���ɂP�O�{���炢�̑�o������Ă����Ƃ����A���N�͑������B
�@�����͎d�����A���j���̎d���������[��ɂȂ邱�Ƃ����������B����ł��[��Ƀ����o�[�Ɠs���ő҂����킹��A���̎ԂŖړI�ɒn�ɂ͒��̂U�����܂łɂ͒����B�������Ƃ炸�ɂ��̂܂ܓ��R���āA���̓��͑�Ŗ��c�B�����ɗŐ��ɔ����ĉ��R����Ƃ����A�܂��n�[�h�X�P�W���[���ł��������̂��B
�@�V�[�Y�����߂̂U���͒O��Ƃ��������̓����ߍx�̑�o��������āA�V���ɂ͓�A���v�X�A�W�����}���Ă悤�₭�ړI�̗����삾�Ƃ���z�̑�ɂ�����悤�ɂȂ����B�Ƃɂ����V���܂ł͎c��̉e���ŁA�܂��܂���o��̃V�[�Y���ɂ͑�������Ƃ������ƂɂȂ�B�z���P�x�ɏオ���ł́A�X�����I��肾�Ƃ����̂ɁA��k�̏�Ŗ��c�������Ƃ�����B����ł��Đ��̊m�ۂ��ł��Ȃ��B���傤���Ȃ��Â���̒��ŁA��k�̊���Ă���Ƃ����T���āA�U�C���ɂȂ������������ɓ�������āA����Ő��������Ƃ��������B�܂�ň�ː������ݏグ�Ă���悤�������B�܂薋�c�����[���̂��̎��Ԃł́A��k���~��郋�[�g�������ł��Ȃ��������ƂƁA�ӂ��т��V�������h�Ɉ͂܂�āA���łɐi�ދ��܂��Ă��܂����Ƃ������Ƃł���B����ł������P���܂����ɂ�������Ǝv���A�Ƃ肠�������ɂȂ�܂ł̐�k�e���g���ȂǁA�����ł͓���I�Ȃ��Ƃɂ��߂������B
�@�V�[�Y���ɂP�炢�́A���j�̂����ɉ��R�ł��Ȃ����Ƃ��������B���̐�k�h���́A�z���P�x�̐�����ɍs�����Ƃ��������낤���B�o�����x�ꂽ���������������A���j�̖�ɂ܂��㕔�S���W���̒��ɂ����B�����z���̑�n�i��ɂ������Ƃ����A�\����啝�Ɏ��Ԃ�Q��Č��j���R�ɂȂ����B���̂��z���P�x�̑�͎��Ԃ����������B���ォ��O�V�K�n�i�̗Ő��𐅖���ɉ��肽�Ƃ��ɁA�Ō�̐�̓n�_��������Ȃ������B�ǂ������Ԃ��x���̂��B������o�������̂��[���̂S���B���ꂾ����Ɏ��Ԃ����������̂����炵�傤���Ȃ��B���̂Ƃ����łɊJ�������Ă����B�m���X���͂T�������炢�܂Ŗ��邢�B�S���ɉ��R����ƂP���Ԕ������͖�����̒��������B���̎��ԓ��ɏ㕔�̊�S�c�S�c��ʉ߂��Ă��܂��A���Ƃ̓w�b�h���C�g�̉��R�ł����Ƃ��Ȃ邾�Ƃ��Ƒ��_�Ɗo��͌��߂Ă����B�����čŌ�̓n�_�ɂ����̂��A��X�����������낤���B�������ȃy���L�}�[�N�����܂ɂ���̂����A���͂��P���Ԃ��炢�T���Ă�������Ȃ��B�K���ɐi��ł��s���l�܂��Ă��܂��B�����ɓn�낤�Ƃ���ƓK���Ȕ�ѐ���Ă��܂��B����ɓn������̓��ݐՂ�������Ȃ��B���̂����ɕ�������Ă��鎩�������̓��ݐՂ��A�Ȃ����m�ȓ���̂悤�Ɍ����Ă���B�u������߂悤�v�ƁA�����Ƀe���g���B�܂����j�̒��ɂȂ��ē����o��A�ȂA�������Ȃ������Ƃ������͕�����̂��B�R�̒��̖�Ƃ����̂́A�����������̂��B
�@���j�͖��f���Ƃ������ƂɂȂ����B�u�����������ɂ͓d�b���炢�����v�Ɨ��A�Ηj���ɏ�i�Ɍ�����B�������R�̒��œd�b���Ȃ��B�u����A�O�����ċ��j�ɓd�b���Ă����v�Ƃ����A���ꂪ�Љ�l���낤�ƁB�ǂ��������Ă����E�̐l�Ԃɂ͗����ł��Ȃ��B�������̂��ƁA����������Ƃł������A������₷���̂��낤���B
�@���ė�����̑�o��ł���B�������̑�ƌ��������Ă����B��ؑ�_���̏㗬���w���B���͂��̃_���̒ʉ߂ɂ���B��ؑ�_���Ƃ����̂́A�Ⴆ�Č������l�_���Ɠ������炢�L�����̂��B���������͂ɓ����Ȃ��B�̂̍z�R���Ƃ̓��ݐՂ�H�����Ƃ��Ă��A�{�ɂ́A���t���܂łP�O���ԂƂ������Ă���B������������������l���A���̉������̉��l�ƌ�����n���̏���Ȃ̂ł���B�ނȂ�P�����낤���A�����ŏ��ɗF�l�Ɠ������Ƃ��ɂ́A��������������B���̂Ƃ��ł���A���͂₱��������l�͂܂�Ȃ̂ł���B

�S�l���̃S���{�[�g�ɂR�l���Ə㔼�g�͂͂ݏo���Ă��܂��܂��B�����ł���l���B�e���܂����B�i��ؑ�_���������j
�@���̌㉜�����ɓ���Ƃ��ɂ́A�S���{�[�g���g�����Ƃɂ����B�S�l���̒ނ�p�̃S���{�[�g���ƂS���Ԃʼn�������n�ꂽ�B�ۈ�X�|�[�c�ق̃N���W�b�g�łS���~���炢�Ŕ������{�[�g�ł���B�D���ȓo�R�����邽�߂ɂ͂�����ɂ���ł͂����Ȃ��ȂǂƁA�����ɉۂ��Ă������̂������B����ł����Ɨp�Ԃ̃o�b�e���[��d���ɂ��ċ�C������A�T�����x�ł����Ɩc��B�����ɓo����̓������U�b�N�ƁA���̂Ƃ��̎R�s�ł͂R�l����荞��ł��A�����ƃ{�[�g�͋@�\�����B�����S���{�[�g�Ƃ����̂́A���̂��炢�̏��^���ƒꂪ�^���ɂȂ��Ă���B�Ƃ������Ƃ́A�D�Ƃ��Đ�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ŁA����Ńo�����X�悭�����ł������ł��A�D�͂��̏�ł��邭��Ɖ���āA�i�s������ς��Ă��܂��̂��B�X�̏�������Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B������܂��A�ǂ��ɂ��i��ł����B���������ɂ��ă_���T�C�g����_���K�܂łW�L���قǁB�����Ƃ��ꂪ�R�{�����肵�Ă��������ݐՂ��r��āA��̓�����B�{�[�g�Ȃ玞���Q�L���Ƃ����킯�ŁA�S���ԂŖړI�ɂɂ��B����Ƀ{�[�g�𑆂��͂Ƃ����̂́A�債�ĘJ�͂��g��Ȃ��B�S���ԗ����Ă��قƂ�ǔ��Ă��Ȃ��B
�@���̃{�[�g�Ń_���������Ă܂œ��R���鉜�����̎R�s�́A���ǂQ���Ȃ����B�Q��Ƃ�������x���̉z���ɓ����āA�������̉E���ƒ��������ꂼ��̋@��ɓo���Ă���B��������o���ɂȂ��Ă��܂����B���̂Ƃ��͂��̉E���R�s�������낤���B�T���̓���Ԃ̗\��ł��������̂������B
�@���U���Ƀ{�[�g�𑆂��o���ĂP�O�����B�[���̂T���܂łɖ{������A�x���̉z���ɓ����āA���̉����Ńe���g���B�����͒����炢�܂łɗŐ��ɔ����āA�x�������o�����ɉ��~���āA����ɖ{�����j�����肵�ĉ���B�Ăу{�[�g�ɏ�荞�̂͗[���B���ꂩ�炳��ɂS���Ԏ葆���Ŗ߂�̂�����A�^���Èł̃_�����T�C�g�̉��̊ɌX�Αт�ڎw���Ă����킯���B�s�������Ŗڂ̑O�Ƀ_���̂��̋���ȕǂ��o�������Ƃ��ɂ́A������Ƃ����������̂��A�����߂��������B�Ƃɂ�������������́A�o������Ő��ɔ�����܂łɂP�O���Ԓ��x������ȏォ����B�T���̓���ԂŁA�ŒZ���Ԃ��Ƃ������B
�@�z���ɂ́A�R�i�łQ�C�R�O�O���[�g���̑ꂪ����B��ɓ����Ă܂��Ȃ��A�E���A�����A�����ɕ���B���̂ǂ�ɂ����̃T�C�Y�̑ꂪ�|�����Ă���B�Ƃ͂����Ă�����̓t���[�N���C�~���O�œo�����x������A���ꂪ�܂��y�����B�鋫�ɂ���f���炵����Ȃ̂ł���B

�z���E�����̌㔼�����B����������_�ȑꂪ��D���ł����B
�@�Q�n���̂��̉������ƁA��̐V�����̉z����т̋��쑤�̗���Ƃ́A���͂킸���ɂP�{�̔��������ɂ��āA�ד��m�ɂȂ��Ă���B����͗�����̌����̑吅��R�Ƃ����P�W�O�O���[�g�����炸�̎R���A���͌Q�n�A�V���A�����R���̌����ɂ��邩�炾�B���̗l���͂܂�A��z�̍�����Ƃ����Ă��������炢�̔鋫�Ɩ��͂��������B���ɂ��Ďv���A�m�炸�m�炸�̂����ɁA���͂��������R�悪�D���������Ƃ������ƂɂȂ�B����ɂ��̈�т̎R�́A���w�̔������ԛ���ō\������Ă����B��o�������ɂ͍ł��y�����⎿�������B����͌��x�̃`���l�Ɠ������̂ŁA�^�����Ŕ������B�J��x�̂��̋t�w�̂���炵���X���u�̊�̐������Ƃ����Ă����B����ɐϐ�ʂ����x��тƔ䌨����قǂ���B�X���ɂȂ��Ă��c��͖L�x�����A�܂��������č~���Ƃ��ɕ�����̂����A�S�O���[�g���U�C�����_�u���ɂ��Ėڈ�t�L���Ă悤�₭�쏰�ɍ~�����Ƃ����n���ŁA�܂肻��ȉ��ɂ͊����琶���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B����͐ϐ�ʂ����傤�ǂS�O���[�g������Ƃ������Ƃ̏ؖ��ɂȂ�B�����玄�́A�V�~���̂S�T���[�g���U�C�����Q�{�����p�ӂ��Ă����B��ʂ̉�����X�~���S�O���[�g���̃U�C�����������Ă��Ȃ��āA������Ɏ����Ă����u����ŏ\���ł���ˁv�Ƃ����ƁA�܂������V���E�g��o�艮���Ɣn���ɂ��Ă������̂������B�d�������Ŗ��ɗ����Ȃ��B�u����Ȃ̂���Ȃ�����A���̂�����P�{���āv�ƁB����ƁA�u����H����y���ł��˂��A����Ȃ�ł�����ł����H�v�Ƃ����B���̍��̑��_�́A���łɌ�y����Ɍ����Ă����B���N�����́A�����A�d���ŎR���痣�ꂽ�B
�@���o���Ă���̂́A�Г��Ŏ葆�����S���Ԃ������ŁA�悭���������ɓ������Ȃ��Ƃ����L�����唼���B�Ȃ������u�o��v�Ƃ����ˋ�̎g�����B�n���̏����A���邢�͊m�������V���̖����L�҂̖{�����ꂳ����A�������Ɍ�ɓ����Ă���̂����A�����͂Ȃ������D�ł��̃_����n���Ă���B�n���R�x��̖��Ȃ̂��낤�B���T�t���Ȃ̂��B
�@����ɂ��Ă�����������́A����ȑO�ɐl���ʂ����Ƃ������Ղ���قƂ�ǂȂ��B���[�g�}�ɂ͏Љ��Ă���̂����A�N�ɂP�p�[�e�B���������͑������炢�Ƃ����悤���B
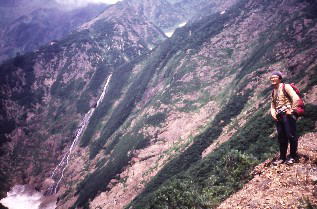
���R�̓r������̑��̂悤���B�Q�O�O���[�g���ȏ�͂���܂��B���������ꂪ�o�����E���������̂��A���邢�͒����������������̂��͖Y��Ă��܂����B���ꂼ��̎x���ɂ������悤�ȑꂪ�������Ă��܂��B
�@���͍K���Ɏ������g���R�ʼn�����������Ƃ͂��������͂Ȃ��̂����A�m�����̂Ƃ��̎R�s�ŁA���������������Ă��āA�Q���[�g�����炢�v�킸�����Ă��܂������Ƃ��������B����ʼnE����������ɂԂ����B�Q�Z���`���炢���̔炪��āA�����Ă��锖���s���N�F�̖��̂悤�Ȃ��̂������Ă��܂����̂��B�債�Ēɂ��͂Ȃ������B���������u�͑����ق��������Ǝv���āA����ɖ߂��Ă��瓖����̈�@��T���ďo���������̂��B�����̌ߑO�Q�����ɂȂ��Ă������B������͉�������~��Ă��āu�Ȃ�ŁA�����Ƒ������Ȃ������́H�v�u���Ƃɖ߂��Ă�������ł�����v�u�{���͖D�����ق����������ǁA�܂��[�邾���A���̂܂܂ł��������Ȃ��v�ƁB�܂����̒��x�Ȃ�悩�����ƁA�����ɂȂ��Ă���҂ɂ͂������ɁA�܂��Ȃ����͎������̂����A���͂��̂Ƃ��̏��Ղ����ł��E�������Ɏc���Ă���̂��B�D�����킹�Ȃ������̂����������̂��B�������ɂ�������Ă͂��܂����̂����A���ł����C�ɓ������Ƃ��ɂ�������Ă��܂��ƁA�u�܂�Ȃ����ƂŎ��s�����R�s���������Ȃ��v�Ƃɂ��ɂ������A�v���o���B����ł�����Ȃ�����������킯�ł͂Ȃ��̂����炢���̂����B
�@���̂Ƃ��͊m����y�̊w����l��A��Ă����̂����A�A���͐�y�̎����Ō���Ȃ̂��������ƂɁA�ڈ�t��l�ő����ēo��܂���̂��B�������j�S���͉߂��Ă���B�܂�����Ȃ��͕̂����Ă��������̂����A���̂��x��Ă��鎄�͏����ł��ĕt���Ă����B����ȂƂ��ɕs�p�ӂɊ���͂�ŁA���ꂪ�܂ꂽ�Ƃ������s�������B
�@�p�[�g�i�[�ƔN�オ����Ȃ��Ƃ����̂́A���������Ƃ��ɂ܂�Ȃ����̂��B�R�s���ɘb������Ȃ��B������͂����������Ďq��������B�������͂Q�O���߂�������̊w���B�Ⴓ�ɂ��̂����킹�ăo���o���o�邩�Ǝv���ƁA�������Ă��Ă��������ɉz�����������������������Ă��u����́A�����ł����ł���v�ƁA���ȕ���������B�u�����J��������A�ǂ����v�B�u����A���v�ł���v�B�����ӋC�ȂƂ�������B���̂Ƃ��̎R�s�ł́A������Ǝ������b�Ƃ��čς��A���̂���w���p�[�g�i�[�Ƒg�Ƃ��ɂ́A�R�Ŏ������������̂ŁA������߂Ă��܂����҂����l�������B�����͎����̊w�������U��Ԃ��āA��͂萶�ӋC�ő���Ȃ��Ƃ���͂��������낤�Ǝv�����A�o�R�̃p�[�g�i�[�Ƃ����̂͒ʏ��l�ŁA����͓��N�オ��͂肢���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���ӋC����͂��ꓯ�m���g��ŁA���邢�͂��ꂪ�����Ŏ��s���Ă��A����͎��Ǝ����Ȃ̂ł���B�Ⴂ���肪�P�O���N���ɁA�N���҂𗧂����Ȃ���o�R����ȂǁA��قǐl�Ԃ��������肵�Ă��Ȃ��Ƃł�����̂ł͂Ȃ��B�P���ɑ̗͏��������̓o��ɂȂ�ƁA�N���҂͂�͂�x�����̂ł���B����Ɂu����Ƃ����ɉz�����v�Ƃ����N���̐ӔC���ʂ��������ƂŁA����͂�����肵�������Ŗ������𖡂���Ă���̂��B���ӔC�Ȋw���͂��ꂪ������Ȃ��B�ǂ����w���A���ȂǁA�A�E���ēo�R�����߂Ă��܂��҂��唼�ɂȂ�B���̂Ƃ��̃����o�[��l�����̌�̏����͕�����Ȃ����A�N���u�͂Ƃ����Ɏ��߂Ă��邵�A���Ȃ��Ƃ���l�͏A�E���ēo�R����߂Ă���B����ȓz�̂��߂Ɏ����C���g���āA���̑㏞�ɉE���ɂQ�Z���`�̏��Ղ����ł��c���Ă���̂��Ǝv���ƁA�m���ɕ����������Ƃ�������B�����������_�I�ȃV���b�N�������̌����ŁA��o��́A���̂��Ɛ��N�Ŏ��߂Ă��܂����B�������o�R�ɖO�����A�N��I�Ȃ��Ƃ�����̂����B
�@�ł����ƂȂ�ƁA��͂艜�����ɂ́A�܂����͂���������̂��B�����͏�z�̍���������ł���B����ɍ����ȏ�Ɍ�ʂ̕ւ͈����Ƃ��낾�B�����̃X�L�[�œK�����T���̃S�[���f���E�B�[�N���Ƃ���Ȃ�A�������������ł���B�����ꂻ������s���Ă݂����C�͂��Ă���̂����B
�O�䍂�x���ʁE�������J�@�P�X�W�W�N�@�P�O���W�`�P�O��
�@�������̒r�Ƃ����Ƃ���ɁA����܂ōs�������Ƃ��Ȃ������B�㍂�n�`�����Ԃ��A����܂ł��������������Ƃ��Ȃ������B����㍂�n�Ƀ}�C�J�[�œ��������Ƃ��Ȃ������B����ȗ��R�ŁA�������J�ɍs�����Ǝv�����B�㕔�ɕH�`��ǂƂ����₪���邻���ŁA��������Ă݂����Ƃ����C�������������B�N���u�̐V�l��A��Ă̎R�s�ɂȂ����B

�������JF1�̎x��
�@�����㍂�n�͉Ă̖~������`���A�}�C�J�[��������邱�Ƃ��ł����B�������������o�āA���ɏ㍂�n�ɒ����B���ԓI�ɂ͗����Ɏ��t�������킯������A����Ńe���g���B�H�̘A�x�ɂȂ�̂����A����͐l�����Ȃ��āA�Â��łƂĂ����������������B�����㍂�n�`�����Ԃ͑����ɍQ�ĂĒʉ߂��邾���̏ꏊ�ł��Ȃ��B
�@�p�m���}�R�[�X�̉������J�̂Q�{�ׂ��A���̉������J�ɂȂ�B���E�i�Ƃ����Ă�����̂��Ƃ����j����߂����ɂ͕s�����͂��Ă��邵�A�l������Ȃ�����J���育�킭�A�ȒP�ɓo��Ȃ��Ƃ����̂͒��ׂĂ��������ƁB�N�����Ȃ��͌����A������l�œ����Ă����B

F2���t���ւ̉��~
�@�����P�O�����Ƃ����̂ɁA��͂�c�Ⴊ����B�ŏ��̑�ɏo��O�ɐ�k�ɂȂ����B���̐�k�̏��i��ł����̂����A��͂��ɂ���č~���ꏊ���Ȃ��B�V�������h���傫�������J���Ă���BF1�͓����̎����ł͖��o���Ƃ������Ƃ��������A���ʂ�������ł��邱�ƂƁA��k����~����Ȃ����Ƃ��A���t�����Ƃ����ӗ~�����킹����̂������B�E���̎x���ɓ����āA�������㕔�܂œo���ăg���o�[�X���Ǝv�����̂����A���̎x���ɓ��邽�߂̐�k���~��ɂ����B�������傭��k�ォ��ǂɃA���O�����P�{�ł�����ŁA������x�_�ɐ�k���܂Ō������邱�ƂɂȂ����B�ŏ��̑�̎��t�����炱��ŁA������Ǝv�����ꂽ�B�����Ďx�����ǂ�ǂ�o���ď㕔�������Ă���A�{���ɍ~�肽�B
�@���̒J�͑ꂪ�S�����Ȃ��ƃ��[�g�}�ɏo�Ă����B�m���ɂS�����Ȃ̂����A���̎��ӂ���������~�肽��́A���ɑ喡�ȒJ�������B���ʂ̒J�Ƃ͂�����Ɨl�q���Ⴄ�B�ł�����ȈِF�ȂƂ��낪�L���Ɏc��B
�@F�Q���f���ɓo�ꂸ�ɁA����o���Ă��猜�����~�����悤�������B�ʐ^���c���Ă���B���̕ӂ肩��A�H�`��ǂ��]�߂�ʒu�Ȃ̂����A�͂�����Ƃ���ƕ�������̂͊m�F�ł��Ȃ��B�u�������̕ӂȂ낤�Ȃ��v�ƁB�����AF3�ƂS�͂��̘e������قǓ�����Ȃ��o�ꂽ�Ǝv���B
�@�I���_�ɏo�āA���̂܂܃K�����o���Ă����ƁA�O��ւ̋}�o�ƂȂ��āA�s���l���Ă��܂����B�E���͑�����������J�ɋ}���ɐꗎ���Ă���B�d���Ȃ��߂��ĊɌX���g���o�[�X����ƁA�Ȃ�Ɖ������̒r�ɂ����Ȃ�o���B�����Ă���قlj����r�ł��Ȃ��B����ɑ傫���B����ꍇ�͂��̐��������߂邾�낤�Ǝv�����B�O��̊�őт̂Ȃ��ɁA����Ȃ̂ǂ��ȂƂ��낪������̂��Ɗ��S����B��͓o�R���̕t���������܂�����ɉ��R���邾���������B�J�̏I������őт̐^�Ƃ����A�Ȃ����������ِF�ȒJ�������B

F3�o��
�@�Ƃ���Ŗ��x�̂��Ƃł��邪�A�A��čs�����V�l�����҂͂��ꂾ�������Ƃ��v���o���B����g�b�v�łS�O���[�g�����o��Ɓu�r���[�����v�Ƃ����R�[�������̉��ɏ�����āA�������Ȃ����̂Ȃ̂��B����Ȃ��Ƃ͂��炩���ߕ����肻���Ȃ��̂Ȃ̂����A�V�l�͎������o���Ă݂ď��߂āu����̃R�[�����������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ�m��B���������́A���������������Ƃ����炩���ߐV�l�ɋ����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����B�����Ă����̏�ł͗����ł��Ȃ��B���̔ނ��������g�ŋC�����܂Ŗق��Ă����̂��B
�@�C�S�m�������ԂȂ�A�������U�C�����L�тĂ���Ƃ��ɂ͓o�����ŁA���ꂪ��U��~�����Ƃ��̓Z���t�r���[���ŁA���̌゠����x�̃��Y���ł܂��L�яo�����Ƃ��ɂ́A�]�����U�C���̉�����ŁA���悢��O�C�O�C��������o������A����̓��X�g�̃r���[�̐��ɂ���Ƃ������Ƃ���������̂��B�Ƃ��낪�������X�g�œo������Ƃ��ɂ��̐V�l�͂��������B�u��̉������邳���āA�����ʂ�Ȃ��ă_���ł��ˁv�B�����_���Ȃ̂��낤�B�U�C�����g�����Ƃ��_���Ȃ̂��A�����������[�g��o�邱�Ƃ��_���Ȃ̂��A�R�[�����|���������Ƃ��_���Ȃ̂��B�R�[�����ʂ�Ȃ��Ƃ���܂œo���Ă��܂����ގ��g���_���Ȃ̂��B�o��������̑�̏�ŁA�ނƂ��̘b�����āA��肠�����̌��_�Ƃ��āA�u�R�[�����������Ȃ��Ȃ�A����ȂƂ���܂œo�����L�~�������B�S�OM��t�o��̂ł͂Ȃ��āA���߂Ėڎ��ł���Q�OM�Ńs�b�`���Ȃ������L�~�̐ӔC���v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��A���͔ނɌ������Ǝv���B�ނ͖c��ʂ������B�������Ă܂��Ȃ��N���u�����߂��B�U�C���̑���́A�������̗͏��Ղ̒��œI�m�ɑf�����ł��Ȃ��ƒv�����ɂ��Ȃ�B�ʂɗD�G�ł���K�v�͂Ȃ����A�@�q�Ō����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�����������Ƃւ̓w�͂̂����炷�猩���Ȃ��l�́A�͂��p�[�g�i�[�Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ��Ǝv���̂��B

�Ō�̑��F4�͊ȒP�ɓo���B
�@���̂Ƃ��ȗ��O�䓌�ʂɂ����@��Ȃ������B�����t�̏㍂�n�X�L�[�Ɏv������ƁA�����͌��������܂Ŋ����Ă��������Ƃ������̂ł��Ȃ������ŁA�ϐ�̂��̕ӂ��U���k�J�����x�͔`���ɍs���Ă݂����Ǝv�����̂Ȃ̂��B
�P�X�W�X�N
�@���̔N�̉ċx�݂́A�o�R����߂ă��[���b�p�ɂP�T�Ԃ̗��s�����Ă���B����ȑO�ɂ́A��Ђ̓s���łS���Ƃ��A�P�P���ɉ��Ă𗷍s�����̂����A�Ȃɂ���^�Ă͗�������B�Ƃ����Ă��A�x�X�g�V�[�Y���̃��[���b�p�����Ă݂����Ɠ����ɁA�^�Ă̂P�T�Ԃ̑�o��ւ̈ӎu���A�������Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ����̂��A�����ȋC�������Ǝv����B
�@���s�ŕ����������Ƃ́A���[���b�p�l�͎���ɉԒd����邱�Ƃ��{���ɑ�D�����Ƃ������Ƃ��B�}���V������c�n�Ȃǒ낪�Ȃ��Ƃ́A�x�����_�ɂ�����Ƒ傫�߂̐A�ؔ�����ׂāA�ԁA���F�A�I�����W�Ȃǂ̌��F�̉ẲԂ��A�{�����Y��ɍ炩���Ă���B����͊ԈႢ�Ȃ��A�t��Ɏ���܂��āA�������Ĉ�Ă����̂��B�Ẵ��[���b�p���Ԃő����Ă���ƁA�Ⴆ�������s��ł����Ă��A�Ԓd�Ɉ͂܂�Ă���悤�ȋC���ɂȂ����B���[���b�p�̌Â�����̊G��ʐ^�Ȃǂł��A���F�����������Ɏg���Ă��邪�A������ԈႢ�Ȃ��e���X�̉Ԓd�ł���B���n�ł͒N�������ϓI�ɂ����������Ƃ����Ă���̂����A���Ԃ��D���Ƃ������{�l�ł��A�ޏ������̕��ϒl�ɂ��߂Â��Ȃ��B����ɂ́A�ƂĂ����������̂������B���Ƀh�C�c���������B
�@����ƁA�C�^���A�̒n���C���Ƃ��A�h�C�c�̃��}���e�B�b�N�X���𑖂��Ă݂�ƁA���ʂ̉Ƃł��A����͓��ꂳ�ꂽ�悤�ɁA�����������݂��L�����Ă����B�n���C�ł́A�ǂ̉Ƃ����œ��ꂳ��A�h�C�c�̓����K�F�B�O�C�̎q�ň�Ԃ������肵���Ƃ̓����K�̉Ƃ��������A�܂��ɂ��̂悤�ȉƂ����ł�����ė�������ł���B���̕��i�����āA�������Ȃ��Ǝv�������Ƃ́A�����ł͂قƂ�ǖ������A���[���b�p�ł͂ǂ��ɂ����Ă�����������B������`�̃A�����J�l���A���ł����[���b�p�ɃR���v���b�N�X�������Ă���Ƃ���A����͂��̗��j���琶�܂ꂽ�A�������������ɑ��Ăł���B
�@�h�C�c�̂���c�ɒ��̃z�e���ɔ��܂邱�ƂɂȂ������A�u�����̓��}���`�b�N�X���̒�����ˁv�Ƃ����Ă��A���̃I�o�T���͉p�ꂪ������Ȃ������B���ꂪ���ɐ\����Ȃ������ɂ��������B�u�Ԃ��Ȃ������A���Ă��邪�A��������Ε������v�ƁB�ŁA�n�}�������āA�w�����ƁA���}���`�b�N�X�����h�C�c��ł����̂��B�u�h�C�c��ł͉��Ă����v�Ɛ����Ԃ��āu���}���e�B�b�V���E�V���g���E�[�v���ƁB�ȂA�p����h�C�c����߂�����Ȃ����Ǝv�������A���n�̐l�͂����ł��Ȃ��炵���B�z�e���̃I�o�T�����₩���āA�Ȃ��ʔ��������B
�@���̂Ƃ��Ƃ͕ʂ̗��s���������A�C�^���A�Łu�����������v�ƁA�u�g�D�}���E�v�Ɖ��x�����Ă��ʂ��Ȃ��B���̓c�ɂ̎o������p�ꂪ������Ȃ������B����ł��ǂ��ɂ��ʂ��āu�h�}�[�j�v�ˁA�Ƃ������ƂɂȂ����B�C�^���A��ł͖����̓h�}�[�j�B����Ȏ������t���番�����̂��ƁB�ł����̌�h�}�[�j�Ƃ����Ԃ��z���_����������������āA�����m���Ă���C�^���A��̓h�}�[�j�����ɂȂ�B
�@�܂��ʂ̗��s�ŃX�E�F�[�f�����������A�����Ƃ��c�ɂŃo�X���P���ɂQ�{�����ʂ�Ȃ������������B���̃I�o�T���̓o�X��҂��Ă����̂����A���x�ꂽ���Ńq�b�`�n�C�N���Ă����̂��B�ɂɕt���悹�Ă�����B�ړI�n�͂P�T�L�����炢��ɂ��邾���B�k���̉p�ꋳ��͂ǂ������w�Z�̂P�N���炢�������Ă���悤�ŁA�N�����b����B������X�|�[�c�ԑg�ȂǁA�p�����������������Ă��Ȃ����炢���B�ŁA���{����̗��s�҂��Ɨ������āA�u�X�E�F�[�f���̏����͂ǂ��H�v�Ƃ��A�u�K�[���t�����h�͂ł����H�v�Ƃ��A�����Ă���B�J�b�v���ŎU������ɂ́A�œK�ȐX���ǂ��ɂł������Ƃ��B�Ȃ����s�҂Ƀi���p���߂Ă���l�ł��������B�u�Ⴂ�����́A������C�ɓ���ƁA�y�����߂�����̂�v�ƁB���ꂪ�t���[�Z�b�N�X�̍��Ȃ̂��ƁA����͎��̊��Ⴂ�������̂��B�ł��I�o�T���̘b��������ƁA�ǂ��������������Ă����B�~���Ƃ��ɁA�o�X�ゾ���ǂƁA����͂T�O�O�~���炢���ꂽ�B
�@����ȗ��s���̗^���b�͂ǂ��ł������Ƃ��Ă��A���Ȃ��Ƃ��Ԃ̉^�]���ɁA�a�͉��Ăł͑S���Ȃ����ƁB�ǂ����i�F���f���炵�����ƁB���̂Q�_�����ł��A���{�͐�ɒǂ����Ȃ����Ƃ����A�A�W�A�Ɣ�r���Ăǂ��Ȃ�ƁA�v���Ă��܂������̂��B�O���猩��Ɠ��{���{���ɂ悭������B
�@���̂W�X�N�͓��{�̌i�C�͍ő傾�����B��Ђ��������悩�����B�`�[������莩�R�Ɏg�����B����Ȃ��ƂŁA�P�T�Ԃ̋x�݂ɂ́A���������N�ł����s�Ȃǂ��Ă����悤�Ɏv����B
�@�m��Ȃ����Ƃ�m���Ă��܂��A�ꉞ�����̏�M�͗₦�Ă���B�Q�O�O�O�N���z���āA�܂���l�Ŋό����s�����悤�Ƃ́A�����Ȃ��Ȃ��v���Ȃ��B�ł������@���������A�o���������Ƃ͎v���̂����B
�����A��A�O�ʐ�E��䖓��@�P�X�X�O�N�W��
�@���U�ōŌ�̑�o��������̂��A�Ȃ��������̊�䖓��ɂȂ��Ă��܂����B�Ō�ɂȂ��Ă��܂������R�́A���̑�Ɏ��]�������ƁB�Ȃɂ���S���W�����W���Q�O�OM�Ŏn�܂��āA���܉��߂Ă��̎��ӂ̒n�}�����Ă��A��̗��e�̎R���W���T�O�OM�Ƃ��U�O�OM���x�����Ȃ��̂��B���̃S���W�����I���̂��W���T�O�OM�ł��Ƃ͌����B���̒Ⴓ�̂��߂ɁA���W���̑�Q�ɏP���āA�u��������͓o�R�ł͂Ȃ��āA�A�}�]���T���Ȃ̂��v�Ǝv�����قǂ������B�������A�����E�Ƃ܂����������̏��������ŁA�e���g�̒��ł͉�������𐆂��Ă��������ŐQ��B���N���Ă݂�ƁA�e���g�̒��ɂP�O�O�C�ȏ�̉Ⴊ����ł���Ƃ������낵���قǂ̒��̌��B�܂����������A�����Ɠ������x�̃O���[�h�ŕ]������Ă���Ƃ����A�����ǂ����Ă������[�g�}�W�B�m�����̋A��ɁA�k�y���̕W���P�V�O�OM�ŁA�p���O���C�_�[�̂P���̌��Ȃǂ��Ă݂�ƁA�̂�C�ɗV�тʼn߂��������̕W���̂Ȃ�Ɨ������������Ƃ��B�^�ĂɃA�}�]���ɓ˂�����ł����������ɕ����ƂƂ��ɁA���̏��ꂵ���āA���L���R�o�肩�牓�������Ă��܂����̂ł���B�u�����䂦�ɑ����炸�v�Ƃ������A����u�����Ƃ������Ƃ́A�������̂��v�ƍĔF���������̂��B

�������Ȃ����C���[���B�����Ɋۑ��A�肷�肪���C���[�P�{�B
�@���͂��̗��N�ɂ��A�����悤�ɒ����A��̑�o��̌v�悾���͂������̂����A�p�[�g�i�[�����܂�Ȃ��������ƂƁA�^�Ă̂P�T�Ԃ̋x�݂��A���[���b�p�̊ό����s�ʼn߂��������Ƃ����A�o�u�������̌o�Ϗ̊Â����������̂��B�C�O�ό����s�͐^�Ăɒl�i���������A�ł��邱�ƂȂ炻�̃V�[�Y���͔������������̂����A����������ł��Ẵ��[���b�p�A���v�X�����Ă݂����Ƃ����~���ɑς���ꂸ�ɁA���̂Ƃ��ɂ̓V�����j�ɂ��A�C���^�[���[�P���ɂ��s���Ă݂��B���҂𗠐�Ȃ������^�Ẵ��[���b�p�A���v�X�B�P���l�������̓��b�`�ɂȂ����Ɗ��Ⴂ���N�����āA�ґ�ɂȂ����B���͒��L���o�R���痣��邱�Ƃ��A���b�`�ɂȂ����؋��Ȃ̂��Ɗ��Ⴂ���N�����Ă����̂��B

��䖓�̉��₩�ȓ�
�@�����A��͎��ŕW���P�W�O�OM.�Ȃ��������ɂ������y�����������x�ł��炠��B���{�C�ɋ߂����Ƃ��l������ƁA���n����k���Ő��������āA�����x�Ɠ����x���B������������n���ȘA��ł�����̂����A���̒n�����������͂悭�m�肦�Ȃ������Ƃ��v���Ă���̂��B���������̑咩���͕S���R�ł�����A���܂ł��l�C���肦��B�������@�������̓o�R�����Ԃ�Ă������߂ɁA���̂悳�������炸���܂��ŏI����Ă���̂��B�����R���b�g���̃X�[�p�[�J�[���肪�ǂ��͂Ȃ��B�P�T�O�O�����̃J���[���̂��̂悳��]�����悤�Ƃ��Ȃ��������������������̂��Ǝv���Ă���B
�@�O�ʂ͐V���̐�Ȃ̂����A�_���̉e���œ��R�͎R�`�����炾�����悤�ȋC�������B�Ԃ̗ѓ��̏I�_�ł��łɃ��W�������ł���B�o���Ă���̂͗ѓ�����o�R���Ɉڂ��Ă܂��Ȃ��A�ۑ��̈�{���Ƃ��������C���[���̕s�C�����Ȃ̂��B����ɑς�����ȒP�Ȓ��Ƃ����ƁA�����������C���[��{�����̍\���ɂȂ�̂��낤���A�U�b�N�w�����Ă̋��n��ɂ͈�a�����������B�܂��Ƀ}�^�M���������Z��ł��Ȃ��R�Ȃ̂��낤���B

�S���W���т��Ă����B
�@�n�}������ƁA��䖓�ɂ͗��݂���Q�O�ȏ���̎x�����������Ă���B����Ȃ��Ƃ����ł͂���o���B�ѓ����猜�����ĎO�ʐ�ɉ���āA�n���Ċ�䖓�ɓ������B���̍��ɂȂ�ƂP�O�O�C�ȏ�̃��W���Ɉ͂܂��B���̒��ɂ������Ă���B�S���W���Ő��v���ē����Ă��A�܂�������オ��ƈ͂܂��B�r���p���p���Ɏ��オ���āA�y���A�ɂ��B��̓g���A�S���W���A��Ƃ��낢�날�����̂��낤���A�����č��������K�v�Ƃ����ɁA�˔j����B�s�\�ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��B���[�g�}�Ɋj�S���͂S�قǂ������Ǝv���̂����A������w���ɏ]���Ēʉ߁B��łQ�C�R�������Ǝv�����A�Ő��ւ͊��]�R�ӂ�Ŕ������̂��Ǝv���B�R���̎ʐ^������̂����A�R�͕s�����B�������đ��͎R�̔����������Ė߂�B���ꂪ����ɒ��������������B�P���Ŕ�����ꂸ�A�r���Ńr�o�[�N�B���̂Ƃ����H���s���ŃV�����o�e���Ă��܂��āA�P�O���N���̑��_����傢�ɒx��āA�̗͒ቺ��Ɋ������B�������ėѓ��ɉ��R����ƁA�܂����W�����o�Ă��āA�ԂւƓ�����悤�ɖ߂����B
�@����ȑ��Ő��̂ǂ��ɖ��͂�����̂��낤�ƁA�����͎v���Ă����B�W���Ƃ������������炩�Ɉ����Ƃ��v��ꂽ�B����ȗ������A��ɍs���@��Ȃ��A���ǂ��̎R��������Ȃ��܂܂ɍ����Ɏ���B���߂ăJ�[�i�r�ŎR�`�̊��͍]�܂ł̋������m�F����Ɠ�������S�O�O�L���B�x�R�܂łƓ������炢���B�x�R�ɂ͂��ł������̂ɁA���͍]�ɂ͍s���Ȃ��B�H�킸�����̎R�����̒����A��ɂȂ�B�����ϐ�̎����ɂƎv���B
�@
�P�X�X�P�N
�@�O�N�̂W���̒����̑�o��Ő��_�I�ɔs�ނ��āA���̋A��ɌQ�n�̍ȗ����ŃJ���V�J�̎�Â���p���O���C�_�[�̃X�N�[���ɂ͂������B�Ă���H�ɂ����Ė��T�̂悤�ɒʂ��āA�H�ŏI�������X�N�[���̌�A�~����͖ؓ����̃X�L�[��ŕʂ̃X�N�[���̃G���A�Ńr�W�^�[�t���C�g�����Ă�����āA���̔N�͎n�܂����B
�@���̃X�L�[��Ńp�C���b�g�̃��C�Z���X���擾���āA�t����Ăɂ����ẮA�ɓ��⒩�������Ńt���C�g���ĉ߂������B
�@�o�u���X�|�[�c�������p���́A�@�̂̃��[�J�[�Ɍ��킹��Ɓu�����I�Ō�̃t�B�[���h�X�|�[�c�v�B���̂Ƃ���ɁA���������͍��ł������Ă���B���悻�P���̏㏸��������A�����Ԃł��ӂ�ӂ�Ɣ��ł�����B
�@�����̃o�u���͂͂��������̂́A���ł��p���̃X�N�[���͑S���ɂ���B����A���̐e�ʂ̃n���O�O���C�_�[�������A���j�͒����B
�@��̎�̍D�������͖{�l�ɂ���Ă܂��܂��Ȃ̂��낤���A�p��������ȏ�ʔ����Ȃ������̂́A���炩�Ƀt���C�g�G���A�������Ă������Ƃɂ���B�Ⴆ������ɂ́A�R���f�B�V��������D�ŁA�����Ԕ��ł���ꂽ�Ƃ���B�����Ă��̗��T���A�����悤�ɔ��ł���ꂽ�Ƃ��Ă��A���T���T�������Ƃ���Ă��āA�����ʔ����̂��Ƃ������ƂɂȂ�B�P�L���l���̃G���A���A����̃l�Y�~�̂悤�ɍs�����藈����B�����������Ƃł͖O���Ă���Ƃ����킯���B����ł̓G���A���яo���āA���R�ɔ�s�ł��Ȃ��̂��Ƃ����A���������������Ƃ�����ƁA�~���ꏊ�������Ȃ��Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ�B���ʁA�N���̓c�ނ┨�ɖ��f�Œ���������Ȃ��Ƃ��A�����ꍇ�ɂ́A�_�Ƃ̃r�j�[���n�E�X������A���l�̉ƂɂԂ����ẮA�����ǂ����悤���Ȃ��B�������L���͐�~�Ȃ�����̂����A�ł����Ă����O�ɂ�������@���āA��������ݒu���ĕ���������画�f�ł���悤�ɂ��A���邢�͔�ї��ꏊ���炻���܂Ŋm���ɔ��ł�����̂����A���̂Ƃ��ɂȂ��Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��B�܂肻�ꂾ����s�ɐ�����B�܂��l�Ԃ������Ȃ蒹�ɂȂ��킯����Ȃ�����A�������낤�B
�@����Ə��������R�ɂ����ƁA��͂艸�₩�ȓ��ł��A�˕��Ƃ��}�ȏ㏸�≺�~���ɔY�܂����B�������������̃W�F�b�g�@�ł����A����ꍇ�ɂ͕��ɂ���Ă��Ȃ��s�������̂ɁA�����R�O�L���̏�蕨���A���ł����S�ɂ͂����Ȃ����̂��B
�@���̑��Ƃ����X�N�[���̃J���V�J�̎В����A���̌�X�N�[���͕��������A�{�l���t���C�g�����߂Ă��܂����B�u���͂ł��܂�ɂ����̂����������v�Ƃ����̂��A�В��̃_���v����̌��������������A�������������������B
�@����ɉ��₩�ȓ��Ƃ����̂́A�������ł�����킯����Ȃ��B�܂�̓��ɔ��ł��A��̂P�O�����炢�Ŏ��R�ɒ������Ă��܂��B�O���C�_�[�Ƃ����̂́A���V�̓��ɁA�㏸�����Ȃ��ƃ_���Ȃ��̂��B�܂�܌�����Ƃ��H����Ƃ����悤�ȁA�ړ����Ɍb�܂ꂽ���B�����������́A���͐�����قǂ����Ȃ����̂��B����Ə��ł͋ɓx�ْ̋����ƁA�W���͂����߂��āA����ɑς��������Ȃ����Ƃ������R������B�����Đ��N�̌�Ƀp���͎��߂Ă��܂����̂��B
�@����ł����̔N�́A�P�N�����������ɂ����āA�y�����߂��������̂������B�������ēo�R���邱�Ƃ́A����x��̂悤�Ɏv���Ă����B�l�Ԃ͓������ɓ����ƁA�y�������锽�ʑ�����B�X�L�[�Ƃ�����������A������R�ɔ�ׂ铹��̕����A�@�\���������B���̕��A���_�I�ɑ����Ă����Ƃ����Ă������B
�P�X�X�Q�N
�@���̔N�ɂ͂Q�[���b�p�փt���C�g���s�ɏo�������B�X�L�[������Ă���I�[�g���[�g�B��o�������Ă���V�����j�j��Q�B�������Ƃ��B�p���ƊE�ɂ��A���[���b�p�c�A�[�Ƃ������̂�����ɂȂ��Ă����B
�@�Ƃ����Ă��A�������[���b�p�Ńt���C�g����Ƃ������Ƃ́A�������������O���[�h�����߂邾�������R�ł��Ȃ��B���R�̂悤�Ɍ������ɂ����S�҂́A������ł�����B���́A��l�ŊC�O���s����悤�ɁA���̂��Ńp�������{����S���ł����āA���n�ŏ����W�߂āA�y������ׂȂ����낤���Ǝv���������ł���B����ɗ��s�ɂ��Ȃ�Ă���ƁA�ό����s�����ł͖O������Ȃ��Ȃ�B�X�L�[���s�������Ă��������A�o�R���s�������Ă������B
�@���n�ʼn����������̂́A�p���Ƃ����L�����m�X�|�[�c�ł��A���̊ό��ē����ɂ����ƁA�Œ�ł��d�b���̃C�G���[�y�[�W�Ȃnj��Ă���āA�V���b�v��G���A���Љ�Ă��ꂽ���Ƃ��B�܂��l���Č���Γ�����O�̂��ƂȂ̂����A�ό��q���������Ƃ��Ɉē����Ƃ������̂ɂ����킯�ŁA�����ł͂��̍��育�Ƃɂ��������^���ɑ��k�ɏ���Ă��ꂽ���Ƃ��B���ꂪ�t�ɓ��{�ł�������Ǝv���Ɓu���������H�ȃX�|�[�c�Ƃ����̂́A�킩��܂���˂��v�Ƃ����āA�ǂ��Ԃ���邾���B�܂��p���̔��˂̓��[���b�p�ł����āA���{�����t���C�g�l���͑�����������Ȃ����A��������ʐl�̊��o���炷��A�\���S���B�傰���Ɍ����A������̊ό��s���̏[���U��̈�[���������悤�Ȃ��̂ŁA���ꂾ���Ŋ������Ă��܂������̂������B
�@����ɂ��̊ό��ē����Ƃ����̂��A���{�̌�����s�����ւ̕W���̂悤�ɁA���ɕ�����Ղ��Ȃ��Čf������Ă������Ƃ��B����ɖ�̂W�����炢�܂ł����Ɖc�Ƃ��Ă���B�����ĂT���ɏI���ꂽ��A�ό����Ă����̂͂��̎��Ԃ���n�܂�ꍇ�����邵�˂��B
�@�C�^���A�ł́A���O�͖Y�ꂽ���A���[�v�E�F�[�̂���W�����U�O�O�����炢�̎R�Ńt���C�g�ł����B�X�C�X�ł��A���������܂����悤�ȃ��[�v�E�F�[�̎R�B�I�[�X�g���A�ł̓X�L�[��B�������T�������b�c�̃X�L�[��ɂ́A�u�G�A�^�N�V�[�v�Ƃ����������ȉ�Ђ������āA�ނ͓�l���̋q��T���āA�ό��t���C�g���Ă����̂��B���O���Y�ꂽ���A�R�k�ɏЉ�ꂽ���Ƃ�����X�C�X�l�ŁA���̎G���������Ă��ꂽ�B�Ȃ��P�T�N�ȏ���O�ɁA����̃p��������Ă��āA�ŏ��͂���Őጴ�C���ɑ��蔲���ėV��ł����Ƃ����B
�@�������s�����G�߂��A�t�ƏH�ŁA�����͂���قǂ悭���Ȃ��A���{�ȏ�̑听���̃t���C�g���ł����̂��Ƃ��������ł��Ȃ��������B
�@���̗��N���������A�t���C�g����F�l�Ɠ�l�ōs�������Ƃ��������B���̔ނɂƂ��Ă͏��߂Ẵ��[���b�p���������A�X�C�X��h�C�c�Ȃǂ͎����D���ȍ��Ȃ̂����A�u���������Ƃ���͂����ɖO����v�Ɣނ͂������B����̓Z�C�R�[�̎��v��Ԃ̃x���c�݂����Ȃ��̂ŁA���ɐ����Ɍv��I�Ȃ̂����A���҂͂���Ȃ��Ƃ��Ȃ��Ƃ����̂��B�ނ���C�^���A��t�����X�̂悤�ȃ��e���n�̍��̂ق����A�m�[�V�C�Ȃ��Ƃ������āA�y�����ƁB�����p����Ԃ��̂��̂�I�ԂƂ��ɂ́A�h�C�c��������сA�Ԉ���Ă��C�^���A�̎ԂȂǂ͏��Ȃ��B�͂͂��A�����B
�@�ł��p���ł��ό��ł��A���Ă͖{���Ɋy�����B�t�ɓ��{�Ɋό��ɂ���O�l�ȂǁA��ɂ��Ȃ��Ɍ��܂��Ă���ƁA���̍��͎v���Ă����̂����A�P�O�N�����Ă݂�ƁA���ꂪ��ɂ��ό��O�l�������ɂ���������������̂��B���s�⊙�q�ɂ�����B����͓������j���[���[�N���炢�̓s�s�ɂ悤�₭�߂Â��Ă��������m��Ȃ����A���j�̂Ȃ��A�����J�l�ɂƂ��ẮA���E�ŌÂ̖ؑ��@�����Ȃǂ́A���͓I�ł����낤���B
�@
�@
�p���O���C�_�[�E�b���P�x�t���C�g�@�X�R�N�W��
�@�p���O���C�_�[�̓A�E�g�h�A�̂P�W�������ɉ߂��Ȃ��B�Ƃ��낪���̂����R������A���̗V�тɓ������l�����������B�Ⴆ�U�b�N���[�J�[�E�_�b�N�X�̎В��̔��J����B���邢�͓o�R�X�J���V�J�̎В��̍�������B��ۂ́A���������ނ����R������OB�̃X�|�[�c�Ƃ��Ă����Ƃ����������̂ł͂Ȃ����Ƃ��A�v�������炾�B���͂��̃J���V�J�̎В��̓X�̃X�N�[���ɒʂ����B�X�O�N�̉Ă̂��Ƃł���B���N�̂R���ɁA�ʂ̃X�N�[���ŁA�p�C���b�g�̃��C�Z���X�̌�t�����B���������͎��Ɋ�Ȃ��Ƃ������B

�b���x���������ɏ����������ӂ肩��̃t���C�g���O
�@�����ϐ���̎R�o����Ō�ɂ����̂́A�W�W�N�����ɖ��_�x���牜�䍂�x�ɓo�����R�s�������B�Ƃ������ݔ����ł̖��c���ƂĂ����������̂ł���B�܂������̎R�Ȃ瓖����O�̂��ƂȂ̂ł��邪�A�p�[�g�i�[�������Ă����p�b�N����̓��{�����������Ƃ�����A���ꂪ�[���[��ɓ����Ă����̂ł���B����������Ƃ��ɁA�Ȃ��]�b�Ƃ��Ă��܂����̂��B����ɓ��ɐ��Ⴉ�ꂽ�킯�ł��Ȃ��̂����A���̓��̃e���g�������̂��������������B���N�����悤�ȃV�����t���g���Ă����̂ɂł���B�u�N���Ƃ����̂��Ȃ��v�Ǝv���̂��B����ɗ�ɂ���āA�ϐ���̎R�o��̊��삪���������Ă���킯�ł��Ȃ��B�y�������Ƃ����h���Ǝv�����Ƃ������Ȃ�A�Ȃ�ƂȂ��������̂��B�u����Ȋ������̂͂������߂悤�v�����v���ƁA�`���I�̂悤�ɎQ�����Ă����C�������A�}�ɋx�܂������̂��B�����ł������߂Ă��܂����ȏ�A�������Ȃ��A�ȍ~�͈�̐ϐ���̖��c�̎R�s�ɂ����ĂȂ��B�~�̃e���g���͊�������Ƃ����킯���B�~�̊y���݂͓Ɛg���ォ�瑱���Ă����Q�����f�̃X�L�[�����ƌ��߂��������B���̃Q�����f�X�L�[�����̌�A�܂��Ȃ���߂Ă��܂��āA�N���J�����[�X���n�߂邱�ƂɂȂ����̂��B��̂ǂ̎Ζʂł������悤�ɂȂ�ƁA�^���ǂ��́A�������Ă��Ȃ����́A�܂�Ȃ��Q�����f�\�����ɕt�������Ă����Ȃ��Ȃ������炾�����B���[�X�Ƃ����̂́A�N���J���̊Ԃł͗L���ȁA�k�C���̗N�ʁA���l�A�D�y�̃��[�X��������A�����̗��֒�A�V���̘Z�����̃��[�X�̂��낾�B�����ĉĂ̎R�s�͑�o�肾�ƁB
�@��o��͂��ꂩ��R�V�[�Y���͑����Ă����B�Ƃ��낪���̍Ō�ƂȂ��Ă��܂����̂́A�X�O�N�̉āB�V���E�����A��̊�䖓��ɏo�����Ă����B���͂����Ŏ��ɑ傫�Ȏ��]������B�S���W���̔����������҂��Ă��̑�ɓ������̂����A����͑�o��Ƃ��������A�W�����O���T���ɋ߂����̂������̂ł���B�v����Ƀ��W���Ƃ�����A�u�̑�P�����Ă��܂����̂��B���̒��ɉB��Ă��A��������𐆂��Ă݂Ă��A�Ƃɂ������S�C�Ƃ������̑�Q�������Ԃ������ƕt���܂Ƃ��B�����z������ł��A�̒��ɓ����Ă��Ă��܂����Ƃ�������B�h���ꂽ�r���⑫���Ƃ�ł��Ȃ��c��オ���āA�y���Ă��傤���Ȃ��B����ɉ����āA��o�肻�̂��̂��A���[�g�}�ɏڂ����f�ڂ��ꂷ���āA�Ȃ�猻��œo���ĐV�N�����Ȃ��������Ƃɂ����B
�@�܂�V���̎O�ʐ�̂悤�ȃT�P���o��悤�Ȃ��ꂢ�Ȑ�ɂ́A���̃��W���̑�Q����ɌQ�����Ă���Ƃ������ƂȂ̂��B����ɍs���Ă���C�����̂����A�W�������ɒႢ�B�킸���ɕW���Q�O�O����S���W�����n�܂��Ă���̂ł���B�C�������E�ƑS�������ŏ��ꂵ���B�܂肻��́A������◘����̂悤�ɁA������x�̕W���Ɛ�k�Ɨ����������߂��R�s����͎��ɂ�������Ă������̂������̂��B�Ƃ��낪�A���[�g�}�̐���҂ɂ����̂��낤���A�������������A���іL�R��̑���A�����◘����̃S���W���Ƃ܂����������ɏq�ׂ�A�����܂������̂ł���B����͖��炩�ɈႤ�B�W���̒Ⴂ��́A�u����͓o�R�ł͂Ȃ��āA�A�}�]���T���Ȃ̂��v�ƁB�����������ƂɁA���͌��C�������Ă��܂����̂ł���B�{���Ȃ�A���N�͂܂��C�ɓ������Ƃ���ɍs�����Ƃł��v���悩�����̂����A���̃A�}�]���̋A��ɁA�Ⴆ�Όy���ȂǂɊ���������ŁA�������͕W�����P�T�O�O����B���ɗ������̂��A����Ȋό��n�ł��B��������ƁA���̒����A��̎R�s�͂��������Ȃ����̂��H�Ǝ��Ȍ����ɂ��ׂ��Ă���B�J���V�J�̂��̃p���O���C�_�[�X�N�[���͖k�y���̕W���P�V�O�O�ȏ�ōs���Ă����B�؍݂��邾���ŗ������B�u�����A�����d�ׂ�w��������͂�����v�Ǝv���Ă����̂ł������B����ɓ����̘A���̈��ނȂǂŁA�p�[�g�i�[���}�ɔN��ቺ���Ă��āA�ꏏ�Ƀe���g�����Ă��A�b������Ȃ��Ă܂�Ȃ��Ȃ�������������B��͂�P�O���Ⴂ�A���Ɖ�b���Ă��A����͊y�����Ȃ��A�q���ƈꏏ�ł���B�܂���������������̂悤�ł͂���̂����A�m���ɂ����������R�ʼn����������B

���̕��̌��������Ƀe�C�N�I�t
�@�p���O���C�_�[�́A�o�u���A�E�g�h�A�̓T�^���ƍ��ɂȂ�Ɩ��炩�Ɏv����̂����A�n�߂������͎��Ɋy���������B�Ȃɂ���킸���P�O�L�����x�̑����ŁA�{���ɋ�ɕ����オ��邾�́B�̃��g�N���X���Ƃ������̂́A�䂪�Ƃ̋߂��̖k��Z�ɓX�������A�����X�L�[��ŃX�N�[�����J���Ă����ނ��������A�u�����I�i�Q�O���I�j�Ō�̃t�B�[���h�X�|�[�c�v�Ɛ�`���Ă������[�J�[���������B�u���ɂȂ�v�Ƃ����̂́A�X�J�C�X�|�[�c�����߂Ă��҂ɂƂ��āA�����Ă��̗U�f�̃Z���t�Ƃ��Ȃ�B
�@���͑����̋Â萫�Ȃ̂ł��낤���A���߂������疈�T�̂悤�Ƀ��b�X���ɒʂ����B�����Ęr���グ��B���N���炢�Ńp�C���b�g�̃��C�Z���X���擾����B����������Ă���A�ǂ̃G���A�ɂ����Ă��A���R�ɔ���Ă����Ƃ����킯���B
�@��������ʎ҂ɂ͋��Z��������J����Ă������A����͓��i�����̋@����A��ɍŐV�̂��̂ő������ĂƁA�����������肷����B��ʓI�ȃt���C�g�Ŋy�����̂́A����ꏊ���e�C�N�I�t���āA�܂��Q���Ԃ��炢�����Ɣ��ŁA���������ɖO�����Ƃ���Œ��n����Ƃ����悤�ȁA�߂������ł��낤���B���ꂽ���Ƃ����̂́A���z�ɉ��߂�ꂽ��C���R�̎Ζʂɂ����āA�ǂ�ǂ�㏸���Ă���̂��B�㏸���i�T�[�}���j�Ƃ����B��������܂����ނƁA���̃p���V���[�g�i�p���O���C�_�[�j�́A�ǂ�ǂx���グ�Ă����B�Ⴆ�ΎR�̒��������яo���Ă��A���̎R�̎R�����z���Ă���ɏ㏸�ł���B�x�m�܌̖{���̗��ɖі��R�i�P�X�O�O�j������B�����ɃJ���I�P�̑�ꋻ���̕s���Y����̓�����Ƃ��ăG���A���ł����B�����ɂ悭�ʂ��Ă����B�e�C�N�I�t���U�O�O���́A�W���P�R�O�O�B��������o�ĂP�X�O�O���z���āA�Q�R�O�O���炢�܂ōs�������Ƃ�����B���ׂď�������Ȃ̂ł��邪�A����������Ƃł͂Ȃ��B�������ď��ł����V�ԁB���܂ɋ}�~�����āA�܂��㏸��������ł���B
�@�p���O���C�_�[�Ƃ����̂́A�����R�O�L�����x�̏�蕨���B����䂪�V�B�����R�O�Ƃ����̂́A�����悻�b���W���[�g�����炢�ł��邩��A���̊Ԃɖ�P�C�Q���[�g�����~����v�Z�ɂȂ�B�Ƃ��낪�b���P�C�Q���[�g���̏㏸���������ɂ���A�i���ɒ������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�Ƃ��낪���ۂɂ́A�b���R���Ƃ��T���Ƃ��̏㏸��������B���̋�C�Ƃ����̂́A���͍��E�ɐ����Ă���悤�ȋC�����邪�A���͏㉺�ɐ����Ă���Ƃ�������̂��B�ł������ϗ��_�̏㏸���͂����悻�����P�O�O�L���Ƌ���邵�A�����Ɋ������܂��Ƒ������P�����[�g���܂Ő����グ���āA�ȒP�Ɏ���ł��܂���Ƃ������ƂɂȂ�B�ϗ��_�̓W�F�b�g�@�̔�s�����킹�邭�炢�Ȃ̂�����B
�@�������ăG���A�Ŏ��R�ɔ�ׂ�悤�ɂȂ�ƁA��͂茳�R������Ƃ��ẮA�{���̎R�Ŕ�т����Ȃ�B����������͐����ɂ͊��}����邱�Ƃł͂Ȃ��̂��B���̂����邩������Ȃ��B���l�ɖ��f�������邩������Ȃ��Ƃ����A�܂��u�R����сv�Ƃ����Ă���B�������A�@���I�ɋK���ł�����̂ł��Ȃ��B���Ăł������������Ƃ͎嗬�ɂȂ��Ă���B�����R�̃N���u�̂Ȃ��ɂ��A��������Ƀp������肾�����҂����āA�O��Ŕ�сA���̂����ɐ�̔����x�A�J��x�A�����Ă��ɉĂ̍b���P�x�Ŕ�Ԍv�悪�i�s�����B

�z�[���O���E���h�������і��R�ł́A�w�i�ɕx�m�R���i�D�悭�f��B
�@�b���ɂ́A�ɓ߂���o�X�Ŗk�܂ł����āA�Ő������ɂS���ԂŎR���ɒB����B�����Ńe�C�N�I�t�ł������ȏꏊ��T���āA���������x�̔���������B�����Ɍ��߂��B���傤�ǐ^�Ẳ����A�R���f�B�V�����������B���敗�̌����������炢���A�ł����������ɂȂ�B�Ƃ��낪��͂�R�O�O�O���̎R�ł���B����������������ƁA���̂��|���B�e�C�N�I�t���Ă����V�т����̂���܂�܂����A�Ƃɂ������S�ɍ~��邱�Ƃ������ŗD��ɂȂ炴������Ȃ��������߂ɁA����́u�Ԃ���сv�ƌĂ��A���s�t���C�g�̕��ނɓ����Ă��܂����̂��B�����ړI�n�Ɍ������ĉ��~���Ă��������������̂��B�㏸����߂܂���ȂǂƂ����]�T�́A���̂Ƃ��͂Ȃ������B����ɏ㏸���̂Ȃ��Ƃ����̂́A�����@�̂��K�T�K�T�Ɨh�����̂Ȃ̂ł���B�G���A�Ȃ炢���Ƃ��Ă��A���ꂪ�W���R�O�O�O���Ƃ�͂肿����ƕ|���B����ɎR�����猩�郉���f�B���O�i���n�j�\��n�̌ˑ�̉͌��Ƃ����̂́A���ɉ������̂��B�o�����Ƃ�����Q���͂�����̂��낤���B�W�����ɂ��Ă��A�Q�O�O�O�͉z���Ă���B��Ƀp�[�g�i�[���e�C�N�I�t���āA���͔ނ����n����Q�O����҂��Ă����ї����ƂɂȂ����B��������ł��݂��A���͎�荇���Ă���B�����ꎖ�̂̏ꍇ�A���̑���̓t���C�g���Ƃ��������A�����ƒn�ɑ��������Ă����Ԃ������Ƃ����悤�ɁA���݂��̒��Ō��߂����̂������B���̂Q�O���ԂɁA�ނ͌����Ȃ����炢�����֔��ł����Ă��܂����B���c���ꂽ���͏����₵�����Ȃ�B����ɔ�s�@�͂Ƃɂ����A�e�C�N�I�t�ƃ����f�B���O��������̂ŁA��s���͂܂����S�Ȃ��Ƃ��������̂��B��s�@���̂����̂ǂ��炩�ŋN���邱�Ƃ������B�����Ƃ��܂��e�C�N�I�t�ł��邩�ǂ����ł��A�h�L�h�L�����B
�@���_�����n���Ă��玄�̓e�C�N�I�t�����B�܂��X���[�Y�ɂł����B��ї����Ă�����x����ƁA�����C���͂����B�U��Ԃ��čb���̗Y��ȎR�e�����x�����Ԃ����肵�Ă����B�������ċ��x����̔������z���ăh���h���ˑ䑤�̉����Ɍ������Ă����B���_�������`���Ɛ^����ʂ�߂��čs�����肵���B���x�������ꏊ�Ȃ�ł͂̌o���ɂȂ�B�����J�ɍ~���Ƃ��ɂ͕������肵�Ă��Ȃ��Ă���Ȃ̂����A�����͍L���͌��Ŗ����Ȃ������B�������Ė�Q�O���Łu�Ԃ���сv�̌v��͏I������̂����B�ς�ł݂�ƁA�Ȃ��A����������ƒ��킵�Ă݂Ă��i�㏸�������܂��邱�Ɓj�悩�������ȂƂ����]�T���ł�B
�@��яI���Ă݂ċC�������B�������悯��ΕW�����Q�O�O�O�ȂǂƂ������̂́A���̖����Ȃ������Ȃ̂ł���B�����悤�ɒ��������̂W�L���A�P�O�L�������̂Ȃ������Ȃ̂��B�Ƃ��낪�����������ƂȂ�ƁA���ꂱ���W�����̂T�O��P�O�O�ł��傫�Ȃ��ƂɂȂ�B�R�Ƃ����̂͂����������̂Ȃ̂��ƁB�����ɐ��R�z���Ō��ɓ��낤�Ƃ����p�[�e�B�������āA�Q�T�Ԋ|���Ă��A�n�V�S�J��z�܂ł��ǂ蒅���̂�����ƂŁA�~�����ꂽ���Ƃ��������B����������f�����̂͂������A���̃n�V�S�J��z�ւ����̂ɁA���������č����ʎR�̎��z���Ƃ������[�g�Ȃ̂ł���B����Ƀn�V�S�J�ł͐V��Ɉ͂܂�āA�S�g�̃��b�Z���ŁA�^�������֎��t�����̂͂����̂����A�P���ł킸���ɋ����ɂ��ĂQ�O�O���[�g�������O�i�ł��Ȃ��B�����̈����Ƃ��͂���Ȃ��̂��B�Ƃ��낪���ꂪ���V�̉���ƂȂ�A�X�L�[�ō�����܂łR�O���Ƃ͂�����܂��B��������ŎR�́A�P�O�{����P�O�O�{�h�����Ȃ邵�A���Ɋy�ɂ��Ȃ�B���ꂪ�R����璭�߂��Ƃ��ɁA��w�g�ɂ��݂ĕ����������̂������B
�@���̃t���C�g��O�サ�āA���[���b�p�Ƀt���C�g�c�A�[���Q��s�����B���[���b�p�̊ό��n�̈ē����͐i��ł���B�\���m�����Ȃ��Ă��A�ʏ�̈�ʂ̈ē����ł��p���O���C�_�[�̖₢���킹�ɁA�G���A�̏ꏊ��A�A����������Ă����̂��B���͂����ȃA�E�g�h�A�ł͂Ȃ��̂��B
�@�����x�ł̃t���C�g�́A�z�K���̍s�ҏ����̂������̉͌��ɁA�ϐႪ����Ƃ��������Ƃ������f�ŁA�t��̓V�C�̂����������v����Ă����Ȃ����B���̂Ƃ��͏[�����Ă����B���_�͂Q���ԁA�����P���Ԃ��炢��щ�����B�Ԋx�̒���t�߂���A�����x�̒���t�߂��P�O��ȏ�����E�ɉ����������낤���B�R���ɂ����o�R�҂����U��A��͂蒿�������̂�����Ȃ��Ƃ����d��������B���̂܂ܔނ͍��v���ɔ��ōs���ėV���n�ɍ~�肽�悤�������B���͍s�ҏ��������Ƀ����f�B���O���āA���R���Ĕ��Z�˂ɒu���Ă������ԂŔނ��}���ɍs�����B
�@�J��x���Ƃ����A�}�`�K��ɐ�k���c���Ă���Ƃ��������ƁA�����ŃX�L�[�u�K��Ă���Ԃɍ~�肽���̂������B���̂Ƃ����Ԃ���ԃv���X�P�O�����炢�A���ŗV�B�e�C�N�I�t�̂Ƃ��Ɏ��͂Ɋϋq�����������B

�J��x�ł͒���e�̐�̎c�����Ζʂ���e�C�N�I�t
�@�Ƃ��낪�ł���B���̃p���ɔM�������̂��A�����T�N�Ԃ��炢�������낤���B���̊Ԃ͂��������o�R�͂��Ȃ������B���łɂ�߂Ă����~�R���������A��o����B���̗V�тɂ��Ă��A��͂�W�����Ă��Ȃ��Ƃł��Ȃ����̂��B����ǂ��̊���ɏ����̂������Ƃ����̂͏��Ȃ��B�G�ߕ��̓��ɂ͔�ׂȂ��B���܂�ɔ��ł������Ƃ��㏸�ł��Ȃ��B���ɏ������悭�Ă��A�u���Ⴀ�A�Q���ԑ؋�������āA���H�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�ȒP�Ɍ����Ă��܂��A�W�F�b�g�R�[�X�^�[�ɏ���Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B�ŏ��͂����A�ł�����Ă���Ƃ����������ƁB�ǂ�����ł��������ƁB���̂����ɏ����������̂ɁA�R�O�����؋Ă���Ɓu����������A�~��ċA�낤�v�ƁB�ǂ����ŁA���̎��̃X�e�b�v�A�b�v�Ƃ������̂��Ȃ��B���ɕ䍂�⌕�����Ƃ��Ă��A�Ԃ���тQ�O���ŏI����āu�Ӂ`��A����Ȃ��v�ŏI��������낤���B��������蕨������A�o�R�q���������̂͂����̂����A����A������l�Ŕ��ł݂āA���Ăǂꂾ���ʔ������̂Ȃ̂��낤���B��͂肠��Ȃ��̂ŋ���ł���̂�����A���S�̒��x�Ƃ������̂͒m��Ă���B�o���W�[�W�����v�Ɠ����x���Ƃ͂���Ȃ����A�����قǃR�N���o��Ƃ����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂��B�s���Ȃ��Ȃ鎞���������Ȃ��āA�v���Ԃ�ɂ����ƁA����͋}�ɏ���̐^�ɕ���o�����悤�ŁA�|�����Ȃ�B���Ɏ��߂Ă��܂����B�Q�N�O�Ɉ����z�����Ƃ��ɁA�S���S�~�ɒu���Ă��Ă��܂����B�T�N�ԂłS�O���~�قǂ���p�����S���芷�����̂����B���ł����܂ɏ�����ł���l������̂����A�Ӂ[��ƌ��グ����̂́A�܂�����Ă݂����Ƃ����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��B���ł��邻�̋C�����͂��ނ悤�ɂ킩���Ă��܂������߂��낤���B���̃o�u���A�E�g�h�A����͂�l���������Ă��Ă���悤���B
�@�������Ď��͂X�U�N�ӂ肩��U�N�Ԃ́A�~�̃N���J���X�L�[����邾���ŁA�p�������̓o�R������Ȃ��Ȃ����B�~�ȊO�̏T���ɂ܂������ʂ̎����Q�[���ɎQ���������Ƃɂ����B�������ĂQ�O�O�R�N���}�����B�ڍׂ͂��̂R���̐�m�q�J�̋L�^���u�x�l�v�̋I�s�ɏ��������A����ɏڂ����B��P�ɑ̗͒ቺ�B��Q�Ɉ��Ⴓ�ꂽ�N���J�����[�X�ɂ�����ƖO���Ă��܂������ƁB��R�ɂ悤�₭�A�{���̎R�X�L�[�̊y�������������Ă������ƁB���ꂪ�N���J���R�X�L�[�̎n�܂�ƂȂ����B
�@�l���͉����]�@�ɂȂ�̂�������Ȃ����A�ł��d���ȊO�Ŋy�������Ƃ���ɐg�̉��ɂ��������Ƃ��A�ƂĂ��悩�������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�P�X�X�S�N
�@���A�O�����ۂ����i�ł����B�R�N���炢���Ɖ������M����߂Ă��܂��܂��B�T�N�ʑO����n�߂��Q�[���̃o�b�N�M�������ɂ��̔N�͋Â�܂��B�Ƃ����̂��A����ȑO�ɂ́A���̃Q�[���̃��[�J�[�哱�ŔN�ɂP��̑��J����Ă��܂����B�Ƃ����Ă��A�P���ɕ�����Ƃ������Ɓu�A���Ă��������v�Ƃ����悤�Ȃ���ŁA�Q���҂͑S�R�ʔ����Ȃ��B�b�q���̖싅�ł��A�e���r�Ō��Ă���t�@���͐���オ��܂���B�ł��˂��A�Q�����Ă�����̐g�ɂȂ��Ă݂�ƁA�g�[�i�����g�Ƃ����̂́A���ɎQ���҂ɗ₽�����B
�@�k�C���̃`�[�����b�q���ɂ����āA��������͊J�Â̂P�T�ԑO�ɍb�q�����肵�āA���K���Ƃ������߂����B�������Ē��I�����Ȃ��āA���킪����ɂ܂���T�Ԍ�Ȃ�Ă��Ƃ�����B�������K��Ɨ��ق̉������āA���Ď������n�܂��Ă݂�ƁA�싅�P�Q�[�����Ă̂́A�Q���Ԃ���ΊȒP�ɏI����Ă��܂�����ŁA�Q�T�Ԏ��ԑ҂�����āA�Q���Ԃŕ����āu�A���Ă��������v�B
�@�����悤�ɁA�A�}�̏����̃g�[�i�����g�Ȃǂ��A�T���̓���ԂŊJ�Â���āA�y�j�̌ߑO�P�O���Ɏ����J�n�Ƃ������āA����ň���ŕ�����ƁA���O�Ɂu�A���Ă��������v�Ƃ����̂��g�[�i�����g�̊�{�Ȃ̂ł��B�v���Ȃ炻��ł������ł���B�ł��������A�}�A�����A�T�������̃Q�[���y���݂ɂ��Ă���̂ɁA����ȃC�x���g����ʔ����͂����Ȃ��B
�E�E�E�Ƃ����悤�ɁA�����Ǝv���Ă����̂ł��B�ł��̔N�ɁA�����Ƃ����l���A�ߋ�[�J�[���C�x���g�̎�����������Ƃ����������ɂ��āA�o�b�N�M�������̍����̃C�x���^�[�Ƃ��Ċ��g�������̂ł��B����ɂ��ĎQ�����āA���ɖ��T�i�����͊u�T�j���̐V�h����ɏo���肵�Ă��܂����B�������������Q�[���ł̎��Ԃ̉߂�����������ƁA�A�E�g�h�A�ɂ͂܂������o�����Ȃ��Ȃ�܂��B
�@���T�̂��̃C�x���g�Ƃ����̂́A���悻������[���T���܂ŁB���̂T���Ԃ����[�O��őΐ킷��킯�ł��B�g�[�i�����g����Ȃ��ł�����A�����Ă����̎���������B�����Čl�̐��т��A���[�e�B���O�ŊǗ�����B������Ăł̓����Q�[���ł̗V�ѕ��@�𒇊Ԃœ��������킯�ł����A���ꂪ���ɂ������낢�B
�@�T���̊y�����߂��������o����ƁA����i�s�Ƃ����̂́A������Ɠ���B
�@�����ł̓v���̈͌�A�����̘A�����A���̃Q�[�����Ă���l�����܂����B�w���������o�g�������B�I�Z���o�g�Ƃ����̂����܂��B�����Ƃ����̂́A��͂��⓪�]�����W�c�����āA�Ē��Ȃǂ́A
�u���̌Z�M�͓��������������瓌��ɐi�w�������A���͂���ȏゾ��������A�����ŏ����E�ɓ������v
�@�Ƃ������Ă��܂��B�܂��A�����悤�ȘA�������܂����B���⍡���吨���܂��B
�@�Q�[���͓��̃X�|�[�c���Ƃ������Ă��܂����A�����ɂ��Ă��B�A�E�g�h�A���̍��g����X�|�[�c���Ƃ���A���̍����玄�͓��̃X�|�[�c�Q�[���ɂ��Q�����n�߂��Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B���ƂȂ��ẮA�Ƃ��ɍb���t���������B
�@�o�b�N�M�������ɂł����āA�l���傫���ς���Ă����Ƃ������܂��ˁB����ɂ��̃Q�[���́A��������ł����Q�[���ł͂Ȃ��B��̂̃��\�|�^�~�A����ɂ����������A���{�ɂ͒�������P�T�O�O�N�ȏ���O�ɓ`����Ă��܂��B���[�����ȒP�Ŗ��l�ɗ����ł��āA����Ő헪�����G�Ȃ��̂��A���������邱�ƂɂȂ�B�X�|�[�c�ł����A�T�b�J�[���܂��ɂ���B�P�P�l�Ń{�[���R���āA����̃S�[���ɓ��������B������P�T���̋�����āA�����S�[����������Ƃ��������B���Ƃ��Ƒo�Z�ł�����B
�@���̒��ɃT�C�R���Ƃ������̂����݂���̂́A���̃o�b�N�M����������邽�߂Ȃ̂ł��B�����Ɏq��������Ă���G�̑o�Z�́A����̎q���p�B�O�i�ނƂ��A�U��o���ɖ߂�Ƃ��ˁB�U�U�͎O�ǂ��납�Q�S��i�ނ��A�q�b�g�����A�ő�łQ�S��߂炳���B���������Q�[���ł����B
�@�]�ˎ���̒������ł́A���̑o�Z�����������ł��Ȃ������҂悤�ɁA���ɋ����A������Ŕ��ł��n�߂��̂ł��B�{���̃Q�[���̋����җv�ł����A�����ǂꂾ���̐l�������~�Ŕ��ł���āA�܂����N�U�͂ǂꂾ�����K���҂������B�q���p�ł����ʔ����̂ł���A�����Ƒ�l�p�𗝉�����A���̂P�O�O�{�͖ʔ����Ɍ��܂��Ă��܂��B�������Ď��͎v��ʕ����֗�����Ă������̂ł����B
�P�X�X�T�N
�@�M�������̍����g�b�v�A���́A���N�Q�炢�͊C�O�̑��ɂ����Ă��܂����B���݂������ł��B�Ȃ��g���b�N���Z�̃g�b�v�v���A�����A���[���b�p�T�[�L�b�g�Ƃ����Ă܂����A�M�������������B�Ƃ����Ă��A�}�ł�����A���܂ɂ̓v�������܂����A����Q���ƂȂ��Ă��܂��B
�@���`�̃M�������O���[�v���A�����Łu�A�W�A���v���J�Â������ƌ����o�����悤�ŁA�O�N�ɂ͉�������@�Q�����Ă����悤�ł����B���͂P�O���ł��B�ŁA���̔N�ɂ́A���̑��ɂ��U��ꂽ�̂ł��B�m���ɖ��T�V�h�ɂ����āA�Q�[��������Ă͂��邪�A���̂��߂ɊC�O�ɂ܂Ŗ{���Ɏ������s���̂��H�ƍŏ��͋^��Ɏv���Ă����܂������A���̂������l���s���ƌ����o���āA���ɎQ�����邱�ƂɂȂ����̂ł��B�T���̂R���Ԃ��J�Ó��B
�@����܂ʼn��Ăɂ͗��s���Ă܂������A�A�W�A�ɏo��̂͏��߂Ăł��B���`�Ƃ����Ƃ���ɂ��A�����͋�������܂����B�l���̂X���̓`���C�j�[�Y�Ȃ̂ł����A����x�z���Ă���P���̔��l�̊ԂŐ���Ȃ̂ł��B��`����Ί݂̓��ɓn���āA���̍���Ƀ��N���G�[�V�����N���u�������āA���̍L����c�������ɂȂ��Ă܂����B
�@��{�I�ɃM�������v���[���[�Ƃ����̂́A���b�`�n�ł�����܂��B�Ȃɂ���Q�[���Ɋ|������������B�������p�`���R�̂悤�ɁA���ɓ�������̂ł͂Ȃ��āA���̏��s�ɐ헪������B����łĂ��T�C�R���U���Ă���킯������A�R�����炢�͉^�̗v�f���t���ĉ��B�����ɋ߂��ł��傤���B
�@���ŃQ�[������Ă��āA�u�R�[�q�[�v�Ƃ��u�сv�Ƃ����ԂƁA�����̃��C�h�A���������ɋ삯���Ă��܂��B������������N���҂̒j�̃`���C�j�[�Y�̃��C�h�B���ꂪ�A�T�[�o���g�̂悤�ɓ����āA���ɂ͎U�炩�����ςȂ��ʼn��������Ă��A�x�b�h���C�N���Ă����̂Ɠ����ŁA�Еt���āA�|�����Ă����B����Ȃ��ƂɈ�a��������A����������B���̐g���Ń��C�h�Ɏw�����Ă����̂��ƁB�ł����n�̘A���ɂƂ��Ă���͓��R�̂��ƂŁA�������������͂Ȃ��B�����Ńf�j�[�Y�ŃE�F�C�g���X�ɒ�������̂Ɠ������Ƃ������������ǁA�����̓��X�g��������Ȃ��āA�����������V��ł���ꏊ�B���{�ȊO�͐g���Љ�ŊK�����ɂȂ��Ă���̂ł��B
�@�����������̓g�[�i�����g�ł����A�M�������̑��̂����Ƃ���́A���C���g�[�i�����g�ň���Ă��A�܂��R���\���[�V�����i�s�ҕ�����j������B����ɕ�����ƁA���̃g�[�i�����g����͂͂�����邪�A�u���b�c�g�[�i�����g�Ƃ��A�T�C�h�C�x���g���܂�����B����Ȃǂ́A�����Ă��܂����G���g���[���ł���B����JP�Ƃ����g�[�i�����g������BJP�̓��C���Ɠ������炢�ɍ��z�܋��ł�����B����ɂ܂��܂��A�P���}�b�`�̃g�[�i�����g�Ƃ����̂�����B�܂�o�鎎���A�o�鎎���ǂ�ǂ��Ă��A�܂��܂��G���g���[�i������������j����A�O���邭�炢�ɁA�ǂ�ǂ�ł���B�����炢�ł����Ƃ����ƁA�吨���W�܂��āA�N�����ŏI���̌�����̍��܂Ŋy���߂�Ƃ����d�g�݂ɂȂ��Ă���킯�Ȃ̂��B���������C�x���g�̊J�Ì`������͂�A���ẴM�������t�@�������j�̂Ȃ��ō��o���Ă������Ƃ��Ǝv����B�������Ɉ�̂������|���Ă͂����܂���ƂȂ��Ă���킪���ł́A�Q�[���C�x���g������ɂȂ�͂����Ȃ��Ǝv���B�q���̗V�т���Ȃ�����B
�@���`�̘A���Ƃ������A�A�W�A�l�͌��X��x���܂ŗV�ѕ����Ă���A���ł��B���`�͓��������x���܂ŁA�ߑO�R�����܂Ől�ʂ肪���₩�ł��B���������`���C�j�[�Y�̐H�ʂƂ����̂��A���̂Ƃ��ɖڂ̓�����ɂ������ƁB�X�̒��ɂ������������āA�j���ł��鋛�𗿗�����X�͂ǂ��ɂ����邯�ǁA���̃s���N�F�̃i�}�Y�͂��������Ȃ����̂��ƁA�v���o���B�u���X�̂����߂ł���v�Ƃ����̂��B�ǂ������V�i�C�Ƃ��A�g�����C�̃i�}�Y�Ɍ��܂��Ă���B�����ڂɓŃL�m�R�̂悤�ȐF�����Ă���B�{���ɐH����̂��H
�@��������ƁA���̂���������i�}�Y���o�P�c�ɂ���āA�ꉞ�����Ă���B�u�������̓R���ł������܂��ˁv�ƁB�i�}�Ō�����A�Ȃ��C���������B
�@�ł����ꂪ�A�P�T�����炢�ŗ�������ďo�Ă���ƁA�O�����̋��ŁA����Ȃ��܂����̐H�������Ƃ��Ȃ��Ǝv�����قǁA���܂������B�`���C�j�[�Y�͉��ł��H�ׂ�̂��B�l���͈֎q�ƃe�[�u���ȊO�͑S���H�ׂ�B
�@���ʂ���U������ƁA������������B�Ăɐ������܂܂̃j���g�������������āA�q�������ƁA�{���ɖڂ̑O�Ŏ�͂˂āA�������B���ʂ̋����ł��A�j���ł��鋛���A���̏�ōق��Ĕ����Ă���B������юU���Ă����C�B�̂̓��{�ɂ������悤�ȓX�͂������̂��낤���A�ŋ߂͌��Ȃ��B�ł����`�ł��ꌩ��ƁA������܂������B�����Ă���ǂ����̉ƒ�̎�w���A���ꌩ�Ă����Ƃ��Ȃ��āu���������ŕ|���v�Ȃ�Ă������{�̏��ɂ́A�{���̔��������т͍��Ȃ����낤�Ǝv���Ă��܂��̂��B�l�Ԃ͒��⋍���E���āA�{���ɐH���Ă���Ƃ������Ƃ�������B
�@�M�������v���[���[�ō��`�ɂ��Ă����̂́A���n�̔��l�͂��������A�^�C�A�}�J�I�A����������B���͂��̃^�C�Ƃ����̂��Ȏ҂ŁA�����^�C�̌��n�l���M����������Ă���̂ł͂Ȃ��B�������ɂ́A�h�C�c��k���Ȃǂ���u�����ăC�����v�Ɨ���Ă������[���b�p�l���S���S���ƏZ��ł�����̂��B
�@����h�C�c�l�́A�N�ɔ��N�����Ƃ��Ƀ^�C�ɏZ��ł��āA�Ƃ�ł��Ȃ��������������߂Ƀ��C�h�����āA���������h�C�c����̓c�A�[�ό��q������悤�ŁA���̃u�b�L���O�Ƃ����āA�ȒP�ɕ�点��Ƃ����Ă����B�������o�[�ɂ���ƁA�M��������낤�Ƃ����q������B�����炩�|���āA�X�g���[�g�t�@�C�g���āA�ʏ폟���Ă��܂��B���ꂪ�т̎�ɂ��Ȃ��Ă���ƁB�u�����Ⴂ�A�����A�����̐����v���Ȃ��āA���̏ꂵ�̂��̐����̂悤�Ŗ{���ɂ����̂��v�Ǝv���̂����A�V�l�ɂȂ��Ă��A�����ƂƂ̂Ƃ��ɐv�ł���炵���B
�@��̃^�C�ɂ͓��{������ό��q���吨�s���B���[���b�p���������̂��B���n�ɂ��ău�b�L���O���āA�����ꍑ�֗A�o�ł���悤�Ȃ��̂�����A������f�Տ����ɂȂ�炵���B�����獁�`�Ƃ����Ă��A���Ăقǂ���Ȃ����A���l�R�~���j�e�B�������킯���B
�@���Ď��͂��̑��͂S�O�l���炢�̋K�͂��������A�T�C�h�C�x���g�̂Pp�}�b�`�̃h���S���E�X���[���[�Ƃ����C�x���g�ɏ����i��ł����B�����E���Ƃ����Ӗ��ɂȂ�B�G���g���[��~�B���ʂU�S�l���Q�����邱�ƂɂȂ����B���킩�炾�ƂU�A������ƗD���B���̒��ɏ����T�O���Q�[���łU�A��������Ă��Ƃ����݂���̂��Ǝv�����B�ł��U�S�l���Ɉ�l�����A���������l�͑��݂�����̂��B
�@�R��킭�炢�œ��������̂́A���C���ŗD�������k���n�̌Z���������A�ł��ނ͎�������邻���ŁA�C�^���A�̃s�b�L���O�̃v���݂����Ȋ�����Ă����B����ɂ����������A���̎��ɂ͎O���̃M�����O�f��̈����ɂ҂�����̒j�ɂ��������B�������ĉ��������̂Ƃ��ɂ́A�x�X�g�S�ɂR�l���{�l���������B�������̎R�͉����ƒ��J��B�������͎��ƁA���Ɛ��͏��Ȃ��`���C�j�[�Y�̃I�W�T���B�������������āA�������͒��J��B���`�̑��̌����ŁA�V�h�̃����o�[�Ɠ�����Ƃ����̂����������������A�����������܂ł���A�R���𗎂Ƃ������͂Ȃ��B�Q�[���͔����ȓW�J�ɂȂ������A���̏����B�S�̒��ł��ꂵ�����B
�@�D�����āA�܋��͐�~���炢���T���~���炢�ɂȂ����B�Ƃ��������A���̃C�x���g�ɂ��D���J�b�v�������Ɨp�ӂ���Ă��āA����������ċA�邱�Ƃ��ł����B���݉䂪�Ƃɂ͂������̗D���J�b�v��g���t�B�[�����邪�A���̍��`�̑��̃Q�b�g�����̈�ڂƂ������ƂɂȂ�B��̃Q�[���̌�����ɂ��Ă��A�T����ɂł����A�S�s�ŏ��D������Ƃ����l������B�����Ƃ����̂͂���Ȃ��́B���ꂪ���߂Ă̌����ŁA�������C�O�ŏ������Ƃ����̂́A����͖Y����Ȃ��o�����ƂȂ����B
�@�M�������ɔM���Ȃ��ĂQ�N�ڂɂ����������Ƃ������āA����ɂ܂��̂߂荞�ށB
�P�X�X�U�N
�@�M�������ɂ̂߂肱��łR�N�ځB
�@���́A������P�O�N�O�ӂ�̂��Ƃ��A���Ŏv���o���Ȃ���Ԃ��Ă���̂��Ƃ����ƁA���͉��ō��S�V�ɂȂ邪�A�͂����肢���đ̗͂̒ቺ�B�ŁA�ǂ����Ă���Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����낤�Ƃ������ƂƁA�܂��R�V�ł��\�������̂ɁB����ꂽ�P�O�N�́A�ǂ����Ă����Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��܂����̂��낤�Ƃ����A�������������߂ł���B
�@�y�������Ԃ͂����߂��Ă��܂��Ƃ����̂́A�{���݂������B���A��̂��Ƃ��Ƃ��������B���ꂪ�����Ȃ�A���̂P�O�N�͂悩�����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̖�̔@���̏ؖ����A���̂X�U�N�Ƃ�������ɁA�����������������낤�Ǝv���o�����Ƃ��Ă��A�R���Ƃ��������Ƃ��Ȃ��B����ʼnߋ��̎����������o���Ă݂�A�Ȃ�قǁA�V�h�̃M�������N���u���Ăɕ��ɂȂ��āA�ԍ�Ɉڂ��āA���͂���ȍ~���݂܂ʼn��̒S���ɂȂ��Ă���B�܂�N���u�̌����V���s���Ă���Ƃ������Ƃ��B����͌��݂܂łW�N�������Ƃ������ƁB�̏�ɂ��W�N���B
�@���邢�͂P�O���ɂ́A�O�N�̂悤�ɁA���l�̒��Ԃƍ��`�ɂ������B�ł��R���Ƃ��������т͂Ȃ��B
�@�Z�{�̃��X�g�����t�B�����h�̃}�}���A���̂Ƃ��̒��Ԃ̈�l�ŁA�ŋߋv���Ԃ�ɉ�������Ɂu���̍��`�c�A�[����W�N���o���Ă��܂����̂ˁv�Ɯ��R�Ƃ��Ă��܂������̂����B
�@����ɂ��̔N�̏t��ɁA���a�T�N���܂�̕��e���U�U�ŖS���Ȃ��āA���ꂩ����W�N�B
�@����ȊO�̕��i�́A�܂������T���ɂ́A�M�������Ђ��ł��������B
�@�ł��܂��A�d���͕��i�ǂ��菇���������Ǝv�����A�q������l�����w�����������A�X�L�[�V�[�Y���ɂ́A�q�A��ŃX�L�[�͂��Ă����͂������A���}�Ȃ�A�y�������Ԃ͉߂����Ă����͂����Ǝv���B�������ĂP�N���߂��Ă��܂����B
�@�����Ɖ������Ă����Ηǂ������ƍ��v�����Ƃ��Ă��A�����͂����v��Ȃ���������A�������Ȃ��āA���}�ɉ߂��Ă������̂��낤�B����́A���v���o���邱�Ƃ��Ȃ��Ă��A�ǂ��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ͎v�����B�Ȃ�ƂȂ��V���āA�Ⴂ����̃J�^���V�X�����Ă��邾���Ȃ̂����m��Ȃ����B
�P�X�X�V�N
�@�M�������ŁA�����C�O�]����n�߂悤�Ǝv�����B�킪�Ђ́A�T����GW�̂P�T�ԑO�ɋx�ɂ�����B���傤�ǂ��̂Ƃ��́A���X�x�K�X�̃M���������̓����ł��邱�ƂɋC���t�����B���̐��E���́A�T���̂T���ԍs�Ȃ�ꂽ�B����ɏ��߂Ĉ�l�ŎQ�������̂��A���̔N�B���̖��O�́A�c�C���o�b�N�M���������B�����ł́A�C���^�[�i�V���i���J�b�v�ƃl�o�_�J�b�v�̓�̃^�C�g���������āA�g�[�i�����g���J�Â��ꂽ�B�A�����J�̑��ł́A�i���o�[�������c�[�̋K�͂ɂȂ�B
�@�Ƃ��낪���Ԃ́A���E�I�茠�Ɩ��̕t�����A�V���̃��i�R�̑��ɂ͂P�O�l�ȏ�Q�����Ă����̂����A���̃A�����J�̑��ɂ͎Q�����Ă��Ȃ������B�x�݂̊W�������̂��B����Ȃ��ƂŁA�����̃M�������N���u�̑g�D�̒��ł́A���́u�A�����J�S���v�Ƃ�������悤�ɂȂ������B
�@���̑��Ł��T�O�O�̂P�U�lJP�łQ�ʂɂȂ����B�܋������Q�Q�O�O���炢�o���B�ߋ��̐��E�`�����s�I����A���E�̗��_�Ƃƌ�����l�Ƃ̑ΐ�����������A����ɉ^�ǂ������Ƃ��ł����B
�@����������Ȃ��Ƃ����A�ŏ��͊ό����s�̊C�O�n�q�Ɏn�܂��āA���̂����ɓo�R�B���̂����Ƀp���A�������ăM�������ƁA���s�ɖړI���t���悤�ɂȂ����������A�i�������悤�Ɏv���Ă����B���X�x�K�X���A�ߋ��ɂ͊ό��ł������A�h���C�u�̓r���ł���������A���̂Ƃ��͂R��ڂ��炢�̖K��ɂȂ����B
�@���̍��́A���E�̃g�b�v�I��Ƃ��ĒN������F�m����Ă����l�ɁA�E�B���R�b�N�X�Ƃ����v���[���[�������B���݃A�����J�ł̓i�b�N�o���[�h�����l�҂Ƃ���Ă��邪�A�����̓i�b�N�����E�B���R�b�N�X�����炩�ɋ��������B���܂��ܑ��ŔނƑΐ킵�āA����͂������蕉���Ă��܂����̂����A�F�l�ɂȂ����B���͔ނ͂��̒��O�ɍč����āA����͒��ẴR�X�^���J�o�g�̎q���������������B�ޏ��͂܂��p����悭����ׂ�Ȃ��Ď��Ɠ����x���������A�v�w�̓��X�x�K�X�ɏZ��ł������A�܂��S�������Ƃ��ŁA�ޏ��͎Ԃ��^�]���Ă����������炢�������B�ł��̔N�̉ĂɁA�R�X�^���J��USA�J�b�v������ƁA��Â̓A�����J�ɏZ��ł���A���B����ɂ����ł�Ȃ�Ă����b�ɂ��Ȃ����B
�@���ĉċx�݂̂Ƃ��ɁA���̃c�A�[�ɎQ������B�ŏ��̏T���́ALA�ŃR���͂��łɃ~�j�g�[�i�����g�ɏo�邱�ƂɂȂ����B�����ł܂��U�S�l�̂P���g�[�i�����g�ɗD�����āA���Ƃ��Ă͓�ڂ̃g���t�B�[�̃Q�b�g�ƂȂ����̂����B
�@���͂��̂Ƃ��̃z�e������A���܂ł͂��悻�����ĂQ�O�����炢�̓��̂肾�����B��������āA���̓��̂��������Ƃɂ����̂����A���̂Ƃ��u�Ȃ�ŁA�Q�O���̋������邭�̂��炢�v�Ǝv�������炢�A�A�����Ă��܂����̂ł���B�l���Ă݂�A���́A���̂R�N�ԁA�قƂ�lj^�������Ă��Ȃ��B�~�̐����Ԃ̃X�L�[�������A�����Ȃ��B�����Ԃɏ���Ă��āA�u�P���ɂP�O�O�����炢���������Ă��Ȃ���Ȃ����낤���v�Ǝv�����������炢�������B����ɊO�l�Ƃ����̂́A���̃f�u�����̂ł��A���H�p�[�e�B�ȂNj�ɂ��Ă��Ȃ��炵���āA����ȂɈ֎q�ɍ���Ȃ��̂��B���{�l�͔w���ł��ア�낤���Ǝv���B
�@���ʂ̃z�e���̃��r�[�ŃE���E���ƕ��������B���邢�̓z�e��������܂łQ�O�����������ŁA���͋�ɂȑ̂ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B�u����Ȃ̂ł͂����Ȃ��v�Ǝv�����̂��A���̂Ƃ��ɂȂ�B���Ƃ����āA�Q�O�Α�̂Ƃ��̂悤�ɁA�܂��}���\������낤�Ƃ��v���Ȃ��B�G���ɂ��Ȃ�B����A���U���A�E�H�[�L���O�Ƃ������ƂɂȂ�B���傤�ǂS�O�̂Ƃ����B�v���Ԃ��A�R�T�܂ł́A���i�͉����^���Ȃǂ��Ȃ��Ă��A���C�������B�ł��S�O�ɂȂ�ƁA�ɒ[�ɒቺ���Ă����̂��낤�B���߂Ď����̌��N���v���āA�������Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ǝv�����̂����̂Ƃ��B
�@���������A�A�����J�ł̓G�N�T�T�C�Y�̃N���u�Ȃǂ��A������ł��������B�Ƃ���̃E�B���h�[����A���̃l�Y�~�̂悤�ɁA���[�������i�[�̏�𑖂��Ă���A����������ł�����B
�@���悻���E�ł͒m���Ă��Ȃ����ł��A�Ⴆ�R�X�^���J�Ȃǂł��A�M�����������悤�ȃ��]�[�g�͂�����ł�������̂Ȃ̂��B�z�e���ɂ̓J�W�m���������B�a�q����Ƃ����l�́A�P�j�A�܂ŃM�����������ɂ��������̂��B���E���Ń��]�[�g���Ȃ����́A�k���N������������Ȃ��B�C���h�����āA�j����������Ă��邵�A���҂��̃��[���X���C�X�������Ă��邵�B�������q���Y�[���̃X�����X�ŁA���̓���炵���Ă���l������B�����̎R�J�ɂ������悤�Ȑl������B�u�n�������v�Ƃ��u�r�㍑�v�Ƃ��ꌾ�ŕЕt���Ă��܂����A����͑S�̌o�ς��r��ɂ��邾���ŁA�����ł݂�A�ό������ɗ����Ă���y�n�͂�����ł������āA�܂����������y�n�ɂ́A���������ό��ɂ����Ă�����̂Ȃ̂��B�R�X�^���J�Ȃ�Ă������ɁA�z�e��������́H�Ƃ��A�J�W�m������́H�Ƃ��A���������Z��ł���́H�Ƃ������A�����ȃA�z�ȋ^�������̂́A���̐��\�N�Ő���オ�������{�l��������Ȃ��̂��ƁA�v���B�吳��A���a�̐�O�͓��{���n���������Ƃ����̂����A������������f��ŁA���s�ɂ͂��̍����痿�������������A�|�q���������A�����ŗV�ԘA����������ł��������̂��B
�@�ŏ��̊w�����s���A�o�X��d�Ԃ̃q�b�s�[���s�������̂����A���̍��ł́A�M�������Ƃ������b�`�ȗ��s�ɂȂ��āA�w�L�т��Ȃ炪�A�D��ȘA���̐U�镑�������āA�����������̂ɁA�������Ă������ł�����B�ł����X�x�K�X�Ȃ�ĂƂ��́A�����������̃��]�[�g�Ƃ����킯�ł��Ȃ��āA�����̃f�B�Y�j�[�����h���x�́A�e�[�}�p�[�N���Ǝv���̂����B���X�x�K�X�ł͂܂����̂Ƃ��͌��ݒ����������A�x���[�W�I�Ƃ����z�e���́A�C�^���A�̃R�����e�[�}�ɂ����z�e���ɂȂ����B���̂ƂĂ��Ȃ������̃z�e���ł���B�ł��R���ɂ́A���̂Q�N�O���������A�p���c�A�[�ɏo���Ƃ��ɁA���܂��܊�������������ŁA�m���ɑf�G�Ȍ̏����Ȓ��������B�C�^���A�̘A���́A���t�͓������Ƌ��ŒN������ꂽ�炵���A�f��̃��[�}�̋x���ł��A�~�j�o�C�N����l���ő����Ă��܂��B����Ȃ̂��ƂĂ��������������悤�ȋL��������B�x���[�W�I�̂��̃e�[�}�̌��n��m���Ă���l�ƂȂ�ƁA����͋ɒ[�ɏ��Ȃ��B���[�}��~���m�ɂ͒N���������Ă��A���̖k�ɂ���R���͂�قǗ��R���Ȃ��ƍs���Ȃ��B���������k�ɍs���X�C�X�Ƃ̍����ŁA�z�������K�m�Ȃ�Ă������́A�X�C�X�ɂ���̂ɁA�C�^���A�ꌗ�������B�X�C�X�ɂ͂S�̌��t������B
�@�����������Ƃ�m���Ă��邱�ƂɁA�܂��D�z�����������肵�Ă����B
�@������ɂ���A�̗͒ቺ�A�Q�O����������ɂɂȂ������ƂɁA�C���t�����L�Ӌ`�ȔN�������Ƃ������Ƃ��B
�P�X�X�W�N
�@���̔N�̉Ăɂ́A�_���X�̃��[���h�J�b�v�i�����M�����������ǁj�̑O����ɎR���ƎQ���B�L�^������u�����v�Ƃ͎v���o�����ǁA�N�Ԃ̃I�[�f�B�i���̃X�P�W���[���ŁA�V�т܂�����Ċ������ˁB
�@���͂��̔N���������A�O�N�̃R�X�^���J�̂Ƃ����������A�����Ă������p�\�R���Ńl�b�g�𗧂��グ���Ƃ��ł����B����Ȃ��̖{���ɕK�v�����Ȃ�����͎n�߂Ȃ����̂ł��B�R�X�^���J���������_���X���������A����ɎQ�����邽�߂Ɏ������A����͑����HP�Ȃǂ��猟�����邵���Ȃ��B������}�W�ɁB���������K�v���ɋ���Ă̂��Ƃł����B���Ȃ݂ɃL�[�^�b�`�́A���̂Q�C�R�N�ʑO�ɁA����̓��[�v���̕K�v������A���}�W�Ɋw�Z�ɒʂ����̂ł��B�P�����X�O���ŁA����P�T�����炢�܂ŁA�R�T�Ԃ��炢������܂������B�|�����o����Ɂu�u���C���h�ł�����v�ƌ����āA���l���Ă݂�A���̓w�͂Ƃ����̂́A�����^�]�Ƌ��擾�̂R�O�{���炢�̈Ӗ����������̂����m��܂���B
�@���̑O�ɂ́A�P�O���~�Ń��[�v���������炢�Ȃ�A�P�O���~�̖��N�M�����Ƃ��A���ӋC�Ȃ��Ɩ{���Ɍ����ĂāA����}�W�ɂ���Ă��܂����B���M�Ȃ̂ɁB
�@�ł��������Ď��オ�p�\�R���ɂȂ��Ă���ƁA���������̂��A�菑���̂P�O�{���������y���Ƃ������Ƃ��A���ɂȂ��ė����B���Ǔ����́A���[�}�����͂ȂǁA���т����������Ƃ������āA�L���m���̐e�w�V�t�g���ǂ��Ƃ��B�ł��l�b�g�ʼnp���̕K�v�����v���A���傤���Ȃ����E���ʂ̂��̃^�b�`�����Ȃ��킯�ł��B���̍��e�w�V�t�g�Ƃ��A�a�����͂Ƃ����Ă����A���ǂ�������ł��傤�A��������ł��˂����ƁA����ɖ�����āB
�@���̃^�b�`���A���̔N�ɂȂ��āA�悤�₭�ʏ�ɂł�����ł��傤�B��̃M�������̉����n�߂āA�Q�N�ł����B����͎��̃^�b�`�̗��K�̂��߂Ɏ����ł��o�����Ƃ����Ă������B����܂ł͂ƂĂ�����Ȃ����A���͂Ȃ�ď����C�ɂ��Ȃ�܂����B�^�b�`�ɐ_�o�g���āA�������Y��Ă��܂��܂��B�K�v�͔����̕�Ƃ͂����܂����A�K�v�́A���C���A�^�b�`����ł����B
�@���������f�X�N���[�N�ɒǂ��Ă��܂����B��ɂ���āA�A�E�g�h�A�͂�������Ȃ��B���̂�������Ȃ��Ȃ��āA�S�N�ł����B
�@�_���X�ł͂Ȃɂ��������ƂȂ������ł����A��͂�P�O���ɍ��`�ɂ����āA���̔N�̓X�[�p�[JP�ŗD���B����͂P�O���~�̂W�l�ŃX�^�[�g�������̂ɁA���̂S���̂P�����ɐl���W�܂��āA�������傭�Q���T��~�̂R�Q�l�Ƃ����v�Z�ɂȂ�܂����B�T�A���ŗD���B�T�C�����Ƃ��A�X�e�B�[�u�l���\���Ƃ��A���i�R��A�g�݂Ƃ̑ΐ������܂������A����^�ǂ��D���B�����ɏオ��ƁA��̏��Ă�Ȃ�Ă����ςȎ��M�����Ă܂����B�܋��͂W�O���~�قǂ��Z�g���ł��悻���X�ŁA�S�O���~���炢�ł������B�����Ȃ�Ɩ��S���āA���͏܋��P���h�����ƖڕW�ɂ����̂ł����A�R���͖����Ɏ��������B�M�����������̔N�łS�N�ڂł����A��͂܂肵�Ă܂����B���܂ł��E�E�E�B
�@�l�b�g��GG�A�Q�[���Y�O���b�h�ɎQ���������̂��̔N���������B�A�����J�̃T�C�g�ŔN�ԂU�O�O�O�~���炢�B���̒��ɐ��E���̑��肪�ڑ����Ă��āA�����͌��n�̖�ɂȂ�ƂP�O�O�l����ď��Ȃ����̂ł������A�ŋ߂͂��ł��T�O�O�l���炢���܂��B���̃l�b�g�̌������̐l�Ƒΐ킷��B���ꂩ�琔�N���āA���t�[�ł��������Ə��߂āA���܂ǂ������ł��I�Z���ł������ł��A�i�}�ł��l�Ȃǂ��܂���B�l�b�g�̕����܂������ȕցB�����GG�ł́A���̐��N��ɂ́A�������|������悤�ɂȂ��āA�����I�ɂ����ł���B�A�����J�̃T�C�g�ł�����B�����Ȃ�ƁA���̃p�`���R��ɘU���āA���������z���Ă���A���́A�܂������A�z�Ɏv���Ă��܂��B�n�R�l���ǂ�ǂ�n�R�ɂȂ���Ă̂́A���������d�g�݂ł����B
�@���������Ύ������Ă�����A�|�[���}�O���G�������������{�ɌĂ̂��A���̂X�W�N�ł����B�M�������E�̐_�l�ł��B���w�҂̔ނ́A�����M�������ɂ͂܂�Ȃ���A�m�[�x���܂���ꂽ��������Ȃ��Ƃ����V�ˁB���������A�������̃Q�[���E�ɂ̓S���S�����܂��B�F�d���̗]�͂ŁA�]�͂��{�E�̖ʔ������̂��ŁA���̃Q�[���ŗV��ł��܂��B�����������w�҂͂����͂Ȃ����ǓV�˂ŁA����ς肻�������l�ɂ̓p�g����������̂ł��B�����̓p���ɏZ��ł����炵�����A�����������{�ɑ؍݂����P�T�Ԃ́A�ނ̓S�[���h�}���T�b�N�X���������̃t�@���h�}�l�W���[���A�ԍ�̍��w�}���V�����ɏZ��ł��āA�W�����Ƃ��������A�ނ̉Ƃɂ��܂����B�ꍑ�A��ƁA����̓A�����J�ł����A���X�x�K�X�ɍ��͏Z��ł���悤�ŁA�������N���̃A�p�[�g����Ă���Ƃ������A�|�[���Ɂu�݂��ďグ���v�Ƃ����X�|���T�[������킯�ł���B�^�j�}�`���Ă̂́A�����o��������Ȃ��āA���w�҂ɂ����Ă���Ȃ��ƁA�v�����킯�ł��B
�@�M�������͒m�I�X�|�[�c�ł�����A�����Ɋy�������āA�[�����Ă������ゾ�Ƃ������Ƃł����B
�P�X�X�X�N
�@�A�E�g�h�A�̂U�N�ځB
�@�P�O���P��̓��{�I�茠�̑��O���Ԓ��ɁA���̗[������̃C�x���g�Ƃ��āA�W���p���I�[�v���݂����̂́A�����ł����B���̔N�́A���̑�T��ځB���ߋ��ɃW���p���I�[�v���ŗD���������Ƃ��������̂ł����A���̂Ƃ��̃g���t�B�[���āA����͂X�X�N�̑��������Ƃ��m�F�B�ߋ��̉h���A����Ȃ��Ƃ��������̂ł��B
�@��������ƁA�R�Q�l���傤�ǃG���g���[���Ă��܂��B�g�[�i�����g�T�A���ŗD���B�������܋��S�O���~���炢�l�������ł��傤���B�u�ߋ��ɃM�������œ��{��ɂȂ������Ƃ�����v�Ƃ���́A�����ウ�邱�Ƃ��ł��܂��B�ł����{�I�茠���Ƃ��A���l�킾�Ƃ��A���{�ꖼ��邽������̃g�[�i�����g�����邱�Ƃ��܂������A�y�������Ƃł���B
�@�Q�[���C�x���g�̍\���Ƃ��ẮA�M�������̐��E�W���̑����Ƃ��ɂ́A�ŏ��͋����܂����B�O�ɂ��������悤�ɁA���ׂẴC�x���g�ɃG���g���[���āA����K���ɕ����Ă��܂������ł���B�������ǂ���ǂ�ǂ��i��ł������Ƃ��ɂ́A�����P�����A���̋x�ݎ��Ԃ��Ȃ��āA���X�ɑΐ킪����Ă��܂��B����͂������ƂĂ��y�������ƂȂ̂ł����A���������̎����ɏW���ł��Ȃ��āA���邢�͔��āA����Ƃ��ɁA�x�X�g�W����S�֏��������鎎���ɁA�ǂ��������ꋓ�ɕ����Ă��܂��Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ����ƂɊׂ��Ă��܂����̂ł��B�ߋ��ɂ��������l��������ł����܂����B
�@�e�j�X�̐��R���Ȃǂ́A�V���O���ƃ_�u���ƁA�~�b�N�X�_�u���X�̂R�ɂ����G���g���[���Ă��܂��B�������Ĕޏ��͐��E�ł�������x�����ł�����A������x�X�g�W���炢�ɏ����オ���Ă���킯�ł��B�����Ȃ�ƁA�P���ɑ����Ƃ��ɂ́A���̂R�������ׂĂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�������B�ޏ��Ⴍ�ăp���[������܂�����A�����������Ƃł��܂����A�������A�����������@���Ȃ��I������܂��B�ߋ��̏����̃G�o�[�g�́A�_�u���X�ɋ������Ȃ������̂��A�G���g���[�͂����V���O�������B����ł����x���D�����Ă��܂��B�����ޏ��Ƒ����ΐ킵���A�i�u���`�����́A�ǂ���ɂ��G���g���[���Ă��܂����B�v���[���̃G���g���[�͎��R�ł��B�{�l�̈ӎv�������B��������オ���āA��̎������������ԑтɗ\�肳��Ă����Ȃ�A��Î҂͎��Ԃ����炷�ȂǕX�͐}���Ă���܂����A����ł���̎������I����āA�Q�O�����炢�̋x�݂����ŁA���̎��������Ȃ��Ă͂����Ȃ��B
�@���������l�q�́A�S���M�������Ɠ����Ƃ������A���͂ǂ�ȑ��ł��A�^�c�V�X�e���Ƃ����̂́A���E�W���ɂ����ẮA�������ƂȂ̂ł��B���͂��̐��N�̃M�������̐��E���Ɏ��ۂɎQ�����āA�����������Ƃ��{���ɂ悭�������Ă��܂����B
�@�~�̌ܗւɂ́A���͂����݂����Ȏ�ڂŁA�J�[�����O������܂����A���̑I��Ȃǂ́A�e�n�̃N���u�o�g�҂Ȃǂō\������Ă��܂��B����́A�M�������N���u���A�����ł��C�O�ł��ǂ̓s�s�ɂ�����悤�ɁA������������ƂȂ̂ł��B�N���u��Â̑������邵�A�t�F�f���[�V������Â̑�������B�F�������ƁB
�@���������̃C�x���g�������Ă���ƁA����͑����ɖ��n�ʼn����킩��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B����Ӗ��ő����̃C�x���g���c��ł���킯�ł��B
�@�Ⴆ�A���{�ł̓Q�[���̃v���I��Ƃ��������ŁA���̂����h�����B����͈͌�Ə����Ƀv�������݂��Ă��邩��Ȃ̂ł��B���c�̂̃p�g�����͐V���ЁB�ǔ��́A������Ƃ����^�C�g���ɔN�ԂR���~�̃X�|���T�[�����Ă��܂��B�����悤�ɖ����͖��l��ɁA�T���P�C���A���o���A�Ԋ��܂ł��A�����������A���ׂĂ̐V�������̂Q��ڂɏo�����Ă��܂��B����������A������{���@���v�������w���A�͌�ł��ɕ��z���Ă���Ƃ����\�}�ł���B�܂�p�g���������Ȃ��ƁA���������オ���Ă��Ȃ��Ƃ����̂��A���{�̌���B�ł��C�O�̂Q���S���t�I��Ȃǂ́A���������łP���~���炢�o�����āA�P�O�O�l�ő��J���āA�D���҂��P�O�O���~�̑���肾�Ƃ������āA�Q���C�x���g�J�Â��Ă���̂ł��A���͂��̕��������ƌ��S���Ǝv���Ă���̂ł��B�Q�[����肽���Ƃ����l�́A������H����Ȃ��B�p�g������X�|���T�[�����Ȃ���Ή����ł��Ȃ��ȂǁA�������Ȃ�����q�������ĂȂ��Ɠ������ƂŁA����͂Ў�ȍl���ɂȂ�܂��B
�@��̃J�[�����O�̑I��݂͂�ȃA�}�����A�A�e�l�̃A�[�`�F���[�̋�̂��̂���������A���Z���t�Ƃ����A�}�ł��傤�B�A�}�̉��������̂��B�o�R�����Ă݂�ȃA�}�ł���B�����炱���D���Ȃ��Ƃ��ł���B�v���Ƃ͌���������Ό�H�Ƃ����A���ɂ͎v���Ȃ��̂ł��B�^�����g�͓d�g�|�҂����A���N�U�̏W��ł��Ă��Ώo��������Ȃ����́B�v���Ɩ��̂������ŁA���h�̂܂Ȃ��������ʐl�́A�{���ɃC�x���g�̍\���𗝉����Ă��Ȃ��킯�ł��B�R�̃K�C�h�����āA�ւ�Ă��I�o�T���ɌĂꂽ��A�ē����邵���Ȃ��ł���B
�@����ƍ����̃C�x���g���܂�Ȃ��̂́A�����Q�[�����[�J�[���Ƃ��A�オ���O��Ɉꉞ��������Â��Ă���B����͑I��̂��߂ł͂Ȃ��āA��Ђ̐�`������ł��B�v���[���[�͍l�������n������A����ɏ�������Ă��邾���B������A���o�C�I�ȑ�����ŁA�O���Ԃ̏����̌ߑO�P�O���̎����J�n�ɂ����āA�P�O�����ɂ܂��Ă��܂��Ɓu�A���Ă��������v�ƂȂ�B���������O���Ԃ̗\�肭��ł���̂ɁA�u���Ɠ���͉������炢���́H�v�ƂȂ�B���\�ł�����Ȃ́B
�@�v���[���[�������������y���݂�������ƁA��悵�����ł͂Ȃ��̂ł��B��������ƁA�{�����e�B�A���Ƃ��A�\����悾�Ƃ��A�����̔\�͏o���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B����Ȋ������̂̓C�����ƁA���{�l�͑ӂ��҂̗��j������̂ł��B�y���ݕ���m��Ȃ��Ƃ����Ă������B������v���싅�ł����A�`�[���͂��ꎩ�g�������ł��Ȃ��āA�ߓS�Ƃ����c�ɂ̉�Ђł����̕��������x�������Ȃ������̂ł��B�����������Ƃ���Ɏ��悤�ɕ�����B
�@���������l�����A�M�������̑��ɋ�����ꂽ�悤�Ȃ��̂ł����B�ŋ߂͍��̂ł��{�[�����O���Ƃ��r�����[�h����ڂɂȂ��Ă��܂����A���̃M���������ܗւ̎�ڂɂƌ���ꂽ�Ƃ����������̂ł��B���Ȃ��炨�������b���Ƃ͎v��Ȃ��BIOC����Â������̂���Ȃ��ł����A�؍���IT�֘A����Â��āA�}�C���h�ܗւ��J���ꂽ���Ƃ�����܂����B�Q�[���̌ܗւƂ����Ӗ��ł��傤�B�ł��M�������Ȃǐ���オ��Ȃ������̂͏܋����łȂ��������Ƃł��B����͑I��̃G���g���[�t�B�[�i�|�����j���֎~���Ă������߂ŁA���ꂶ��q���̉^����ł���B�e�j�X��A�����J�僊�[�O���{���̌ܗւł��o�Ȃ��̂́A�q���̉^����Ȃǂɂ͎Q�����Ȃ�����ł��B����Ɠ����B�}�C���h�ܗւł́A������͌���v���͏o�܂���ł����B����ɂ͓�̗��R�������āA���E�F�m�̃Q�[���ł͂Ȃ����ƂƁA�����̃v���ΐ�őǗ�������������A�����Ƃ�������ł��B��l�̃C�x���g�Ƃ����̂́A�����������̂ł��B
�@���悻�����̉ߋ��܂Ƃ߂āA���̂X�S�N�X�X�N�̂U�N�Ԃ��A�M�������ɍł��M���Ȃ��Ă������������̂��Ǝv���܂��B�W���p���I�[�v���̗D���Ƃ����̂́A���炩�ɉߋ��̉h���ł����āA���������̎v���o�Ƃ����̂́A�������Ԃ߂Ă������̂ł�����킯�ł��B�N�̂��̂ł��Ȃ��āA������������l���������Ǝv���āA�����Ɉӎv�������Ă�������ł��B
�@�Ȃ����̌�A���̃C�x���g�͂���ɍ��ۉ����āA�܂����{�̃M���������x��������ɏ㏸���āA�N�X�W���p���I�[�v���̃^�C�g���͓���Ȃ��Ă���킯�ł��B����ɑ��ɂ��傫�ȃ^�C�g�����������ł��܂����B���̃g�[�i�����g�ɏo�āA���̗D����ڕW�ɂ���̂��Ƃ������Ƃ��A������e�l�̈ӎv�̒��ɂ���܂��B���̎��ɂƂ��ẮA���X�x�K�X�̃^�C�g�������A�����̃W���p���I�[�v���̃^�C�g���̕��ɁA�����ƈӖ�������B���x�������F�Ȃ��B
�@�������Ă��̃^�C�g���͋��ł͂Ȃ������̂ł��B�ł���Ȃ疈�N���������Ƃ��v���B�ł����̂X�X�N�ȍ~�́A�[���ł���g�[�i�����g�̐��т͂���܂���B�X�[�p�[JP�̍ŏ�J�b�v�ł́A������ŕ����ĂQ�ʁB�������������ʐ��������ŕ����ĂQ�ʁB�Q�ʂ͒ʏ��_�������m��܂��A����Ȃ��ƂŊ��ł���̂͑f�l�ŁA�g�[�i�����g�͍Ō�܂ł����Ə����Ȃ��Ă͈Ӗ����Ȃ��B�������Q�ʂł��܋��͂���̂ł����B
�@�l���W�܂��Ă����ŃQ�[�����J�Â����B�����Q�[���Ƃ������t�����邵�A�ܗւȂǂ͖��炩�ɃI�����s�b�N�Q�[���Ɖp��ł͂����܂��B���̃Q�[���A�܂�C�x���g�̍\���Ɗy���ݕ����w�͖̂��炩�ɃM����������ŁA�����ɂ͂��̎Q�l�ɂȂ�ׂ��C�x���g�́A�c�O�Ȃ���ǂ��ɂ����݂��܂���ł����B���ł������ł��B����͎̂������̒c�̂̃M�������t�F�X�e�B�o�������B����������������Ă�ꂽ���̂U�N�Ԃ��Ǝv���Ă���킯�ł��B
�Q�O�O�O�N
�@���R�͕s���������̂����A���̔N�̂U���ɖk�C���̔��l�ɉƂ̉�����Ɠ�l�ŎU���ɏo�������̂ł���B����Ȃ��Ƃ���̂́A�U�N�Ԃ̋�������ňȗ��B
�@������ɂƂ��Ă̖k�C���Ƃ����̂́A���������낤�ƍ��ɂȂ��Ďv���B�q�����������������̊G�{�ŁA��������ƒj�̎q�̖��K���s�݂����Ȃ��̂��������B�k�C���̃T���x�c���삪�e�[�}�ŁA�e�q�ł����̋��t�����ɐQ�܂Ŕ��܂��ĎU�����s���Ă����̂��B�G�{�͎q���ɂƂ��Ă͖��m�̒n�ւ̃��}���B���[�ɂƂ��Ă������������̂��낤���B�ǂ����T���x�c����Ƃ����Ă��A���قnj��n�͗���ɖ����Ă���Ƃ͎v���Ȃ��̂����B
�@���H�̍���������A�{���ʐ^�ŁA���R�Ƃ���������������������Ȃ��B���̍��A�q�������Z���ɂȂ��āA�Ȃ͏T������Ԃ����A�Ƃ��Ă����܂�Ȃ��Ǝv���n�߂��̂�������Ȃ��B������ɂ��Ă��A�k�C���炵���Ƃ����ꏊ�̔��l�ɂU���ɂ������B
�@��������ɂ͂����Ƃ����U�������邼�ƁA�U�N�̋������Ă��A���̓A�E�g�h�A�̐��_�͖Y��Ȃ��B���������n�͂ǂ��ł����H�k�C���ȂǁA�k���ŗ��s���Ă���l�͊F���Ȃ̂ł��B���l�͐̂̃X�J�C���C����CM�ŗL���ȃP�������̃|�v���̖ƁA���l�̋u�B���ꂪ���蕨�Ȃ̂ł��B�ł��U������ꏊ�Ƃ����̂́A�����ǂ��ł��������ƂȂ̂ł��B�i�D�悭�����A�����ɓ�����������B�m���ɂ������N�́A����߂������U�����Ă������Ƃ͂���܂����B�ł����ꂪ�u���N�̂��߁v�Ƃ������R�ɂȂ�ƁA�R�����܂�Ȃ��B�������𐔉�����ƁA�����C���ɂȂ�B�U���ł����ꎩ�̂��y�����Ȃ���ƂȂ�ƁA�R�ɍs�����������|���āA�����Ƃ����I�Ԃ悤�ɂȂ�B�ł�������ł���B����𗷍s���ƍl����B���s�͉����������Ղ���邾�����y���݂ł��Ȃ��B�U�����Ă�������������Ƃ��ړI�ɂȂ��Ă������B����Ȃӂ��Ɏv���悤�ɂȂ����̂ł��B
�@������[���܂łU���Ԃ��炢�����ƁA�Q�T�L������R�O�L���߂�������B���ꂾ���̃p���[������Ȃ�A���̎R�ɍs���Ȃ������̂��Ƃ�����A��������̗��R�����邯��ǁA�R�����̃g�C�����L���ĉ������ƂƁA�R�ɂ͒������Ċ��L�����Ƃł����B����ɉ��E�̎U���́A���ł��D���ȂƂ��ɃR�[�������߂�B�����A���Ղȍl���ł��˂��B
�@�U���̔��l�ɂ́A�Ȃ��C�w���s�������܂�����B�����^�����]�Ԏ�āA�W�c�ł��������̓������Ă���̂ł��B���ܑ͕�����Ă��Ă��A�k�C���̓c�ɂƂ����̂́A�Ԃ͂��܂葖��܂���B����ɖq��Ƃ������A�����̒��ɓ������邾���B�����̑�^�@�B���������Ă��āA�����傫�ȃ��[���[�^�Ɋۂ߂Ă��āA����͓~�̊Ԃ̉ƒ{�̊����ɂ����ł��傤�ˁB�����n�̃T���u���b�h�̐H����������Ȃ��B�ł��������k�C���ɂ͉����āA�������������ł��˂��B�Ȃ͕x�ǖ�̃��x���_�[�������������Ƃ����܂����A�����܂ŕ����ɂ͉����āA�����ȃ_���Ƃ��̎��ӂ̔��l�̋u�B�P�������̃|�v���B����ɓs��ƈ���Ď��̋@�����Ȃ��āA�ȂA�������܂����ˁB���ԂȂ̂ɐl���S�R���Ȃ��ꏊ�������āA�������A�k���̉Ă̐^�钆�݂����Ȋ����������������ˁB�������h�����A���̓����߂��Ă����y���V�����ł����B
�@���������A���ˉ���̂�������́A���܂ł����C�������̂ł��傤�B�����đS������B�����V���������U���̃u�[���ɏ悶�āA�ɔ\���h�̓��{�n�}��������Ȃ�āA�C�x���g�����̂��A���̃~���j�A���̔N�ł������B����̌��N�u�[�����N�Ƃ����Ă������B��������̒��ԓ���ł���A���ԂƂ��āB
�Q�O�O�P�N
�@�䂪�ƎU���u�[���Q�N�ځB
�@JR���U���̃u�[���ɏ悶�ăC�x���g��悵�܂����B���C���h��̊J�{�S�O�O�N���Ƃ��ŁA���C�������l��JR�V�����̂R�����L�b�v���������̂ł��B�������ē��C���̖����n�̏Љ���n�߂܂����B�������s�Ԃ̂T�O�O�L���̒��łP�O��ԁB�P��Ԃ��P���s���Ƃ������Ƃ́A�S���łP�O���s���B�T��������p����A�Q�s�����j�ł���ƁA�v��͔N�ԂłT��T���B�t�悩����s���܂����B������̕������C�������̂ł��B
�@�t�ɏ��c�����甠���z���B�����ɎO������|��B�����̐�Ƃ����G���A�L�d�̂T�R���ɂ���܂����A����͖���ł��B���̊����ցB
�@�H�ɂȂ��āA�F�Ãm�J���z������A�����͗鎭�̓��܂ŁA�ւ�T�R�B����̉J�������āA����ւ��B�É��̓�����B�����̏���̒��R�B�v���o���ΐ肪�Ȃ��B������Ɖ����ɂ���āA���c�̑���̖ؑ����̖H�����̓M�l�X�ɂ�����Ă��܂��B
�@�v��ʂ�A�P�O���ԓ��C���ʼn߂������̂ł�����A�Q�T�O�L�����炢�����܂������B���悻���C���̔��������A�߂ڂ������͊F�����܂����B�ł�����A�����悤�Ȃ��Ƃ��Ă���l������������̂ł��B�^�_�̎U������̂ɁA�Ȃ�ŐV�����ɏ��̂��ƁB�R�o�邾���Ŗk�C���ɂ��x�R�ɂ��s�����炢�ł�����A�����ɖ��É��ɂ����Ă��������낤�ƁB
�@�S���ɂ́A�L���܂ł����̂ł��B�{�B�l���̂��܂Ȃ݊C���������ƁB�����V�O�L���B����ԁB�����̖��h�݂����ȂƂ���ɏh�����܂����B
�@���˓��͊C�ɂ��Ă����̂����������Ȃ��悤�ȏꏊ�ł��B�������͊C�ꂪ�ł��ԛ���ł����B���l�ɂȂ�܂���B�ׂ��C���Ƀ^���J�[������B���n�̒��̉^�݂͂����Ɍ�����B�C���}���ɐ[���Ȃ��Ă���B���悻�P�O�̓��������āA���������Q�̍����B����ڂɂ͓k���ɂ͎��Ԃ�����Ȃ��āA�����^�����]�Ԃ��g���Ƃ����C���`�L���܂������ˁB�{�B�l���̋��ŁA������̂͂��������ł����B�r���ɓn���̑D�Ȃ�Ă̂����邵�A�����ȓ��ɂ����Ɛl���Z��ł���̂ł��B�ʔ�������B
�@���C���͕�����Y�ł��ˁB���E��Y�ł��A�����͎��R��Y���ڗ��B�O�����h�L���j�I���ɂ��Ă��B�ł����s�҂̖ڂ��삦�Ă���ƁA������Y�ɒ��ڂ���悤�ɂȂ�B�����ɂ͐l�����̗��j�����邩��ł��B���R�̈�Y�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��B�Ⴂ�q�������Ă��Ƃł��ˁB
�@���̒m���Ő���A�b��̕��c�͗��j�Ɏc��Ɛт͂Ȃ��ƁB�������������̑��̐M���炾���ŁA���{�j�ɂ͕]������Ă��Ȃ��B����͐�ꂪ�����O���������ƂƁA�����̏�̂Ȃ��Ŏ�r���т��ĉ߂����������B����������ߍ������B�̐S�ȂƂ��ɁA�Ƃ����̂͐M���������Ƃ��ɁA�a��������Ȃ��������ƁB�n���b�{�̐l�͓{�������ǁA�ł������B����ɕ��щΎR�͑��q�̃Z���t�ŁA���c���p�N���������B�Ȃ�ŕ��c�H�ɕ��щΎR���ƁB
�@�܂�����Șb�͂����ł��B���N�U���u�[���ɏ悶�āA�y�������Ƃ����������Ƃ�������������̂ł��B
�@�ւ̌Â��h��ł́A���s����̂����吨���āu���s�͂����ό������ă_���B�ւ�T�R���������̂��c���Ă���v�ƁB�����ł����B�]�˂̒����݂P�L���������Ă��܂����B�Ƃ̋ߏ��̑�����ɂ��A�P�O�O�����炢�͎c���Ă���̂ł��B
�@�o�u���u���͂����_���ł���B���҂��W�����W���������āA�x���c�̓����̃����W���ɏ�������āA�����z�e���߂���ȂǁA�j���[���[�N�̃c�C���^���[�����Ă���āA��K�����i���y�������Ȃ�āA���悻�i���ɂ����܂��B�C�X���������������o�u���̏ے��ɒ�R����̂��A��������Ȃ�B�Z�{�q���Y�����ł��ō��̏ꏊ���Ǝv���Ă���y���Ȑl�́A�����Ƃ����Ԃɂ�������ɂȂ�܂��B
�@���������N�Ŗ����A����ɏ�����̂Ȃ��B
�Q�O�O�Q�N
�@�U���̂R�N�ځB�^�Ăɑ咬���牖�̓������܂����B���R���̌y��獲�v�A��������O�̘a�c�܂ŁB
�@�ԂŒʂ�߂��邾���ł́A���܂ł����Ă�������Ȃ����Ƃ��c��B���߂ēr���Ŏ~�܂��āA�P���ԂقǃE���E������Ε����肻���ȂƂ���ł��A���ʉ߂��Ă��܂��B���s�Ƃ͂���Ȃ��̂ł��B
�@�ǂ����Ē��R���́A�]�˂��狞�s�Ɍ����̂ɁA�k�̌Q�n����ڎw���Ă���̂��A�i���ɕ�����܂���ł����B���肩������ցA���C�w�C�V�̊X��������̂ł����A�ǂ����Ă���ȂƂ���ɐ̂̊X��������̂�������Ȃ��B�����ւ́A�]�˂�������X�������邶��Ȃ����B
�@�����Œ��ׂ�Α������ł͗����ł���̂����m��Ȃ����A����͂����Ƃ����ɖY��Ă��܂��B�Y��邭�炢�Ȃ璲�ׂ�K�v���Ȃ��B�ł����Ă݂������߂ɏo�����āA�����ŗ�������ƁA�����i�v�ɖY��Ȃ��B�m���̏d�ςƂ����̂́A�����������@������̂ł��B
�@���m�Ɍ����Ȃ�A���C���Ƃ����̂́A�]�˂���쐼�ɉ��тĂ���̂ł��B���哹�Ƃ����̂́A�]�˂���k���ɁB�����狤�ɓ����p�x�Ő������Ă��邽�߂ɁA���������Ȃ��B���s�Ƃ����̂́A�]�˂̓�ɂ���̂ł͂Ȃ��āA���ɂ������̂ł��B�����Ȃ�قǁB�ł��։z���i���R���j�Ƃ����ĒJ��x�����̂ɁA���ɂ������Ċ��o�͂Ȃ��ł���B����ς�k�����B
�@���v����a�c�ւ́A�k�����x�̑�g���o�[�X���[�g�ł����ˁB�������̒J�Ə����Ȕ���������B�a�c���瓻�z����Ɛz�K�B��������ؑ]��ɉ����Ē��R���ł��ˁB���������ƂȂ��ł����B
�@����Ƌ��s��������ւ����ɂ́A�]�˂ɏo��K�v�͂���܂���B���R���̍���h���炻�̂܂ܓ����֏o����B�]�ˌo�R�͑��肾�����̂ł��B
�@���N���Ȃ���A���j�ώ@�ł����ˁB�������ĎU���R�N�͏I�����āA�N���C�~���O�ɃJ���o�b�N���܂����B
�������A���̑��k�@
�i���̌��e�́A�Q�O�O�R�D�U�D�Q�Q�Ɏ������̖k�ҒJ�̐�k���[�g����o�������Ƃ��̂��̂ł��B���͂Q�O�O�R�D�U�����̎G���u�x�l�v�ɁA�R�X�L�[�̐�m�q�J�̋I�s�����̗p����āA����ŋC���悭���Ă��̎R�s���Ăщ��債���̂ł����A�ǂ������I���Ă��܂����悤�ł��B����ŕ������܂���ɁA�����Ɍf�ڂ��܂��B������x�X�g�N���C�~���O�ł����B�I�s�̉���́A�����Ƃ̕��ڂ͔����Ă��������Ƃ���܂������A����͎�����HP�Ɍ��J���邱�Ƃ��܂�ł���̂��Ǝv�����킯�ŁA�ł����ƂȂ��Ă͂�������J�̈Ӗ����Ȃ��ł��傤�Ƃ������Ƃł��B�R�s�̃y�[�W�Ƃ͎���̂�����Ă��܂����A�܂��C�y��HP�ɕ���̂ƁA�^�ʖڂɋI�s���Ƃ��ĉ��債�����Ƃ̈Ⴂ�ł��傤�B
�@���͊x�l�̂��̉���Ƃ����̂́A���̍��Z����̉��t�����N����Ă������ƂȂ̂ł��B�܂����e�}�j�A�ɂȂ�̂ł��傤���B����ł��܂������ł��C�ɓ������R�s���ł�����m�q�J�ʼn��債�č̗p����āA�ĂтƂ����o�߂ł����B�ǂ����A�Ƒ��Ƃ��q���Ƃ����o�ꂷ��ƁA���̉���ɂ͍̗p����₷���悤�ł��B
�@�������ɒ��N�������Ă����̂́A�S�������ɏ����Ă���Ƃ���ł��B����ɂ��̎R�s�̐����ŁA�܂�����ɐ�̃��[�g���D���ɂȂ��Ă��܂����B�ʐ^�́A�y�[�W�ɂ�����̂��Q�Ƃ��Ă��������B�Ȃ����[���ŘA����������G�N�X�g���[�}�[�́A������̑��삳��ł����B���肪�Ƃ��B�j

�i�S���W���̌������Ɏ������Ő��B���[�����A�E�[���k��B�ݔ����͂����܂ŗ��Ă��Ȃ���w�������j
�@�W���Q�S�O�O���[�g�����߂����Ƃ����̂ɁA�ړI�n�ɂ͂Ȃ��Ȃ��H����Ȃ��B�}�ΖʂƏ�����������ɁA�����r���B�C���肪�}���B�������͎��O�̖�j���āA�㕔��҂��E���ɓ����Ă����B����ňꕔ�����Ƃ��낪���������A������ۂǂ��������Œʉ߂ł����B���Ă͓~�̖k���ł��A�T���̌��ł��A�}�Ȑ�k�͂�����ł��o�����Ă������A�܂����I���_�ԋ߂ŊԈႢ�Ȃǂ����Ă����ȂƁA�v���B�Ζʂ���g�𗣂��A�A�C�[���͐����ɕۂāE�E�E�B���x�������������Ȃ���A�l�̓p�[�g�i�[�̃g���[�X���O��Ȃ��悤�ɁA�ĂёO�܂��R�肱��ł�����蒅���Ă����̂������B���̌��̃��[�g����A�ǂ����Ă��������ɗ����Ă݂��������B
�@���N�͋��R�ɂ��X�L�[�̊y������m���āA���Ԃ��������B���̂S���ɂ́A���������w�R�s�݂����Ȃ��Ƃ������B�܂��Ⴊ�P���[�g�����c���Ă����J������ѓ��ɃX�L�[�����点��B�t�X�L�[�̃p�[�e�B���O�シ��B�P���Ԃ�����Ət�̓��������ڂ́A���̐����o���ɒ����B����F�̑����̂悤���B����ɂ���������Ƃ����~���o���āA�k�Җ{�J�ɓ����Ă݂�B����������������������̉����B�W���͂P�T�O�O���[�g���Ȃ̂ɁA�����͗��h�Ȃt���k�J�B�Ⴊ�Z����܂������y�����͌��������Ă���B����������ƕX�͊��̖k�ҒJ�́A�������䍂�����A���x���������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
�������O�i�ł���̂͂����܂łŁA�꒼���ɐL�т��{�J�̐�ɂ́A�g�̖т��悾�قǂ̃S���W���B���������̉�����f�u�������X�Ɣ����Ă���B��X��ɂ�����ꂽ�ܐՂ́A�`�����ނقǐ[���B�{�J�̓˂��グ���́A�����ɂ��藧�������ƁA�����悤�Ɉ�_�̓܂���Ȃ��^�����ȃV���[�x�b�g�ɕ����Ă���k��B������ɂ₩�ɂȂ��ݔ����ւƏ����Ă���B�������̔�r�ΏƂ��Ȃ��B
��������@�R�Ŏ���E�E�E�́A�i���_�E�f���B�B
�P���Ԃ����ɂ�������ł��Ă��A�A��ۂɂ͌�딯�������ꂽ�B
���Ζʂ͂R�O�N�O�̂��Ƃ������B
�u���̑o����̌������́A�����x�R������v
�@���Z�P�N�̓~�ɐ�y�����Ɣ����x��o�����Ƃ��A�ږ�̋����ɋ�����ꂽ�B�����̒��Ɍ��������̎R�́A���������s�̂Q���ڂɂ悤�₭���ǂ蒅�����Ԋx����A�܂��܂���̓͂��Ȃ��n�̉ʂĂɂ������B�v���͕�����Ȃ̂ɁA������ɂ͌��邾���̎R�ƂȂ�A�ϐ���ɂ͓������R�ɂȂ��Ă����B
�@�`�����X�͂P�O�N��A�������P�x�����������B�R���ɏc�����悤�Ƃ������Ԃ̃v�����ɉ����āA�Ґ���̂Ȃ����L���b�g��������U�C���������܂܂̑僉�b�Z���̃g���o�[�X���������āA�����O�ɂ悤�₭�ݔ����̐�݂̏�ɂQ�l�p�e���g�邱�Ƃ��ł����B���̓��̈ړ������͂W�O�O���[�g���B�����ɕ����߂�ꂽ��ǂ�����ē�����H�@��������J���ْ�����a�炰���̂��A�n�����ċC���������́A������悤�Ȑ�Ɍb�܂ꂽ�B���̒ɉ��ȎR�s�́A�ȍ~�܂��Ȃ��������ĎR���牓�������������A�����ԈԂ߂Ă��ꂽ�B
<�m���ɂ��̂Ƃ����́A���̐����Ȓݔ����ň��𖾂������̂�>�B
�@�厅���̎ԓ�������A���쓹��L�ȃC���^�[�ō~�肽�Ƃ����A���グ���͂��������Ȃ��B�M�Z�咬�ɏZ��ł���l���A�܂��������B�R�x�����ق̍���̏Z���́A������̌������ɖ����ݔ�����������B�ނ�͓s��l�����T�O�N�͒������ł���͂����B
�@�N��Ƌ��ɁA��ו��̖��c�R�s�͌����ɂȂ����B�����������邾���̎R�ɂȂ������R�́A�Q�ԖڂɈՂ������[�g���Ȃ����Ƃ������B��u�����������������̂悤�Ȃ��́B�������̖�������Ƃ́A�����Ă����l�ɂ͌����Ȃ��B�s����ŏX�Ԃ��N�����ɂ́A���������Ȗ��킢�ɂȂ�B
���̂܂ܒ������Ԃ��߂��Ă��܂��͂��Ȃ̂ɁA�^�C�~���O�悭��Ȓm�点���͂����B�t�X�L�[���Ԃ̃z�[���y�[�W�ɁA�G�N�X�g���[���̃p�[�e�B���k�Җ{�J�����~�����Ƃ����L�^���ڂ�B�U���̂��Ƃ��B�����������������̂́A�o���ɓ����[�g���A�C�[���ŋ삯�オ�����Ƃ����������B���m�炸�̃X�L�[���~�ɂ́A���������Ă��������ޗ��͂Ȃ��B�X�L�[�����ċ���ԘA���܂ł���B���������̒J���o���Ƃ����́A���͂��܂܂ŒN��������������Ƃ͂Ȃ������B�������T�O�{�̓�[�g�ɂ��A����͏Љ��Ă��Ȃ��B
�������[����łB
<�{���Ɉ��S�ɓo�s�ł����̂��B���Ƃ����炻�̃A�C�f�A�Ɋ��S���Ă��܂�>
�@�����ɂ͕Ԏ�������B
<�N�ԂłU�������͈��S���Ƃ����܂��B�o�邾���̓�Փx�������Ȃ�Ղ����B�������㕔�͍����ցB�ő�X�͂S�T�x>

�i�ݔ��������܂����B�ł��܂������āj
�@���̈ꌾ�Ŏ��̓o�R�ς́A�����ꂽ�Ƃ����Ă��傰���ł͂Ȃ������B�Q���T�番�̂P�̒n�`�}�𒎊ዾ�Ō����Ȃ���A���~�̉\���������ł����߂Ă���G�N�X�g���[�}�[�́A���a��������V�O�N�̗��j�œo���Ă��邱�̎R�ɁA���������Ƃ��Ȃ����@�ň��S�ɓo���A���~���Ă����̂��B���E����꒼���ɍŒZ���[�g�ŁA�ŒZ���ԂŁB
�R���܂ł͒N�����t���Ȃ����|�I�Ȑϐ�ƋG�ߕ��̐������܂�B�T���܂ł͒����w�r��������悤�ȃu���b�N�����B�V������͂��������ɐ���k�B�P�O������͂܂��^�����ȗv�ǁB�����U�������́A�㗧�R�̏�����������������V���N�P���ɂȂ��āA�ق�̏��������`�����X��^���Ă����Ƃ����B�������P�O�O�O���[�g���ȏ�ɓn���āA�P�_�̂ق���т��Ȃ��B
�@�������b���B�������o���ɂ̓g�Q������B���₻��ł��������O�Ɏ��H�����l������B�s�ނ��Ă���������A�r���܂ł����Ă݂悤�B�����̔ޏ��́A�R�O�N��ɂǂ������}���Ă����̂��낤���B���N�̃p�[�g�i�[�ɘA�������B�U���ɂ͂܂��R��̏T�����������B
�@�v��͒Z���ԂŖȖ��ɂȂ����B�܂������n�̑��k������킯�ł͂Ȃ��B�����ɒZ���Ԃʼnz���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�̂�т肵�Ă����Ȃ��B��k�̏����̓^�C���g���C�A���̗l���ɂȂ��Ă����B
�@���s�������͂��܂��܉Ď��ɓ�������������B����ł��w�b�h���C�g�ɗ����ďo���B�S���ɂ͌�����̂��������������̃f�u�����A�������肨�ƂȂ����Ռ`���Ȃ��B�͌��ł͂P�O���[�g�����z����d�����炪�p�������Ă����B�ϐ�͎����̐�̉�L�����̂��B�����̂Ȃ��炩�ȌX�̓A�C�[�����v��Ȃ��̂����A���łɐ�k�̓S���W���ɓ����Ă����B�ٗl�Ȍ��i�ɐg�k��������B�������A�_�C���N�g�����Ƃ�����ł������𔗏オ���Ă����B�������z�͂܂������Ă��Ȃ��B��~�J���������Ă��ꂽ�B�O�i�s�\�ɂȂ�������߂悤�B
�@�Ƃ��낪��k�͑f���ɑ����Ă����B��҂͂ǂ����o���Ă��ݔ����ɏo��炵���B�Ȃ�Ή��E���獂��������k��ɂ������B������肾���A�����������Ȃ��悤�ɐT�d�ɁB���x�v���������ݔ����I���̂Q�V�O�O���[�g���ɋ߂Â��Ă���B
�@�c��R�O�O���[�g���́A�̂�肭���Ɖ���Ă��鐅�Ԃ̂悤�ɁA�~�܂邱�ƂȂ��������������R�荞�B�������삯�オ���āA�����݂������Փ��ɋ����B�}�X�͑z���ȏ�̓�G�������B���������グ��A�Ȃ�قǐ�݂̎c�[�͂�����ɒ���o���Ă���B�G�ߕ��̐������܂�́A��ΖʂɌ����B�c�Ⴊ��������ꂾ���댯�����Ȃ��B�����͎��Ԃ̌o�߂Ƌ��ɂ��������Ă��邾�낤�B
�@�I���_�͖k�������B�c���H���L���b�g�����։���n�߂镪��_�������B�k��̑Ί݂͕��n�Ƃ��v����J�N�l���ւƁA�^�t���܂ɐꗎ���Ă����B�����o��K�v�͂Ȃ��B�l��̓X�L�[���[�̔{�̂V���Ԃ��������B��ꂫ����������l�ɁA�o����̋C�i�͈ˑR�Ƃ��ėh�邬�Ȃ������B
�t�^
�����E���P�x�@�P�X�V�P�N�X���P�W�`�P�X��
�@�ʂ��Ă������w�Z�͍�ʑ�w�̋���w���̕t���{�݂������B��O�ł����Ƃ���̎t�͊w�Z�ŋ����{���w���̕t���Z�������킯���B�w�Z�̉^�c�`�Ԃ́A�C�M���X���������ƌp�����Ă���悤�������B���{�̈�w��@���̓h�C�c���炾�������A����̓C�M���X���炾�����̂��낤���B�싅��肠�̓����ł��łɃT�b�J�[�����w���������Ă������A���̃T�b�J�[�S�[�������ɑ傫�������̂́A���O�r�[�̃S�[���T�C�Y�ƌ��˂Ă������߂�������Ȃ������B�����������j������Ƃ����킯�ł��Ȃ��낤���A���n�̓������̊ԂŁA�o�R���u�[���ɂȂ��Ă����B����ɏ��w�Z����ɂ́A�T�ɂP��̃N���u�Ɂu�A���R�E��v�Ƃ����̂��������B��������Ă���N���u���͒m��Ȃ��������A���Ɗԋ߂ɂȂ��Ă���́u��������v���Ƃ������Ƃ����������B�ċx�݂Ȃǂɐ搶�ƒ����̐��ۓ��Ƃ����V�O�O���[�g�����炢�̎R�Ƀn�C�L���O����N���u�������̂ł���B
�@���̔N���͒��w�R�N�������B�t�ɂ������w���Ղ��������̃C�x���g�ɁA��҂̑��q��M�N���A�����Ŏ����Ă����R�k�̃A���p�C���K�C�h���P�O�����w�Z�Ɏ����Ă��āA�W�����Ă����B�u�Ӂ`��A����ȃK�C�h�������āA���낢��ȎR���Љ��Ă���v�ƁB���̓W�����Ԃ����܂�ɂ������āA���͎��i���āA�{�̊����ɂ���ǎ҉���̐ؔ��������ׂĐ����Ă��܂��A������o�ŎЂɑ����āA�G���u�R�k�v�����߂Ď�ɓ��ꂽ���̂������B�ǂ����{�l���C�����Ȃ����낤�ƁB

�܂��Ȃ����P�x�B�ł�������ɉf�肷���Ēp���������B
�@����M�N�𒆐S�ɂ��āA���Ԃ̉��l�����A�t��ɔ��������P�x�ɓo�R�ɂ����Ă����B�u�������͕������ɂȂ�B���k�ꍂ���R���v�Ƃ����킯���B���̂������ɓ��ꂽ�B
�@���̗V�ђ��Ԃ͔ނ�Ƃ͈�����̂����A���͂�����ɂ��R�D�����������̂������B�Ƃ��낪�ނ͐T�d�h�������B�u�F�B���������͓���B���̑O�ɈՂ����R�ɍs���Ă������v�ƁB�t��ɒ������̏�쌴�ɋ߂��P�S�O�O���[�g���قǂ̌����R�ɂR�l�ōs�����ƂɂȂ����B���̏����Ƃ��āA��͂�R�k����o�ł���Ă����u�o�R�ǖ{�v�����߂ēǂB���ɂ��Ă��A�o�R�̓��发�Ƃ��ĂƂĂ��悩�����Ǝv���Ă���B�������R�x��̖^���������Ă����B���͂��̐l�͍��ł��V���Ƀn�C�L���O�R�����������Ă��邱�ƂɍŋߋC�������B�̂ǂ��ȎR�o��ł��邪�A���̊�{���������菑����Ă���{�������B
�@���������ĂR�O�N���O�̓o�R�������������菑��������̂́A��͂肻�̖{�̂������ł�����B���R������L�^����������Ǝc���܂��傤�Ə�����Ă����̂��B����ɃA���o���̐��������ł͂Ȃ��āA������d�Ԃ̃L�b�v�Ƃ��H�ׂ��w�ق̕�ݎ����L�O�ɂȂ�܂���ƁB���͂����^�������߂ɁA���͍~�肽��쌴�̉w�ŁA�L�b�v�Ɂu�����v�̃X�^���v�������Ă��炤�̂ɐ�����Ԏ���Ă��܂������̂��B���₤���o�X�ɏ��x�ꂻ���ɂȂ����̂��B���̌㍂�Z����ɂ́A�ʂ̎R�s�ł���Ȃ��Ƃ����Ă���ԂɁA�{���Ƀo�X���o�����Ă��܂������Ƃ�����A�d���Ȃ��������킹�̋������Ȃ��̂Ƀ^�N�V�[�ɏ��A����ɖ��f�������Ă��܂������Ƃ�����B�ȍ~�́A������d�Ԃ̃L�b�v��ۑ����Ă������Ƃ͂�߂��B�������܂��A���̖{�̋����𐔔N�͎���Ă������߂ɁA���̍��̊ȒP�ȃA���o���͂P�������c���Ă���̂��B�P�O�N�Ԃ肭�炢�ɂ�����J���Ă݂�B
�@���̌����R�����̐l���̏��o�R�ɂȂ����Ƃ����Ă����B�������w�T�N���̉Ă̗ъԊw�Z�ŁA�ߐ{�̒��P�x�Ɋw�N�S���œo�������Ƃ͂������B�������A���ɂȂ�Ƃ��̓o�R�̈�ۂ��ƂĂ��悩��������Ȃ̂��Ȃ��Ƃ��A�v���Ă���B�n�C�L���O���w�Z�̎w�����j�������̂��B
�@�����Ē��R�̉ċx�݂��}�����B�T�b�J�[���̘A�����l�Ƃ��̌ږ₪�A�x�ݒ��ɉ��������T���ŏc������Ƃ�������Ȍv��𗧂ĂĂ���悤�������B���̓e�j�X������Ă����B���̘A���́A��̂T���ɔ����ɂ��������S�����o�[�̂悤�ł�����B����ɂ��̌ږ�Ƃ����̂́A���͒��Q�̂Ƃ��̎��̃N���X�̒S�C�ł��������B�m��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���͂��̎R�s�ɎQ�������������B�������̑S�R�Ƃ����̂́A�_��x�������R�̂��Ƃł���B�E���獶�֑S�������Ƃ����̂��B���̂��������������B���������̂��Q���͒f��ꂽ�B�ǂ������o�߂��������A�����o�[�ɎQ����\������ŁA�����搶�ɓ`�B���Ă��炤�Ƃ������Ƃ������̂��B���ǃN���X���Ⴄ���炩�A�T�b�J�[������Ȃ����炩�̗��R�ŁA������Ȃ������B���������A���R�̏t�̉������A���̉_��R�ɒʂ��閶������Ƃ����P�S�O�O���[�g���ӂ�̕Г��P���Ԃ��炢�̃n�C�L���O�������B�T�b�J�[�A���O�r�[�A�n�C�L���O�͂�͂�C�M���X�ƃt�����X���琢�E�ɕ��y�����B
�@���̕s���̈ꌏ�͎��Ɏ����ԕs�����ɂ��Ă����B���̂��߂̑R�S���N���o�Ă����B���ۂ���闝�R�͂ǂ��ɂ��Ȃ��͂��ł���B��̒��S�����o�[�Ƃ����Ă��A���Ă͓����N���X�ɂ��āA�猩�m��B�����炢�̋����̗F�l�����ł���B�ږ₾���ĉߋ��̒S�C�B����Ɏ����^�����ő̗͂����邱�Ƃ��炢�͒m���Ă����B�^����ł͏��w�Z���炯�������������т��c���Ă���B����ɂT���ɂ͗F�l�ƌ����R�ɂ��o�����B���̂Ƃ��Ɍv��ׂ͗̐�R�܂ł̏c�����������A���Ԑ�œr�����牺�R�������̂��������B�����A���̂Ƃ��́A�R�Ŏ��Ԃɒx�ꂽ��Ԃɍ���Ȃ��Ƃ��̏����́A�������Ȃ����Ƃ��ƁA���s�̐T�d�h�ɋ�����ꂽ���̂������B������f���闝�R���Ȃ��B
�@�Q�w�����n�܂��āA��̌����R�̂R�l�̃����o�[�ŁA���x�����ړI�����P�x�ɍs���v�悪��̉������B��͂�v�����͂��̎R�̐�y�Ƃ����Ă��������̐T�d�h�����Ă��B�y�j�̊w�Z���I����Ă��炷���ɂ����B����̑�{������c�܂ł̉^���͂S�V�O�~�B�}�s�����Q�O�O�~�B���̃L�b�v���A���o���Ɏc���Ă���B�قƂ�LjÂ��Ȃ����[���ɁA�o�X�ő吴���ɒ������B�����ɔ��܂�A�H���͂���Ȃ��B�f���܂�Ƃ�����ł���B����ɗ����̒��H������Ȃ��B�Ȃɂ���o�����܂��Â����Ԃ������悤�Ɏv�����B�ނ̗��Ă��v�����́A���ɐ��m�Ō��������̂������B
�@���n�}�����Ȃ���A�O�����A���������A���̒���ׂɂ���A�{����������Ĉ����A����̃i�e�b�E�B�����������O�ł���B
�@�m���t��̍��ɂ́A��̒��S�����o�[�̈�l�Ɂu�ŏ��̓R�[�X�^�C���̂Q�{�̎��Ԃ�����v�Ƃ��u�Ō`�R���������Ă����ƁA���[�������H���邼�v�Ƃ��A�h�o�C�X���Ă����B�R�[�X�^�C���̌��͂���قǂł��Ȃ��ɂ��Ă��A�Ō`�R���͎����Ă����B�K�X�R�����͒��w���ł͂܂������Ȃ����������B
�@����������{�w�ɂ͉w�r�������̍��ɂ͂ł��Ă��āAOSB�u��{�E�X�e�[�V�����E�r���v�Ƃ��������B���̏�K�ɃX�|�[�c�X�������āA�n�C�L���O�p�i�������Ă����B�����Ƀz�G�[�u�Y�̏��^������ł��āA�T�O�O�O�~�قǂ����̂��낤���B�ƂĂ��~���������̂����A������l�ɂȂ����̂́A�R�N��ɂȂ����B���ł̓K�\�����R�������g���Ă���l�͂܂��������Ȃ��B
�@�吴���������P�x���P���ʼn�������̂�����A���ł���ςȃR�[�X�ɂȂ�B�R�l�ŖفX�ƕ������B�ʐ^������ƎO�������z���Ĕ������ɏo���Ƃ���ł��܂����Â��̂��B�����̂S�����ɂ͏o�������̂��낤���B�R�����ɔ��܂����̂����̂Ƃ������߂Ăł�����B�u�o��̎��ɂ́A����͌�ɑg��ł���̂�������v�ƁA�T�d�h�̔ނ������B�u���`�����āA��͂�ŃO�C�O�C�o�������������v�ƁA���Ƃ�����l�̑��_�B

�����̒��������B�������ĕς���ĐV�����Ȃ��Ă���ł��傤�B
�@������ԋ߂ɂ��āA�����Ă����Ō`�R���Ń��[���������B������������܂łɂS�O�����炢�͂����������B���R��ɗ�̒��S�����o�[�ɂ��̂��Ƃ������Ɓu������Ō`�R���̓_���Ȃ�v�ƁB�ނ͂��łɃR�����������Ă����悤�������B
�@�����Ē���ɏ���āA��g�ŎĈ����������āA�i�e�b�E�̊₪�S���S�������������R����B����ɗ�������߂�A�O��������̉���ł͎��͂���������ꂽ�B����Ɉ��S���ėV�т����Ȃ����B�F�l�̌��ɂ�����āu��ꂽ��v�B�u�悹��A�d������v�B�Ԃ��X�q�����Ă����̂����u����Ȃ��Ƃ���̂́A�Ԃ��X�q�̌F���Ɓv����ꂽ�B�������ď[�������O�锭�̓��A��R�s�͖����ɏI������B��ꂽ��A�R�ɂ͂������������Ȃ��Ƃ��v�����̂����A��͂葽���̐l�Ɠ����悤�ɁA�����Y���Ƃ܂��o�肽���Ȃ�B

���P�x����Ĉ����ւ̋�g�̉����B
�@���Q���璆�R�ɂ����ẮA�t�A�āA�~�x�݂̂��тɂǂ����ɏo�������B�P���̃T�C�N�����O�Œ����̃��[�X�z�X�e���ɂQ�l�Ŕ��܂�ɍs�������Ƃ�����B�o�R�Ƃ͕ʂ̗F�l�ł��������B������P���ɂP�O�O�L�����z��������ŁA�A�蒅�����͖̂�ɂȂ��Ă����B���̌�A�Q���ŕx�m�̐��ƁA�����̂�������[�X�z�X�e���ɔ��܂��ăT�C�N�����O�B����͂��̂R�l�g�v���X�P�l�̂S�l�g�݂������B�h����ŏo������A����͏��q�w���̃O���[�v���Ǝv�����u���w�����烆�[�X���p����Ȃ�āA���ꂩ��܂��܂��������s���ł����˂��v�ƑA�܂�����ꂽ�B���̈Ӗ��͂悭������Ȃ��������B�~�ɂ́A�����x�̘[�̏����ɃX�P�[�g�ɂQ�l�ł������B�V�h���璆�����ŏ�����ɏo�āA���C���ɏ��p���B�A��ɂ͂��̂܂����܂ł����āA���x�͐M�z���ŋA���Ă���B�����̕ӂ肩�猩���������x�́A������Đ^�����łƂĂ��傫�������B���̑傫���͍��ł��ڂɏĂ����Ă���̂����A��ɓ��������Ŕ����x�����Ă��A���̑傫���ɂ͉f��Ȃ��B�s�v�c�Ȃ��̂��B
�@�w�ɃX�^���v���u�����悤�ɂȂ����̂��A���̍����炾�����B���������ȃ}�j�A���������ɂ��āA�ނ������̃C�x���g�̎��ɑS���̃X�^���v��W�����Ă����̂��B�������Ƃ��D�y�Ƃ��܂ł������B���ǂ���A�����͂����Ɂu�w�̃X�^���v���~�����v�Ƃ����āA����Ԃ��Ă��炤���@�ŃR���N�g���Ă����Ƃ����̂��B�C�̌��������@�Ȃ̂����A�{���ɒ��w���ł���Ȃ��Ǝ����ōl����ꂽ�̂��ƍ��ɂȂ�Ǝv���B����Ⴆ������ꂽ�Ƃ��Ă��A���s����Ƃ����̂�����A�ނ��}�j�A�Ƃ������B���������A�����̓A�}�`���A���������s���Ă��āA������Ƌ��������Ă��̋@�B��e�ɔ����Ă�������̂��낤�A�w���ՂȂǂł͂�����I���Ă����B�����A���͏��w�Z�̂S�N�̍��ɂ��łɃn���Ƌ��������Ă����B�u�q���̉Ȋw�v�ȂǂƂ����G���̈��ǎ҂����������B�萻�̃Q���}�j�E�����W�I�����Ƃ����āA�H�t���ɕ��i���ɍs���Ă���F�l�������B
�@���̃X�^���v�R���N�^�[�����Ƃ��̂Ƃ��̗F�l�͐^���āA�Y�a���珬����`���C���`�����`�Y�a�̂P���R�[�X�̑S���̉w�̃X�^���v���W�߂Ă��܂��Ǝv�����B
�@�����ł͗L���ȐV�h���Q�R�E�T�T���̋q�Ԃɏ��B�ǂ̉w�ɂ����������Q���͒�Ԃ���B���̎��Ԃʼn��D���܂ő����ăX�^���v�������āA�܂��߂��Ă���B�u�L�~�����A��Ԃɏ��́H�v�Ƃ����ɉw���Ɍ�����B�u���܂��v�Ƃ����āA�삯�߂�B�ǂ����h�A�̂Ȃ��q�ԂȂǁA����o�������Ĕ�я���Ƃ�����͎v���Ă���B����Ƀz�[���ɋ삯����鎞�����āA�܂���Ԃ���Ԃ��Ă��Ȃ��̂ɔ�э~��Ă���̂��B�N��������Ȃ��Ƃ����Ă��邩��A���w��������^�����Ă���낤����ǁB
�@�����ł̓X�P�[�g��������B�Q���Ԃ��炢�������낤���B���ꂾ�����ċA���Ă���B���̗��s�́A��s���A��Ƃ�����������B
�@���ł��V�т����Ƃ������w���ɂƂ��āA�o�R�͂P�W�������ɉ߂��Ȃ������̂��낤�B�ł���͂�A�����̗V�т̒��ł����̒��S�ɓo�R�͂������悤�Ɏv����B
�@�T�C�N�����O�͍��Z�R�N�̂Ƃ��Ɍ��t�Ƌ�������Ă���́A���Ȃ��Ȃ����B���t�ŏ����s�ɂȂ�B��e�j�X�͍��Z�ŎR�x���ɓ����Ď��߂��B�d�ԏ��͌��t����N���}�ɕς���āA���炩�ɏ��Ȃ��B�o�R�����́A��U�x�~�̌�ɂ܂��߂����B����͂ǂ̎�Ɏ����������Ă���̂��Ƃ������Ƃ��Ƃ͎v�����A�������A��̐��̂͂�͂�ǂ����Ń}���l�������ĖO����B
�@���E�̐l�́u�R����������ǁA���͊C���D���v�Ƃ悭�����B����Ȃ��̓�������M���Ă͂��Ȃ��������A���̌㑽���̒m�������ł́u�R�͉Ȋw�ƌ|�p����B�n���w�A�V�̊w�A�A���w�B�G��`���l�����邵�A���w�ɂ����ĂȂ�B���j��������ł�����B����ɔ�ׂĊC�͂ȂH�@����ɊC���D���Ȃ̂ł͂Ȃ��āA���l���D���Ȃ����ł���B�O�m�ɏo�����Ƃ���܂����H�����m�̐^�ɂ͉����Ȃ��Ď₵����������v�ƁB�������A����܂ŒN���ɕ���������ł���B�u�t�����X����͂��ׂĂ̌|�p�ƉȊw�𐢊E�ɕ��y�������B�����t�����X���畁�y���Ȃ��������̂����E�ɓ���������āA����̓��b�N�~���[�W�b�N�ƃT�[�t�B���v�B����́A�n���̕������̃��[���b�p�҂ɏ����Ă��������̂��Ǝv�����A�܂��ɂ��̒ʂ�B�܂�t�����X�ȊO�̂��̂Ƃ����̂́A�y���Ō������������̂Ȃ̂��B�T�[�t�@�[�A�����܂��ɂ����B�u�V���E�g�ƎR�̂��Ƃ�b���̂͂���ɂȂ�v�Ƃ������̂́A�S���Ȃ����������p���������A��������̒ʂ�B
�@���������ł͂���ȍd�����Ƃ͂�������Ȃ����A�m���ɂ���Ȃ��Ǝv���Ă����̂́A���w�Ɏn�܂荂�Z����Ɉ�����̂��Ǝv����B
�@�������R�̎R�s�͔����łȂ��Ă��ǂ��ł��悩�����̂��B�ł��F�l�R�l�ł�����Ƃ����ړI��B���ł������Ƃ��A���̌�Ɍq�����Ă����B
�@��N�A��̃T�b�J�[���̌ږ�ɓ�����ŏo������B���͕ʂɗ��ł��Ȃ������̂����A������������n�ł��̐搶�ɂ͌����Ă������̂������B�Ƃ������Ƃ́A�����D���Ȑ搶�ł͂Ȃ������B�ł��R�O�N���ĂΉ��߂Ă����������Ƃ͕�����B�u�Ȃ�ŁA�A��čs���Ă���Ȃ������̂��H�v�B�搶�����̂������͖Y��Ă��Ȃ������B�u����̓T�b�J�[���̗��s�݂����Ȉ����ŁA���ɂ��ӔC�����邩��A���������Ɍ��������̂���������˂��v�Ƃ����B���̊���ɂ́A�R�s�̎ʐ^�����͓���������ꂽ���̂������B�����������B
�u���ꂪ�g���E�}�݂����Ȃ��̂ɂȂ��āA�R���v���b�N�X�Ƃ��Ďc���Ă����v�B�搶�͕Ԏ������Ȃ������B�������搶�͂��̌�o�R�͂��Ă��Ȃ��B��v�����o�[�����߂Ă���B���̂悤�Ȏ҂����ۂ��āA���̑㏞�͑傫���������ƁA�����Ԃ������B�����̐搶�͂Q�V�̂Ƃ��������B
�������̏c���͂��̌�A���Z����ɁA�b���M�x�`����R�͂T���ɂ������̂����A�_��`�b���M�Ԃ͖����ɍs���@��͂Ȃ��B����A���łɂȂ��Ƃ����Ă����B��⓻�͓��{�R�哻�̈�������悤�Ɏv�����A��������ɍs���`�����X���Ȃ��܂c��B�������Ƃ͂����Ȃ����낤�B�R�̐^���ɂ́A�ŋߗL���������J�ʂ��Ă��܂������B����ɗ�̂R�l�g��S�l�g���A���قǂ̓o�R�͂��Ă��Ȃ��B���̍��̋���Ȉ�ۂ����������Ă���̂́A����l�ɂȂ����B
�����x�@�P�X�V�Q�N�P�Q��
�@�ŏ��̓~�R�ɂȂ����B���Z�P�N�̂P�Q���B�P�U�̂Ƃ������A���������˂��B��Z�͒j�Ȃ̂ɃV���N�����j����Ă���ƈ����ȍ�ʌ����̐�z���Z�B�f��ɂ��h���}�ɂ��Ȃ��Ă��܂����炵�����ǁB�ł��݊w���ɂ͐��j��������ȕςȂ��Ƃ��Ă܂���ł�����B
�@���Z���͓~�R�ɂ����Ă͂����Ȃ��Ƃ��A�A�C�[�����g���悤�ȎR�ɂ����Ă͂����Ȃ��Ƃ��A���������̂͌��̋���ψ���Ō��܂��Ă����悤���������A�ł��e�Z�̌ږ�ɕ�������Ă����悤�ɂ��v���B�������́A�ږ₪�R�G�L�X�p�[�g���������߂ɁA�~�ł������x�ɂ������킯���B��s�̊��삩����Z�˂��o�āA�s�ҏ����Ƀx�[�X�B�����͂Q�p�[�e�B�ɕ�����Ď������͕��O�Y������Ԋx�B�A�H�ɂ͈���Ɋx�ɂ������BC�߂�B�����͗����x�ւ����āA������A�H�Ɂu��̏��ڕ�v�B����m���Ă܂����˂��B�����x�Ƃ����̂́A�W����킯�ŁA�Ԋx�A�����x�Ƃ����āA���̕�̏��ڂ����̈�Ȃ�ł���B���̂킩���āA�����炢�܂ł̑僉�b�Z���ŁA���Z���ɂƂ��Ă͖ʔ��������ł��˂��B���т̎R�ʼn��̊댯���Ȃ��������ǁA���ԗ]���āA�ږ₪���������̌������Z���ɂ�点���Ƃ������Ƃł��傤�B�Ⴞ��܂ɂȂ��ĉ��R���܂�����B

�R�x�������O�œ��������X�i�b�v�B�����X�l�B�ʏ�Q�w�N�ō��h�s���ƂP�W�l���炢�ōs���Ă܂����B
�@���Z�̓~�x�݂͂��������P�Q���̂Q�O��������Łu�N���X�}�X���g�v�Ƃ������t�������āA�u���̑O�ɓ��R���悤�v�ƏI�Ǝ��̂��̓����������炢�ɂ͓����čs���܂����ˁB
�@���̂Ƃ��P�N�̎��͋C�یW�ł����ˁB�ߌ�U�����炢�̋C�ےʕ������ł���B�ł�����A�Ȃ����w���̗��Ȃ̎��Ԃɂ����K�����L���������āA����Ȃ���ł��ˁB�ł���������̂U���̒ʕ���Y��āu����̐}���E�ɂR�Z���`���炢�������Ă���������v�Ɛ��k���m�̉�b��ׂ̃e���g�̌ږ�ɕ�����āA����ɂȂ��ăo���o���������Ƃ�������܂����ˁB�ŋ߂͋C�ۗ\��m�̎���ɂȂ����炵�����ǁA�C�ۂ̊�{�͂���Ȃɓ���Ȃ��Ǝv���܂��ˁB��b�m���͒��w�A���Z�ŏK���܂���B�ł����̃A���_�X���Ȃǂ͂܂��O��܂���A���m�ɂȂ�܂����B
�@�s�ҏ����̃e���g��ɂ́A�Ⴊ����܂肠�����L��������܂��B�Ԋx�z��̕��ɂ����ƁA������Ɠo������Ɋ����̂悤�ȉ��肪�����āA���ꂪ�ʔ����ĉ��x���������悤�ȋL��������܂��ˁB����������A�u�o��̃X�e�b�v��ׂ��ȁv�ƁA��������ӂ��ꂽ�̂��Ȃ��B�܂��������̒ʂ�ł����ǂˁB�����̃R�����͓����̃X�x�A�ł������A���n�����Đ������̂��ʔ��������ł���B�R�b�t�F���ɂ��������������Ă���̂ł͂Ȃ��āA�傫�ȃS�~�̃r�j�[���܂݂����̂ɁA�����������Ă��Ă�����e���g�e�ɒu���Ă����A���������O�ɏo�����Ȃ��Ă������ƁB����������I�ł����B�����������������Ƃ��A�������Ă��Ȃ��A���͂��̌ソ������A���ł��������܂����ǂ˂��B�e���g�̊O�ɂł�Ƃ��ɂ́A�I�[�o�[�V���[�Y�����Ă܂����˂��̂Ƃ��́B��ɑ����i�H�ьC���j�ɐi�����܂������B
�@�Ԋx�̓o��ł͐��Ⴉ��܂����B�ዾ�ɐႪ�t���āA����������͂ǂ���������̂��ƁB�����x�̓��͉����������̂��Ȃ��B���������������̂͂��̓��������Ǝv���܂��ˁB�A�C�[�������鎞�ɁA��ɍ������낷�Ȃƌږ�ɂ���ꂽ�̂��A���̍ŏ��ɃA�C�[�����g�������̂Ƃ����������H�@����͐�����ł���B�Ƃɂ����ϐ���Ɍ��炸�A�}�Ζʂ̏���ɔw����������Ƃ����̂́A�V���E�g����邱�Ƃ��ˁA���ł������������邯�ǁB��Ɋ�o����悤�ɂȂ��āA��m�q�ȂǂŁA����ɗ�������Ƃ���ł����C�Ō������ċx��ł���̂����邯�ǁA�܂������ꃉ�N�̒����܂��˂��B�A�C�[���͗������܂܁A�Ζʂ̏�̕��ɑ̂��������܂܁A�ΖʂɃA�C�[���u���āA�����ɌC�������悤�ɂƁB���ł�����v���o���܂��˂��B�R�ł͗p�S�[���ɉz�������Ƃ͂Ȃ��B
�@�Ƃɂ����~�R�Ƃ��������A�ϐ���̃L�����v�݂����ł�����B���������o�R�́A���Z���Ƃ��ċ���̈�тƂ��ĂƂĂ������Ǝv�����A�̌����������ƂĂ������v���o�ɂȂ����ˁB�a�C�\�X�Ƃ����y�����R���̍��h���������ǁA���������o���Ƃ����̂́A���̌�͂Ȃ��˂��A�Ȃ������R�������Ȃ��Ă��܂������B
�R�����E���u�R��E�䐳�̎R�@�P�X�V�S�N�Q��
�u�݂��傤��������v�ƓǂށB�W���P�U�W�QM�B�Ŋ��͕x�m�}�s�̒J�����w�B���Z�݊w���̌l�R�s�ŁA�ł���ۂɎc���Ă�����̂��B�����͐_�ސ�̋��{����R���ɔ����铹�u�����̓����ܑ�����Ă��Ȃ��āA�͌��܂ł����J�ʂ��Ă��Ȃ����������ԓ��̗��X���ƏЉ��Ă����B���t�ʼn��x���ʂ������ł�����A���̂��ƃN���}�̖Ƌ����Ƃ�����ɁA���x���ʂ������̂������B�R���s�������ʂ��ĉ������֔����铹���A�������̗����X���ƂȂ��Ă��āA������������ɖʔ��������B���ł͂ǂ�������h�Ȋό��X���ɕϐg���Ă���B�䐳�̂́A���̓��u��ɉ����Ă���B
�@���͍��Z�̑��ƕ��W�ɂ��̌䐳�̂̋L�^���������B���ꂭ�炢���M�Ɉ�ꂽ�R�s�������̂��낤�B
�@���Z�Q�N�̓~�ɁA�����ł��Q��Ⴊ�~������̓y�j�̖�ɂ����ɏo�������B�����R�x���̃����o�[�ɁA�k�����x�ŃX�L�[�����悤�ƗU��ꂽ�̂����A�ǂ������ԂƂ̂�����炯�R�s�ɋC���i�܂Ȃ��āA��l�ł��̎R�ɓo�����B���ł͓s���s�ƌ������A�����͒J�����������B�w���~�肽�̂��[���B�P���ԂقǕ����āA�ѓ��̓K���ȂƂ��납������Ɏ��t�����B�o�R�����悭������Ȃ������̂ł���B���̂܂܉����d����_���ēo��B���҂��Ă����悤�ɁA�ϐ�͕G���炢����B�g���[�X���Ȃ��B������l�ōs���ϐ���̃g���[�X�����̓o�R�Ƃ��ẮA�܂��ɓK���ŁA���������E�ɋ߂����̂Ƃ����\���͌����ɓI�����Ă��Ċ����������B��������Ԃ������Ă����Ƃ����J���V�J�R�s�B
�@�钆�̂O�������낤�A�R���ɒ������B�x�e�̎��ɂ͉����d���������Ƃ������Ƃ��A���C�ɂ�����Ă����B�d�r�̏��Ղ�h�����߂ł���B���Z���Ȃ̂ɓ������牌���������Ă��āA���̉����̉̂킸���Ȗ������r���v�ɋ߂Â��āA���������x�����Ă������Ƃ��v���o���B�u���̏o�͌ߑO�U����������A��U���Ԃ��v�Ƃ��B�^�钆�Ƃ����Ă��A�~�͐ᖾ��ł�������Ɩ��邢���̂��B�܂������̈Í��ɂȂ��Ă��܂��킯�ł͂Ȃ��B�����������Ƃ��A�₵���̂�����ǂȂ�ƂȂ��I�V�����Ȋ����Ɏv�����B
�@�����}���Ă�����c���͑����B�Ő��`���̐Ί��R��ڎw���Ă���B���X�Ăɂ͓�������Ƃ��낾����A�ԕz�Ƃ�������B�ԈႦ�邱�Ƃ͂����Ȃ��������B�Ί��R�ɓo������̂͒��߂��ɂȂ��Ă������B�x�m�R���������ǂ�������B�������̍��ɂȂ�ƁA���̓��̗[���܂łɉ��R�ł��邩�ǂ������S�z�ɂȂ�B�G�܂ł̃��b�Z���Ƃ����̂́A����قǂ͂��ǂ�킯�ł��Ȃ��āA����������ꂽ�B�x��ł���ƁA���ڂ̍��p�ŁA�����Ƃ���̖̊����l�̌`�Ɍ�������A�������Ö������̉����Ɍ�������B����Ȃ��Ƃ����x���J��Ԃ��Ă���Ƃ��������Ɋ���Ă��āA��������̂�M�p���Ȃ��Ȃ��Ă����B�V�c���Y�̏����̉��������Y�̍Ŋ��ł��A����Ȍ��e�̂��Ƃ��菑����Ă����B���������v�����݂��������B
�@�Ί��R�̒���Ŕ������ԈႦ�āA��U������������o��Ԃ��Ƃ������X�������̂����A����ł������ɕ���ӂ�ɉ��R�ł����Ǝv���̂��B�o�X�ɏ���ĕx�m�g�c�Ɍ������A��������A�蒅���B�Q�O���Ԉȏ�̓o�R�ɂȂ����B
�@�������������L���Ȃ̂����A����ł��Ȃ��y�����R�s�������B���R���đ������������₯�ɂȂ��Ă����B
��A���v�X�S�R�i���x�`�b���P�x�j�U���c���@�P�X�V�U�N�X��
�@���܂ł��悭�o���Ă���B���傤�ǂQ�O�̒a�������}���鍠�ɁA�P�T�Ԋ|���ē�A���v�X�����x����b���P�x�܂őS�R�c�������̂��B
�@���Z�̎R�x���̂R�N�Ԃ̉ĎR���h�͂��ׂē�A���v�X�������B�u��A�́A�k�A���v�X���R���傫���v�Ƃ͂悭����ꂽ�B�R�O�O�O���[�g����̐����A�����k�A���������B����ɁA���̂R�O�O�O���[�g���A�P�O�O�O���[�g���ȏ�̕W�����������āA��������ƓƗ����Ă����B�u�k�A�ɔ�ׂĐl�����Ȃ��v�B�R�ɍs���͓̂s��̎G��������ĂƂ����̂��A��V�ɂȂ��Ă���B�l�͏��Ȃ����������̂��B�u��A�́A���h�炵����ו��o�R�Ɍ����Ă���v�B�Ƃ����̂́A�����ɍ����n�V�S�ŏ��ԑ҂��ɂȂ����Ƃ��ɁA��ו����ƑΌ��҂ɖ��f���|����̂ł͂Ȃ����Ƃ����z�����炾�Ǝv���B����ɃN�T���ꂪ�����k�A�ł́A��ו����Ƃ�͂�ʉ߂ɕs����ɂȂ��Ă��܂��B�u�����͖k�A�ɂ����̂�����A��A�͍��Z���̍����������@��Ȃ��v�B����͎��ɐ������ۂ��B�ǂ����A�J�[���A�X�͒n�`�A���Ԕ��Ƃ����I�V�����́A�k�A�Ɉ��Ă�����̂��B�̗͏�����{�̓�A�ɂ����̂́A�����炢��������Ȃ��̂��B
�@����ł������Q�O�l���炢�̒��ŁA���h�̌��n���ǂ��ɂ���̂��͓��[�ɂȂ������Ƃ�����B��A�W�[�A�k�A�S�[�A���A�P�[���炢�������낤���B���A�̃v�������o���ĕ[�����ꂽ�͎̂��ł���A���P�̂Ƃ��̂��Ƃ��B�����������������B���l�ɏ]�������Ȃ��A�t����Ă݂��������̂ł���B
�@���P�̉ẮA�ɓ߂̉��삩��R�����ɏオ���Ėk�x�܂ŏc���B��U�L�͌��ɉ����čĂіP���O�R�ɓo��Ԃ��Ė鍳�_���ɉ������B���N���ɓ߂̉��R�삩�琹���ɏオ���āA�ԐΊx�A�r��x�Əc�����ē����Ɉ�U���R�B�Ăѓ`�t������g���ɍ~�肽���̂������B����ɗ��N�́A���˔�������b���P�x�ɓo���āA���P�x���痼�������ɍ~��āA�Ăіk�x�ɓo��Ԃ��Ĕ_���x�܂ŏc�����A����ޗǓc�ɉ������B�������ĂR�N�Ԃœ�A�̂R�O�O�O���[�g���͂��ׂčs�������ƂɂȂ����B��������Ȃ��̂́A�ł���ɂ�����x�ƂȂ����B

�����̃j�b�R�E�L�X�Q�@�i�W�S�N�āj
�@�c�����������ׂĂł��������Z���ɂƂ��āA�Ȃ�ׂ����������Ƃ����̂́A���l�Ƃ̗D��ɂ��Ȃ������A�撣���Ă��镔���̏؋��ɂ��Ȃ����̂ł���B���������ɂ������Â��R�k�Ɂu��A�E�Q���R���̑S�R�c���v�Ƃ����M�����Ȃ��L�^���ڂ��Ă����B���j�����̂́A���ł��o���Ă��邪�u�R�ē��l�v�Ƃ������������������A�^��j���������B����ɁA���ÂɁu�J���V�J�R�x��v�Ƃ����c�̂�����悤�ŁA�����̓J���V�J�R�s�A�����܂���O���ĕ����Ƃ����c�̂������悤�ł���B�Љ�ꂽ�y�[�W�ɂ��A�P���̂W���ԍs���Ƃ����K���ɂƂ��ꂸ�ɁA���ɂP���Q�S���ԍs�����ł���A����͂P���łR�����̋������҂����Ƃ��ł��āA�y�j�̒��Ɏd�����I����ďo�������Ƃ��Ă��A���n�ɒ������邩��o��n�߂āA���j�̖�܂łQ�S���ԂɂR�����̎R�s���ł���Ƃ����A�܂��������̂悤�ȎR�s���@�������̂ł���B�Ƃ��낪���͂���ɖ��Ɉ�����Ă������̂��B�m���ɉāA�~�A�t�x�݈ȊO�́A���j�P�������̓o�R�ɂȂ�킯�ŁA���������w�͂ł����Ȃ�����A�R�ɂ͂�������s���Ȃ��̂��낤�ƁB
�@������U���Ă܂��������̎R�ł���Ȃ��Ƃ����Ă݂��B�����ܓ��s����o�X�ɏ���āA�n�������������x�R�ɓo�邱�Ƃ���n�߂��B�X�^�[�g�͓y�j�̌ߌ�U���B���R�A��O�R�Ɛi�̂͂����̂����A�[����߂���Ɩ����Ȃ�B�x�e���ɓ�l�ŋ����肵�Ă��܂��B�������̂��B���͓����̗ѓ��̕ӂ肾�������A���l�����������Ă����ɓ��荞��ł��炭�Q���B���ɂȂ�Ɛ�q�������悤�ŁA�ނ͊w�����ۂ��B�����ɂP�����ɂԂ��؍݂��Ă����悤�Łu�~�R����v�ȂǂƂ����K�C�h���]�����Ă����B����ȂƂ��Őϐ���̏��������Ă��āA�Ȃ�قNJw���͗D��ŁA��l���ۂ����Ԃ̉߂����������Ă���Ȃ��ƁA���Ɋ��S�����o��������B
�@�������͂܂��o�������̂����A���ĎO���R�ӂ�܂ł��������̂������낤���H�@�v��ł͂������牄�X�Ɠ������ɁA�����ƎR���̌���������i��Őw�n�R���獂���ɉ��R����\�肾�����B�܂�\��̂R���̂P���������ł��Ȃ��R�s�ɂȂ����B�������^�钆�ɍ��Z���������d�������œ�l�ŕ����Ƃ����A�����o�����ł����B���̃��[�g�͒��J��P�v�̎R�x�}���\���̃R�[�X�ɂȂ��Ă������Ƃ��������B
�@�����悤�ȎR�s���A�x�m�R�ł������x�ł�����Ă݂��B�x�m�R�ł͌�y��A��āA���Ԃ͐��i�Ő��j�����ėV��ŁA��������o��o���B����ǂ��̂Ƃ�����Ԃɏ��X�������Ƃ��Ă��܂��āA����ł��[���ɂT���ڂ̌䒆���ɏo�āA�����͂������������̘e��o���đ����ɏo�āA��ʃ��[�g���牺�R�����B���|���^���N�Ɋe���łS���b�g���̐���w�����Ă̎R�s�ɂȂ����B�����x�͈�l�ł��������A�����ɒ����ŏI��Ԃŕ����n�߂āA�������ɐ^���������̒����ɏo�āA�Ԋx���痰���x�܂ŏc�����āA��q�����ʂɉ��R�����B��͂蕁�ʂ̂W���ԍs�������A�����s�����҂����悤�ȋC������B�x�m�R�[�ɂ���䐳�̎R�Ƃ����Ƃ���ɁA�Ⴊ�~������̂Q���ɂ����āA���̂Ƃ�����ʂ������āA�E��̑��ɍ~��ĕx�m�}�s�ɏ���ċA���Ă����L��������B���Ă���ƁA���f�Ƃ����قǂł��Ȃ��̂����A���ȕ�����������̂��Ǝv�������̂��B�̌`���l�Ɍ�������A���ꂪ�����ĕ����Ă���悤�ɂ�������B�|�����Ă��Ă��肪�Ȃ��Ȃ��ƁB���������Y�̎R�x�����ɂ��A����O�ɓ����悤�Ȍ��f������悤�Ȃ��Ƃ������Ă������̂����A���Ă���Ƃ����ȂƊJ�������Ă������̂������B
�@�������ĂR���̏t���h�ɂ��Q��A�����̓~���h�ɂ��Q��Q�����āA���Z�R�N�Ԃ͏I����̂����A����ɂ��Ă��A���̎������Ȃ��̂ɁA�悭����Ȃ��Ƃ��ڂ����o���Ă�����̂��ƁA��Ȃ�������B�N�����Ɩ��ɎႢ���̂��Ƃ������L���Ɏc��Ƃ����邪�A���łɂ����Ȃ̂��낤���B
�@���Ƃ��鍠�Ɏ��͌����ł̎Ɏ��s���A�Q�l���ė��N�ĎȂǂ̎������߂����āA�R�o��ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ����Ƃ����������B�������Ă��̓�A�̏c�����v�悷�邱�ƂɂȂ����B
�@���͂��̔N�̂P�O��������A�o�C�g�ɐ����o�����ƂɂȂ��āA�R�o������炭�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂���������Ȃ��Ȃ��ƁA���R�ƕs���ɂȂ��Ă������̂������B����Ȋ������ڑO�ɔ����Ă����Ƃ��ɁA�}�Ɏv�������R�s�ɂȂ����B

�O���������Ő剖�����ƕ��s����x�����E�ێR��̃R���̍r�ꂽ�R�e�@�i�W�X�N�V���j
�@����ɂ��Ă����̔N��̍��́A�{���ɎႭ�Č��C���B�����g���[�j���O���Ă����Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂ɁA����ɎR�o�������Ƃ����̂��A�Q�N�Ԃ��炢�̃u�����N���������Ƃ����̂ɁA�킸���ɂS�����̐H�����������āA���̓�A�̑S�R�c���Ɍ��������̂ł���B�É�����n���S���ƃo�X�����p���Ŕ���_���ɓ���B�������璃�P�x�ɓo����āA���x���������āA��͖k�シ��̂݁B�v��ł͂P���P�U���ԍs�������āA�c��W���Ԃ͐����ł����ƁA���߂������Ă����B�܂�����̎R�ē��l�̂悤�ɁA�Q���Ŏ��s�ł���킯�͂Ȃ��B�ł����̔{���炢�Ȃ�ł���̂ł͂Ȃ����ƁB�m�����̈ē��l�͏����ƂQ���ڂɂ��ꂼ��Q�O���ԍs�������āA�R���ڂ͂P�S���Ԃ��炢�ʼn��R���Ă����B�R�[�X�^�C��������ƁA�ǂ̂R�O�O�O���[�g������Q���Ԃ��炢�œo���Ă���B�Ƃ����������Ă���̂��B�k����쉺����c���ŁA�����͔_���x������쓌���ɉ����āA�ᓊ�牖���x�ɓo��A�������������B�X�L�[�̗����ƈꏏ�ł���B�o���~�̑����Ő��͔����������Ă̏c���ł������Ƃ�������炵���B���邢�͉����x��������x�͑���̐����ɉ����āA�r��x�ɓo��Ԃ��Ƃ�������́A���n�̈ē��l�Ȃ�ł͂̏n�m�����閧�̓��ゾ�����̂��낤���B���������������o���~�͂P�T�O�O���[�g���������āA�o��Ԃ����̂ł���B����ł��Q���ԏ��X�B�������ł���B
�@�����w���s�ŏo�铌�C�����Ŏ��͐É��ɓ������̂����A����_������o��n�߂�̂͌ߑO���x�������̂��낤�B���P�x�̕���ɗ[�������B����ł����̎���������x�������ł�����̂Ǝv���āA��g�ŏo�����Ă��܂����̂��B�Ƃ��낪�P���Ԃقǐi��ł������Ƀo�e�Ă����B�d���Ȃ��U�b�N�f�|�ɖ߂�B�Ő��ɃV�[�g��~���������̂Ƃ���ʼnėp�V�����t�ɐ���B
�@���ɂȂ����B�������R�������H���������Ă��邪�A�Ȃ������Ŕ��������悤�ȋC�ɂȂ��āA�낭�ɐH���������ɍĂы�g�Ō��x�Ɍ������Ă������o��������B���n�}�̃R�[�X�^�C�������ĕ��ꂽ�B���P�x������x�܂ŕГ��U���ԂɂȂ��Ă���B�����̒n�}�ł͂S���Ԃ��Ǝv���Ă����̂����B�u�R�[�X�^�C���̔����v�Ǝ��͌��߂Ă��āA�{���ɂS�����ԑ��炸�Ō��x���������Ă����̂��B����Ƃ����ɓo�R�q�������B�u�m�c�r�ɂł������Ă����̂ł����H�v�u�������A���x�ł��v�B����Ƃ�Ƃ�������ɁA���ȗD�z�������Ƃ����A����炵���c���}�V���ł���B���nj��x�Ƃ����R�́A���ł����̌`������Ȃ��̂��B�R�e�߂Ă����Ȃ��̂ɁA�c���H�ɏ]���ēo�����Ă��܂��Ƃ����A�ϑ��o�R���c���ɂ͑����B����O����ȒP�ɒ��߂���قǁA��A���v�X�͈��Ղł͂Ȃ��A�R���Ȃ��Ƃ�������̂����B���������x�Ƃ����̂́A�ǂ̉��E���猩����̂ł��낤���B�R������ǂ��̉��E�������Ȃ������C�������B�܂����������R���D���ł������B���H������āA�k����n�߂�B���̓��i�Q���ځj�͐����ɔ��܂����Ǝv���̂����A���̓������͂悭�v���o���Ȃ��B
�����͐��x�A�ԐΊx�Ɛi��ŁA�r��x����������B�r��x�̓o��ŗ[���B�e���g��ɐ��l�������B�R���ŐQ�]�������Ƃ��ɁA���V�̐��ƂĂ����ꂢ�������B�������ăm�R�m�R�ƍ��R���Ƃ����e���g��ɂ��B�R���ڂɂȂ����B
�@�Ƃ��낪�����ɐ��ꂪ�Ȃ��B�X���ɂȂ��Č͂�Ă��܂����悤���B�|���^���ɂɐ��Z���`�������͎c���Ă��Ȃ��B����ƃr�X�P�b�g��H�ׂāA�����悤�ɃV�����t�ɕ�܂��ĐQ���B

�œ암�̑喳�ԎR�ɏオ��I���̑劘�i�W�W�N�j
�@�S���ڂ́A�܂��������������܂܁A����̂���R�����Ɍ������B�������牖���x���z���āA�F�m���̃e���g��ɂ����B�܂���ɂȂ����B�^���Âŏꏊ�������炸�A�����������̃h�A���J����ƁA�����Ԃ��N���Ă����B�u�e���g��͂ǂ��ł����H�v�u����Ȗ�ɁH�������珬���ɓ���Ȃ����v�B�����Ŕ��߂Ă��ꂽ�̂��B�R���������āA���̂Ƃ��̓X�p�Q�e�B��H�ׂ��B�I���W�̓r�[�������݂Ȃ���b�������Ă����B�u���R�����炫���v�Ƃ����Ɓu����͌��r���˂��B��������P���ł����l�́A���N��l�ڂ���v�B�S���ڂɂȂ����B�n�������\��ł͖������R�ɂȂ�B���������������C���ł͂Ȃ��B���Ȃ��Ȃ����H���͉��Ƃ��ߖ�ɂ��āA�v��͍Ō�܂Ŏ��s���鎩�M�������Ă����B
�@�����͉J�͗l�������B�ԃm�x���z���Ėk�x�̗Ő������ɓ������B�����͂����������O�������B�Q�O�O���[�g�����ɖk�x�����������āA�����ɂ͐��ꂪ���邽�߂ɁA�e���g���̘A���͉��̏������ӂɔ��܂������̂��B��ɐ���ɂ��ꂽ�̂����͏����Ղ����ɂȂ��Ă���炵���B���̗Ő������Łu�x�e�������v�Ƃ������B�Q�O�O�~�����ƁA�������o�Ă����B���J�����Əo�Ă������̂�����A���{�����߂ē������悤�Ɏv���B�܂����J�̒����o��B�R�����痼�ҏ����ɍ~���B�����ɑf���܂�łƂ܂����̂��A���l�����������̂��B�J�̒��Ńe���g�͎����Ă��Ȃ������̂�����A�����̒��ʼn߂��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���łɃV�[�Y���I�t���������H�h���҂������B�����łT���ځB�H�������Ȃ����A�����������Ȃ��B�����������Z����̋����Ƃ��āA�R�����Ŕ����H�����Ă͂����Ȃ��Ƃ����K�����������B���������Ƃ���͑�l�����p������̂ŁA���Z���͗�������Ă͂����Ȃ��ƁB�R�ŕK�v�Ȃ��̂́A���ׂăU�b�N�ɓ����Ă���ׂ��Ȃ̂��B�����̌ږ�̋����́A�Ȃ�قǗ��h�߂���قǂ������B�����Ƃ���ɂ���ɏڂ����m�邱�ƂɂȂ�̂����A�ږ�͐��U�T�O�O��قǂ̓o�R���s���A���h�Ȋx�l�ł���A�R�x�J�����}���ł���A�p�ꋳ�t�ŁA�V�̊w�ƐA���w�Ə����ɏڂ��������B���蒆���搶�Ƃ����A���̍ő�̓o�R�̉��t�ɂȂ����B
�@�����J�オ��B���s�ƂȂ����I���W����Ɛ��P�x���ʂɓo��Ԃ��B�J�[���̒��ォ��k�ɉ���B����ɍb���P�x�Ɍ������ēo��o���B��͂�܂��J���~���Ă����B�ߌ�R�����ł��W���ڕӂ肾�B�����Ă���l�������B�u����Ȏ��Ԃ���ǂ��ցv�u�b���ł��v�u���ፕ�˔����ɏ��������邩�炻���ɂ����Ȃ����v�u���̂���ł��v�B����Ȃ���肪�������B���ォ�獕�˔����ɓ����āA�V���̏����ɓ���B���l�ŊJ������Ă����B�U���ځB���ɖ����͍ŏI���ʼn��R�͖��ꂽ�悤�Ȃ��̂ɂȂ����B
�@���͂��̏����ɓ��h�̂R�l�������B�w���̗l�q���B�����J�ŔG��l�ɂȂ��ē����Ă����̂ɁA�ނ�͉ו����U�炩�����܂܂������B�������B�V�����t���т���G��ŁA�܂������k���Ȃ��犦������߂������B�r�j�[���ɕ��ŃU�b�N�ɋl�߂�Ƃ����K�����Ȃ������̂ł���B�J��͒x��Ă����B�ނ�̎U�炩���������̒��ɁA�r�X�P�b�g���������H�����������Ă����̂��B���̈���]�����āA���̕��ɔ��ł����B���̂܂ܘA���͖����Ă���B�����ł������̂����A��������肪���������Ă��܂����Ƃɂ����̂��B���̍߂��Ȃ��B�R���������킸���Ɏc���Ă��āA����𐆂��ď����H�ׂ����炢�������B
�@�����͂������R����̂݁B���������̃o�X�₩����͔B��܂ōs���������Ƃ͕������Ă����̂����A�o�X����P�`���ē���t�w�߂��ō~�肽���߂ɁA�Ȃ�ƂP���ԋ߂��w�܂ŕ������ƂɂȂ��Ă��܂����B�b�B�X���ƓS���̉w����������Ă���B�c�ɂł͂���Ȃ��Ƃ�����̂��낤���B����ł��V�h�ɂ܂��܂����邢�����ɂ��āA�����ŗF�l�Ɨ��������Ă����ʂ̎���ɖ߂����B
�@����ɂ��Ă��C���������قǂ������ĂQ�V�N�O�̎R�s���o���Ă�����̂��B�����ł������B�܂肱��́A�����̓��̒��ʼn��x�ł���䍂������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B���������͂P���ɐ���ł��B����𐔃����͌J��Ԃ��Ă����̂ł͂Ȃ����B���ꂾ����S�̎R�s�������̂��낤�B���́u��A�S�R�U���v�Ƃ����̂́A�U���ɉ��l������Ǝv���Ă����B�ނ���\������H���͏��Ȃ��ق��������B����ʼnו��͌y���Ȃ�B�U�b�N�̏d���ɒׂ�Ă��܂��R�s�����A���͌y���Ȃ��Ă��U�b�N�̌y���ő����s�����������������̂��Ƃ����X�}�[�g�����ւ�Ɏv���Ă����B���̌㕠�������āu�V�����āv�ŕ����Ȃ��Ȃ�R�s�͂�����ł��o�����Ă��܂����̂����B
�@����ɂ��������댯�x�̏��Ȃ��̗͏����̖`���^�R�s���A���͎��͍D���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ��v�����B��Ƀt���[�N���C�~���O������o��ɋÂ肾�����̂��A���͂����������R���B�A�����J�ɂ����Ă����Z�~�e��o������A���̑嗤�ɂ͂ǂ������A�����Z��ł��ĉ������Ă���̂��ɋ������N���B���������l���ꂼ��̋����͎d���̂Ȃ����ƂȂ̂��B�t���[�N���C�~���O��X�L�[���~�̓�Փx���������Ă��A�����ɋ������W�����Ȃ�����A����͐l���݂ɒB�����Ȃ��B������u���v�Ƃ���������Ȃ̂�������Ȃ����A���������̑����ׂĂ̊S���Ƃ𑍌v����A�܂���̐l�Ԃ͒N�������v���}�C�[���ŁA�s���������Ȃ�̂ł͂Ȃ����ƁA�ŋ߂͎v�����肷��̂��B�Ƃɂ����������ƎR�ɐڂ��Ă�����悤�ɂȂ��Ă��������̂��B
�@