
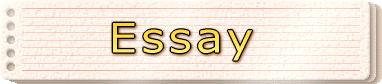


| 文鳥 あの子を返して |
 父が突然手乗り文鳥の番いを買ってきてくれた。3人の兄弟に挟まれ、女ひとりで育っていく、娘の気の 強さを案じたのだろう。 父が突然手乗り文鳥の番いを買ってきてくれた。3人の兄弟に挟まれ、女ひとりで育っていく、娘の気の 強さを案じたのだろう。
人形遊びに興ずることも少なかった私は、生きた愛玩動物に夢中になった。
間もなく成鳥になった文鳥は、家族の中で誰よりも私になついた。家にいる時はたいてい籠からから出して、肩や手に止まらせて遊んでばかりいた。
勉強するときは、机の隅で居眠りをして、勉強が終わるまで待っている。
食事も私のお膳の傍で、ご飯やお菜をもらう。
眠るときでさえ籠から出て枕の近くに寝た。寝つかれぬ夜など、文鳥相手にひそひそ内緒話をした。
私が学校から帰ると、鳥はその物音を聞きつけて、籠の中で大騒ぎをする。
私の足音だけを聞き分ける鳥に、私は有頂天だった。
私は鳥への愛情を作文に書いた。
その作品が入賞して表彰された。作文の締め括りに中一の私は、「心配なのは猫と寿命です」と書いた。
中三の晩秋、暗くなって帰宅した私は、玄関に近づくと聞こえるはずの鳥の声を聞かなかった。
不吉な予感が過ぎった。早鐘を打ち出した心臓。
玄関の引き戸を開ける。すべてが一目瞭然であった。
上がりかまちに空っぽの鳥かごが、ぽつんと置いてあった。その日から10日ばかり、目を泣きはらして学校に通った。
以来、私は20余年、文鳥の「ブ」の字も口にすることができなかった。小鳥を失した傷が漸く癒えたころ、娘の事故死が私を襲った。 |
| 身近な死 あの子を返して |
彼はいつも独りであった。教室でも彼の声を聞くことは稀であった。
女生徒の前を通る時などは、顎を引き、うつむき加減で目を伏せるようにして、素早く横切った。彼の顎の右下には大きな黒子があり、山羊のような毛が生えていたのを皆知っていた。
中三の夏休み彼は常のごとく多摩川へ釣りに行った。
広い河原の石の陰には、当時も、ガラス瓶の破片や太い針金などの凶器が潜んでいた。
彼はガラス片で足を切った。野遊びに慣れた者らしく、彼はヨモギで血止めをし、一日中釣り没頭して、夕方遅くに家に帰った。
彼の担任が彼の死を知ったのは、それから約10日後だった。死因は破傷風。担任から呼び出されたクラスの主立った生徒たちは、駅近くの寺に、彼の新しい墓を訪ねた。
墓には木の香立つ白木の卒塔婆立ち、幾らかの花がまだ枯れずに供えられていた。
生そのものへの疑問を漸く持ち始めたばかりの私は、同じクラスの男生徒をいきなり襲った理不尽な「死」に当惑していた。
最早この世のどこにも存在しない彼。
この墓の奥に「骨」となって納まってしまった、かつての眼差しや顎の毛。
とらえどころのない曖昧な「死」は、理解を超えたものとして、私を大きく圧倒していた。
今も駅近くの寺を見る度に、早々と人生から淘汰されてしまった一人の不幸な少年と、彼の伏し目がちの横顔を思い起こす。 |
| ヒョウという名の猫 あの子を返して |
6年前の春、夜帰宅すると娘が玄関に飛んできた。「母さんお帰り、きれいな猫がきたの。兄ちゃんの後をずっと 付いてきたんだって」。 付いてきたんだって」。
家には赤ん坊の時に拾ってきた三毛の「こまち」が居る。
こまちは闖入者の威勢に気圧され、隅で身じろぎもしない。新参者は短毛の洋猫で、ロシアンブルーが混じっている。金と銀の眼を、ぐいっと向けて、真っ直ぐに私を見る。どこかで捨てられたか、迷子になったか、骨と皮ばかりになって、足に怪我まで負っていた。病院での治療が済むと、娘は高らかに宣言した。
「黒ヒョウみたいだから、名前はヒョウちゃん、私の猫よ」。
気性の激しい洋猫は缶詰のペットフードしか食べない。抱くと爪を立てる。夜は当然といった顔で人の布団に潜り込む。果ては二・三度毛布の上で糞までした。
喧嘩には勝ったことがないお嬢さん猫のこまちは、この暴れん坊との共存にすっかり参った態であった。
が、やがて2匹で連れ立って朝の散歩に出かける姿が見られ始めた。
猫2匹を抱えての生活がうまく回り始めたころ、ヒョウを欲しがる人がいて、私は娘に内緒でやってしまった。
その夜、娘は身も世もない風に泣いた。オーオーと身をよじって。
3ヶ月後、娘は暴走車にねられ、突然この世から姿を消した。
私は毎晩、オーオーと泣き続ける。身も世もなく、このまま死んでしまいたいと願いつつ。 |
| 暗闇 あの子を返して |
暗がりの中に、じっとしているのが好きだった。
前々からそうだった。今はもっと。秋の日は釣瓶落とし。午前中のノロノロとした動きから、急に速度を増す、時計の針。
3時を回ると既に夕方の色が滲み出してくる。
本の活字がふと読みづらくなっているのに気づく。
夕闇は部屋の隅から、地面から立ち昇ってくる。
夕闇は遙か遠くから、電車の音を運んでくる。
一時、子供等の賑わいが響く。手元はすっかり暗くなる。本を置く。冷蔵庫から冷えたお茶を出してコップに注ぐ。じっと座って何も考えない。
蘇えらんとする思い出を封じ込める。
何も考えまいとする。
独りで過ごした一日。やっと凌いだ一日が、やわらかな闇に包まれて、もう少しで終わる。
何でこんな暗いところで料理をしているんだ!。何でこんなに暗いのに電気も点けず本を読んでいるんだ。
夫は今でもすぐに電気を点ける。
白い蛍光灯の光は、部屋部屋のあちこちに堆積した、
苦しみの歳月を容赦なく剥き出しにする。
ここに居るはずの娘の不在を否応なしに突きつける。
私は娘を喪った事実を、未だ認められずにいる。
闇が好きなのではなく、ただ明るさが嫌いなのだ。
明るさは、在るものと無いものを明確に解からせるから。
あの日以来、私は暗闇の中で、音を立てぬようにして入浴する。闇の中で居ない娘と小声で話をし、そして歌をうたってきかせる。 |
| 桜紅葉 あの子を返して |
桜紅葉。7つの子供が知っていたとは思えない。春の桜の美しさと、秋の紅葉の華やかさ、君はどちらの人生を 歩まむとするや・・。 歩まむとするや・・。
そう尋ねられた娘は、やや思案をしてから、晴れやかな顔で「桜紅葉」と答えた・・・。
夫は昨年の年賀欠礼状に、そう書いた。娘はよく山を歩いた。親子3人で、また5人揃って。
時には女ふたりだけで。私が休日出勤の日は、夫が連れて歩く機会も多かった。
花を見、草を摘み、雲を仰いで寝ころび、雄大な裾野を遙々と眺め入った。
蕨・蕗・ぜんまい・根曲がり竹・山椒等々、夢中で採った。藪こぎも厭わず、大人の後について歩いた。
河原でもよく遊んだ。多摩川の広い河原には朝露の残るマツヨイグサが幻のように咲く。
夕方は丹沢山塊から富士山にかけて、空を焦がして夕日が沈む。娘はどれをも好んだ。 休日、思い立つとお結びを握って、お昼を食べに出かけたものだ。ゆったりと日差しが動くにつれて、楽しい時が心に刻まれる。葭が一面に生い茂り銀色の旗を振る。
淀みには蒲が垂直に伸びた茎の先に、キツネ色の穂を巻きつける。それを見つけると、娘は小躍りしてをねだった。
野茨の藪を掻き分けて進めば、娘の手には赤い実のついた小枝が、必ずある。
至福の時。幸福の日々。夫は先の葉書に続けてこう書き添えた。
神は娘を美しく着飾らせることもなく、幼木にして断ち切った、と。神の存在を、夫は信じない。 |
| 京の坂 あの子を返して |
京都、清水二年坂の石段は、中ほどが窪んでいる。
最初からその形の自然石であったかのような顔で置かれているが、夥しい人が上り下りして摩耗していったものだ。
古い都の洛外を、急に降り出す五月雨も構わずに歩く。
この石段を擦り減らした夥しい数の人生を思う。
取り分け、理不尽な運命に翻弄され、生きる宛を無くた空っぽの心をどのようにもできずにいたであろう人々を想像する。
清水詣でにかけた、暗く炎をあげる思いに我が身を重ねる。
既に無に帰し、いまは黙して語ることをしない多くの悲運な人生。彼らも私も、歴史の流れに黙って流されてゆく小さな点だ。
私が抱えきれずにいる痛苦も悲哀も、やがては時の舞台から静かに消えていく。そう思う。
二年坂、三寧坂を幼い娘と胸躍らせて歩いた。6年前。
清水焼を眺め、店の和紙を手に取り、小さな娘の傍らで、幸福感に酔っていた。
室生寺の長い長い石段。戒壇院の石組みの階段。
高雄神護寺の荒く大きな石段。三千院入口の十数段の石段。知恩院の大ぶりな構えの石段・・・。
娘と古都を訪ねる旅は、多く石段の思い出に絡まっている。
どこの石段でも、娘の眼はキラキラ輝いて、喜びにはち切れそうだ。「母さん、早く、早く」。
私を急かす弾んだ声。今も鮮やかに聞こえる。
幸福でいることが当たり前だった。有頂天であった。
突然の娘の死が、私たちに襲いかかって来ようとは、つゆ思わなかった。 |
| 狂う あの子を返して |
9月も末になると、日暮れが急に早くなる。
どこかにじっと座っていることができなかったあの当座。学校帰りにバスを待つことが苦痛でならなかった。
林の奥から闇が靄のように広がる。車のライトが明るく輝き出す時刻。
僅か数分の待ち時間にさえ、心がふわふわと体から抜け出して、夕闇に舞うコウモリさながらに飛び回る。
ベンチを立ってみる。心は戻って来ない。
涙だけが止めどなく落ちる。じっとしていられない。
心の抜け出した殻から、殻そのものを振り払ってしまいたい。
動き回る。せかせか、苛々、靴っぽの心の奥から「母さん」と娘が呼ぶ。
顔が涙でぐちゃぐちゃになる。「母さん、母さん」呼び声が高くなる。
この地球上を、端から隈無く探したとて、もう未来永劫、顔を見ることすら叶わぬ娘。急に覆された天地の有り様に、心が動きを止めてしまった。
それなのに娘を追い、追い求めて泣いた。
数分のバスの待ち時間にさえ。あの時、夕闇に紛れて飛んでいった心は戻ってきたろうか。
バスに乗る。空席に座る。動く車窓の暗い町を見続ける。林がある。学校がある。歩道橋がある。
親子連れが家路を急いでいる。
乾きかけていた涙が、バラッとこぼれる。
慌てて目をそらす。が、既に目は食い入るように見てとった後だ。
死ぬことだけを考えて、操り人形のように日々の流れを見送っていた、あの頃の私。 |
| 札幌の夏 あの子を返して |
夏も盛りだというのに、この寒さは何だ。
歯の根が合わない。二人で菓子パンと牛乳だけの貧しい夕食を、北海道初日の夜、札幌は大通り公園のベンチで済ませた。
周囲には名物の焼きモロコシの屋台が出ている。ぐっと我慢する。
私の財布の中身は約20万円。キャッシュカードも免許証も東京に忘れて、遙々北海の地にやってきてしまったのだ。ホテル付けで至急郵送を頼んだものの、前途三千里の思いで、今晩はケチケチ札幌泊になった。
娘は文句も言わない。歯をガチガチ鳴らして震えながら「母さん、たまにはいいよね」と言う。
家族から遠く離れて二人ぼっちになって、私は娘の全てが一層いとしかった。
余りの寒さに夜の大通公園を歩き回って、そのままホテルに戻った。時計台のすぐ裏手のホテル。
娘を失って後、私は声のない寂しさにテレビを点けるようになった。
札幌の大通公園が何かと映される。その度に、あの夜と、翌朝の散歩の気持ち良さがフラッシュバックして、涙が堰を切って溢れる。
ラジオ塔に昇ってみたかったが、お金が心配で取り止めた。楡の木が枝を重ねるように周囲に植えられていて、朝の陽光が澄んでキラキラこぼれていた。
娘が子供っぽく水と戯れ、光と遊ぶ姿を、私は満ち足りた思いで見つめていた。滑り台で何度も歓声を上げ「母さんみててね。」と、手を振った。眩しい笑顔は、私の胸に鮮やか刻まれている。
幸せは、今はもう無い。娘と共に、失せた。 |
| 利尻富士 あの子を返して |
「母さん遅いねえ。私、もう一時間も昼寝していたんだよ」。利尻岳の山頂で、娘は生意気な口を利いた。
夫と一緒に山に行くと、大抵この調子で、夫は先に登って山頂で寝ころんでいる。
海抜ゼロメートルから1800メートル強の山頂まではきつい。
女二人の冒険であった。登山道入口で、日本百名水のひとつと言われる甘露泉の水を水筒に詰めて、利尻島の最高部を目指して歩き始めた。
快晴。昨日島巡りをした礼文島が向こうに望める。
スカシユリの傍で、頬杖をついて得意げの顔をした娘の写真を撮った。
花気違いの娘は、次々と出現する高山植物の花を見て歩くのに夢中だった。
レブンアツモリ草は見ること能わず。利尻岳は、長官小屋までは花もない。
針葉樹林帯を抜け、落葉灌木の間を、ひた上りに登った。小屋の前での娘の写真は、童女のようにあどけなく写っている。そこからが本格的な登りだった。
笹原がえぐれてVの字の溝となった道を、足を傷めぬように注意して歩く。
やがて尾根にでると、頂上は目の前に屹立している。
急勾配とガレ地に足を取られている私を後目に、娘は身軽に登っていく。
それでも花はいちいち立ち止まって見ている。小一時間遅れて到着の私を、娘は保護者ぶって迎えたのだ。
娘と登る予定だった山は、本州・九州にまだ十数山残っている。
今や永久に残ったままだ。 |
| 泣かない子 あの子を返して |
人が一生に流す涙の量は決まっているという。
私はほとんど泣かない子であった。悔しくて泣くのが精々で、他は大抵の場合堪えた。 気の強い子、強情な子で通っていた。多分、優しさが足りなかったのだ。
自分のためになんぞ、泣ける筈がない。
本を読むようになってからは、非情で過酷な運命に生きる人、死に追い込まれる人への涙は、流した。
しかし総じて、涙の少ない少女時代だった。
もっとたっぷりと泣いて、一生分の涙の全てを、小さい頃に流してしまっておけばよかった。そう思う。
頑固で強情で、やるといったら最後まで音を上げず、泣き言も言わずやってしまう人間は、むしろ悲しい。
「知・情・意、共に優れているが、時に知・意が強くなる」。小学校六年の担任が、通知表に書いた言葉だ。
「やっぱりおまえは優しさが足りないんだね」。母がため息じりに、ポツンと言った。 だから妙に覚えている。勉強ばかりさせた技楽面のような顔をした教師だった。
どうして小さい頃、持った涙を使い果たしてしまわなかったのか。
悔やんでも詮無いが、悔やまれてならない。
今夜もひどく泣いた。
一昨夜も、身を震わせて泣いた。
泣いたところで、二度と会えぬ娘故、いや二度と娘の目を見、声を聞くことが絶対にあり得ぬからこそ、消耗するまで、泣くのだ。
泣くだけのひ日々。
|
| 花盗人 あの子を返して |
草や花が好きだった。物心ついた頃から好きだった。
殊に清楚な野草に心惹かれる。草や花を見ることで、生の喜びが実感できる。生きているって、素敵だと。
冬のお茶の花・赤まんまの群落・春田の畦の、サギゴケ・ジシバリ・スカンポ・ギシギシ。
ゲンゲ畑のうっとりする甘い蜜の香りと、土と雑草の泥臭さ。
梅雨の頃、所在なさに眺めた垣根のヤブカラシ。
高尾山で発見したシャガの大群落。友達の家に遊びに行っては、よく草花を無心した。根を分けてもらってきては、小さな庭に植える。世話をする。
ヤグルマギクの種を蒔いた。向日葵も育てた。
土をいじって遊んでいた私を見て、「女の植木屋になれるんじゃないの」と母が言った。
土のむせ返る香り、その立ち昇る香りが好きだ。
移植ゴテでサクッと掘り返すたびに、新しい土の香りが胸一杯に広がる。
野草の標本も作った。が、名前が分からない。
私の手元には図鑑がなかった。理科の先生に聞いても知らない、と言えわれた。
大人になってから夢中になって草花の名前を覚えた。
ひとつ覚えると、十の幸せが得られた。世界がいっぺんに拡がった気がした。
娘を育てた頃は、ほとんどの名を教えてやることができた。
娘は花博士と呼ばれた。私以上に花や草に夢中になった。どこに何が咲いているかもよく知っていた。可愛い野草を何時も摘んで来た。
「草って、とてもいい匂い」。娘の遺した言葉。 |
| 紙魚 あの子を返して |
立川の駅ビルに大きな書店が入っている。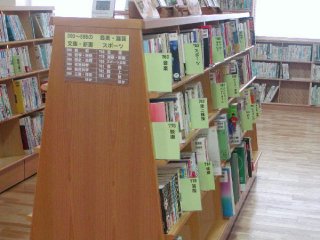
よく二人でそこに行った。自転車で。私は自分が読みたい本のコーナーへ。娘は児童本のコーナーへ。
一時間ぐらいは、すぐに過ぎてしまう。
何冊か本が選べると、私は娘が居そうなところを探して回る。
大抵娘は立ち読みをしている腕に何冊も抱えながら。
買って、手元においた方がよい本か、どうかをみる。
何度も読み返す価値があるかどうかをみて、「これは図書館で借りれば」、などとアドバイスする。
買いたての本の袋をそれぞれに提げて、フルーツパーラーに寄る。アイスクリームを嘗めながら、娘はもう一冊目を読み終えてしまう。
「母さん、この本の・・・」すぐに興奮して私に喋り始める。
私は自分の本を読みさして、娘の話を聞く。
生き生きと登場人物の性格や、事件の粗筋を語っている娘の顔を、肯きながら見つめている。
これも至福の日々の一こま。娘の目は輝き、頬がポーと上気して、私はうっとりと娘の声に聞き惚れる。
彼女の薦めてくれた本で、つまらなかった本は一冊も無い。
五歳の頃には、子供用文庫本を自在に読んでいた。
娘の頭の中には、楽しく、悲しく、怪しい話が沢山詰まっていた。
「母さんへ、日野市図書館から電話があり、頼んでおいた本が入りましたから、どうぞとのことです。よろしく。しな乃」。これが娘が私に遺した、最期のメモだ。 |
  
|