飛行の原理
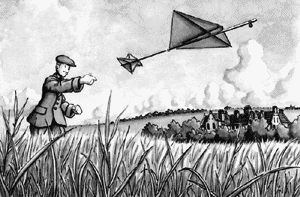
翼は飛行のシンボルです。その翼を支えるのは空気です。 翼の周りを流れる空気の作用が、空中に浮かぶ力を翼に与えます。 目では見えない翼と空気のメカニズムを探ります。
はばたかない翼

鳥のように翼をはばたかせ、空へ舞い上がるというアイディアは、 古代ギリシャのイカロスの時代からあります。 人々は長いあいだ、はばたき機の製作に情熱を注ぎましたが、 ひとつも成功しませんでした。 しなやかで複雑な、はばたき運動を機械で再現することはとても難しく、 また空中で自重を支えるための動力源としては、 イカロスのように人力では明らかにパワー不足だったからです。
19世紀初頭、イギリスのケイリー卿は、 翼を広げて空を舞う鳥と、風を受けて昇る凧からヒントを得て、 凧を翼として利用した模型飛行機を作りました。 彼のアイディアは、(1) まず模型を前方へ投げて風を作る、 (2) 凧の翼が風を受けて上に昇る、という2段階の動作によって、 空中に浮かぶ力を得ようとするものでした。
翼が上方へ引き上げる力を「揚力」と呼びます。 飛行機が前方へ進む力は「推力」です。 ケイリー卿の、揚力と推力を別々に作るアイディアは、 はばたきの長い呪縛から人々を開放しました。 こうして、現在の飛行機開発が始まったのです。
風をとらえる

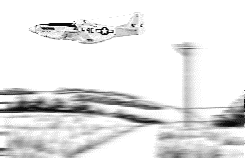
高速で飛び去る飛行機の映像は流れてしまいます。 もう一度、今度は通過する飛行機を目で追ってみましょう。 すると、飛行機の映像はピタリと静止し、 動かない地上の風景が後方へ流れます。
もし、空気を見ることができるなら、 地上の風景が後方へ流れたのと同様に、 空気も後方へ流れて見えるはずです。 それは、見かけ上は静止している飛行機の前方から後方へ、 空気が流れることを意味します。 飛行機が推力によって高速で前方へ移動することで、 その翼は相対的な空気の流れをつかんでいるのです。
かのケイリー卿は、模型飛行機を前方へ投げることで、 相対的な風をつかみました。 推力がもたらす相対的な風は、翼の力学の出発点です。 この翼の周りを流れる空気の作用によって、 空中に浮かぶ力が翼に生じるからです。
風のなかの翼

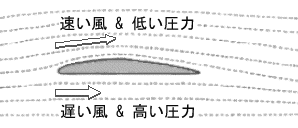
翼の断面形は、上面の緩やかなカーブと下面の平らなラインで構成されます。 翼の上面はカーブした分だけ、下面と比べて長いことが特徴です。
風の流れを観察すると、翼の前方で上面と下面へと2つに分かれた風は、 同じ時間をかけて翼の表面を通過し、後方で同時に合流します。 翼上面はカーブした分、下面より長いのですから、翼上面を流れる風は、 より長い距離を速いスピードで流れなければなりません。
「水や空気のような流体は、流速が速くなるにしたがって圧力が低くなる」 という「ベルヌーイの定理」として知られる空気の性質によって、 翼上面を高速で流れる風の圧力は低下します。こうして生じた圧力の差が、 圧力の高い下方から圧力の低い上方へと翼を引き上げます。
これが揚力を生み出すしくみです。
風に翼を起てる
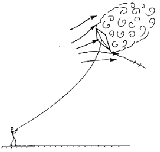
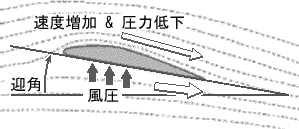
風の流れを下向きに変えるように翼を起てると、 翼の下面には翼を上方へ押し上げる風圧が加わります。 この風圧は、風の流れを下向きに変えることに対して生じる、 上向きの反作用の力です。凧も同じ方法で空中に昇ります。
さらに、風に翼を起てると、翼の上面と下面の圧力差が拡大します。 翼上面を流れる風の経路は、翼を起てた分だけ大きなカーブとなり、 翼上面と下面を流れる風の速度のちがいが顕著になるからです。
「迎角」とは、風の流れに対して翼を起てる角度です。 風に対して迎角を持った翼は、風の向きを変えることの反作用と、 翼の上面と下面で拡大した圧力差との2つの効果によって、 揚力を増加させます。
風を失った翼
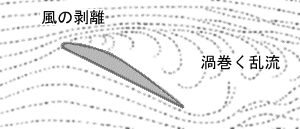
翼が揚力を生み出すとき、風は翼の周りをスムーズに流れています。 翼が風に対して迎角をとるときにも、 風は翼の上面にスムーズにまわりこんで大きな揚力をもたらします。 なめらかな風は、翼の揚力の発生に不可欠な存在です。
しかし、風のなめらかさにも限度があります。 翼の迎角が大きすぎると、風は翼の周りをスムーズに流れることができません。 翼の上面では流れがはがれ、風が渦巻く乱流となります。 この現象が「失速」です。
翼の上面でスムーズな風の流れが途切れると、 もはや翼上面と下面での圧力の差は生じません。 つまり、揚力を生み出すしくみが消滅してしまうのです。 失速によって揚力を失った飛行機は、急激に高度を失います。