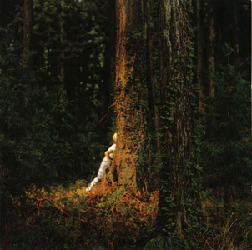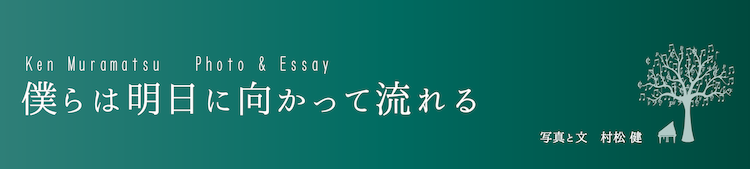
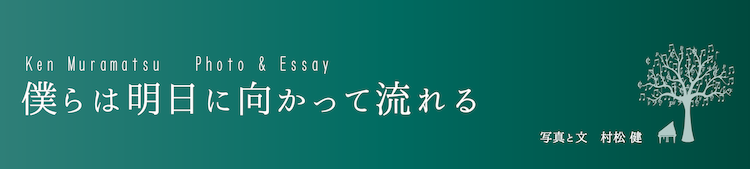
皆さんは“夢” ご覧になっていますか。最近見てないなぁって方でも、実はひと晩に大体3本立てくらいで見ていて、それを覚えていないだけらしい。今回は、この寝ている時にみる“夢”について。
まずは“いい夢”ってなんだろう。
心理学者フロイトは「夢はその人の願望の表れである」と語った。その類の“夢”を見た時は、確かにある種の心地よさを覚えますよね。それが予知夢だったら…なんて思ったり、“夢”の続きをみたいと願ったり。何の根拠もない肯定的な感情が、その後に及ぼす影響は案外大きい、そう思いませんか?
一方で“悪い夢”は、一般的にはストレス過多が原因といわれる。
起きている間に処理しきれなかった感情とか、表立って自覚はないけれどそれが絶えず影響を与えている負の感覚、そんなものが表れるらしい。面白いのは、この手の“夢”にも予知夢を懸念する感情が古来からあり、夢違観音なんていう“夢”の書き換えを願う対象すらあること。
その正体が明らかでないのに否応なく入り込んでくる“夢”という存在を、僕らは信じたり畏れたりしながら付き合ってきたんですね。
夢の研究が進んで、現在では起きている間に経験した記憶や刺激がレム睡眠のあいだに整理され、そのときに作られる一種のドキュメントムービーのようなものだと考えられるそう。にもかかわらず非現実的なロケーションやストーリー展開がそこにあるのは、現実逃避の願望や映画やアニメ、ドラマそして小説といった創造物の中の擬似体験が、実際の記憶の断片を繋げていくからでしょうね。
僕は、能動的なところで“夢”と付き合えたら、といつからか思うようになった。
結局のところ“夢”は、自分の状態を知るにはとても貴重な体験というか、心の窓のように感じるから。“夢”もまた実際に僕らが経験することなのだから、その向こうに何かを占ったりその正体を探るのではなく、見ること自体で完結して意識をしてみるのはどうだろう。
“楽しい夢”は自分の状態の良さ、“怖い夢”は意識してそれを収めていく為の気づき、“悲しい夢”は大切な愛情、“懐かしい夢”は居場所の有り難さ、果てしない夢は旅の終わりの充足感…
空を舞う一羽になって、自分の現在地をそんなふうにちょっと俯瞰してみるのはいかがでしょう。夕べみた“夢”は、もしかしたら起きている時以上に生を実感できる“愛しい一幕”なのかもしれませんよ。
2024.5
今月の曲「夕べみた夢」