
雪交じりの大雄宝殿。
境内を歩く。中国のお寺は本当にどこに行っても造りが同じなので、建築上のおもしろさは特に見いだせない。それでも、なかなか広い敷地の一番奥にあったお堂の回廊から入口の方を振り返ると、連なった黒い屋根に雨から変わった雪が映える。お寺の両脇は山で、霊山なんだとか。やはり街の中にあるお寺よりも風情を感じられるのがよい。ぶらぶら歩いているうちに、おかゆを200人だか300人だかぶんいっぺんに作れる大釜が展示されていた。今は使われていないから展示されているのだけれど、なんともビッグな寺である。

敷地の一番奥から、入口の方角を振り返る。
それなのに、現在は「臨済宗」のお寺だというからよくわからない。日本でも、何らかの事情によってお寺の宗派が変わってしまうことは、そう特殊なことではない。それでも、道元禅師が修行されたくらいのマトモな寺の宗派が変わったのかと感心していたら、なんと「住職が変わったから」という不可解な説明を現地ガイドが始めた。ますますよくわからない。
→日本に帰って、中村元『シナ人の思惟方法』(春秋社)を読んでいたら、中国では宗派がお寺で決まるのではなく、住職で決まると書いてあった。たとえば天○宗のことを勉強したければ、日本ならとりあえず【天○宗の寺】(例・延暦寺)に行けばよい。ところが、中国では【住職が天台宗の寺】(例・国清寺)に行かなければならない、という。中国に寺院の本末制度がないとはいっても、“宗派が変わる瞬間”を体験する住職以外の僧侶のことを考えると、僕は違和感を感じざるを得ない。
寧波の市内に戻って昼食を済ませ、高速道路で杭州に向かう。沿道は折からの雪のせいでところどころが白くなっていて、とても寒そうだ。このあたりで雪が降るのはせいぜい年に1回くらいとのことなので、どれだけ日頃の行いが悪いのかと思う。もっとも、酔っぱらって記憶を飛ばしたことにだいぶ反省しているので、かえって拝み方が足りないのかもしれない。バスは高速道路の三江SAに立ち寄り、給由をした。日本と同じく、トイレと売店にレストランといったSAである。僕はトイレに行ったついでに高速道路地図を購入(18元=270円)した。これで道がわかるかと思ったら、大変にカラフルな内容なのにホントにまあ主要な道路しか書いていないので若干不満である。そのぶん北京から上海まで(1268km)だとか、上海から四川省の成都まで(2213km)の高速図なんかも載っているダイナミックさがよい。ものすごいおみやげになると思う。

高速道路走行中の1コマ。
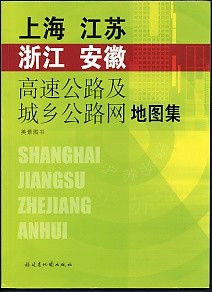
SAで売っていたロードマップ。
14時半過ぎに、トロリーバスの行き交う杭州市内に戻ってきた。だいぶ渋滞気味のなか、船着き場に到着する。待つことしばし、船内での夕食が期待できないかも?ということで、市内の普通のレストランに行く。チェーン店のお店だそうで、ごく一般の中国人が、ごく日常的に食事をするような店だそうな。日本で言うなら立ち食いソバ感覚なのだろう、ラーメン1杯5元(75円)ほか、餃子に肉まんといったメニューをセルフサービスで食べる。

手前にあるのは大根の漬け物。
杭州から蘇州までの船に乗る。14時間の船旅である。高速道路を使えば2時間で行けるのに、と笑われたことも数度あったけれど、僕は乗り物好きなので特に苦ではない。それに、長時間の船旅なんて大島へ行って以来だ。いったいどんな船なのだろう……と思っていたら、隅○川を走る水上バスのような、ぺったんこな船だった。船内は辛うじて二階建てになっているけれど、僕の背だと頭をぶつけそうでコワイ。部屋はピンキリで、僕の部屋は一番上等な六畳ほどの広さの部屋である。ベッドが二つに、テーブルとイスと洗面台といったところだ。他の皆さんは部屋に寝にかえるだけにしてもらい、ふだんは僕の部屋がベースキャンプである。すごくこぢんまりしているけれど、全員の顔が見渡せる広さというのはよい。
船内探検に出かけてみる。多くの部屋は四畳半くらいの広さで、二段ベッドのある二人部屋はともかく、二段ベッド二つの四人部屋なぞ、狭くてビックリする。よくわからないのが「シャワー室」で、廊下から丸見え、しかも船員?の洗濯物が干してあって生活感満点だ。船尾にはレストランがあって、あとで食事が出るという。楽しみにしてみよう。

こんな船です。(翌朝、蘇州で撮影)
船は「大運河」を北上している。大運河は隋の煬帝(聖徳太子が「日出る国の天子……」という書状を送ったことで有名な皇帝)が造営を命じた運河で、江南で取れた農作物を北京に運ぶ目的のために、現代なら高速道路を造るところだろうけど、運河を掘っちゃったのである。その距離1700km!東京から那覇まで行ってもまだ足りないくらいだ。そんなとんでもない運河の最南端を北上する船旅だ。
運河の川幅は100mくらいだろうか、水は茶色く濁って透明度は全くない。そして周囲は普通に高層マンションやら民家やらがあって、お世辞にも風光明媚とは言えない。歴史ロマンを感じるには水上生活?のダルマ船が並び、あまりにもリアルな現実世界である。この船旅は10年ほど前の超人気旅行コースだったそうなのだが、すっかり寂れちゃったというのも頷ける。歴史ロマンだけで観光客を集めるというのは大変だ。

ずっとこんなカンジの風景です。(写真提供:鈴ぽちぇさん)
やたらと声がでかくて迫力のある船員が僕たちの部屋にやってきて、連絡というよりもむしろ宣告という雰囲気で何かをしゃべった。ドキドキしていたら、メシの用意ができたよという話である。船縁の危なっかしい通路を歩いて船尾のレストランに行くと、なんと“普通の”中国料理が並んでいた。食材は豊富で、炒め物各種としか書きようがないけれど、次々と皿が並んでゆく。狭苦しい船の厨房でこれだけ作るのだから、大したものである。ただし、唯一最大の問題がレストランの“雰囲気”である。用事のない船員がのんきにテレビを見たり、カップラーメンを食べたりしている。船員控え室というものがたぶんないのだろうけれど、豪華な控え室を間借りして食事させてもらっているみたいだ。どうも落ち着かない。
なんだかんだと文句を言いながらもレストランで長居をして、部屋に戻ってからもみんなで飲み直し、結局寝たのは何時だったのだろうか。ともかく船はほとんど揺れないので、眠りやすそうだ。布団にくるまると咳が出た。咳が止まらなくなった。えっらいホコリっぽい……